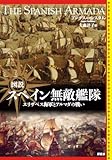映画「エリザベス:ゴールデン・エイジ」
を見ておりまして、
その後の歴史を大きく左右することにもなったアルマダの海戦とはどんな戦いであったのか、
この辺りがちと気になったものですから、図書館で関連書を探し出してみたところ
見つかったのが「図説 スペイン無敵艦隊 エリザベス海軍とアルマダの戦い」というものでありました。
先の映画を見ておりますと、紆余曲折はあろうと思われるものの、
そして確かに当時の一等海洋国たるスペインの艦隊はイングランド軍を圧倒していたと窺えるものの、
それでも結局のところは何ともあっけなく壊滅してしまった…というふうに見てとれたわけですが、
詳細に史実を追いかけていくと(沈没船から引き揚げ品なんかも参考に)、ここにもまた
勝った側が声高に都合よく作り上げた史観があるようで。
まず戦いの発端でありますけれど、カトリック対プロテスタントという宗教観の問題、
そしてスペイン船、あるいは新大陸のスペイン領からの略奪を繰り返すイングランド海賊、
これをイングランド側では処罰するどころか、重用していたという問題、これに加えてですね、
オランダの独立問題があったのですなあ。
スペイン領ネーデルラントは南側(現在のベルギーに相当)がカトリックであったのに対して、
北側(現在のオランダに相当)はプロテスタントが多数派であって、
カトリック擁護の大国スペインからの独立が志向されていたわけですね。
これに同じ(?)プロテスタントであるエリザベス朝イングランドとしては
公然と手を貸す状態にあったと。
これらの問題がひっからまって業を煮やしたスペインが打倒イングランドを掲げることになるという。
また作戦としても、
スペイン本国から派遣された大艦隊は直接的にイングランド海軍を叩きに来たのでなく、
元よりネーデルラントの治安維持に派遣していたパルマ公の軍を
イングランドに上陸させるための護衛、これが第一目的であったようなのですね。
イングランドの側としてみれば、そんな戦略を知っていたかはともかくも、
とにかく捨て置けばイングランドに災いをもたらす敵艦隊を何とかしなくてはならない。
早い段階での本格的決戦を望んでいないスペインと
ちょこちょこちょっかいを出すイングランドてな感じで緒戦は展開するわけです。
一方で、海戦での戦術でありますけれど、
当時の海戦とは大砲を使用するもそれは攻撃の補助的要素であって、
敵艦に横付けし兵士を送り込んで制圧するというのが主流であったそうな。
大国スペインはあっちこっちで戦闘経験のある兵士をたくさん艦載していたのに対して、
イングランド側兵士は寄せ集めの市民兵的なところを出ませんから、
白兵戦では勝ち目がないとしてむしろ主流ではない艦砲射撃での艦隊撃滅を考えていたらしい。
ですので、近づき過ぎるとスペイン艦に絡め取られてしまう可能性があり、
かといって近づかないと大砲の効果は十分に発揮できないてな状況でもあったような。
もっともイングランドがこうした戦術を採用するにあたっては、
スペイン側の艦載砲よりもイングランド側の方が新式であったことにもよるようです。
例えば、大砲の台座の点ですが、
スペインのものは車輪が2つで砲のお尻が床に着き、3点で支えるものだったのに対して、
イングランドのものは車輪が4つで動かすのが容易、
その分元込めの弾を装填する時間が短縮されて、
スペインが1発放って次の準備をしているうちにイングランドは3発打てたてな話もあるようです。
が、当時は弾そのものが爆発することはありませんから、
よほどのことがないと船を沈めるまでにはいたらず、小競り合いを続けながらもスペイン艦隊は温存され、
英仏海峡を横切ってカレー港外に進むことを許してしまったという。
ここに至っては(これまで気付いていないとしても)
スペインがネーデルラント派遣軍との合流を図ることは予測もできましょうし、
イングランドにしてみれば叩くならば今しかないの状況になってきたのではないかと。
そこで登場するのが焼き打ち船作戦でありますね。
火薬や油の類い、燃えやすいものを満載させた捨て船を使い、
結集するスペイン艦隊に近づいたと見るや火を放って操舵員は脱出するというもの。
映画ではスペイン艦隊が大炎上したりするわけですが、実際には大きな被害はでなかったもよう。
その代わり、浮足立った艦がそれぞれに錨の綱を切って(巻き上げる時間が惜しい?)
逃げにかかる。
これを追って、イングランドは決戦を挑むもやはり決定的な打撃を与えるまでには至らず、
ほとんどの艦を北海へと逃してしまうことに。
ここまでのところで、無敵艦隊とネーデルラント派遣軍の合流による
イングランド上陸というスペインのシナリオは回避できたわけですが、
イングランド海軍がスペイン無敵艦隊を完膚なきまでに討ち果たしたといった喧伝は
全く史実に反するわけですね。
当初の目的が叶わないと知ったスペイン艦隊は捲土重来を期して本国への帰還を決意し、
スコットランド、アイルランドを迂回して南下する航路を選びますが、
そりゃあ後戻りはできないでしょうから。
さりながら、この大きく迂回する際に二度の嵐に見舞われ、
それまでほとんど温存されていた艦隊勢力が半分近くにまで減じてしまう…
日本ならば、元寇がそうであったように「神風が吹いた!」というところでしょうか。
当時のイングランドでは後に語られるほどの絶対的勝利とは思っていないわけで、
後にスペインまで出張って残存艦隊の掃討を図るなどの作戦にも出ています。
つまりアルマダの海戦とは、
英仏海峡でスペイン、イングランドが一挙に雌雄を決した戦いではないものながら、
嵐で多くの艦船を失ったスペインの国威が下降路線を辿って行くのに対してイングランドが上り調子になる、
そうしたグラフの交差点付近での出来事であったことは間違いないのでありましょう。
ここでもしイングランド艦隊が壊滅していたとしたら、
イングランドが七つの海を支配するてなことを言われることはなかったでしょうし、
その後の帝国主義の時代に大英帝国として世界中のあちこちに
紛争の種を撒いて廻ることもなかったかも。
ですが、スペインが権勢を保持していたと考えるならば、
これまた中南米で行われた支配がアジア、アフリカにもどんどん及んでいったのかも。
(当時のスペインはポルトガルを併合してましたですしね)
てなことを考えると、何だかどちらにせよいいことなしのように思えてもくるところですが、
こうした歴史の上に立って今がある…ということなのではありましょうねえ。