仕事から帰宅するなり、妻から「面白いから、読んでみ、ほれ、ほれ」と言って渡された、
日経エンタテインメント!11月号。
http://ent.nikkeibp.co.jp/ent/monthly/2016/11/index.shtml
情報量の多さ、深さ、テーマの着眼点、やっぱりこの雑誌、面白いんだよなー。
何と言ってもまずは、表紙でもある櫻井くんのインタビュー。最初の謙遜からして、彼は本当に慎重だよなー。その慎重な櫻井くんが、ソロ活動の特集でもたくさん名前が出てたけど、あれだけ幅広い活動を、しかもあのボリュームでこなすに至るまでには、根気が必要だったでしょうね。
櫻井くんが見事だなと思う点は、自分の立場をわきまえつつ、自分にしかできない立場を確立していったところ。自分にしかできないキャスター像と、自分にしかできないアイドル像を、きちんとビジョンを持って、地道にコツコツと、着実に作り上げたところ、でしょうか。
キャスターをすることで自分のストロングポイントを磨くことができて、それを嵐のグループにおけるポジションにも反映される。それは、嵐5人それぞれに共通して言えることかもしれません。ただ櫻井くんの場合は、アイドルという立場でこそ言えることがあるキャスター、キャスターのように話が展開できるアイドル、という二面性を使いこなすことで、キャスターとしてもアイドルとしても成長できたのかな、ってインタビューを見て思いました。その二面性の意識的な使いこなしこそ、彼の知性の賜物です。
ラッキーな面というか、いろいろうまくいった点もあったのかもしれません。核となる活動が長い期間継続できたというのも、彼にとってはよかったのかな、って感じました。嵐が軌道に乗ったのも、いいタイミングだったのでしょう。それも含めて、彼は知性で運も味方につけて、ここまでのし上がってきたと言えるし、だからこそ、その知性を伸ばすことに貪欲なのかな、って思いました。櫻井くん個人にも、嵐にも、彼の知性が大きな力を与えているはずです。
あと、Kis-My-Ft2の横尾くんのインタビューも掲載されてました。これもすごく興味深かったです。これ読んだら、横尾くんの真面目さ、優しさ、責任感の強さがすごく伝わってきました。
僕の娘が「ペットの王国 ワンだランド」が大好きで、何もない日曜日は、娘と一緒になって番組を見るんです。あの番組での横尾くんって…こう言っては失礼かもしれないけど、敢えて言わせてもらうと、意外とちゃんとしてるんですよね。僕はそこまで横尾くんのことに詳しくないですが、どうしても舞祭組の歌下手なイメージがあったし、ちょっとおどおどしたところもあったので、最初はもっと頼りない感じの子だと思ってたんですよ。
でも、彼も回を重ねるごとに、発言が豊富になってくるし、人との会話もすごく的を射ているし、すっかり板についてきたなぁ、なんて思ってたんです。でもそれって、彼の勉強の成果だったんだな、ってインタビューを読んで知りました。ああ、勉強してたんだ。すごい。
横尾くんの活躍を支えてたのは、ここでも知性なんだな、って思いました。彼も挫折を知った中で、学ぶこと、知ることを通じて、今のポジションを確立してたんだな。そう思うと、真摯に努力する横尾くんのことがなんだか愛おしくなっちゃいました。勉強することで活躍できることを知った人は、この先強いよ。
日経エンタと言えば、堂本光一くんの「エンタテイナーの条件」だけど、今月号の和太鼓の話もそうです。どうすれば音が鳴るか、どういうときに音が響くか、それを考えて、答えを見つけ、知識にしていく力。知識にしたからこそ、言葉にできる。そこまで含めて、彼もまた知性の人だと思います。それは、単行本「エンタテイナーの条件」を読んだときにも思ったことです。
昨日ちょうど、安井くんがクレバーだ、って話を書いたのですが、日経エンタテインメント読んで改めて思いました。アイドルが生き残るために持つべきもの、それは知性です。感性で生きるタイプの人もいます。でも、全員がそうではありません。だから、知性がアイドルを作るんです。僕はそう、改めて実感しました。
いや、今月号の日経エンタテインメント!、読み応えがあって本当に面白かったです。あー、あと、日経エンタテインメント!のインタビューで好きなところをもう一つ。ちゃんと編集されているのに、インタビューの字面を読むと、その人が話をしている様子が伝わってくるところ。インタビューの引き出す力と編集力も、僕が好きなところです。よかったら、読んでみて。
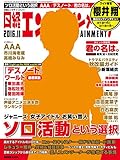 | 日経エンタテインメント! 2016年11月号 630円 Amazon |
