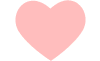今日9月13日日曜日は近鉄の歩け歩け大会
県名由来の「杖衝坂」と佐佐木信綱生誕地に参加しました。
久しぶりの内部線登場です。
この内部線は、日本でも数少ない線路幅762mmの軽便鉄道です。
ここ四日市市から鈴鹿市に入り、さまざまな見所を立ち寄ります。
今日の天候は、晴れのよい天気になりました。
時々吹く風も心地よく、気温は真夏ほど上がらないものと思われます。
ここを渡っていきます。

この道路は国道1号線、旧東海道と並走したり、重なったりしています。
これから、写真の鈴鹿方向にむかって左側の歩道を歩いていきます。

車の通行量が多く、片側2車線の道路で、スピードが出ている車もあり
歩道からはみ出ないように、注意しながら進んでいきます。
右は国道1号線、左は旧東海道です
コースは、左の旧東海道へ進んでいきます。
このあたりの地名は、采女といいます。
采女とは、宮中で天皇のお食事の世話をする女官のことです
「古事記」によると、伊勢の国の采女が捧げ持ってきた盃に
欅の葉が落ち、それを気づかず天皇に献上された。
天皇は大いに怒り斬り殺そうとなさった時、
非礼をわびて歌を詠んだところ、天皇は、その罪を許し
さらに、多くの褒美を与え、彼女の故郷の地を「采女」と呼ぶことを
許されてたと言われています。
これから向かう杖衝坂(つえつきざか)に関する資料が
たくさん展示してあるのが、うつべ町かど博物館です。

すっかり、町かど博物館に見入っていたら、誰もいなくなりました。
前方に見えている電柱に、杖衝坂の矢印と、ハイキングの矢印がありました。
その矢印に従って、この先を左へ曲がります。

曲がって、少し歩いていくと、とても急な坂道に差し掛かりました。
これが杖衝坂です
古事記によると、日本武尊が東征の帰途、
伊吹山の神との戦いで病に倒れ弱った身体で、大和帰還を目指して
剣を杖代わりにして、この急坂を登り「我足如三重勾面甚疲」
(我足は、三重の曲がりのごとくして、はなはだ疲れたり)といったそうです
それが、「杖衝坂」と「三重」の名前の由来と言われています。
近くには芭蕉の句碑もあり、こちらは江戸時代の建立されたもので
「歩行(かち)ならば杖つき坂を落馬かな」と詠んでいます。
なまじ馬に乗って、坂を登って途中で落馬してしまい、
歩いて登ればよかったということのようです。
その昔、東海道を旅する人の、喉を潤したことでしょう。
ナンバープレートに書かれている「三重」は、ここからきているのですね。
結構長い坂ですね。
やっと、杖衝坂もここまでです。
日本武尊が、足の出血をここで封じたという伝説から、
ここに血塚の祠があるそうです。
この国道1号線も、大きくカーブを描いた急坂になっています。
万延2(1861)年、山城国伏見稲荷の祭神である宇迦之御魂神の
分霊を勧請して創建されました。
すぐ右側には、国道1号線も並走していますが、とても静かでした。

やがて、下り坂となり、前方に、また国道1号線が見えてきました。
すぐに地下通路がありました。
この地下通路で、国道1号線を横断します。

横断したあと、左手に車道を見ながら、国道1号線を進んでいきます。
今でこそ、ずいぶんと知られた「とんてき」ですが
ここのお店は、かなり昔から、この看板を出しています。
食べたいところですが、まだ朝の時間です。
右側の道へ入っていきます。
「ここから東海道石薬師宿です」といって、
信綱かるた道のパンフレットを配っていました。
石薬師宿に36点提示してあり、訪れる人が楽しみながら知ることができます。
旅の安全をずっと見守ってきたのでしょう。
直線が続く道筋は、かつての宿場の姿を彷彿させてくれます。

その本陣跡から、少し歩いたところに佐佐木信綱記念館がありました。
歌人でもあり、国文学者として有名で、
鈴鹿市が生んだ偉人として知られています。
館内には、著作や遺品が展示してありました。
信綱は、明治5年(1872)6月3日に誕生し、数えで6歳
明治10年12月に松阪に移住するまで、この家で過ごしました。
コースも、まだまだですが、続きは明日のブログで紹介します。