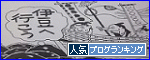大正11年発表の「伊東ぶし」という歌がおもしろい。
新井瀬合を小舟で行けば、
亭石島(手石島)にはしたたるみどり、
波にぬれじと立つ与望島、
岩は潮ふき水けむり
下の画像は与望島。
地元の人は鳥帽子島、間通島、立島とも言っているそう。
(日蓮上人の銅像もあります↓)

手石はなれて帆に帆を揚げてヨホホイ
「伊東ぶし」にはヨホホイ が良く出て来るけれど、
ヨホホイって当時のはやし言葉なのだろうか。。。
「伊東ぶし」は木下杢太郎のお兄さん、太田円三他の人達が
作詞したそうで、36番ぐらいあるらしい。
この日は川奈周辺に物件を探しに来たという人が写真を
撮ってました。
穏やかな波の日
夏は海水浴の人達で賑わういるか浜
海の水が綺麗
川奈の人達が大切にしていた姥子神社とお船石(右下)。
お船石は周囲50m、高さ4mほどだそうで、形が船に似ています。
古老の言い伝えでは、昔神様がこの地に上陸した時に舟を着けた
石であろうと言うー伊東の地名(著・加藤清志)より
「伊東の地名」という本には、姥子神社の姥子神の熱心な
研究者である川奈のS商店のおじいさんのことに触れて
いますが、このS商店には月に一回ほど仕事で伺っているので、
すでに亡くなられているおじいさんのことを訊いてみました。
大変研究熱心な方で、姥子神とお船石のことを調べていて、
時にはふんどしだけで家から姥子神社まで行ったそうです。
何故なのかは判らないそうです。
家を守る為に、鳥居も二つ建てたと言ってました。
夕暮れの初島
江戸時代の潮干の頃は、酔客と婦女が舟で島に渡り、
歌ったり呑んだりと遊んだらしい。
季節関係なく楽しめる川奈の海です。
応援お願いします