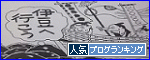宇佐美の朝善寺に関わる民話・伝説が残されていました。
日朝(にっちょう、応永29年1月5日(1422年1月27日) -
明応9年6月25日(1500年7月21日))は、室町時代の
日蓮宗の僧。
字は鏡済、号は行学院。朝善の子。
12世の日意、13世の日伝とともに身延中興の三師と
位置づけられている。 ウィキペディアより
童子(わらし)の旅立ち
著・山本悟 「行学院日朝上人・他」
(童子(わらし)は幼い子供 )
)
宇佐美の山田に、朝善寺というお寺があります。
今から500年余り前、延徳元年(1489年)
日朝上人が父母の供養のために建てたものです。
日朝上人は応永29年(1422年)正月五日、伊豆国宇佐美村
に生まれました。
日朝上人が8歳になったある春の日のことでした。
宇佐美の浜辺では5~6人の子供達が、波と戯れていました。
そこへ、舟から降りた見知らぬ坊さんが、足ばやに駆け寄って
来ました。
「あなたの家を訪ねたいのですが、案内願えますか」
声を掛けられた童子は、大きくうなずきました。
童子の家は村の北の外れ、低い丘の上にありました。
朝善寺の境内。今年は寒いので
「わたしは日出(にっしゅつ)と申します。三島に本覚寺を建て、
近くの村人に日蓮上人の教えを説いて回っております」
日出上人はあいさつもそこそこに、案内してくれた童子の
ことについて尋ねました。
「この子は今八歳。生まれて四十日目、父朝善はこの世を
去りました。
母一人子一人となり、このように叔父夫婦の世話になって
おります」
「左様でしたか。ご存じの通り、世の中は争いが絶えず、
そのうえ大飢饉続き。
この乱れた世を救うことのできるのは、日蓮上人の生まれ
変わりの方。
わたしの祈りが通じたのか、昨夜、日蓮上人が夢枕に立たれ、
(わたしの志を継いでくれる童子に会いたくば、宇佐美の
里を訪ねるがよい)とのお告げ。こちらさまの童子こそ・・」
すかさず叔父が日出上人の言葉を遮りました。
「お言葉は誠に有り難いことでございますが、わたしどもは、
この子の成長する姿を見ることだけが生きがい・・・」
それまで黙って聞いていた童子は、ほおを赤らめ、涙ぐみ
ながら話し出しました。
「わたしも今年はもう八歳になりました。これからは勉学に
励み、偉い坊さんになりとうございます。
そしたら父上さまの後生(死の世界の幸せ)も祈ることが
できます。
お別れは切ないですけれど、どうか出家させて下さいませ」
日出上人のお手に引かれ、三島へと旅立つ童子。
童子は日出上人より日朝という僧名を授けられました。
長い歳月にわたり修行を重ね、四十一歳の時身延山久遠寺
の貫主(最高の位)となり、十二年後を今の地に移し、
立派な建物にしました。
勉学に一生を打ち込み、沢山の本を著しましたが、その
ため晩年目を悪くしました。
「死後は目の病で悩む人達の力になってやりたい」
日朝上人の思いが人々に伝わり、朝善寺は目の寺とも
呼ばれ、参詣人が絶えません。
前の朝善寺の記事は→こちらです(^-^)
行学泉 目の病を治してくれる

お庭のお手入れをしていた方のお話では桜も遅れて
伊東の”民話・伝説”は市内の書店で!o(^▽^)o