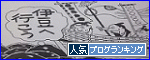昭和の時代、伊豆の東海バスのバスガイドさんは、
『伊豆遊覧案内』で 「曽我物語」 のお話をしたそうです。
 これから 歴史で名高い曽我兄弟仇討ちの発端地
これから 歴史で名高い曽我兄弟仇討ちの発端地
赤沢山 椎の木三本 にかかりま~す。
今もなお、あるいは唄に お芝居に 孝子(こうし)の鏡と
たとえられ 今に残る 曽我兄弟の物語は、こうして伊豆の
この山陰に生まれたのでございます
日本三大仇討の一つ、富士の仇討のお話を申し上げますと、
安元の昔、伊東の庄、伊東入道祐親(すけちか)は、
この山向こうの奥野に狩りを催し、その終わりに余興として
皆に相撲をとらせました。
その時、一番人気を呼びましたのは、祐親の最愛の嫡子
(ちゃくし)、伊豆の国は河津の庄、十八ヶ村の領主、河津
三郎祐泰(すけやす)と工藤祐経(すけつね)の秘蔵の家来、
俣野の景久(かげひさ)との取り組みでした。
お互いに親戚関係でありながら領地争いがもとで 毎々から
恨みを抱く祐経(すけつね)は、剛力(ごうりき)を誇る景久を
出して河津三郎を投げ殺そうと ひそかにたくらみましたが、
剛勇無敵の河津三郎にかえって投げ倒されて負けたので
ございます。
無念やるかたなき祐経が、そのまま収まるはずはありません。
力でかなわぬなら、暗討ちと、弓矢の名人、八幡の三郎、
大見小藤太の二人の家来に言いつけ、椎の木三本に待ち
伏せて、河津三郎が、意気揚々と馬にまたがり、ちょうどこの
谷間に差し掛かったとき、遠矢にかけて射殺したのでございます。
時は安元二年十月十四日でございました。
このとき父を討たれ、河津の館を追われた河津三郎の遺児
(わすれがたみ)一万(いちまん)、箱王の二人は母に伴われ下
曽我 曽我太郎の下に逃れ、のち元服して曽我五郎、十郎と
なりました。
星霜移って建久四年五月、頼朝公富士の巻狩りのとき、十八年
の天津風(あまつかぜ)不倶戴天(ふぐたいてん)の父の仇、
討つは今宵と心あわせ、折しも降りしく五月雨の黒白(あやめ)
も判らぬ、宵闇に、工藤の陣屋に忍び入り、首尾よく
その恨みをはらしたのでございます。
これが、伊豆の山陰にもといを発し、今もなお、あるいは唄に、
あるいは歌舞伎の舞台に天晴(あっぱれ)日本一、孝子の鑑
(かがみ)と伝えられる、 曽我物語 でございます。
あの松の木陰に河津三郎の血塚がございます。
また、この上が椎の木三本でございまして、昔は三本に分かれて
おりましたが、今は枯れて一本しか残っておりません。
参考資料・画 小林一之編 ”曽我の対面”より
*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆ *:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆
当時の東海バスのバスガイドさんは、これを覚えなければ
ならなかったそうです
伊東の観光協会の方達が東京でのキャンペーンに参加したと
伊豆新聞に掲載されていました。
民話、駅弁などが紹介されたようですね![]()
伊東の民話、伝説おもしろいですよー![]()