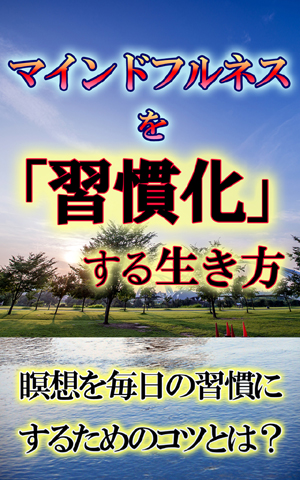マインドフルネス瞑想に興味があって始めてみたけれど、これといった効果を感じられず、すぐにやめてしまったという経験をお持ちではありませんか?
しかし私自身は、2023年の新生活の始まりをきっかけに、あえてマインドフルネスを習慣化することをオススメしたいのです。
今回は、『マインドフルネスを「習慣化」する生き方 瞑想を続けるための3つの方法』を先日kindleで出版いたしましたことをお知らせしたいと思います。
このたび書き上げました『マインドフルネスを「習慣化」する生き方 瞑想を続けるための3つの方法』は、新しい「マインドフルネス習慣シリーズ」の第1弾、マインドフルネスについての電子書籍としては11冊目になります。
この電子書籍のテーマは「マインドフルネスの習慣化」です。
「マインドフルネス瞑想に興味があったけど、試してみたらうまくいかなかった」
という理由で、瞑想を続けていくことをあきらめてしまったという方にとって少しでもお役に立てるように、マインドフルネスを習慣化する方法について詳しく書いています。
以下、この場をお借りして、本書の「はじめに」の内容を公開させていただきたいと思います。
はじめに マインドフルネスは習慣にすることで初めて真価を発揮する。
話題のマインドフルネス瞑想を試しに始めてみたけれど、これといった効果を感じられず、すぐにやめてしまったという経験をお持ちではありませんか?
実はマインドフルネス瞑想は、毎日の習慣にすることで、初めて真価を発揮するのです。
私自身、マインドフルネス瞑想を毎日の習慣にし、『マインドフルネス習慣で「今・ここ」を選ぶ生き方』をキンドルで出版してから三年以上が経ちますが、体の健康面やメンタル面を以前よりも良好に維持出来るようになりました。
また仕事や人間関係のことであれこれと思い悩むことが少なくなりましたし、読書や執筆活動など、自分にとって大切なことに以前よりも集中して取り組むことが出来るようにもなりました。 すなわち毎日の生活が充実したものへと変化していったのです。
ではなぜそのような変化がもたらされたのでしょうか?
その理由は、私自身はもともとストレスに弱く、健康面やメンタル面に自信があったわけではないのですが、普段からマインドフルネスで「今・ここ」を意識する練習を繰り返したことでストレスが減り、さらに過去の経験が蓄積している「無意識」の領域に変化が生じたのだと推測しています。
本書で詳しく述べていますが、「習慣」とは、意識的というより、ほぼ無意識に行ってしまうことなのです。
しかしながらマインドフルネスに短所があるとすれば、それはすぐに効果を実感しにくいという点です。
ある程度の期間、マインドフルネスを実践し続けていると、ハッと今の自分が以前の自分とはどこか違うことに気づける瞬間がやってくるのですが、リラクゼーション効果やダイエット効果など、すぐに分かりやすい効果を期待してしまうと、効果を大して実感できず、「習慣」になる前にあきらめてしまうのです。
ところが冒頭で述べた通り、マインドフルネスは、毎日の習慣にすることで、初めて真価を発揮するのです。
そのため今回の電子書籍では、マインドフルネス瞑想を続けていくことをあきらめてしまったという方にとって少しでもお役に立てるように、マインドフルネスを習慣化する方法について書くことにいたしました。
マインドフルネス瞑想を習慣化するための戦略として、本書では、
1 小さな習慣から始める。
2 繰り返し実践する。
3 瞑想すること自体を報酬にする。
の三つの方法を提案しています。
『マインドフルネスを「習慣化」する生き方 瞑想を続けるための3つの方法』 目次
はじめに マインドフルネスは習慣にすることで初めて真価を発揮する。
そもそも「習慣」とは何か?
習慣化の鍵を握るのは「状況」と「きっかけ」
習慣における「きっかけ→ルーチン→報酬」というループ「習慣化」の鍵を握る「報酬」「ドーパミン」の性質とは?
「ドーパミン」と「習慣」の関係
新しいことを習慣にするのは難しい。
「瞑想」を習慣にするのは難しい理由とは?
マインドフルネス瞑想を習慣化するための3つの戦略とは?
マインドフルネスは「小さな習慣」から始めてみる。
繰り返し実践することで習慣化を促す。
マインドフルネス瞑想に取り組むことを報酬にする。
マインドフルネス瞑想を実践することを最高の報酬にする。
マインドフルネス瞑想を習慣にするためのヒケツとは?
マインドフルネス瞑想を「しない」ことのデメリットよりも、「する」ことのメリットのほうが大きいと経験的に分かれば、習慣化しやすい。
「自分にとって必要だから自然にやってしまう」でマインドフルネス瞑想を習慣化する。
「本当にやりたいこと」「自分にとって必要不可欠なこと」だからと思ってやり続ける。
マインドフルネス瞑想を運動と組み合わせて実践するのも習慣化のためにオススメ。
「感謝」はなぜやる気を長続きさせるのか?
「マインドフルネス」の実践は感謝の気持ちにつながる。
相互の「関係性に気づくこと」が、〈感謝〉する練習になる。
10分間のマインドフルネス瞑想を毎日実践する。
まずは「今・ここ」に在る「呼吸」に意識を向ける。
瞑想は繰り返し実践することが大切。
おわりに 「マインドフルネス習慣化」には人生を変えるチカラがある。
『マインドフルネスを「習慣化」する生き方』、チェックしていただけると大変うれしく思います。
マインドフルネス習慣シリーズ第1弾、
『マインドフルネスを「習慣化」する生き方 瞑想を続けるための3つの方法』
Amazon Kindle で販売中です😊
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪