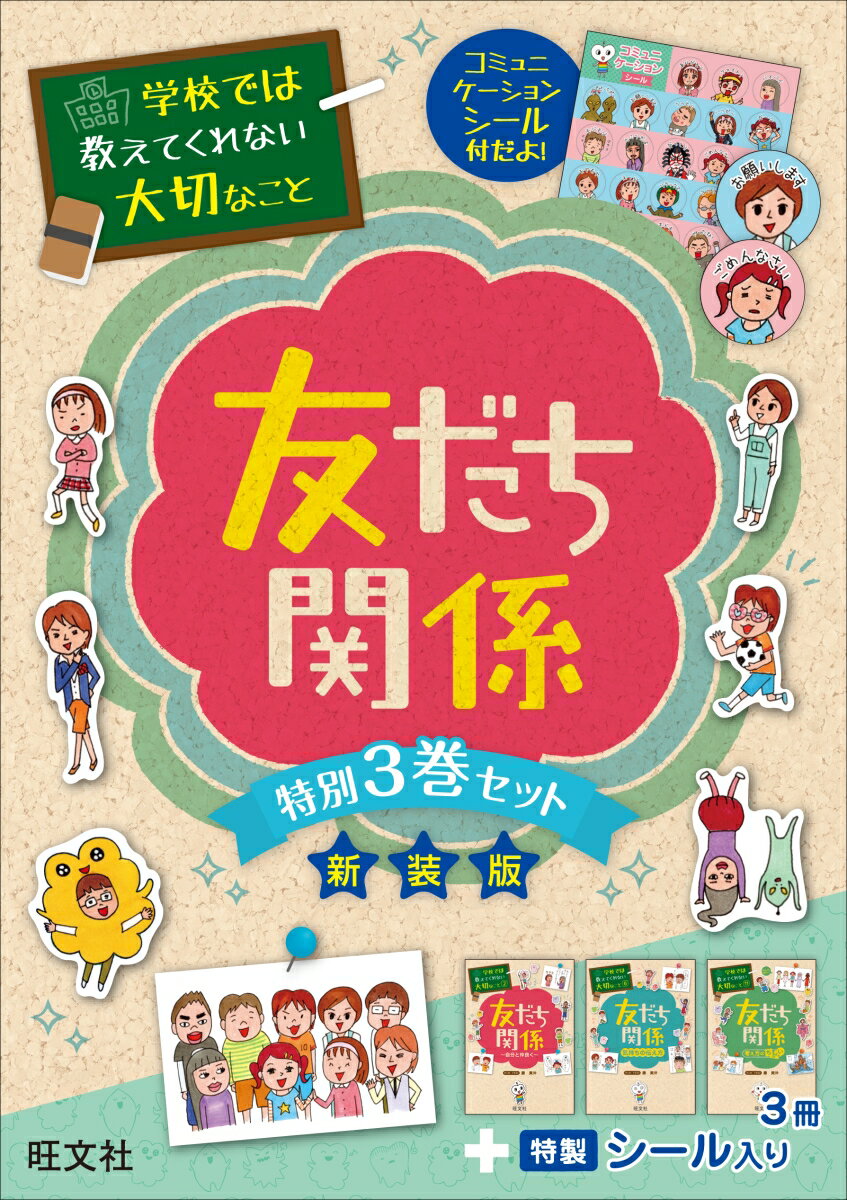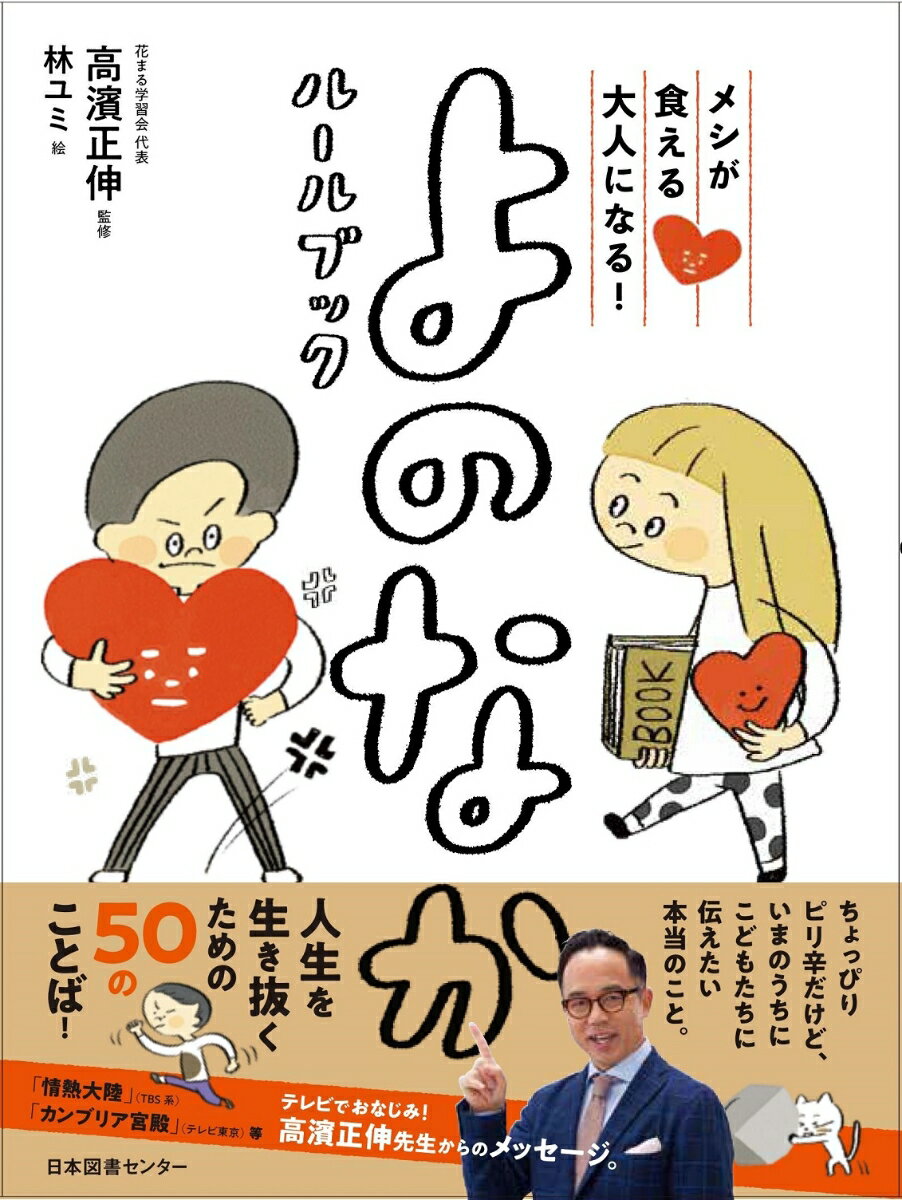3年生になり、友人関係もより複雑化、グループ化していくとききます。
9歳の壁なんて言葉も聞いたりして、親や先生よりも友人関係を大事にしたり
自分のグループ以外の子を避けたり攻撃したりするようになるそうです。
また、長男のように特性があって周囲から浮いてしまう子を
よりはっきりと自分達とは異なる存在として認識できるようになってくる
年齢とも言われました。
学校を見に行って思うのは、やはり周囲より言動が幼いこと。
好きな物が幼児のころから変わっていなかったり、
刺激的な食べ物や映像を好まないため話題も広がっていかない。
一定の動画、食べ物、趣味嗜好でとどまってしまうため
周りで何が流行しているのかの機微がどうも疎いところがあります。
障がいの有無にかかわらず、変わった子って一定数どの学年にも
いると思うのですが、それが変だけどおもしろいやつになるのか、
変だから関わらないでおこうとなるのかは、本人よりも環境の影響が大きいような
気がします。
去年の先生は環境調整がとても上手で
他の子たちの前では大きく注意しない、
他の子から直接注意を受けないよう先生を介すよう他の子に説明してくれる、
本当に周囲に迷惑がかかることははっきり言うけれど、
そうでなければ時間をかけて待っていてくれる、
得意な部分やいいところを他の子にも知ってもらえるよう働きかけてくれる
など本当にお世話になりました。
今年の先生はまだ未知数なところがありますが、
先生に頼ってばかりではなく本人もそろそろ周囲の反応を見ると言うことを
知っていく年齢なのかなとも思います。
正直、他人の感情の機微を推し量ることは障がいの特性上とても
難しいと思われますので、こういった時はこうする、
他の子の表情をみて嫌そうだったら少し引いて離れる、
こういうことをしたら、人はこう思うんだ。など
事実として頭で何度でも覚えて行動できるように時間をかけていくしかないかと思っています。
子供向けのハウツー本も使用中
これが一番最初に読んだ本です↓
ソーシャルスキルトレーニングなどたまにすると、
頭での理解はとても良かったりするんですよね。
つまり、インプットはできている。
それが適切にアウトプットできるようになるには
適度に失敗して経験を積んだり、繰り返し学習していく地道な
作業が必要なんだろうなと思います。