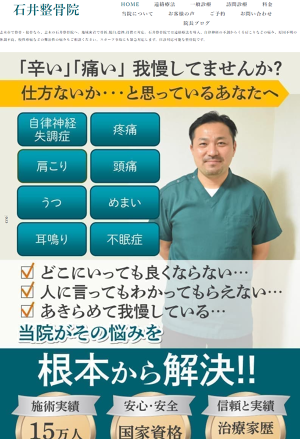今回は私が頭痛・めまいを調整するうえで
必ず確認しているポイントをご紹介します。
◆頭痛・めまいの確認ポイント
①側頭骨(そくとうこつ)の動き確認
②後頭骨(こうとうこつ)の動きと高さの確認
③環椎後頭関節(かんついこうとうかんせつ)
周辺の筋肉の硬さの確認
④第2頚椎(だいにけいつい)動きの確認
⑤副腎の確認
手首・足首の硬さや骨盤の動きなども
確認しますが上記が大まかな確認ポイント
になります。
①〜⑤の順に説明したいと思います。
①側頭骨(そくとうこつ)の動き
側頭骨は胃腸と腎臓経に関連し、
「脳脊髄液」とも関連します。
スーパーで売られている水を張った容器の中で
浮かんでいる豆腐をイメージできますか?
この豆腐のように、私達の脳というのは
液体の中で浮かんでいます。
この液体のことを
「脳脊髄液」(のうせきずいえき)と呼んでいます。
脳脊髄液の働き①
脳と脊髄を守るクッションの役割
脳脊髄液の働き②
脳内の老廃物の排泄
脳脊髄液は1分間に6回から12回くらいの
サイクルで循環しています。
◆側頭骨(そくとうこつ)の拡張と収縮
頭痛・めまいがある方は左右どちらかの
動きが悪いです。
左側は動き過ぎ、右側が動いていないことが
圧倒的に多いので、左右同じくらいの
収縮・拡張の動きに持っていきます。
ちなみにですが、
冷えやリンパからくるめまいであれば
側頭骨の動きを出すことで解決しますが、
心臓からくる血流不足によるめまいであれば、
ダイレクトに心臓を調整する必要があります。
もしくは百会に親指を重ねて、収縮・拡張が
ダイナミックになるまで調整することもあります。
百会は自律神経も関係しているため、
ストレスによる心臓が疲れているときにも
有効です。
軽い症状であれば、
1回で調整できる場合もあります。
②後頭骨(こうとうこつ)の動き
後頭骨は後頭部にある骨で、
この骨の動き(拡張と収縮)が悪いと
脳脊髄液の循環も悪くなっていますので
ここも調整が必要になってきます。
また、後頭骨の高さが左右違うということは
自律神経が乱れているというサインですので
この左右の高さも調整しなければいけません。
③環椎後頭関節(かんついこうとうかんせつ)
周辺の筋肉の硬さを確認
環椎後頭関節の場所は首から脳にいく
血管や神経の通り道になっています。
ここが硬くなっていると脳の血流が悪くなり
頭痛やめまいが発症します。
↑◯で囲んだ凹んでいるところ
④第2頚椎(けいつい)の動き
◆第2頚椎の場所は↓
・偏頭痛持ちの方は第2頚椎の動きが硬いです。
・偏頭痛持ちの方は第7頚椎の辺りが冷たいです。
ちなみに第4頚椎から第6頚椎はヘルニアの
好発部位で横隔膜を動かす横隔神経が出ている
ところです。
その辺が硬いと呼吸が浅くなっているかも
しれません。
⑤副腎の確認
副腎は頭痛もそうですが、自律神経失調症の
方にはメチャクチャ大事なところで、
ここを引き上げてあげないと、
なかなか症状が改善してきません。
副腎の場所は◯をつけたところです。
・副腎に継続的なストレスがかかると
肥大し硬くなります。
→自律神経失調症
・ストレスが長期化すると、副腎が疲労しすぎて
ホルモンを出すことができなくなります。
腎臓を触るとふにゃふにゃと柔らかい感触が
あります。
→重度の自律神経失調・うつ症状
◆副腎・腎臓が疲れて頭痛が出ている方は
タンパク質を控えていただくようにお願いして
います。
腎臓が疲れるているときに、肉や大豆など
タンパクを摂取すると、腎臓に負荷がかり
症状がなかなか良くなりません。
なので、「もう少し内臓が元気になったら
タンパク質をとっても大丈夫です」と
お伝えしています。
上記の他にも心臓の拍動や手首の動き、
足首の動き、骨盤の動きなども確認しますが
おおまかには①〜⑤が中心となります。
【石井整骨院のHP】
【石井整骨院LINE公式アカウント】