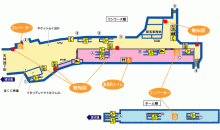以前から、この駅のユーザインタフェースが悪いと思っていたので、敢えて路線と駅の名前を出してネットの検索で掛かるようにしていれば関係者の目に留まるだろうと思って僕の考えを書いてみる。
乗り換え改札機の配置の問題
七隈線の天神南駅には図の様に改札機が設置されている場所が二箇所ある。
一箇所は図のAのエスカレータの左側、もう一箇所は同Cの左側の黒く太い縦線が描いてある場所だ。
問題は、このCの「乗り換え改札機」の場所だ。
ちなみに、この「乗り換え改札機」だが、福岡市営地下鉄は「空港線」「箱崎線」と「七隈線」と3つの路線があり、悲しいことに「七隈線」はホームレベルで相互乗り換えが出来ない構造となっている。
その為「乗り換え改札機」と言う物をを設置して相互に乗り換え出来るようにしている。
「乗り換え改札機」を使うと、ICカードの場合は特に何も問題ないが、切符の場合、改札機を通した後、ゲートの先で再び切符が出てきて、乗り換えが必要な人はその切符を取ると言うシステムになっている。
又、この「空港線」の「天神駅」は「七隈線」から見た時に図の左側となる。
例えば、Aの様に正面に改札機が並んでいれば、どれが乗り換え改札機かは表示が出ているので乗り換えが必要な人はそちらへ流れて行くだろう。
問題はCの場合の様に改札機が正面に無い場合だ。
現状、「乗り換え改札機」はエスカレータから最も近いところへ設置されている。
先の機能を考えるとどういう状況になるのか少し考えるとわかるだろう。
エスカレータやエレベーターを上がってきた乗客は先ず間違いなく最も近いところから出ようとするだろう。
奥の方から順番に利用することなどない。
しかし、この一番手前の改札機が「乗り換え改札機」である為、普通の切符を持っている乗客がここを利用すると必ず切符がゲートの先で出てくる。
単に一番手前から出て、乗り換えをしようと思わないで通っている乗客の切符は取られず放置される。
すると、機械は切符が取られるまで次の乗客を受け入れないのでそこで混乱が発生する。
もちろん、一定時間取られなければ自動的に改札機が切符を収納してしまう機能は付いているが、一定時間ゲートは使えなくなる。
その為、その後ろのICカードの乗客が居ればタッチしたのに入れずに足留めを食わされることになり、その場所はあっと言う間に混乱状態となる。
僕は毎日ここを利用するが、毎日この混乱が発生しているのを見ている。
その為、駅員が改札機の横に立って、切符を取らない乗客の為(乗客に責任はない)、代わりに切符を取ると言う馬鹿な作業を毎列車やっている。
やらなければ、最もエスカレータに近い改札、つまり手前の改札が混乱して全体に波及するからだら。
良く知っている僕は敢えてそこを使わず二列目で出ようとするが、知らない人が手前の改札機で立ち往生すると二列目も通りにくくなる。
おまけに子どもに切符を入れさせようとする子ども連れの馬鹿親が居ればますます混乱状態だ。
不味いことに、この場所はそれ程広くなく、エスカレータの出口にも近い。
エレベーターを使う場合大きな荷物やベビーカーを使っている場合なので余計に大混乱だ。
先に書いている様に空港線は左側だ。
もしこの手前の改札機が「乗り換え改札機」だと、全く知らない人間は右側に空港線があると勘違いする可能性もある。
その為、出口でもボーっと立ってる乗客がたまに居ると、乗り換え改札機を出た後も非常に渋滞する。
何故、この改札機を一番左側(エスカレータを降りた一番奥)へ設置しなかったのだろうか?
そうすれば、乗り換えをしたい人は「乗り換え改札機」を探してエスカレータを降りて先へ進み、一番先が「乗り換え改札機」だとしても空港線も同じ方向なので特に問題は無い。
場合によっては中を通ってAの出口から出ても良いかもしれない。
通常の利用者はそのまま一番手前からサッと通過するだろうから混乱も無く駅員が毎回出て切符を取る必要も無ければ毎列車で発生する混乱も回避出来るだろう。
設備設計のエンジニアもしくは市の担当者が馬鹿な為に365日、毎度毎度こういう風景が繰り返されている。
ICカードを現金でチャージする場合の領収書ボタン
既に福岡市営地下鉄も「fカード」と言うプリペイドカードが廃止されたが、ICカードをチャージする場合に領収書が必要な人も多いだろう。
僕もそうだが、このICカードをチャージする画面。
これは恐らく空港線も七隈線も含めて全線だと思うが現金を入れて最後の画面で領収書ボタンが表示される。
写真を撮っている暇が無いので画面が無いが、この領収書ボタンは
「領収書不要」「領収書必要」と言う2つのボタンが用意されている。
何故2つ必要なのだろうか?
例えばコインパーキングの領収書発行ボタンで「不要」と言うのを見たことがあるだろうか?
必要な人は領収書ボタンを押して領収書を発行する。
不要な人は押さない。と言うだけだ。
それなのに、この画面では二つのボタンを用意しているうえ、仮にどちらのボタンも押さずに一定時間経過すると操作が終了してしまい、二度と領収書は発行出来なくなるので駅員に手書きの領収書を発行して貰わなければならなくなる。
つまり、先の「領収書不要」と言うボタンは実ははじめから「不要」なのだ。
不要だけならまだ良いが、悪いことに、この「領収書不要」と言うボタンは「領収書不要」「領収書必要」と同じようなデザインで横に並んでいる。
「不要」のボタンが内側で「必要」のボタンは外側にある。
通常、人間は自分の目線に近い側、身体の中心に近い側から見ていくので「不要」と言う方が先に目に付くし身体に近いので押しやすい。
「領収書」を発行して欲しい人は「領収書」と言う文字を見て反応するので、誤って「不要」のボタンを押す可能性も充分ある。
恐らく「領収書」が必要ない人は何もしないとそのまま操作が終了するので敢えて「不要」と言うボタンを押す人は殆ど無いだろう。
もし押しているとすれば無駄な操作を要求していることになる。
表示するなら、別の場所に全ての操作(現金チャージが終わった)と言う「確認」ボタンを用意してやれば、待ち時間を短縮出来てより親切だろう。
以上、全く異なるシステムで、こういうつまらない設計を紹介したが、最近良くこういうのが目に付く。
本当にちょっとした事なのだが、想像力や考える力が落ちたエンジニアが増えた証拠だ。