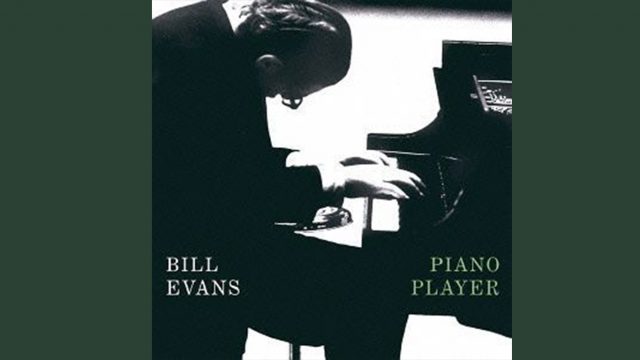ビル・エヴァンス(Bill Evans/本名:William John Evans/1929年8月16日~1980年9月15日)は、アメリカ合衆国のジャズ・ピアニスト。
1929年8月16日、ウィリアム・ジョン・エヴァンスは、アメリカ合衆国ニュージャージー州プレインフィールド(Plainfield, New Jersey,)に、ルシン人の系統を持つ母と、相当な身分を持つウェールズ系の父の間に生まれた。
彼の父ハリー・L・エヴァンスは、兄のハリー・エヴァンスJr.と同様に、幼い頃からエヴァンスに音楽を学ばせており、ラフマニノフやストラヴィンスキーなど、クラシック音楽に親しんだ。
10代に入ると兄とともにジャズにも関心を持つようになり、余暇にはアマチュア・バンドでピアノ演奏するようになった。
1946年、サウスイースタン・ルイジアナ大学(Southeastern Louisiana University)に入学し、音楽教育を専攻。並行してアマチュアミュージシャンとしての音楽活動もさらに活発になり、充実した学生時代を送った。学生時代には後年のレパートリーの一つとなる曲“Very Early”を既に作曲している。
1950年、大学卒業。
1951年、この頃は徴兵制のあった合衆国において、召集を受けてアメリカ陸軍での兵役を強いられた。軍務中は当時の朝鮮戦争(1950年6月25日-1953年7月27日)の前線に向かうような事態もなく、大学での経歴によって陸軍バンドでの活動機会も与えられたものの、エヴァンス自身にとっては不快な期間であったと伝えられる。
また、この兵役期間中に、麻薬常用が始まったという。
1954年、兵役終了後、ジャズ・ムーブメントの中心地ニューヨークに出て音楽活動を開始。ミュージシャンの間で、伝統的なジャズ・前衛的なジャズのいずれにおいても優秀なピアニストとして知られるようになった。
この時代には、サイドマンとしての活動が主であり、リディアン・クロマティック・コンセプトで知られる音楽理論家・作曲家ジョージ・ラッセル(George Russell/ 1923年6月23日–2009年7月27日)の録音に参加している。ラッセルからの影響は、作曲に表れていると言われる。
1956年、それまでの活動ぶりを買われて、リバーサイド(Riverside)・レーベルからのスカウトを受け、最初のリーダーアルバム『New Jazz Conceptions』を残している。だが、このデビュー・アルバムは800枚しか売れなかった。
1958年、マイルス・デイヴィス(Miles Davis/1926年5月26日-1991年9月28日)のバンドに加わり、録音とツアーを行っている。だが、バンドで唯一の白人であること、ドラッグの問題、そして彼自身がリーダーとしての活動を望んだために、短期間でマイルス・デイヴィスのバンドを離れる。
この頃、エヴァンスの生涯について回る薬物乱用は既に顕在化した問題となっていて、ヘロインのために体も蝕まれ始め、金銭的にも余裕はない時期だった。
同年、2枚目のリーダー・アルバム『Everybody Digs Bill Evans』をレコーディング、“Peace Piece”などを収録した。
1959年、バンドを離れたエヴァンスだったが、デイヴィスの要望で、ジャズ史に大きな影響を与えたアルバム『カインド・オブ・ブルー』(Kind of Blue)のセッションに参加、帝王マイルス・デイヴィス(Tp)をはじめ、ジョン・コルトレーン(Sax)、ポール・チェンバース(B)、キャノンボール・アダレイ(Sax)らと共演している。ハード・バップ的な頻繁なコードチェンジではなく、モードに根ざしたアドリブをこのアルバムで目指していたデイヴィスは、エヴァンスのアイディアを必要としていた。このアルバムに、エヴァンスは自作“Blue in Green”を提供しているが、ただし、アルバムでのクレジットはマイルス作曲となっている。後にエヴァンスの『ポートレート・イン・ジャズ』において同曲のクレジットは、エヴァンスとデイヴィスの共作とされた。また、 “Flamenco Sketches”が『Everybody Digs Bill Evans』収録の“Peace Piece”を発展させたものと伺えるなど、『カインド・オブ・ブルー』にはエヴァンスの影響が色濃く反映されている。
同年、エヴァンスはポール・モチアン(Paul Motian/1931年3月25日–2011年11月22日/Ds)とスコット・ラファロスコット・ラファロ(Scott LaFaro/1936年4月3日-1961年7月6日/B)をメンバーに迎え、歴史に残るピアノトリオ(ファースト・トリオ)を結成する。このトリオは、スタンダード・ナンバーの独創的な解釈もさることながら、即興性に富んだメンバー間のインタープレイが高く評価され、ピアノトリオの新しい方向性を世に示した。
従来までピアノやベース、ドラムス、あるいはギターなどの楽器奏者は、ホーン奏者を支えるための「リズム・セクション」(伴奏者)としてリズムを刻む「道具」として扱われ、また、他の「ピアノトリオ」においても、主役はあくまでピアノでありベースやドラムスはリズムセクションの範疇をこえるものではなかった。
ビル・エヴァンス・トリオにおいては、この旧来の慣習を打ち破り、テーマのコード進行を「ピアノ・ベース・ドラムス」の3者が各自の独創的なインプロヴィゼーションを展開して干渉し合い、独特な演奏空間を演出した。特筆すべきはベースのスコット・ラファロで、積極的にハイノート(高音域)で対位旋律を弾き、旧来のリズムセクションの枠にとどまらない新しいベースの演奏スタイルを確立した。また、ドラムスのポール・モチアンも単にリズムを刻むにとどまらずエヴァンスのインプロヴィゼーションに挑みかかるようなブラシ・ワークやシンバル・ワークを見せるなどした。このトリオで収録した1959年『ポートレイト・イン・ジャズ』(Portrait in Jazz)、1961年『エクスプロレイションズ』(Explorations)、1961年『ワルツ・フォー・デビー』(Waltz for Debby)および同日収録の『サンディ・アット・ザ・ビレッジ・バンガード』(Sunday at the Village Vanguard)の4作は、「リバーサイド四部作」と呼ばれる秀作である。
1961年7月6日、『ワルツ・フォー・デビー』と『サンディ・アット・ザ・ビレッジ・バンガード』の収録からわずか10日後、ラファロが交通事故死してしまう。25歳の若さだった。エヴァンスはショックの余りしばらくの間ピアノに触れることすら出来ず、レギュラートリオは活動を停止、半年もの間シーンから遠ざかった。
トリオの活動停止中、他セッションへの参加や、ピアノソロを録音するものの、これらの音源はエヴァンスの生前は総じてお蔵入りとなっている。彼の没後、プロデューサーのオリン・キープニューズにより、ソロ演奏が『The Solo Sたessions vol.1』、『The Solo Sessions vol.2』として発表、またエヴァンスのリバーサイド時代のリーダー作を網羅した『The Complete Riverside recordings』がリリースされた。
同年、ベースにチャック・イスラエル(英語発音:イズリールズ/Chuck Israels)を迎えて活動を再開するが、ラファロ時代のような緊密なインタープレイは後退を余儀なくされた。しかし、イスラエルはもともとラファロの影響を非常に大きく受けたベーシストであり、ヴォイシングこそ地味ながらも、エヴァンスの気まぐれのようなソロ渡しや空間創出に対し、メロディアスなソロで応えており、インタープレイがしっかりと行われている。
同年から翌1962年にかけて、イスラエルが参加したトリオと、ハービー・マンとの連名で『ニルヴァーナ』(Nirvana)を録音し、1964年に発表となった。
1962年、ギタリストのジム・ホール(Jim Hall)とのデュオでアルバム『アンダーカレント』(Undercurrent)をリリース。
この時期の収録作として、“Polka Dots And Moonbeams”を収録した1962年『ムーンビームス』(Moon Beams)、1962年『ハウ・マイ・ハート・シングス』(How My Heart Sings!)などが挙げられる。
1963年、ヴィレッジ・ヴァンガードでの演奏時、右手の神経にヘロインの注射を刺してしまったため右手がまったく使えず、左手一本で演奏をこなすという事件が発生。これを機にヘロインをやめることになったとされるものの、一時的な断薬には成功しても、晩年まで薬物との縁は切れなかった。
1965年、アルバム『Trio '65』をリリース。
1966年、エヴァンスは、当時21歳のエディ・ゴメス(Eddie Gomez)を新しいベーシストとしてメンバーに迎える。若いながら高いテクニックを持ち、飛び込むかのように音の隙に入ってくる積極性を持つゴメスは、ラファロの優れた後継者となる。以降、ゴメスは1978年に脱退するまでレギュラーベーシストとして活躍し、そのスタイルを発展させ続ける。
同年、ギタリストのジム・ホール(Jim Hall)とアルバム『Intermodulation』を録音。"Turn Out the Stars"、"Angel Face"、"Jazz Samba"など佳曲ぞろい。
1967年、ソロ・アルバム『Further Conversations with Myself』をレコーディング、"Emily"を収録。
1968年、ソロ・アルバム『アローン』(Alone)を発表。グラミー賞受賞作品。
同年、マーティー・モレル(Marty Morell)がドラマーとしてトリオに加わり、家族のために1975年に抜けるまで活動した。ゴメス、モレルによるトリオは歴代最長であり、現在に至るも陸続と発掘・発売されるエヴァンスの音源は、このゴメス&モレル時代の音源が圧倒的に多い。このメンバー(セカンドトリオ)での演奏の質は、グラミー賞を受賞した1968年『ビル・エヴァンス・アット・モントルー・ジャズ・フェスティバル』(Bill Evans at the Montreux Jazz Festival)、初期の録音でずっと後に発売された1969年『枯葉』(Autumn Leaves)、1969年ライヴ版『枯葉』(Jazzhouse)にも良く現れており、1969年『"ワルツ・フォー・デビィ"ライヴ!』(You're Gonna Hear From Me)、1970年『モントルーII』(Montreux II)、1972年『Live in Paris, 1972』、1973年『The Tokyo Concert』、1974年『シンス・ウイ・メット』(Since We Met)と、このメンバー最後のアルバムである1974年にカナダで録音した『ブルー・イン・グリーン』(Blue in Green: The Concert in Canada)などがある。この時期、特に1973年 -1974年頃のエヴァンス・トリオは良し悪しは別として、ゴメスの比重が強い傾向にある。
1973年の来日直後、エヴァンスは1960年代前期以来長年内縁関係にあったエレイン(一般にはエヴァンス夫人と見なされていたが、正式には未婚だった)に別れ話を持ちかける。新たに親しくなったネネット・ザザーラと結婚するためで、全くエヴァンスの一方的な意志によるものであった。程なくエレインは地下鉄へ投身自殺した。ゴメスとのデュオ・アルバム『Intuition』収録のピアノソロによる“Hi Lili,HiLo”は、不幸な形で亡くなったエレインに捧げられた名演である。彼はエレインの死に大変ショックを受けたものの、結局はネネットと結婚し、息子エヴァンが生まれている。
1976年、ドラムスはモレルからエリオット・ジグモンド(Eliot Zigmund)に交代。このメンバーでの録音として、1977年2月『クロスカレンツ』(Crosscurrents)、1977年5月『アイ・ウィル・セイ・グッドバイ』(I Will Say Goodbye)、1977年8月『ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング』(You Must Believe in Spring)が挙げられる。
麻薬常習者であり、長年の不摂生に加え肝炎などいくつかの病気を患っていたエヴァンスの音楽は、次第にその破壊的内面や、一見派手ではあるが孤独な側面を見せるようになる。 エヴァンスの死後に追悼盤として発売された『You Must Believe in Spring』収録の“Suicide Is Painless”(もしも、あの世にゆけたら)は、映画『M*A*S*H』(1970年)及びTVシリーズ版『M*A*S*H』のテーマとして知られる曲である。
1978年にゴメスとジグムンドがエヴァンスの元を去る。後任に何人かのミュージシャンを試し、中にはマイルス時代のバンド・メイトでヤク中仲間でもあったドラマーのフィリー・ジョー・ジョーンズ(Philly Joe Jones/1923年7月15日-1985年8月30日)もいた。最終的にはベースのマーク・ジョンソン(Marc Johnson/1953年10月21日-)、ドラムのジョー・ラバーベラ(Joe LaBarbera/1948年2月22日-)に落ち着き、これがエヴァンス最後のトリオ(ラスト・トリオ)メンバーとなった。
1970年代末期のエヴァンスは私生活がまたも荒廃気味となり、ネネットや子どもたちとも別居し、20歳以上も年の離れた若いカナダ人ウェイトレスのローリー・ヴェコミンと愛人関係になっていた。
1979年1月、ラスト・トリオの極めて初期、アイオワ州立大学にて収録されたライヴ映像『Jazz At The MaintenanceShop』における演奏と、非公式録音ではあったが現在公式な形でCD化(総計16枚)されているラスト・レコーディング、キーストン・コーナーにおけるライヴ演奏を比べると、トリオ全体が大きく進化していることが良くわかる。エヴァンスの死の直前まで、彼らは前進し続けたのである。エヴァンス本人がインタビューで語っているように、このラスト・トリオとの演奏がとにかく楽しかったのであろう。
エヴァンス本人のアルバムジャケットなどでは堅く口を結んだ肖像写真が多く使われたが、歯を見せなかったのは、喫煙と麻薬の影響でひどい虫歯になっていたのが一因であると言われている。兄ハリーとの音楽に関する1960年代の対談フィルム動画などでは、対話するエヴァンスの前歯がボロボロの状態であるのが伺える。
1970年代後半のエヴァンスは長年の麻薬常用の影響で、既に健康を大きく損なっていた。彼が1970年代前期以降の晩年、それまでのトレードマークであった堅苦しいヘアスタイルや黒縁眼鏡をやめ、長髪や口・顎の髭をたくわえ、スモーク入りの大きな眼鏡という派手なイメージチェンジを図った背景には、健康を損なったことによる顔面の顕著なむくみを、髪や髭で隠そうとする意図があったと『スウィングジャーナル』元編集長の中山康樹が指摘している。また1978年11月にビレッジ・バンガードでエヴァンス・トリオのライヴを聴いた音楽ジャーナリストの小川隆夫も「彼(エヴァンス)の体が異常にむくんでいることに気付いていた」と記述している。キーストン・コーナーライブ時点でも、演奏時以外での疲労困憊した様子や、通常ではピアノ演奏が不可能と思われるほどに指が腫れ上がる症状が見られた(残された映像や写真によって、60年代にすでにこの手の異常を確認できる)。彼の体調悪化を危惧したジョンソンやラバーベラは、活動を一時休止してでも治療に専念するよう懇請したが、エヴァンスがそれを聞き入れることなく、ピアノに向かい続けた。
1979年、実兄ハリーが動機不詳の拳銃自殺を遂げる。
8月、ハリーの死から4か月後に、エヴァンスは管楽器を加えたクインテットによる『ウィ・ウィル・ミート・アゲイン』(We will meet again)をレコーディング。ピアニストかつピアノ教師であった兄のための作品でもある。
1980年6月、トリオでヴィレッジ・ヴァンガードにおけるライヴ『ターン・アウト・ザ・スターズ』(Turn Out The Stars)を録音しているが、内省的でありつつもよりドライヴした明るい演奏をするようになった。ダイナミックレンジが拡大し、スケールが大きくなっている。しかし一方、時に粗さの目立つことがあり、急速調の演奏とスローな演奏との落差が激しくなっている。これは、常用している麻薬がヘロインからコカインに移ったこととの関係が指摘される。また、兄のハリー・エヴァンスの自殺や家族との別居など、晩年の私生活問題も要因として挙げられる。
9月9日、ニューヨーク市のライヴハウス「ファッツ・チューズデイ」において、同バンド出演初日演奏を行った。既に激しい体調不良に見舞われていたものの、ジョンソンやラバーバラによる演奏中止要請を振り切って、エヴァンスは演奏を続行した。
9月11日、同バンドの開催2日目に、ついに演奏を続行できない状態となり、やむなく演奏を中止し自宅で親しい人達によって3日間にわたり看護された。
9月14日に再度ラバーバラの説得により、ニューヨーク市マンハッタンのマウント・サイナイ病院に搬送された。
1980年9月15日月曜日、ビル・エヴァンスの名で知られたピアニスト、ウィリアム・ジョン・エヴァンスが死去。51歳没。
死因は、肝硬変ならびに出血性潰瘍による失血性ショック死であった。永年の飲酒・薬物使用で、人体の薬物・異物分解処理を司る肝臓に過剰な負担をかけ続けた結末であり、疫学的には周知されている結果であった。肝臓疾患はエヴァンス自身も自覚していた長年の持病と言うべきものであったが、殊に晩年の数年は必要な療養をとろうともせず、死の間際に至るまで頑なに治療を拒み続けた結果病状を悪化させ、死を早めたのだった。
自らが自殺の原因を作った元恋人エレインと、兄弟として仲が良く音楽の面でも絆の深かった兄ハリーの2人の自殺が、晩年のエヴァンスの破滅志向に影響を与えていたとする批評も見られるが、真相は定かでない。
エヴァンスの死の直前に2度に渡り診察を行った医師ジェームス・ハルトは「自分がひどい病気であることを彼は知っていた。(中略)入院を勧めたが応じなかった。彼には生きる意思が全く無いように思えた」と証言している。生前のエヴァンスと親しく、“ワルツ・フォー・デビー”、“ターン・アウト・ザ・スターズ”の作詞者でもあったジャズ評論家のジーン・リーズ(Gene Lees)は、エヴァンスの最期について、「彼の死は時間をかけた自殺というべきものであった」と述懐している。
マーク・ジョンソンによれば、「ファッツ・チューズデイ」で最後にエヴァンスが演奏した曲は、長年の愛奏曲の一つ“マイ・ロマンス”(My Romance)であったという。
2021年、CD5枚組BOXセット『Everybody Still Digs Bill Evans - A Career Retrospective 1956-1980』がリリース。
(参照)
Wikipedia「ビル・エヴァンス」「Bill Evans」