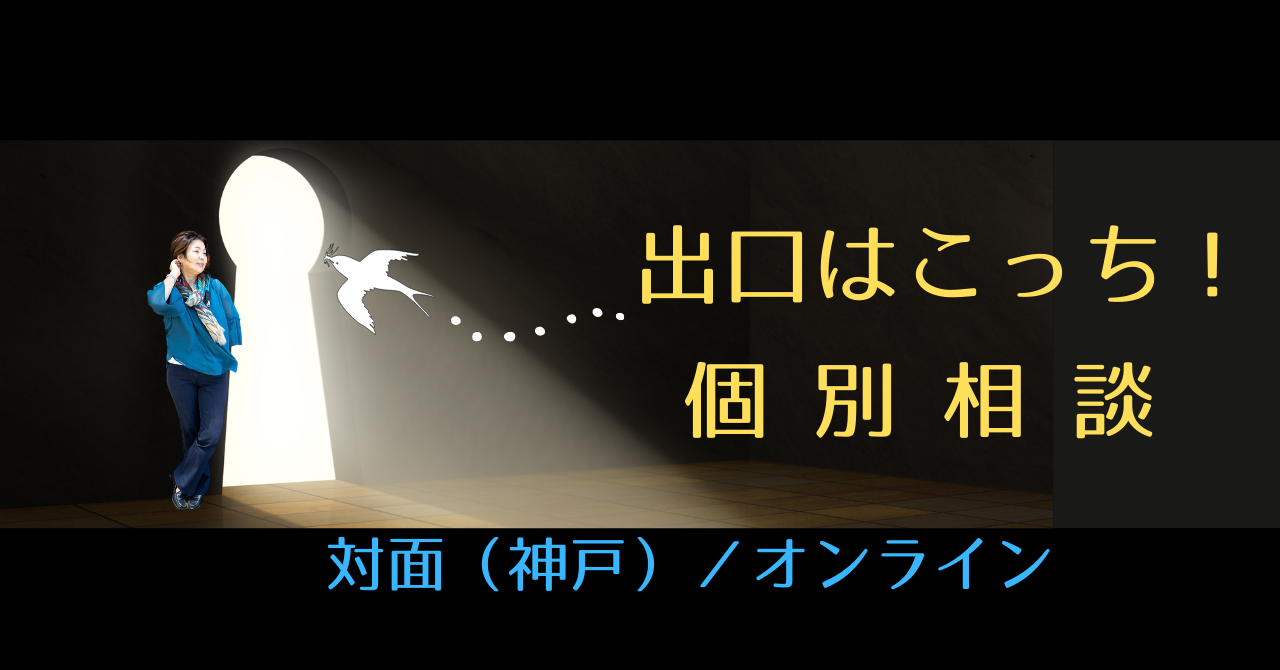【ふつう】にできない息子のおかげで、
しあわせに生きる基準は人それぞれちがうと気づき、
【よそはよそ、うちはうち】と思えるようになりました。
園や学校で、わが子が
集団行動ができず浮いている、なじめていないとか、
他の子たちはふつうにできることができないなどと
お悩みのお母さんへ。
【ふつうの子は…】とか、
【ふつうだったら…】などと、
他のお子さんたちと比べたり
一般的には…という意味合いで
無意識に使うことの多い【ふつう】という概念ですが
そもそも【ふつう】ってどういうこと?
ということを、じっくり考えたことはありますか?
【ふつう】とは、
とびぬけて優秀でもなければ劣ってもいない。
周りと比べて見劣りがしない程度に、最低限に…
そんな意味合いで、【ふつう】という言葉を使うことが多いでしょうか。
私の場合は、
【ふつう】って、
息子が自閉症スペクトラムと知る前は、
幼稚園→小学校→中学校→高校→大学や専門学校→就職…と、
わたし自身や夫が何の疑問も抱かずに歩んできた人生を
【ふつう】だと思っていました。
でも、わたしが【ふつう】だと思っていた
幼稚園でみんな仲良く楽しい集団生活することに適応できず、
苦しむ息子を目のあたりにして、
私が思い描いていた【ふつう】の概念や
子育ての価値観が激変しました。
世の中の大多数の人たちがよしとする生き方が
絶対正しいとは限らない。
【幸せに生きる】方法は、人によって
ちがってもよいのかもしれない。
ならば、私が当たり前のように思っていた
固定観念を取っ払って、
この世の大半の子どもたちが通うであろう
【ふつう】の小学校、中学校、高校…にこだわらず、
息子にいちばん合う場所を、
そのときどきで考えながら、
将来的に「一人暮らしができる自立した大人」
を目指せばよい、と思えるようになりました。
自閉症スペクトラムと診断されて1~2年ほど葛藤する期間を経て
こんなふうに親の覚悟が決まってしまえば
いわゆる「世間体」とか「他人の視線」などに振り回されることなく
「よそはよそ、うちはうち」
と、我が家の場合は、息子の場合は…という観点から
考えられるようになりました。
そして、息子が幸せな大人になるためには、とにかく
息子のメンタルを守ること、
二次障害にならないよう無理をさせないことを
最優先にと考えて育ててきました。
小学1年生の冬に、
ドイツからイギリスへの引っ越しが決まり、
事前にロンドン日本人学校へ行き
息子の特性を伝え、転入の相談をしたさいにも
「環境の変化への適応力の弱さと、
見通しが付かないことへの不安感が強い」息子には
学力よりも情緒面のケアを優先してほしいことを
強調してお願いし、
特別支援学級への入級することになりました。
当時、私達親子がお世話になっていた人たちのなかには、
知能的には境界域だった息子なら
【ふつう】のクラスでもやっていけるだろうに
どうしてわざわざ【ふつうじゃない】進路を選ぶの?
と、私に言ってくるかたもいました。
たしかに、そういう考えで、
多少無理をさせても通常クラスに籍をおく
ケースも多いのかもしれませんし、
それでうまくいくお子さんもいることでしょう。
でも【よそはよそ、うちはうち】を貫いて、
二次障害にならないようメンタルを守るために
息子にとってベストな場所として
特別支援学級を選びました。
大半の子どもたちが通う【ふつう】のクラスとは
ちがう居場所で学ぶこととなりましたが、
あせらず、メンタルを守ることを優先したおかげで、
遅れを心配していた学力面も大きく伸ばし、
小学5年生で帰国後、中学生からは通常学級に籍を移して
高校、大学進学も視野に入るようになりました。