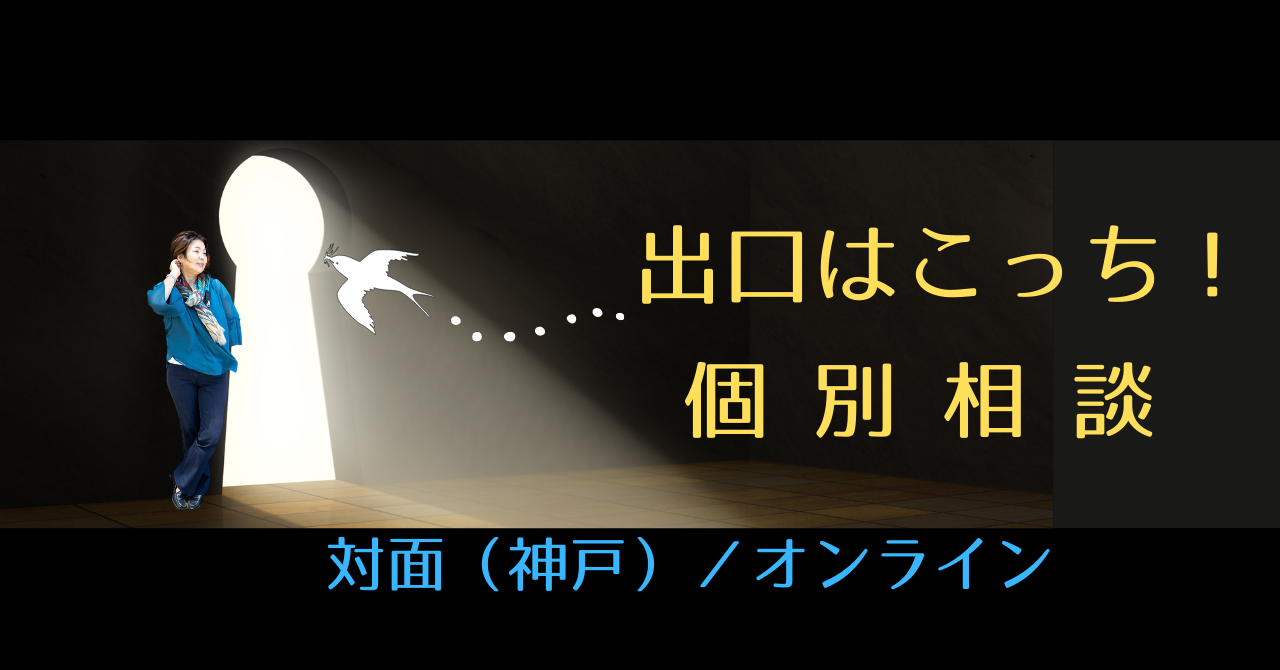様子見期間中のあせりは禁物。
でも、何もせずただ見守るだけでは時間がもったいない。
数か月先、数年先を見とおして、今できることはいろいろありますよ。
お子さんが通っている園や学校の先生や、
行政の子育て支援の相談窓口、それに病院などで
お子さんの発達の遅れやかたよりが心配で相談に行ったときに、
「まだ小さいですし、しばらく様子をみましょう」
と言われたお母さんへ。
【様子見】という言葉を聞き、
あなたはどう感じましたか?
心配だから相談してるのに、
不安だから発達検査を受けたのに、
けっきょく、ハッキリとしたことは何も言ってもらえず、
「成長を待ちましょう」とか
「あせらないで、見守りましょうね」などと
あいまいに言われるだけで、
アドバイスといっても「そんなことは知ってるわよ」
という一般的なことだけ。
不安を解消したくて、勇気を出して相談に行ったのに消えるどころか、ますます大きくふくらむ不安。
けっきょく、お子さんを心配しながらも手をこまねいて文字どおり見守るだけの【様子見】で、
ただ時間だけがすぎていく…。
こんな状況に陥っていませんか?
確かに、子どもはひとりひとり個性があり
成長のスピードどもそれぞれ違います。
だから、あせりは禁物です。
お母さんの気持ちや都合で子どもを追い詰めるような育て方をするのはもちろん良くないことですが、
ただ心配しながら見守りするだけの
宙ぶらりんな状態で半年、1年…と過ごすのは
もったいないですよね。
発達の遅れやかたよりがあるかどうかはっきりしない様子見期間中でも、
お子さんのために出来ることはいろいろあります。
例えば、記録を取ること。
〇歳〇か月時点でどんな遊びが好きか、どんなことが得意で苦手か、おしゃべりの内容などを負担にならない程度にメモしておくだけで十分です。
1か月後、3か月後、半年後、1年後…と時間の経過とともに
お子さんが何が得意で何が苦手なのか、客観的に分かってきます。
心配していたけど、今はできるようになってよかった!とか
心配していたとおり、やっぱりこの子は〇〇は苦手だから対応してあげたほうがよいかもしれないな、など
ばくぜんとアレもコレも心配していたお母さんの頭の中も
何が大丈夫で、何が心配なのかを分けて、少しはスッキリするかもしれません。
そして、その記録こそが客観的な証拠となり、
いわゆる【様子見期間中】が終わり、改めて診断を受けるさいの
判断の材料として大活躍するはずです。
他にもいろいろとできることはあります。
それはまた別の記事にて。