今日も江戸時代の健康書『養生訓』に
ならった晩ごはんです☺️
061
魚は生で食べると消化しやすい
ということでお刺身を。
📍『養生訓』 貝原益軒著
超訳なので、
江戸時代に書かれた古典といっても
とても読みやすい👏
1ページにつき
1、2行、長くても4行ぐらいと
簡単な言葉で簡潔に、
健康のひとことアドバイスが書かれています。
装丁もおしゃれ。
さらにこの超訳の面白いところは、
京都大学医学部を卒業した
内科医の
奥田昌子先生の編訳であり
現代医学の裏付けが
注釈されているところ。
生の魚が消化しやすいというのにも
科学的な根拠があるとか。
さまざまな魚料理の消化時間を調べたら、
🥇生魚・煮魚
がもっとも消化しやすく、
🥈次に焼き魚、
益軒がNGを出す
魚の塩漬けは飛び抜けて消化が悪かったそう。
そして
魚に添えたサラダは
062
硬い野菜は薄く切って調理する
に従ってみました。
サラダなので加熱調理はしなかったけど、
硬い野菜の大根を薄く切りました。
奥田先生の注釈によると、
食物繊維の多い食品は
胃で消化するのに時間がかかるため
繊維の走り方をみて
繊維が短くなる方向で薄切りにと。
本書の著者
貝原益軒(かいばら・えっけん)は、
病弱な子どもでした。
自分の体で実験するように
この養生術をつらぬき、
すべての人がそうなわけではないと
ことわったうえで、
この言葉のとおり
003
長生きできるかどうかは心がけ次第
江戸時代としては
相当長生きな83歳の大往生。
しかも亡くなる
前年に『養生訓』を書き上げています👏
どんなことが書かれているのでしょうか。
目次の一部です。
内容は、腹八分目など
昔からよく言われることから、
今夜の夕食でならったように
硬い野菜や消化の良い魚の食べ方などの
具体的な話も。
👆撮影した後の立派なシイタケはバター炒めに☺️
また、最近注目され始めた気象病や、
ストレスを溜めない
心の持ちようなどのアドバイスもあります。


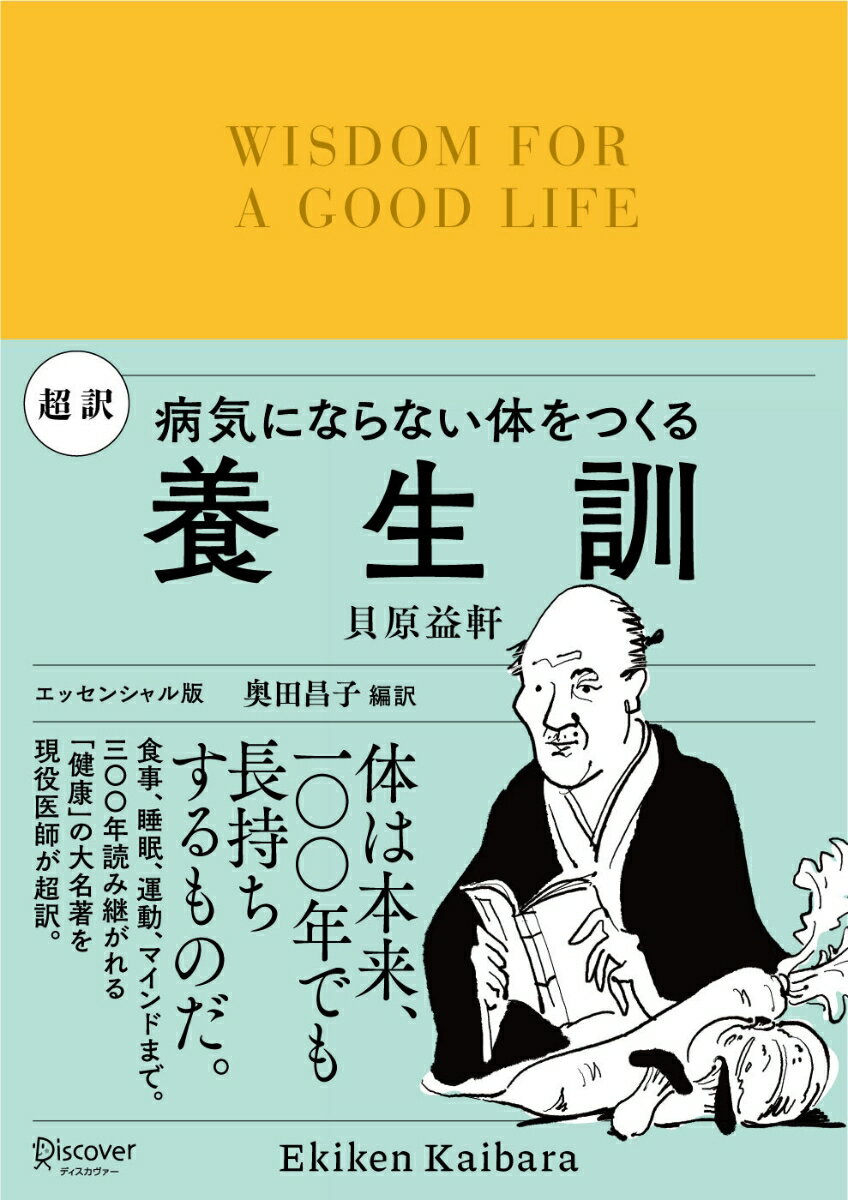




![超訳 養生訓 病気にならない体をつくる [ 貝原益軒 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9924/9784799329924_2.jpg)




![美的スペシャル2024年6月号 [雑誌] 「美的6月号 付録違い版」](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0640/4910100090640_1_2.jpg)
![美的スペシャル 2024年6月号 付録違い版 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/513vfq6sMhL._SL500_.jpg)
![美的 2024年 6月号 増刊 [雑誌] 「美的6月号増刊 SPECIAL EDITION」](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0649/4910074440649_1_2.jpg)