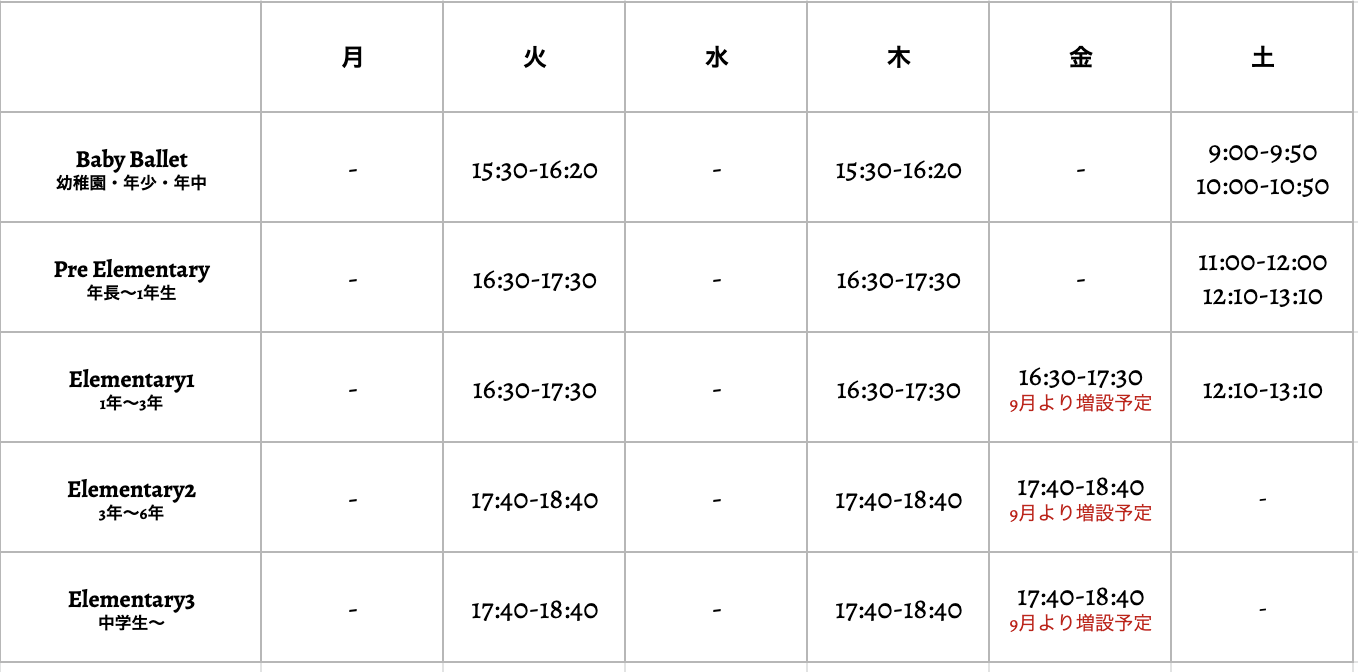こんにちは、池上校講師の木村美那子です。
体験レッスンが続くとなかなかお写真が撮れないのですが、子どもたちは変わらず賑やかにレッスンをしています。
いつでもスムーズに行くとは限りませんし、子どもたちの気持ちの在り方も、その日その日で変わりますから、その中でより良いレッスンを「みんなで」作り上げていきます。
それは「大人の都合」で行うものではなく、子どもたちが「自分事」として体験することに意味があるためで、それらがゆくゆくの「自発的な行動」や「自主性」などを育てていく栄養分となっていきます。
もちろん気持ちの面だけでなく、身体の成長においてもレッスンの中で実施される様々なワークが子どもたちの栄養分になるように、バレエのワークに限らず、必要に応じて取り入れています。
みなとシティバレエ団附属バレエスクールでは、より良いレッスンを提供するために各校共通のレッスン内容がクラスごとに設定されていますが、これも「そのレッスン内容を実施する」ことがゴールではなく、そのワークを実施することで生徒の皆さんが身体性や運動性を身に付けることが目的であり、それが最終的に舞台で踊ることにつながっていくのです。
ですから、そのために必要な「バレエ以前」の動きもおろそかにすることはありません。それがたとえ「遠回り」に見えたとしても、「手間」のように感じられたとしても、そこで焦らずぐっとこらえて繰り返すことが大切なのです。
たとえば近年では子どもたちが成長の過程でハイハイなどの四つん這いをする時間が短いことが問題視されていますが、これは感覚器である手のひらへの刺激が少なくなってしまうこと、自分の胴体を支える体幹の筋肉が弱くなってしまうこと、体幹への刺激が不十分なまま立位へ移行してしまうと骨や関節への垂直方向への負荷が高まってしまうこと、背骨のカーブや動きやすさの獲得が不十分になってしまうこと…などがあげられます。
さらにバレエでは基礎訓練においてバーに掴まってのワークが実施されますが、バーと身体との位置関係は四つん這いでの床と身体の関係とほぼ同じく、またアームスのポジションとして大切な「アンナヴァン(アン・アヴァン=前方に、の意)」、「1stポジション」にもつながります。
誰が見ても分かりやすいバレエ、目に見えるバレエの背景には一見分かりにくいもの、目に見えないくらい微かなものの積み重ねがあります。
特に10年前よりも子どもたちの身体能力に環境格差、経験格差があらわれている昨今、バレエのムーヴメントと子どもたちの身体をしっかりとつなげるためには、バレエ教師である講師たちも「バレエ以前」にしっかりと目を向けて、レッスンに取り組む必要があると改めて感じています。(木村)