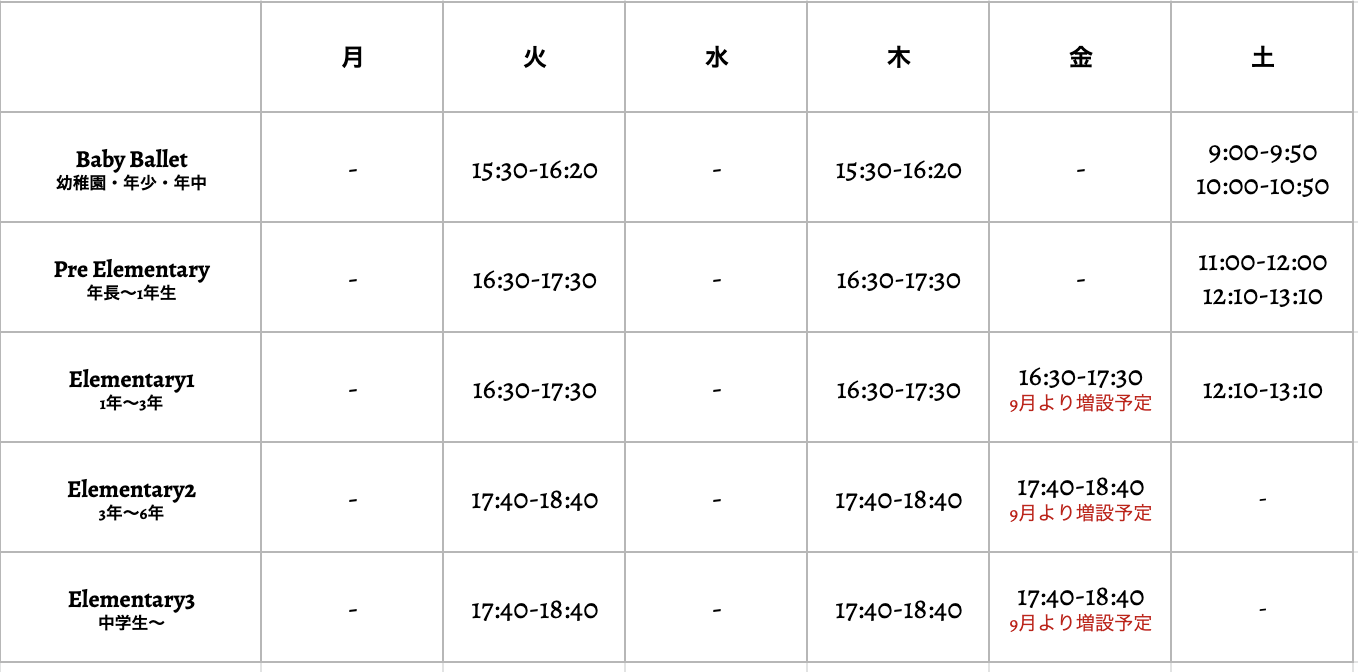こんにちは、池上校講師の木村美那子です。
前回の投稿を見て、白い布地をカットしていたものがお衣裳の胴体部分「ボディ」にあたるものだとすぐに分かった方は、どのくらいいらしたでしょうか?
今回はその白い生地を大まかではありますが、ボディの形にまとめていく様子をご覧いただきます。
あの白い生地は裏地ですので、あの布地に表地の布を貼り合わせていくところから始まります。
ここでポイントなのは、市販されている布地の「裏側」を使うということ。
バレエのお衣裳を作製する場合、基本的にはサテン地を表地として使いますが、あまりにてかてかしたり、照りが強いものは、生地に重さが無い場合、特に品が良く見えないので、木村としては好ましくありません。
そこでサテン地の裏面をもってくることで、ほどよい光沢もありながら、生地に重さのあるような印象を持たせることが出来るのです。
ちなみに木村は昔ながらの重たいお衣裳や、ボディにワイヤーなどの芯が入っている、いわゆる「着づらい」お衣裳が嫌いではありません。
それは、はるか昔の貴族たちが美しさのために苦労をして着こなしていた重たいドレスなどを想起させてくれるからかもしれません。
かつて、宝塚歌劇団で「ベルサイユのばら」という作品を初演した際に、指導に入られた故長谷川一夫氏が「演者が苦しいほど、美しい様子があらわれる」と言ったように、(もちろんパフォーマーとしては出来るだけの障害は取り除きたいと思ってしまいますが)多少の足かせがあった方が、品や重みのある、振る舞いや踊りが出来るのでは無いでしょうか。
さて、サテン地と裏地を合わせたら、それぞれのパーツがほつれないように、ぐるりとその縁を縫い合わせて、かがっていきます。
お客様に見えない部分ですが、着心地の面からも、きちんと「始末をつける」ことが大切です。
そして各パーツを縫い合わせ、また全体の縁を織り込んで、かがった部分が見えないように、毛羽立ちや糸のほつれが見えないように始末をつけて、大まかなボディが完成します。
ここに着る人の体格に合わせて肩ひもを付け、背中を留めるホックとそれを引っ掛けるループ(ムシとも言います)を付けていきますが、それで終わりではありません。
着る人に合わせた微調整や、華やかに見せるためのデコレーションを施していく様子は、また次の回でお伝えしていきますね。(木村)