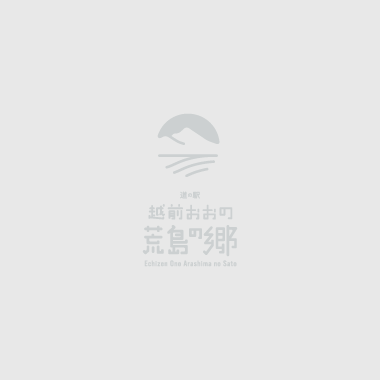#03産業振興
福井県の東の玄関口として、また九頭竜川の最上流域に位置する大野市が自治体として生き残るためには市税などの収入を確保して、その中からそこに住む市民の福祉向上につながる施策へ投資することで、住み続けてもらうことが大切です。森林や河川、農地などすべてのまちの資産を守っていかなければならず、その環境に憧れ、住み続けたいと思う市民を増やすためにどうするのか知恵を出していかなければいけないと思っています。
新たな産業を育成したり今ある産業の価値を高めたりしていかなければ地域間競争には勝てません。素晴らしい移住や定住施策を並べても、市民が住み続けるために優しく受け入れる体制がなければ、人の心を動かすことはできません。そこに住む人の魅力も大切な要素です。
新たな産業の育成については、人口減少が続く中であっても時代の変化に対応して取り組みを続ける企業との連携が必要です。脱炭素・ゼロカーボン一つにしても、元々自然を大切に守り受け継いできた大野市のアイデンティティ(同一性)を理解して取り組もうとする企業の誘致やその地区・集落で自立していくための再生可能エネルギーの導入なども求められています。
※手前が『荒島ポーク』。4月に開駅した大野市道の駅・越前おおの荒島の郷で購入できるほか、市内の複数店舗でのメニュー化を進めています。購入時に道の駅で発信するなど、大野市に来て味わっていただけるような仕掛けを政策提案していきます。
また、今ある産業は付加価値をいかに創造するか、そこをウリにどう大野市へ誘客を図りブランド化していくかといった視点で官民連携が求められます。名水で育てられたお米や野菜などの農産物、九頭竜まいたけなど特用林産物、奇跡の豚と言われる荒島ポークや酪農などの畜産において生産された商品にどれだけの価値があり、さらにどう価値を高められるか。そこに、地球温暖化防止の観点からも、農林業の役割は非常に重要であり、できる限り地元で生産されたものを地元で加工・調理して提供する地域内経済循環の仕組みが必要です。
名水のまち・大野市を訪れていただき、その価値をさらに向上していけるよう生産者と販売・加工事業者の連携、消費者へ訴えかける官民連携の効果的な発信など、チーム大野市で考え、提案していきます。
※地元で採れた旬を味わえるJR越美北線終着駅・九頭竜湖駅前、道の駅九頭竜向かいで毎週水曜日限定で提供される『より処』ランチ。この品数、味わい、ボリュームで500円ワンコインは贅沢すぎます。これはもっと価値を高めていけるよう議論していきます。