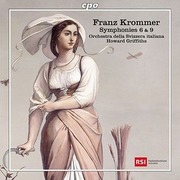今回紹介したいのは、フランティシェク・ヴィンツェンツ・クラマーシュ(František Vincenc Kramař)の交響曲シリーズ第3集 ハワード・グリフィス&スイス・イタリア語放送管弦楽団。
クラマーシュは一般的にはドイツ名で フランツ・クロンマー と表記されていますので、ここでもクロンマーと表記します。
クロンマーは、モーツァルトが生まれた三年後の1759年ボヘミア生まれ、親戚にヴァイオリンと作曲の手ほどきを受け、ハンガリーで活躍していました。
1785年にウィーンに行き、シュテュルム伯爵の宮廷に仕えていたのでモーツァルトやハイドンと交流があったものと思われます。
1790年から1795年までハンガリーに戻り、ペーチ大聖堂の教会楽長に就任。その後はカーロイ連隊楽師長やグラサルコヴィチ侯の宮廷楽長を歴任。
1810年からは、『後宮からの誘拐』、『フィガロの結婚』、『コジ・ファン・トゥッテ』、ベートーヴェンの交響曲第1番の初演会場が行われたことで有名な「ウィーン・ブルク劇場」の楽長を務め、1818年に皇室専属作曲家となりました。
その作品はハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンの影に隠れてしまって存在自体すらも忘れられてしまいましたが、20世紀後半から再発見され、管楽器のための協奏曲や管楽合奏曲などの録音が増えていきました。最近は特に録音が多くなってきています。
作品はまだ研究途中らしいですが、300曲以上の作品を残し、そのうち100曲以上の弦楽四重奏曲、13曲の弦楽三重奏曲、30曲の弦楽五重奏曲、ヴァイオリン協奏曲、オーボエ協奏曲、クラリネット協奏曲などが10曲あまり、7つの交響曲に管楽器のためのパルティータ、ミサ曲などの宗教曲があるとされます。なかでも管楽器のための作品が良く知られています。
クロンマーの交響曲録音は珍しく、CHANDOSからバーメルト/ロンドン・モーツァルト・プレイヤーズの「モーツァルトと同時代の音楽シリーズ」として交響曲第2番、第4番が聴けましたが、ドン・ジョヴァンニ序曲のような序奏、ハイドン交響曲のような第二楽章など聴きごたえありましたし、第4番などのオーケーストレーションは見事で、お気に入りの一枚でした。
cpoというレーベルではクロンマーの交響曲全曲録音シリーズを2014年から開始、ハワード・グリフィスとスイス・イタリア語放送管弦楽団の演奏は、すっかり忘れられてしまったクロンマー作品を丁寧に演奏、現代によみがえらせています。
第3集は 交響曲第6番&第9番。
フランツ・クロンマー: 交響曲第6番&第9番
ハワード・グリフィス 、 スイス・イタリア語放送管弦楽団
失われてしまったとされる第8番を除き、これで全曲録音が完成となります。
すごいです。
生きている間にクロンマーの交響曲を全部聞けるとは思いもしませんでした。
全曲を通しての感想です。
第1番は古典派の典型的交響曲で、ハイドンの影響が大きいかな、と思いますが、第2番~第4番へと段々とドラマチックな展開と管弦楽法が駆使されていきます。
第5番では、やや時代が戻った感じで、モーツァルトの第39番と酷似した音色、ハーモニーが聞かれます。
ここからです。
第2集で聴いた第7番、そして今回の第6番と第9番ですが、オーケストレーションの派手さや、軍隊行進曲的華やかさが見られますが、全曲を通すと没個性的で、第4番などがわくわくさせた展開だったことを思うと、とても普通の古典派の交響曲に戻ってしまっています。もともと管楽器の室内楽や協奏曲に美しい旋律を散りばめた作品を多く残しているクロンマーにしては、主題も展開も弱いです。
もちろん、駄作ではないのですが、クロンマーの交響曲が素晴らしいと思っていた私にとっては、第1番から第5番までが重要かつ今後もよく聞く作品ということになるでしょう。
第1集・第2集のレビューもご参照ください。