本来はlivedoorブログで書いているような内容ですが、今違うシリーズ原稿続けているので、こちらで。
さてクラシックの作曲家:Franz Krommer(フランツ・クロンマー)の交響曲の紹介です。
クロンマーの正しい氏名は、フランティシェク・ヴィンツェンツ・クラマーシュ(František Vincenc Kramař)です。
クラマーシュは一般的にはドイツ名で フランツ・クロンマー と表記されていますので、ここでもクロンマーと表記します。

クロンマーは、モーツァルトが生まれた三年後の1759年ボヘミア生まれ、親戚にヴァイオリンと作曲の手ほどきを受け、ハンガリーで活躍していました。
1785年にウィーンに行き、シュテュルム伯爵の宮廷に仕えていたのでモーツァルトやハイドンと交流があったものと思われます。
1790年から1795年までハンガリーに戻り、ペーチ大聖堂の教会楽長に就任。その後はカーロイ連隊楽師長やグラサルコヴィチ侯の宮廷楽長を歴任。
1810年からは、『後宮からの誘拐』、『フィガロの結婚』、『コジ・ファン・トゥッテ』、ベートーヴェンの交響曲第1番の初演会場が行われたことで有名な「ウィーン・ブルク劇場」の楽長を務め、1818年にウイーン皇室専属作曲家となりました。
この時期がどういう時期かというと、40歳になっていたベートーヴェンは既に6番までの交響曲を発表し、ピアノ協奏曲全5曲完成、発表された後のこと。押しも押されぬ巨匠としてヨーロッパ中に名を轟かせていた。
フンメルはエステルハージ宮廷の楽長の職を辞し、再びウィーンに戻ったのが1811年。それでも今知られるようなピアノ演奏のヴァルトォーゾではなく、ピアノの公演も行っていない。おもな作品はピアノ曲、室内楽曲、劇音楽の作曲家として大いに活躍していた時期である。
クロンマーの作品はハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンの影に隠れてしまって存在自体すらも忘れられてしまいましたが、20世紀後半から再発見され、管楽器のための協奏曲や管楽合奏曲などの録音が増えていきました。最近は特に録音が多くなってきています。
作品や生涯についてはまだ研究途中らしいですが、1831年に亡くなるまで300曲以上の作品を残し、そのうち100曲以上の弦楽四重奏曲、13曲の弦楽三重奏曲、30曲の弦楽五重奏曲、ヴァイオリン協奏曲、オーボエ協奏曲、クラリネット協奏曲などが10曲あまり、7つの交響曲に管楽器のためのパルティータ、ミサ曲などの宗教曲があるとされます。
さて、今回紹介するのは交響曲集。
クロンマーの交響曲録音は珍しく、1990年代後半から2000年代初頭にシリーズ化されたCHANDOSのバーメルト/ロンドン・モーツァルト・プレイヤーズによる「モーツァルトと同時代の音楽」の1企画としてとして「交響曲第2番、第4番」が聴けましたが、初めて聞いたときからドン・ジョヴァンニ序曲のような序奏、ハイドン交響曲のような第二楽章など聴きごたえありましたし、第4番などのオーケーストレーションは見事で、お気に入りの一枚でした。
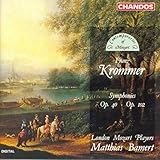 | Krommer: Symphonies Nos. 2 and 4 1,500円 Amazon |
今回紹介するのはCPOレーベルからリリースされている交響曲第1集(1番~3番)、第2集(4番、5番、7番)です。
6番だけ無いのですが、クロンマーの交響曲を買おうと思うマニアックな人間が世界に何人いるだろうか?と考えると、赤字覚悟で録音してリリースしたcpoには拍手です。
個人的にクロンマーの交響曲や協奏曲は、モーツァルト的な管弦楽手法とハイドン的なテーマや展開が見受けられ、同時代の作曲家の中では「もっとも好きな作曲家のひとり」です。
フンメルは交響曲を書きませんでしたが、彼の管弦楽序曲などと似ている雰囲気を持つ第一楽章、ハイドン的な全管弦楽で演奏される元気な第二楽章、モーツァルト的でありウイーン的である舞曲の第三楽章、たまに見え隠れするベートーヴェンの第1交響曲的な部分....などなど、古典派好きの方なら気に入ること請け負います。
ハワード・グリフィス(指揮)/スイス・イタリア語放送管弦楽団
クロンマー/交響曲集第1集
 | フランツ・クロンマー:交響曲集 第1番-第3番 1,290円 Amazon |
クロンマー/交響曲集第2集
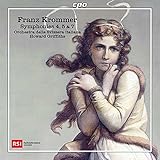 | クロンマー:交響曲集 第2集 2,583円 Amazon |