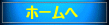明治~平成【値段史】素晴らしい!待っていました!Ⅺ【終】1…
付2. はしりの値段 (⇒ページトップ)
参考文献
(A1)週刊朝日編、「値段史年表 明治大正昭和」、1988 および「戦後値段史年表」、1995
(H1)本間立志監修、「日本経済統計集」、日外アソシエーツ、1999
(I1)岩崎爾郎、「物価の世相100年」、読売新聞社、1982
(I2)岩波書店、「岩波日本史辞典」、1999
(K1)角川書店、「角川日本史辞典」、1966
(K2)厚生労働省、「賃金構造基本統計調査」
(K3)国税庁、「民間給与実態統計調査」
(K4)「公共料金の推移」
(M1)文部科学省、「学校基本調査」および「文部省年報」
(N1)日本銀行の統計データ
(N2)内閣府、「主要耐久消費財等の普及率(一般世帯)」
(S1)総務省統計局、「日本長期統計総覧」、日本統計協会、昭和63
(S2)総務省統計局、「東京都区部の小売物価統計調査」
(S3)総務省統計局、「家計調査年報」
(Y1)矢野恒太記念会、「日本の100年」
(T1)東洋経済新報社、「明治大正国勢総覧」、昭和2
(T2)東洋経済新報社、「日本近現代史辞典」、1978
(T3)東京都の統計データ
(T4)東洋経済新報社、「昭和国勢総覧」、1991
(T5)✖貴金属のホームページ
(T6)東洋経済新報社「長期経済統計」、昭和63
(Y1)矢野恒太、「日本の100年」
(Y2)吉川弘文館、「明治時代史大辞典」、2013
(W1)Wikipedia
(Z1)造幣局、「造幣局百年史」、昭和49
その他
2015.1.3 / 2015.7.25 「庶民には縁遠い数字」を追加。 / 2015.7.30 「はしりの値段」を追加。 / 2016.7.12 「娯楽(戦後)」を追加
/ 2016.7.23 「公共料金」を追加。
その他、都度更新
- 必ずしも厳密な意味での本邦初の値段とは限りません。 いわゆる”はしり”の値段とお考えください。
明治初期には、江戸時代の貨幣単位が使われることがありました。
金1両=金4分(ぶ)=金16朱=1円。 金1分は25銭、金1朱は6.25銭。
銀1匁=銀10分(ふん)=銀100厘=60分の1円。 銀1匁は1.67銭、銀1分は1.67厘。
銭1貫=銭1000文=10銭。 銭100文は1銭。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
(A1)週刊朝日編、「値段史年表 明治大正昭和」、1988 および「戦後値段史年表」、1995
(H1)本間立志監修、「日本経済統計集」、日外アソシエーツ、1999
(I1)岩崎爾郎、「物価の世相100年」、読売新聞社、1982
(I2)岩波書店、「岩波日本史辞典」、1999
(K1)角川書店、「角川日本史辞典」、1966
(K2)厚生労働省、「賃金構造基本統計調査」
(K3)国税庁、「民間給与実態統計調査」
(K4)「公共料金の推移」
(M1)文部科学省、「学校基本調査」および「文部省年報」
(N1)日本銀行の統計データ
(N2)内閣府、「主要耐久消費財等の普及率(一般世帯)」
(S1)総務省統計局、「日本長期統計総覧」、日本統計協会、昭和63
(S2)総務省統計局、「東京都区部の小売物価統計調査」
(S3)総務省統計局、「家計調査年報」
(Y1)矢野恒太記念会、「日本の100年」
(T1)東洋経済新報社、「明治大正国勢総覧」、昭和2
(T2)東洋経済新報社、「日本近現代史辞典」、1978
(T3)東京都の統計データ
(T4)東洋経済新報社、「昭和国勢総覧」、1991
(T5)✖貴金属のホームページ
(T6)東洋経済新報社「長期経済統計」、昭和63
(Y1)矢野恒太、「日本の100年」
(Y2)吉川弘文館、「明治時代史大辞典」、2013
(W1)Wikipedia
(Z1)造幣局、「造幣局百年史」、昭和49
その他
2015.1.3 / 2015.7.25 「庶民には縁遠い数字」を追加。 / 2015.7.30 「はしりの値段」を追加。 / 2016.7.12 「娯楽(戦後)」を追加
/ 2016.7.23 「公共料金」を追加。
その他、都度更新