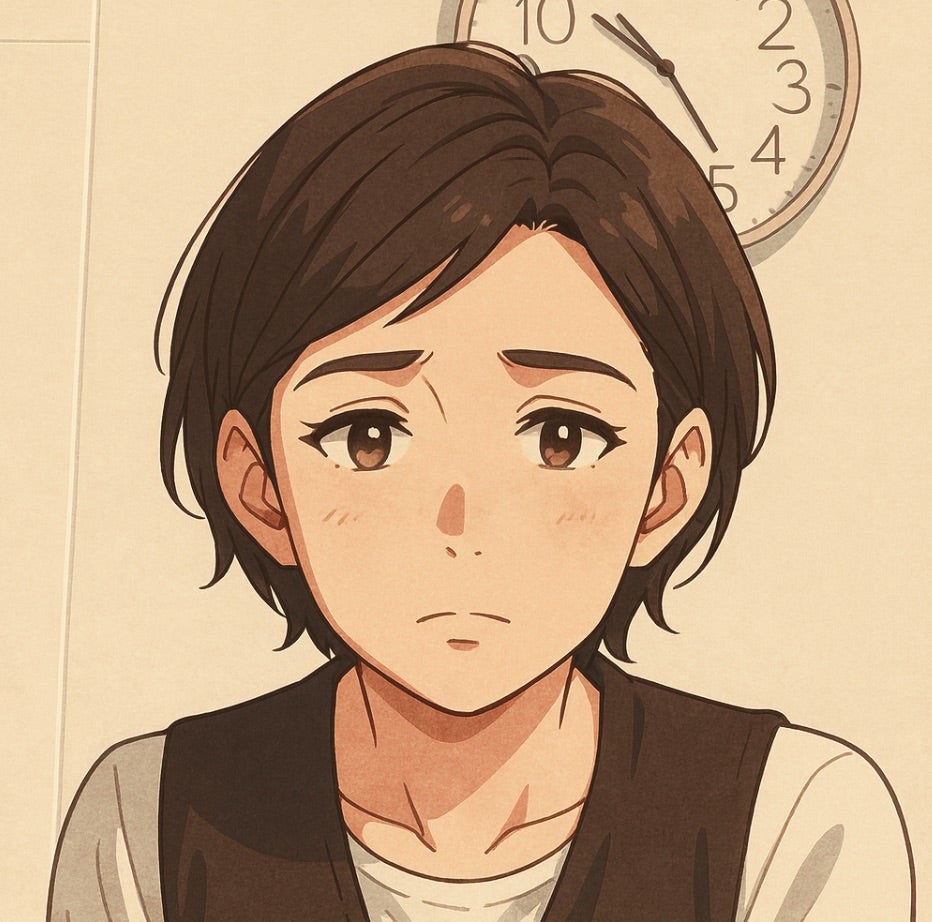前の記事はこちらから
HSS型HSP×アダルトチルドレンが、
人の顔色を過剰に伺ってしまう理由を
【HSS型HSPの愛すべき個性】から解説していきます。
中学1年生の息子が身長が伸びて、
制服のズボンの丈が短くなり、
丈をなおしてもらおうと
制服屋さんに行ったときのことです。
いつもニコニコしている店長さんに
「丈のお直しをお願いしたい」と声をかけた瞬間、
初めて見る、ものすごく機嫌が悪そうな表情。
その一瞬で思わず身体がビクッと反応してしまいました。
頭の中には、ほぼ同時にこんな考えが浮かびます。
-
お店に行くタイミングが悪かったかな?
-
丈直しなのに、そのまま測れるように制服のズボンを履かせて行ったのはまずかった?
-
言い方が嫌な感じだったかも?
ほんの一瞬の出来事なのに、
自分の言動を総点検するスイッチが一気に入りました。
丈出しをする長さを測って、
息子が持ってきた私服のズボンに履き替えている間は
ずーっと頭の中がグルグルと、
私何か悪いことしたかな?と
考えが止まりませんでした…。
その後、お直しを出す伝票を書く頃には
店長さんはいつものニコニコした表情に戻っていました。
それでも、なぜか「怖かった」という感覚だけが残ってしまいました。
帰りの車の中で、運転中に
「自分が何かしたわけでもないのに自分が原因かもしれないと考えてしまうのが、いつものパターンだな」
と、ふっと浮かんできました。
もしこれが、非HSS型HSPの夫だったら
おそらく、気にも留めない出来事だったと思います。
でも、HSS型HSP×アダルトチルドレンの場合、
ここにははっきりした理由があります。
① HSS型HSPの「高感度センサー」
HSS型HSPは、
-
人の表情の微細な変化
-
声のトーン
-
空気の揺れ
を、無意識レベルでキャッチします。
「気にする」という前に、すでに気づいてしまっている。
いつもと違う表情は神経にとっては「環境の変化」。
この感度の高さ自体は、欠点ではありません。
② アダルトチルドレン由来の危機回避回路
そこに、アダルトチルドレンの影響が重なります。
幼少期、
-
大人の機嫌で空気が変わる
-
不機嫌=何かが起きる前兆
という環境にいた場合、神経は学習します。
「相手の機嫌を読むこと=安全確認」
そのため、
-
相手が不機嫌そう
→ 自分の行動を即チェック
→ 原因が自分にないか探す
という流れが、反射レベルで起こる。
これは性格ではなく、
長年の経験で身についた生存戦略です。
③ 「自分が悪かったのかも」と考えてしまう仕組み
この2つが重なると、
-
表情の変化にすぐ気づく(HSS型HSP)
-
不機嫌=危険信号として処理される(AC)
-
自分が原因かもしれないと内省が始まる
という構造が自動的に動きます。
実際に原因があるかどうかは、関係ありません。
神経は「確認せよ」という命令を出しているだけなのです。
以前の私だったら、
家に帰ってからも何度も同じ場面を思い出し、
頭の中で延々と再生していたと思います。
でも今回は、
「これは、私のいつもの反応パターンだな」
と、帰りの車で気づいて、落ち着くことができました。
●まとめ
HSS型HSP×アダルトチルドレンが
人の顔色を伺ってしまうのは、
-
感受性が高いからでも
-
気にしすぎな性格だからでもなく
そうやって生きてきた、いつも通りの神経の反応の仕方の名残です。
そして今、「またいつもの反応が出ているな」と
少し距離を取って見られるようになったなら、
それは神経が回復してきている証拠。
ただ、とても長い間、
他人の顔色を伺って気を張って生きてきただけなのです。
つづきはこちらから