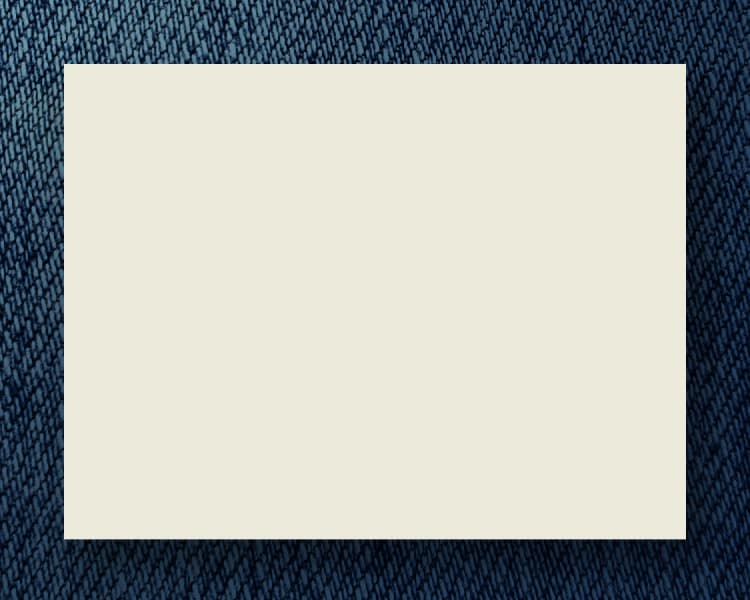誘蛾灯に夜が集う。
あのひとは悪い人。薄い唇の間から嘘ばかりこぼす。あの嘘にはまって、わたしは沼の底、今も抜け出せずにもがいている。
夜が満ちて、指先まで浸して、何をしようとわたしの勝手。だけど、満ちる夜の細々とした節目にぽつり、あのひとがこぼした内なる呟きが、今でもわたしの脳みそをかき回すのだ。
どうしてそんなことができるのだろう。あのひとの癖。
しなやかな手が伸びてきて、わたしを未来に引き抜こうとする。あのひとの見る未来にわたしはいないくせにね。
溜まった洗濯物を洗濯機に放り込んで、自立した気になっている。窓を拭く。思考した気になる。
一歩も進んでいないことはわたしが一番わかっている。
あの長い指の先にわたしがいたこと、白い手の甲にわたしの手が、手のひらが、重なったこと。覚えている。覚えているのだ。
身を委ねて、それはもう寄り添い合うというよりはわたしの一人芝居だったけれど。あのひとは確かに言ったのだ。
「忘れないでいて」
覚えたての歌を口ずさむように、軽薄に。
やさしい手を、拒んだ。あの日のわたしは。今ここにいるのに、あの日はどこにもいなかったのだ。
熱がある気がする。
夕枯れの街を背にソファにもたれかかって、手緩いファッション誌のページをめくる。髪の長い女が笑っている。ここでも、あそこにも。
死にかけの西日に照らされた頬は物憂げで、涙の一つでも流しそうな気配がしていた。男は剥がれ落ちた鱗をまた体に貼りつけるように服を着て、何も言わず、出て行った。わたしばかり目で追って、男のぶ厚い背中が目に焼きついた。
記憶の根は深く深く、心臓にまで達して、手折ることはすでにできない。わたしの少しばかりの知性を引き合いに出しても、それは敵わない。
あのひとの影を、匂いを、皮膚の冷たさを、こぼれた言葉を、掬い取れなかった痛みを、記憶は鮮明に紡ぎ出す。瞼の裏に浮かび上がる真白い月のような、ゆらゆらと水面で揺れる月のような、海底には届かないか弱い月の光のような。そんな曖昧さをもって、鮮明だ。
今日も会えなかった。ここに来る男たちは皆、不満と不義と不名誉を抱えて道のただ中に立っている。花束を抱きかかえるように、幼子をあやすように、男たちはわたしを撫でる。それはつまり、あのひとの残骸だった。
部屋にさっきの男の苦い香りが残っている。煙草を吸う人なのだろう。銘柄を嗅ぎ分けようとして、わたしは煙草が嫌いなのだと思い知る。
「煙草なんて、ね」
低い声はそう言った。覚えないほうがいいんだよ。君はそのままでいて。
純真なまま、無垢なまま、素直なまま。年を重ねられるはずがない。わたしを勘違いしないで。決めつけないで。あなたの思うわたしは遠い闇の彼方、距離も手触りもわからなくなるほど遠くの、幻。
西日は街の向こう側へ落ち、緩やかな夜が滑り込んでくる。男は今頃、電車にでも乗っているのだろうか。歪みを縫うような線路の上を、男を乗せた箱はひた走る。家に着いたらきっと、妻と娘が出迎えるのだ。ただいまを言える家族、あたたかい部屋。結露した窓ガラスが咽び泣くのも知らないで。
想像する。明日、ここへあのひとがやって来る。素知らぬ顔で、わたしは紅茶を入れてやる。いつわたしに気づくのかと鼓動を高鳴らせながら。
それから、短い会話を二、三する。そこに意味はなくとも、あの日に置いてきた言葉をわたしは投げかける。あのひとの胸の内に届くよう、十年の歳月をかけてしたためた、しっとりと熟成された言葉を放つ。
わたしの裸体を見て、あのひとは気づくのだ。ひさのちゃん、と唇が動く瞬間を、わたしは心待ちにしている。
部屋が夜に染み渡ったから、カーテンを閉めた。原石のような街灯が目の端で光った。
九時にまた別の男が来る。あの男はいつも早めに来るけれど、それでも二時間は眠れる。仮眠ならソファで十分だ。チャイムが鳴ったら起き上がればいい。わたしの準備はいつだって整っているのだから。
目を閉じる。さっきの男の後ろ姿が、瞼の裏であのひとの華奢な背中にすり替わる。脳髄まで浸される。あのひとに、あのひとの眼差しに。ひそやかに詩的な眠りが、わたしの体を満遍なく押し上げた。
起き抜けには白湯を飲むと決めている。
ケトルに水道水を入れ、スイッチを押す。コポコポと沸き立つ音をぼんやりと聞く。沸騰したお湯をマグカップに注ぎ、ぬるくなるまでしばらく放っておく。
秒針が目まぐるしく回り、長針が気怠そうに時を進める。短針はまだ動かない。
朝は大抵、男たちは来ない。来るのは夕方から。待つのは嫌い。あのひとを待つことも、本当は嫌い。来るか来ないかわからない、来ない確信のほうが強い、そんな人間のために一日を捧げるのは自傷行為と大差ない。
マグカップに口をつける。まだ少し舌がビリビリする。わたしの空白を埋めるには白湯では熱すぎて、水では冷たすぎる。ぴたりとはまる熱を探している。
日常は常に一定の速度で、土星の環のようにわたしの周りにある。早いと思うのはわたしの従順、遅いと思うのはわたしの怠惰だ。
この部屋にはテレビはない。雑多な情報が鼓膜の合間で膨大な音となり、煩わしさが吐き気となって込み上げるから。色彩にまみれた解像度の高い映像も微細な粒の寄せ集めに見えて、目にうるさい。静寂に沈んだ部屋で孤独を手のひらに転がしながら、丁寧に折りたたむような日々を過ごしたいのだ。
読みかけの本を開いた。無数の言葉がわたしの宇宙を漂い、思考の裏に不時着する。恋愛小説など、とうの昔に読むのをやめた。それなのに、出てくる男は皆あのひとに、女は皆わたしの姿に変換される。どんなに手酷い殺戮でも、生ぬるい生活でも、あのひとはわたしの前に現れて片手を挙げる。初めましてのときも、久しぶりのときも、相棒であったり妹であったり、猫であっても。
十年の隔たりが、わたしにとっては彩りを増すだけで何の沈静にもなっていないこと。強弱の強ばかりが濃くなり、弱が次第に薄まって透明になっていく。透き通った膜越しにあのひとを見つめれば、茶色の瞳がまどろみの中に明滅する。
適当なページに栞を挟み、白湯を口に含んだ。水になっていた。変わり映えのしない朝の日課に、一石投じられた気がした。
午前中はメイクをして、外へ出かける。長い髪を梳かすとき、いち、にい、さん、しい、ご、ろく、しち、はち、きゅう、じゅう。数を数える。鏡の前に佇むわたしの唇がうっすら開いて、数を数える。さらさらと流れる髪を下ろしたまま、飾りもつけず、ヘアオイルもつけない、まっさらな状態で出かける。
わたしの髪を男たちはよく褒めた。きれいだ、コシがある、ツヤがある、絹のようだ。昔は毛量が多くごわついていた。うねりもあったし、梳かしても今のようにさらりと流れはしなかった。
あのひとと一度だけ体を重ねた夜も、わたしの髪は汗で湿って収拾がつかなくなっていた。それをあのひとは世界一愛おしいもののようにやさしく、なめらかな手つきで撫でたのだった。わたしの思い過ごしでなければ。
玄関で靴を履いていると、鞄の中でスマートホンが震えた。男からの予約だった。今夜行っていいですか。シンプルな文面に、どうぞ、とこちらもシンプルに返事をする。特に時間は書いていないが、この男はいつも仕事終わりの九時頃にやって来る。今日は他に予約は入っていない。男が来なければ、読書でもしようかと思っていた。
セックスルームひさの。それがわたしの営みだった。この部屋に来る男たちにセックスを提供する。行為後にお金をもらう。金額は男たちが払えるだけ。わたしとのセックスに満足した男たちは大抵万札を数枚置いて帰っていく。満足がいかなかったと、百円玉を投げつけられて去られたこともあった。
お金なんて、わたしにはどうだってよかった。もちろん生活するには必要不可欠なものだが、体を売ってお金を稼ぐという感覚がわたしにはなかった。わたしはただ、あの夜が忘れられないだけだ。あのひとと共に過ごした、奇跡みたいに美しい夜。あの夜に取り憑かれて、わたしは今もあのひとの影を探している。どこで何をしているのだろう。つまりは、あのひとに辿り着きたいのだ。あのひとに見つけ出してほしいのだ。それだけだ。
外はよく晴れていたが、風は冷たかった。コートの襟を立て、気休め程度の風よけにする。冬は色のない季節だと思っていた。黒い服ばかりが街に増え、皆気忙しそうに体を丸め急足で歩く。
「冬は、きれいだ」
あのひとが言った。わたしたちは寒い部屋で毛布にくるまり、並んでベッドの中にいた。
「きれい? どうして? この街には滅多に雪も降らないのに」
わたしはあのひとの白く伸びた首筋を見つめながら訊ねた。小さなほくろが一つ、呟きを漏らすように浮かんでいた。
「冬は冬ってだけで、それだけできれいだ」
あのひとは電気ストーブをベッド際に引き寄せながら言った。炎のように赤く、頬が照らされていた。わたしはそのときに知ったのだった。冬は色がない季節ではなくて、黒や白が踊る季節なのだと。
あのひとがきれいだと言った、それが冬のことではなくてわたしのことだったなら。君は君のままできれいだ、と言われていたなら。わたしはセックスルームなんてやっていただろうか。仮定の話なんて何の意味もないのに、思考ばかりが先を行く。
駅前のデパートでウィンドーショッピングをし、地下のスーパーで買い物をして帰宅した。少食なわたしは普段、片手で持てる分だけしか食料品を買わない。大して重くもない袋、それほど遠くもない距離の外出でも、部屋に着くと額に汗が滲んでいた。冬にかく汗は、よるべのない物語の主人公のようだ。
九時頃に来るであろう男のために、先にシャワーを浴びた。体を丁寧に洗う。髪にトリートメントを撫でつけ櫛でとかす。この一手間を加えることで、髪は絹のようになめらかになる。
バスルームから出て、ふと洗面台の鏡を見る。三十になったわたしがそこにいる。あのひとと出会ったときから十年分歳を重ねた、退廃的な体がそこにある。髪の先から水が滴る。バスマットに染み込んでいく水滴は、わたしの体から剥がれ落ちた錆のようだった。
九時五分前にチャイムが鳴った。わざとゆっくりドアを開ける。男の顔が覗く。しずしずと部屋に入ってくる。寡黙な男なのだ。いつも言葉数は極端に少なく、行為中も声を上げない。何かをじっとこらえるように目を閉じ、苦しげな息を吐くだけだった。
「いらっしゃい、お仕事お疲れ様です」
声をかけても、男は軽く顎を引くだけだった。
男が部屋に入ってきた途端、むせ返るような花の匂いがした。香水とも柔軟剤とも違う、女の匂い。男は自分が匂いを振り撒いていることなど気づいていないように、スーツを脱ぎ始めている。
「シャワー、浴びなくていいんですか」
男は頷く。行為の前にシャワーを浴びる男がほとんどだが、まれに浴びない男もいた。
裸になって男と体を重ねると、衣類だけではなく男の髪や皮膚にも花の匂いが染みついていることに気づいた。こんな匂いをさせて来るような男だったろうか。まるで花とセックスをしているみたいだった。
男はわたしの耳朶を舐めた。舌の先で、何度も。やがて舌は耳の裏を這い、形をなぞってまた耳朶へ戻ってきた。裸体を突き合わせているのに、男はわたしの胸や陰部にはまったく興味を示さなかった。元から淡白なセックスをする傾向があったが、今日は一段とそっけない。ただ執拗に耳だけを舐っている。
男の首筋に爪を立ててみた。反応しないので、さらに強く。男ははっとしたように顔を上げた。首筋に手を当て、わたしの顔をじっと見つめる。何か言いたそうに唇が震えている。
「どうして今日は耳ばかり舐めるの」
男は答えない。深海のように暗い色の瞳でわたしを見据える。静かな男だが、果たしてこんな哀しげな瞳をしていただろうか。
「あなたは寂しいのね」
男は何も言わない。わたしの呟きは互いの間にある沈黙に溶けた。
再開する気は男にもなかったようだ。ベッドに入ってたった三十分しか経っていないのに、万札を三枚手渡された。
「こんなに、いいの」
男はすでに着替え終えて帰ろうとしていた。ゆっくりと振り返る。花の匂いがふわりと鼻腔をかすめた。
男の表情を見て、わたしは息が詰まりそうになった。男はやわらかく微笑んでいた。何かを諦めた人間の、それでも諦めきれない最後の足掻きのような切なる顔だった。どうしたの、と問う前に男が口を開いた。
「忘れられるのは、寂しいね」
それはさっきベッドの中で言った、わたしの呟きに対するものだったのだろうか。独り言のようにも聞こえた。男は決して泣かない。寂しいと言いながら涙を見せるほど、男はきっと弱くも強くもなれない。平穏そうな表情で、無事を繕って、内心は枯れるほど泣いているのだとしても。
「寂しいです、とても」
わたしはあのひとを思い出していた。本当はあのひとの首筋に爪を立てたかった。あのひとの皮膚に傷痕を残して、死んでいった細胞の一つ一つを悼みたかった。男の表情は、わたしのあのひとに対する欲望を呼び覚まさせた。醜い欲望だ。けれど、湧水のようにとめどなく溢れる想いだ。わたしはあのひとに会いたい。会いたいのだ。ずっと会いたくて、今も変わらずに、会いたい。なんて単純で、醜い欲望なのだろう。
男の去った部屋で、わたしは一人泣いた。何を思っての涙なのかは、わたしにもわからなかった。滔々と流れては、顎の先からこぼれていった。静かな夜だった。
あのひとと出会うまで、わたしは誰とも体を重ね合わせたことがなかった。付き合ったことは、一応ある。でも、子供みたいなキスを二、三度したきり、わたしが彼を嫌になってしまった。
わたしは自分が恋愛に向いていないことを自覚していた。誰かに心惹かれるという経験に乏しかった。自分のどこかに欠陥があるのではないかと、いつも感じていた。わたしの心身には虫喰いのような穴がいくつも空いていて、その隙間から恋愛に必要な感情がしゅるしゅると漏れ出ているのではないかと思っていた。
だから、大学二年の冬にあのひとと出会ったとき、わたしは心底驚いた。自分の中にこんな豊かな感情があったなんて。それは枝がたわむほどたくさんとまっていた鳥が、一斉に空に羽ばたいていくように爽快だった。まぎれもなく、豊かさの象徴だった。
あのひとは構内にある小さな池のほとりで煙草を吸っていた。ベンチに座り前屈みになって、水面を撫でるように泳いでいる鴨を見つめていた。黒いタートルネックのセーターが白くて華奢な体躯によく似合っていた。
わたしはすぐ横のベンチで昼食をとろうとしていた。その日は天気が良くて暖かく、構内のあちらこちらで日向ぼっこをしている人を見かけた。
購買で買ったおにぎりのフィルムを剥がしていると、ふいにあのひとに話しかけられた。
「ごめんね、煙たいかい?」
あのひとはわたしが答える前に携帯灰皿に煙草を押しつけて火を消した。空気中に残された煙があのひとを取り囲むようにゆらゆらと揺らめいていた。
「大丈夫です」
それだけ言うと、あのひとは目を細めて笑ったのだった。弧を描いた薄い唇が、目を閉じても瞼の裏に張りつくようだった。左右対称の、きれいな半円だった。
わたしがおにぎりを食べている間、あのひとは池を眺めていた。風が吹くたび水面がキラキラと光った。鴨が蓮の葉の間を縫って泳いでいた。
わたしはちらちらとあのひとの様子を横目でうかがっていた。あのひとは何かを思うように指を組んで、わたしの視線には気づきもしなかった。細くて長い指がときどきぴく、と動いていた。
食べ終わり手持ち無沙汰になったわたしは、あのひとと同じように前屈みになって池を見つめてみた。どうにも立ち去り難かった。あのひとはあれきり一向に話しかけてはこないし、わたしから声をかけるのも照れがあった。
けれど、わたしはあのひとと何かを共有したいと思っていた。何でもいい、何か言葉を交わしたい。焦燥に似た気持ちが駆け巡っていた。
「煙草、銘柄は何ですか」
やっと出た言葉は、酷くつまらないものだった。あのひとが振り向いたのがわかっても、恥ずかしさで顔を見ることができなかった。
「君も煙草を吸うの?」
「いいえ。でも一度くらいは吸ってみてもいいかなって、思って」
瞬きをしてそっとあのひとの顔を見た。苦みを我慢するような表情をしていた。
それからあのひとは、ふ、と笑って、
「煙草なんて、ね」
と言った。
「覚えなくていいんだよ」
「どうして、ですか」
「君はそのままでいて。そのほうがいい気がする」
名前も知らない人に、そのままでいて、などと言われ、わたしはわずかに動揺した。決して嫌な動揺ではなかった。心が揺れ動いて震えているのがわかった。ゆりかごのような心地良い振動だった。
わたしたちは昼休みが終わるまでの少ない時間を共に過ごした。同じ学部の、さらにはわたしが希望する研究室のマスター二年だということがわかり、一気に会話に花が咲いた。
「今度研究室に遊びにおいで」
そう言ってあのひとは去っていった。午後の講義に向かう途中、わたしは何度も振り返った。あのひとの背中が小さく小さくなっても、見えなくなるまで振り返り続けた。
今日の夜遅くに来る男は、わたしが大切に織り上げてきたあのひとへの想いを、簡単に切り裂いてしまうような人だった。それはまるで賽の河原だった。積み上げても積み上げても壊される石の塔。男は行為中わたしに、愛している奴の名前を呼びながら喘げ、と言いつける。
男が服を脱いでいる。わたしの準備はとうに済んでいて、ベッドの上で男を待っている。
「さあ、今日もしっかり喘いでくれよ。奈良崎さあん、ってさ」
男は下卑た笑顔でわたしの胸に顔を埋めた。
ルームを開いて初めて男と体を重ねたとき、あのひとの肌触りと違うことに戸惑い躊躇った。あのひととわたしは完全なる別個体だった。どこまで行っても混ざり合わない、あのひとはあのひと、わたしはわたしで、二つの個体がそれぞれの裸体をぶつかり合わせ、重ね合わせ、問い質し、見つめ合い、求め合っていた。
違う個体であることを恐れも嘆きもせず、それゆえに抱き合うことができるのだという喜びが胸を打った。あのひとの体をよく見ることができたし、あのひとに触れられた頬や背中が熱くなった。
なのに、他の男との行為では、わたしと男はどろどろに混ざり合った。わたしの体は跡形もなく溶けて、男の肉体と区別がつかなくなった。あのひと以外の男たちとは境目がなくなるくらい溶け合い、粘り気を帯びた液体になった。
それでよかった。あのひととの違いをはっきりと認識することができたから。わたしにとってあのひとだけは特別なのだと優劣をつけることができたから。
けれど、この男はわたしの優越を踏みにじる。わたしとあのひとの美しい夜を汚れた手でかき回す。
「ほら、もっともっと。お前の好きな男の名前を呼んで。叫んで」
「奈良崎、さ」
「奈良崎さん……」
「奈良崎さああんっ」
個体にも液体にもなりきれないわたしは、一体どこにいるのだろう。どこを浮遊して、彷徨って、転がっているのだろう。わからなくて、怖い。恐怖だ。目を開けることができない。
「今日は中じゃなくていいや。口で受け止めて。奈良崎さあんって言いながら舐めて」
わたしは暗闇の中、手探りで男の性器を口に含む。舌の裏で突起をなぞり、先端を小刻みに動かして舐め回す。男から呻き声が漏れる。
「奈良崎さんっ」
あの夜、わたしはこんなことをしなかった。あのひとはわたしを慈しむように撫で、微笑みを向けてくれた。ほんの一欠片の哀しみを宿して。
「もっと叫べよ。奈良崎さあん、奈良崎さああんってさ。こんなんじゃイけねえよ」
「奈良崎、さん……っ」
嗚咽が一緒に漏れ出た。思わず目を開けると、わたしの唾液にまみれた男の性器が飛び込んできた。赤黒い突起に猛烈な吐き気が込み上げ、わたしはベッドの上に胃の中のものを吐き出した。
昼間何を食べたのか思い出せないほど鮮やかな吐瀉物が、白いシーツの上に広がった。男が大袈裟な悲鳴を上げた。
わたしの耳は正常で、屠殺寸前の豚のような男の声が聞こえている。目も問題はなく、今し方自分の口から出た吐瀉物がじわじわと男の足元に迫っていくのが見えている。
「奈良崎さん」
わたしの呟きが吐瀉物の真ん中にぽとりと落ち、葉のようにくるくると円を描いて沈んでいく。深く、手の届かない底のほうへ。
男が怒鳴っている。立ち上がり、わたしのそばから離れて行く気配がした。その間、わたしはずっと葉を見つめていた。じっと、嗚咽の一つも漏らさず、やがて消えゆくのをひたすらに見つめ続けた。
朝になり、カーテンの隙間から光が差し込んできた。夜通し、あのひとのことを考えていた。昔のあのひとを思い浮かべ、今のあのひとに思い馳せた。その中で一つ、思い出したことがあった。
「年が明けたら、初詣に行こう」
あの夜、あのひとは確かにそう言ったのだ。わたしの髪を指で梳きながら、それまで口にしなかった未来の約束を、とても大切なことのようにわたしに伝えたのだ。
けれど、あの夜の約束は叶わなかった。あのひとは年が明ける前に突然、大学院を辞めたのだ。周囲に何も言わず、霧の中に隠れるようにいなくなった。
わたしの時間は、あの夜から止まったままだ。すべてが完璧で美しく、泣きたいほど愛おしかった夜から。
早朝の宇治橋は人気がなくて、ツンと冷たい空気を存分に吸い込むことができた。わたしは今、この世とあの世のあわいに立っている。神聖な世界が手招きしている。一歩、また一歩とわたしは進む。
伊勢神宮に行こうと思い立ってからのわたしの行動は早かった。その日のうちに手はずを整え、夜行バスで伊勢へ向かった。十年前、あのひとの生まれ育った地へ行くはずだった。あのひとの言う初詣とは、伊勢神宮以外あり得なかった。
「俺は神社と言えば、伊勢神宮しか行ったことがないんだ。地元だからな。あそこは本当に神様がいる気がする。大して信じてないく
せにね。不思議と縋りたい気持ちになるんだ。どうしてだろうね」
わたしは行ったことがありません、と言うと、あのひとは目を細めて、じゃあ行こう、と笑ったのだった。
「年が明けたら、初詣に行こう」
その約束に縋っていたのはわたしのほうだった。本物の神様などいてもいなくても、その拙い口約束がわたしにとっての神様だった。
あのひとへの想いは、重い。とても両手では抱えきれない。だから、半分置いて来ようと思った。この橋を渡って、神域に入ったところに。手放した想いはどうなるのだろう。浄化されるのだろうか。反対に、わたしの手に残った想いはきっと細胞のように分裂して増殖していくのだろう。半年もすればまた抱えきれないほど大きくなる。
手水舎で手と口を清め、正宮に向かう。階段の途中で腰の曲がった老婆とすれ違った。一段一段、体を横にしてゆっくり降りて来る。手助けするべきかと迷っているうちに老婆は階段を降りきり、順路に沿って歩いて行った。
神前では熟年の夫婦らしき男女が手を合わせていた。二人ともランニングウェアを着ていた。女の足は折れそうなほど細く、男の足はウェア越しでも目立つほど筋肉が立派に隆起していた。振り返った顔は二人とも日に焼けていた。
祈りを捧げる。
あのひとに会えますように。
あのひとがわたしのことを忘れていませんように。
あのひとが幸せでありますように。
あのひとの願いが叶いますように。
どれも違う気がして、わたしは何一つ満足に祈れなかった。祈りの中でのあのひとは薄靄に溶け、曖昧な輪郭を残して漂っているだけだった。かと言って、自分のことを祈ろうとしても、うまく言葉が出てこない。密度の薄い、意味をなさない単語が頭上をふわふわと浮遊して、掴めそうで掴めない。
結局、わたしは手を合わせただけで何の祈りの言葉も捧げられなかった。もどかしい気持ちで階段を降りる。わたしには叶えたい願いはないのだろうか。あのひとに会いたい。これは心からの願いではないのだろうか。あのひとの幸せは、わたしにとってどうでもいいのだろうか。あのひとと幸せになりたい。そう願ったことはなかったのだろうか。
ふいに、ざり、とアスファルトと靴底が擦れる音がした。顔を上げると、階段の下でこちらを見上げる人影があった。男と小さな女の子。六歳くらいだろうか、肌の色が抜けるように白かった。目が大きく、髪を両サイドで結っていた。
男は濃灰色のコートを着て、わたしをじっと見ている。半開きの唇、その薄さと形を見て、わたしははっと息を呑んだ。見覚えが、あった。見覚えどころじゃない。変わっていない。歳は相応に重ねているけれど、面影は十年前のままだった。
「奈良崎さんっ」
「ひさのちゃん?」
わたしと彼の声が重なり合った。駆け降りて抱きつきたい衝動をぐっと堪え、先程すれ違った老婆のように一段ずつ踏みしめて、彼の元まで降りて行った。
「奈良崎さん」
「本当にひさのちゃん? いやあ、久しぶりだなあ。元気だった?」
「奈良崎さん」
「どうしてここにいるの? こっちに住んでるわけじゃないよね? 旅行か何かで?」
「奈良崎さん」
「あ、こっちは娘の美岬です。ほら美岬、挨拶」
美岬と呼ばれた少女はわたしを大きな瞳でじっと見据え、ぺこりと頭を下げた。口を開けて何か喋ったような気がしたが、声は聞こえなかった。
彼の矢継ぎ早な質問にまだ一つも答えていないのに、彼はすでに満足そうに目を細めて、久しぶりだなあ、と繰り返している。
「奈良崎さん」
わたしはさっきからずっと、彼の名前しか呼んでいない。そうしないと、体が崩れていきそうだから。現に今、骨が軋んでいる。鈍い音が耳の奥に響いている。どうにかして取り繕わないと、わたしは音を立てて粉々に砕け散ってしまう。
「せっかくだから、どこかでお茶でもどう?」
彼の誘いに、頷くことしかできなかった。わたしには拒否権はない。わたしには彼を拒むことはできない。だって、あんなに会いたかったのだ。十年待ち焦がれた。それなのに、こんなに哀しい。
彼と美岬が参拝するのを待って、三人で内宮の外へ出た。宇治橋を渡るとき、わたしは神域を振り返った。ぼんやりと、ただ静かな空間がそこにあるだけだった。
朝から営業している参道の近くの喫茶店に入った。わたしと彼はホットコーヒーを、美岬はクリームソーダを注文した。コーヒーはあまり好きではなかったけれどメニューが少なく、温かい飲み物はこれしかなかった。
先にクリームソーダが運ばれてきた。緑色の液体の中に微細な泡がいくつも閉じ込められている。海中に差し込む朝日に向かって呼吸をしているようだ。グラスの中の幻想的な光景を何とはなしに眺める。
「腹壊すなよ、美岬」
彼がスプーンでアイスクリームを掬おうとしている美岬に声をかける。やさしい手つきで美岬の前髪を梳いた。胸が締めつけられる。見ていられなくて目をそらした。
彼は九年前に地元で結婚したこと、一年後に美岬が生まれたこと、美岬が二歳のときに離婚して自分が引き取ったこと、今は美岬と二人で実家の隣の市のアパートに住んでいることを滔々と話した。けれど、何故急に大学院を辞めたのか、何故わたしに何も言わずにいなくなったのかについては巧妙に避けているように感じた。
どんな理由があってもいい。彼とまたこうして再会できたのだから。そんなふうに思えたのならどれほど楽で、幸せなことだろう。彼の話に耳を傾け、相槌を打って、共感しようと努力しているわたしはなんて滑稽なのだろう。
美岬に目をやる。アイスクリームが溶けて濁ってしまったソーダをストローで懸命に吸っている。すぼまった小さな唇が可憐な花びらのようで、やるせない。
「ひさのちゃんは今までどんなことをして過ごしてた?」
柔らかい表情で彼が訊ねた。何も疑っていない、潔白の、清い表情。わたしがこの十年、どんなことをして過ごしてきたか。言えるわけがない。あなたを想って、あなたのことだけを考えて、他の無価値な男たちとセックスをしてお金をもらって生きてきました。もう一度あなたに会いたくて、あの夜が忘れられなくて、探すように彷徨って手を伸ばしては引っ込めて、あなたの面影だけを追って過ごしてきました。
口をつぐんだわたしを訝しむわけでもなく、彼は穏やかな目でわたしが話し出すのを待っていた。彼の目元に細かくやさしい皺を見つけて、わたしはたまらない気持ちになった。
「ごめんなさい」
どうしてか、口をついて謝罪の言葉が出た。だが、わたしの声はあまりに小さく、彼には届かなかったようだ。
「ん?」
穏やかな目のまま顔を近づけてくる。やめてほしかった。また胸が苦しくなる。息継ぎもできない、底のない沼に沈んでいくようだ。美岬がストローを咥えながらじっとわたしを見ていた。
「もう、帰ります」
それだけやっと言って千円札をテーブルの上に置き、逃げるように店を出た。参道には入ったときよりも人が増えていた。人波を縫い小走りで駆け抜ける。彼が追いかけて来ないことなど痛いほどわかっていた。それでも、途中で振り向いてしまう。何度も、何度も。
わたしはやっぱり、あの頃と何一つ変われないようだ。あのひとしか詰まっていなかったからっぽの心に、晴れ渡った冬の空がひどく沁みた。
彼と再会した日から二週間が経った。その間、わたしは日がな一日毛布にくるまって窓の外を眺めたり、ベッドに寝そべってじっと目を閉じ、外や上階や部屋の四隅から聞こえてくるかすかな音に耳を澄ませたりして過ごしていた。彼と会ったことを記憶から追い出したかった。
男たちからくる予約のメールはすべて無視した。誰にも会いたくなかった。男の前で裸になり体を重ねることを想像すると、美岬の曇りのない瞳がわたしを責め立て問いただしてくるようで怖かった。それはつまり、彼の瞳だった。彼がわたしを鋭いナイフのような瞳で突き刺すのだった。
いや、もしかしたらそれすらも幻なのかもしれない。わたしはただ、自分自身の罪悪感を誰かの糾弾に塗り替えて、怖い怖いと逃げ回っているだけなのだ。美岬はわたしを問いただしてなどいない。彼だって、わたしを責めない。わたしを一番責めているのは、許せないのは、わたし自身だ。
雨が降りそうだった。ぶ厚い雲が今にも落ちてきそうで、目の奥がずんと重かった。寒くて暖房をつけようか迷ったが、冷たい空気の中に身を置いたほうが頭が冴える気がして、毛布から顔だけ出しソファで小さくなっていた。
部屋が薄暗くなってきた頃、紅茶を飲もうと思い立った。参道の喫茶店で飲んだ苦いコーヒーの味が舌に蘇ってきたから。上書きしなければ。立ち上がった拍子に毛布がするりと床に落ちた。電気はつけずに台所へ向かう。
湯沸かし器に水をたっぷり入れ、スイッチを押す。永遠にお湯など沸かない気がした。いつまでも沸点に達しない水は熱湯と冷水の狭間で彷徨い続ける。明確に冷水ではなく、限りなく熱湯なのだけれど、どこか不完全で曖昧だ。こぽこぽと音が聞こえる。もうすぐスイッチが切り替わるだろう。水は完全な熱湯になるのだ。永遠などないのだから。
カチッ、と湯沸かし器の音が鳴るのと同時に、玄関のチャイムが鳴った。予期しない訪問に驚いて肩を震わせた。いつもは男たちからの予約の時間でチャイムが鳴るタイミングが大体わかっている。返信がないことに腹を立てた男の誰かが乗り込んできたのだろうか。
恐る恐るドアを開ける。目に入ったのは濃灰色のコートだった。ボタンが黒くつやつやと光っていた。あっ、と思い顔を上げると、薄暗がりの中、白く浮かび上がる彼の顔があった。奈良崎さん、と言おうとしたが喉の奥が詰まって言葉が出てこなかった。餌を乞う魚のように口をぱくぱくと動かすと、彼がふ、と笑った。
「ひさのちゃん」
名前を呼ばれて金縛りが解けたみたいに声が出た。
「奈良崎さん」
「来てしまった」
彼は重大な過ちを犯したとでもいうように、バツの悪い顔をした。
「娘さんは」
気づけばそう口走っていた。
「娘さんはどうしたんですか」
「美岬は元妻に預けてる」
頭を握り潰されたような衝撃を感じた。わたしの頭はトマトで、ぐしゃりと容赦なく、幼子の手のひらで残酷に潰され地面に叩きつけられた。悲しみのように涙のように、赤い液体がとめどなく溢れてくる。
「そう、ですか」
それだけ絞り出すように言って、わたしは彼を部屋に招き入れた。
おずおずとソファに腰を下ろす彼を横目に、ちょうどお湯が沸騰したところなんです、と何でもないふりをして声をかけた。
「今紅茶を淹れますね」
「ああ、お構いなく」
台所から、ソファに座る彼の横顔が見えた。部屋の電気はまだつけていない。だから、表情までは見えない。出会ったときと同じように、腿に肘をつき体を乗り出して何かを見つめている。
彼の目線の先には本棚があった。彼の位置からでは背表紙は見えないはずだ。ぎっしり埋まっているわけでもない寂しい本棚を、彼は切実な表情をしてじっと見つめていた。
ティーポットをソファの前のローテーブルに置く。蒸らした紅茶をカップに注ぐと、彼がありがとう、と言った。沈黙が漂う。居心地の悪い沈黙だった。ゆらめく湯気に隠された彼の曖昧な輪郭をぼんやりと眺めた。
「よくわたしの部屋がわかりましたね」
耐え切れなくなって、わざと明るい声で訊ねた。答えやすいように冗談みたいに言ったのに、彼はカップを置きながら深刻な顔をして口をつぐんだ。再び沈黙。
わたしは泣きたいと思った。これほど泣くことを求めたのは今までなかった。泣いて泣いて、体中の水分をなくしてしまいたかった。干上がった蛙のように醜くなってもいいから、何も経験していないまっさらな体にしたかった。
けれど、涙なんてどこからも出てこなかった。わたしの涙腺は機能していないのだろうか。こんなに泣きたくて堪らないのに。
「電気をつけましょうか」
立ち上がったわたしの腕を、彼が掴んだ。
「知ってた」
ぽつりと彼が呟いた。何を、と訊こうとしてすぐに思い当たった。さまざまな思惑が瞬時に駆け巡る。彼を見る。俯いた彼のつむじが見える。うなじが見える。込み上げてくるものがあって、わたしは思わず嗚咽を漏らした。彼がわたしから手を離した。
「どうしてあなたは、そうやって」
そこから先は声にならない。さっきあんなに欲していた涙を、今は拒絶したかった。それなのに、溢れてくる。なんて天邪鬼なのだろう。
「ベッドに行きましょう。ねえ、奈良崎さん」
可哀想な女の声が出た。なんて醜い声。こんな甘ったるくて自制の効かない愚かな女の声を、わたしは持っていたのか。自分自身に吐き気がした。
彼は静かに首を振った。目を伏せ、消え入りそうな声で、できないんだ、と言った。
「できないんだ、誰とも。数年前からかな。したいという気持ちも起こらないんだ。どうしてだろうね。俺は不良品になっちゃったのかな」
ぎこちなく笑う彼の顔を、これ以上見たくなかった。誰ともできない。それが本当ならば、わたしは今まで一体何をしてきたのだろう。彼に会いたくて、彼に見つけてほしくて、あの夜をもう一度手に入れたくて、わたしは、わたしは彼ではない男たちと体を重ねてきた。
全否定だった。わたしのしてきたことは彼にとって、わたしにとっても、まったくの無意味だった。足元が崩れていく。わたしは二度と彼と体を重ねることはできない。わたしは永遠にあの美しい夜を取り戻せない。
ベッドを月明かりが照らしている。シーツは青白くつやめき、海の底で眠っているような錯覚を起こす。いっそ魚にでもなれたなら、深海に沈んで二度と浮き上がってこないのに。わたしは中途半端に人間で、余計始末が悪い。隣で寝息を立てている彼の顔を見つめる。
ベッドに行きましょう、服を着たままでいい、何もしなくていいから、ただ眠るだけでいい、わたしの隣で眠ってください、それだけでいいから。わたしの懇願に、彼は浅く頷いた。了解とも拒否とも取れる仕草だったが、おとなしくベッドまでついてきた。
横になった途端、彼は目を閉じた。すぐ横にあるわたしの顔など一瞬たりとも見ないで。
「奈良崎さん」
名前を呼んでみたが、返事はなかった。明確な拒否だった。もう一度名前を呼ぼうとしたが、やめた。もはや、彼を呼ぶことは虚しい行為でしかない。
顔のそばに添えられた彼の白い手の甲に、そっとわたしの手のひらを乗せた。二枚の花弁が折り重なるような光景に胸が詰まった。遠くの、どこにあるのかも知らない、名もない街の片隅でひっそりと咲く、誰からも忘れられた花。
あの夜、わたしたちは花ではなく二体の人間だった。一糸纏わぬ姿の、孤独でつややかな体を持った男と女だった。あのひとの部屋のベッドの上で、わたしたちは互いの魂を舐り、撫で回し、ガラスを運ぶように丁寧に扱い合った。
その日、わたしたちは初めて二人で出かけた。出会った日以来、あのひととは構内で見かければ挨拶をしたり、軽い立ち話をしたりするようになっていた。
一緒に行く予定だった友達が急に行けなくなってさ、よかったら行かない?
あのひとはそう言って、水族館のチケットを二枚差し出した。学食で天ぷら蕎麦の器を両手で持っていたときだった。わたしはあたふたと辺りを見渡し、器を置けそうな場所を探した。
「ごめんごめん、状況を考えていなかったね」
あのひとはさっとチケットを引っ込めて、恥ずかしそうに笑った。
「いえ、あの、嬉しいです。ありがとうございます。行きたいです。すいません、こんなときに蕎麦なんか持っててすいません」
自分でも何を言っているのかわからなかった。とりあえず行きたいという意志を伝えてお礼を言わないと、と思っていた。間の悪い自分についても謝ったほうがいいのかな、とも。
あのひとは吹き出して、しばらくお腹を抱えて笑っていた。声を出して笑うとこんな顔になるんだな、とか笑い声は幼いんだな、とか案外豪快に笑うんだな、とか。気づくたびに幸福感に包まれた。あのひとについて知らなかったこと、知りたかったことが雪のようにはらはらとわたしの中に降り積もっていった。
水族館ではタッチプールに多くの時間を費やした。生きたヒトデやナマコに触ることができ、休日ということもあって子供たちがたくさん集まっていた。
ナマコを触ったことのないわたしは恐る恐る水槽に手を入れた。指先で触れたナマコは想像以上に柔らかくて、思わず声を上げ手を引っ込めた。水滴が横にいたあのひとの顔にかかった。頬を伝う水滴が涙のように見え、わたしはどうしようもなくあのひとにしがみつきたくなった。
夜ご飯はあのひとの一人暮らしの部屋でピザを取った。あのひとの飄々とした都会的な雰囲気からは想像もつかない、古くてボロいアパートだった。備え付けの石油ストーブの調子が悪いからと、部屋には小さな電気ストーブが置いてあった。
夜も更けてきた頃、雨が降ってきた。どうしよう、と呟いたわたしにあのひとは、泊まっていくかい、と言った。囁くような掠れた声だった。
寒い部屋でわたしたちは裸になり、毛布に埋まって戯れ合った。体を重ね、いくつもの会話をし、神妙になったりふざけたり、小さな声で喋り、大きな声で笑い、空がうっすらと明るくなるまでわたしたちは寄り添い合っていた。
白く細い指先で、あのひとはわたしの頬に触れた。髪を梳き、唇をなぞった。わたしはくすぐったくて、その手を何気なく払った。
そのときに前髪の間から見えた、見えてしまった、あのひとのひどく傷ついたような哀しげな表情が、わたしをいつまでもいつまでも縛りつけているのだ。
弁解したかった。すぐに謝ればよかったのだろうか。いいえ、謝ったところであのひとの朗らかな笑顔は返ってこないでしょう。わたしはとんでもない過ちを犯してしまった。何気なく、それが一番残酷だということをこのとき知ったのだった。
その後は何事もなかったかのようにあのひとは振る舞った。明け方少し眠り、朝八時に起きて目玉焼きとトーストを食べた。外へ出ると、眩しいほどの晴天だった。昨夜のあのひととのすべてが体に刻まれていくように、わざと陽の光の下を選んで歩いた。歓喜も哀しみも虚無も、憂いも快楽も痛みも、何一つ忘れないように。
彼が目を覚ましたようだ。寝室からシーツと体が擦れる音が聞こえる。わたしは紅茶を淹れるためにお湯を沸かしている。
「ひさのちゃん?」
彼がリビングにやって来た。ソファに座るように促し、昨日と同じようにローテーブルの上にティーポットを置いた。
「紅茶が好きなんだね」
彼の問いには答えず、マグカップに紅茶を注ぐ。湯気がふわりふわりと立ちのぼり、宙に溶けていく。
彼は湯気の行く末をぼんやりと眺めていた。わたしはテーブルから一歩下がり、着ていたブラウスのボタンに指をかけた。下まで外し、腕を抜く。ロングスカートも脱ぎ、下着姿になる。ブラジャーのホックを外し、最後にパンツを脱ぐ。彼はわたしの動作一つ一つを黙って見つめていた。
「わたしを撫でてください」
丸裸のわたしが立っている。従順な犬が垣間見せる反抗的な表情。彼の前に立っているのは、そんな女だ。
おいで、と彼は言った。わたしは彼の横に腰を下ろした。頭を撫でられる。やさしい手だった。その手は髪に移り、顔の形をなぞって肩、背中、お尻、太腿から足首、足の裏、お腹、胸、鎖骨の窪みを通って、最後に頬を撫でた。
唇に、彼の指先が触れた。下腹部が疼いた。
「愛しています。ずっと、ずっと」
彼の目を見た。彼も茶色の瞳をわたしからそらさなかった。わたしの言葉が彼の胸の奥底に沈んでいったのを感じた。うん、と彼は小さく、けれどはっきりした声で言った。
「ごめん」
「はい」
「ひさのちゃん」
「はい」
「さよなら」
今まで見た中で一番やわらかく、彼は笑った。
朝の淡い陽に包まれて彼は帰って行った。きっと幼い娘が彼を待っている。わたしは窓から外を眺めた。彼の後ろ姿が点のように小さくなって、やがて消えた。彼がいた風景と彼がいなくなった風景に、大きな違いはないように思えた。
それでもわたしは覚えているのだ。あのひとの白い肌に何の傷もつけられなかったこと。後悔よりも甘い感情があったことを。
ずっと会いたくて堪らなかった人は、一つの夜を経て、もう二度と会わないと決めた人になった。