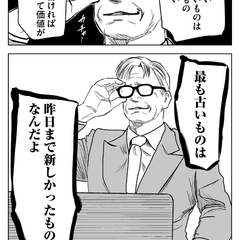Final Survival Results from the Penelope-B trial investigating palbociclib vs placebo for patients with high-risk HR+/HER2- breast cancer and residual disease after neoadjuvant chemotherapy – PENELOPE-B
Annals of Oncology (2025), doi: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2025.03.010.
まだ編集前ですがパルボシクリブ併用の術後内分泌療法PENELOPE-Bの最終結果です
気になってたので早めに読みたいと思います
ショートサマリー
内分泌療法に1年パルボシクリブを追加したPENELOPE-B試験は主要評価項目であるiDFSを改善しませんでした。
今回は全生存(OS)の最終評価になります。
PENELOPE-Bはホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌(luminal)に対して、
タキサンベースの術前化学療法で腫瘍残存が多かった再発ハイリスク症例
(CPS-EG score3以上、もしくは2でリンパ節転移残存)に対して、
術後内分泌療法単剤とイブランス併用を比べた試験です。
中央値77.8ヶ月のフォローアップで225の死亡イベントが確認されました。
6年のOS率は82.4% vs 80.3%でHR 0.87, 95% CI 0.67-1.14, p=0.31と有意差はありませんでした。
追跡期間を延長してもiDFS, 無遠隔転移再発率(DDFS)、領域リンパ節再発率(LRR)も変わりはなしでした。
送別因子でみた解析でもサブグループで差は認めていません。
しかし、探索的解析では浸潤性小葉癌でOSが良さそうな傾向と、有意なiDFSの改善を認めていました。
それぞれHR 0.45 (95% CI 0.19-1.07, p=0.062)、0.52 (95% CI 0.28-0.97, p=0.035)。
全体としてOSの改善は認めませんでしたが、探索的解析で浸潤性小葉癌はいい傾向を認めました。
先に書きましょう。
苦しい…あまりに苦しい結語…
内容を見てから再度結論を…
イントロダクションでは42.8ヶ月の観察期間時点での結果を提示していました。
iDFSの改善は見られず、HR 0.93, 95% CI 0.74-1.17, p=0.52
OSも改善が見られなかったと報告していますHR 0.87, 95% CI 0.61-1.22, p=0.42。
なんか自分の勘違いが2つあって、PENELOPE-Bってネオホルモン+CDKの試験だと勘違いしていました。
Non-pCRだったときの追加でしたね。
あともう1つが、中間評価でiDFSが逆転されている(HRが1.0を上回っている)という印象だったのですが、
一応データとしては下回っていたんですね。
これです。
逆転されているように見えましたが、そのあたりでヒゲが生えまくっている、
つまりはまだ観察期間が短くイベントが発生していなかったということになります。
ちょっと悪いイメージをしすぎました。
さて長期フォローアップの結果です。
統計解析のところで、探索的な解析については多重性の調整は行わないと明記してありました。
なので、探索的な解析についてはあんまり意味ないよと宣言しています。
さて、患者背景です。
アブストラクトで注目していた浸潤性小葉癌はそれぞれ58例、52例と、
数自体はそろっていそうです。
が、それ以外の因子(年齢とか化学療法の奏効具合とか)はばらばらになっています。
イブランス群で108のイベント(17.1%)、対照群で117のイベント(18.9%)が発生しました。
6年のOSは82.4% vs 80.3%で有意差なしです。
徐々に縮まっている感もします…
iDFSについても65.1% vs 64.5%でほぼ同等です。
クロスほどまではいかずとも…ぴたーっとくっついてます。
6年無浸潤性乳癌生存率や(66.0% vs. 65.2%; HR=0.94, 95% CI 0.78-1.14, p=0.58)、
6年無遠隔転移生存率 (67.4% vs. 66.9%; HR=0.93, 95% CI 0.76-1.13, p=0.48)も差なし。
6年累積領域リンパ節再発についても4.4% vs. 5.5% (HR=0.80, 95% CI 0.48-1.35, p=0.41)
サブグループでも同様です。
浸潤性小葉癌については6年のOSとiDFSが、それぞれ
88.8% vs 73.2と73.5% vs 51.1%で、
OS (HR=0.45, 95% CI 0.19-1.07, p=0.062), iDFS (HR=0.52, 95% CI 0.28-0.97,p=0.035)でした。
基本的にこういう解析の時は有意差検定しないのが一般的かと思ってましたが…
まあ最初に断ってやってますからね。
探索的にもう少し見ていて、浸潤性小葉癌の特徴であるE-カドヘリン発現を遺伝子レベル(CDH1)で見ています。
CDH1をlowとhighでみましたが、ここでも差は認めませんでした。
OS HR=0.84, 95% CI 0.40-1.76, p=0.63; iDFS HR=0.73, 95% CI 0.40-1.33, p=0.31
浸潤性小葉癌内で見ると差はあると。そりゃそうだ。
OS HR=0.30, 95% CI 0.07-1.25, p=0.08; iDFS HR=0.33, 95% CI 0.09-1.17, p=0.07
Discussionです。
周術期のイブランスの試験はPENELOPE-B、PALLASともにこけてしまいました。
アベマシクリブのMONARCH-E、リボシクリブのNATALEEではiDFSで良好な結果が出ていて、
OSは結果待ちです。
おそらくはOSまではでないでしょうが、明暗はくっきりわかれてしまいました。
各臨床試験は同じような症例がエントリーされていますが、違いがあると書いてありました。
アベマシクリブとリボシクリブは非二重盲検で投与期間も長い。
PENELOPE-Bは二重盲検で1年しか使っていない!(いやPALLASは2年やないか)
違いが出てしまったのは純粋に薬のパワーの可能性の他、患者選択や治療期間があるかもしれません!
(患者選択も似たようなもんだし治療期間は有害事象のせいで短くなってるのでそれも薬のパワーなのでは)
浸潤性小葉癌で少し差があるように見えますが、そもそも探索的ですし、
浸潤性小葉癌の評価は中央判定ではないので何とも言えません。
CDH1で見ると差はなかったですが、数も少ないし探索的なので限界があります。
(それをいうなら浸潤性小葉癌での差もそうなのでは…)
やはりパルボシクリブのデータは良くない方向に一貫性があります。
再発では悪い成績ではないので、再発で使うことに疑問はないですが…
この結果からいえることは、
例えば術後のベージニオが有害事象で続けられないときに、
「同じCDKだしイブランスでやってみようか」は全く意味がない。ということことかなと…