正月休みを利用して、
買ったもののなかなか読めなかった本を
読みました。
その第一弾が、これ。
- 中学受験 SAPIXの授業 (学研新書)/杉山 由美子

- ¥798
- Amazon.co.jp
SAPIXでの中学受験用の
授業内容についてまとめてあります。
高学年と低学年の授業風景が
講師がどんなふうに声をかけているかとか
書いてあって興味深く読みました。
講師によって進め方は違うのでしょうけど、
有名塾の授業のいったんを垣間見ることが
できるのはおもしろかったです。
高学年の算数にて、黒板・討論形式の授業が
多いときいていた、SAPIXが、ひたすら演習を解かす
とういうこともしているのにはおどろきました。
(作者も不思議に思ってました)
その理由は、
「わかっていても手が動かない子もいる。
それでは力がつかない。
とにかく問題と格闘させたい。
一生懸命解いて、それから解法を聞くから納得できる」
とのこと。
中学受験において、難関校ほど基礎的な問題は出題されず、
緻密な計算力をもとにした、
想像力、類推する力、発想力、ひらめき力が必要で、
そのために、演習をひたすら解いて力をつけているとのことです。
これには、共感を覚えました。
こちらが、教えようとすると、子供は頭を使わなくなる。
こちらが、教えないぞと決めると、子供は頭を使うようになる。
教えてわかった、は、わかったつもりになっているだけ。
実際に解くと、解けないことが7・8割。
本当にわかった になるには、実際に何度も解くことが必要。
これは、いつも感じていることです。
ヒントは極力少なく、最初は自力で考え抜かせる。
ある程度、なれてしまうまでは、定期的に練習をする。
これ子供には大事だと思ってます。
話はそれますが、
この「自力で考え抜いてこそ力がつく」という考えの最たるものが
教育論の宮本哲也氏の考えかな。
もしも、お教室の近くにすんでいたら、
息子を行かせるフリして
見学したいな~と思う教室NO1です。
- 強育論-The art of teaching without teaching-/宮本 哲也
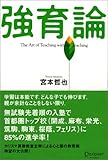
- ¥1,470
- Amazon.co.jp
あ。このSAPIXの本。
私の塾で使える技術がもりだくさんかというと、
ほぼ否、かな。
だって、SAPIXは中学受験をする、と決めた人たちが
くるところであり、その宿題量も半端ありません。
(一応スタンスとしてはしなくてもいいとなってるとのこと。
しかし、実際はほぼ全員がしてくるそうです)
授業も90分が2本連続と、すごいと思います。
子供も親もかなりの覚悟がいります。
一方、私のところは、学校の授業ができればいい、という
考えが多いのですから、宿題をあんな多くしたら
ぜったいにやめていく自信あり。
(学校の宿題でさえ、多いといってる子が半分以上。
私から見たら少ないと思うのに、保護者が担任にクレームを
つけたという話も毎年数件はきいています。
そんなだから・・・・・・・)
うーん。
この考えの違いは、やっぱり地域性の違いだと思います。
が、正直、これじゃあ、この地域の学力がダメダメなのは事実。
息子が小学校にあがるころまでに、
なんとか地域の考え方、すこしでもかわってないかしら。
なんか、私にできることあるかな~
(たいそうなことはできませんけど)