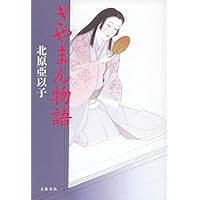 「ぎやまん物語」」 北原亞以子 文芸春秋
「ぎやまん物語」」 北原亞以子 文芸春秋
秀吉が天下を取った頃から幕末までの間、ポルトガル製のぎやまんの手鏡が人から人の手へ渡り、「私」と名乗る手鏡が時代の流れの中で持ち主の状況を通して歴史を語る450ページ弱、16章からなる物語
「鏡は人の顔だけでなく、様々なものを映す。鏡がそれを持っている人のどういう様子を映すかで、その人の内面まで描くことができたらと思う。人から人へ渡り、時代から時代へ受け継がれた鏡が映し出すものは、どんな色合いだろうか」
このような理由で作者は長い時代の物語を書きたいと思い主人公に古い鏡を選んだ、と
16章、450ページ弱の話だけど、時代が変わって行くので退屈しないし史実にフィクションが上手く取り入れられていてドラマを見ているよう
1章ずつ主人公(時代)が違うので、それだけで1冊の本が出来てしまいそうな贅沢な本ですね
ここからは、内容の紹介
すごーく長いよ~
「妬心」
ポルトガルの宣教師が黄金の茶室で秀吉に「ぎやまんの手鏡」を進物として渡す
秀吉は、その手鏡を「おね」に渡しおねの手を経て茶々へ
鏡を覗きながら「朝鮮出兵の成功を祈る」秀吉だったり「茶々、不首尾」と呟くおねだったりを映し出しながら他人には言えない心情を伝える
おねと茶々との仲は良好とはいえず、手鏡も暫くの間、厨子の中へ仕舞い込まれていた
そういう時の鏡は、眠っていたり、女中が話す内容を耳にしたり・・で時代の流れを説明するという話の進み方
「因果」
20年近く眠っていた鏡が大きな音と振動で目覚めるが、それは大阪城落城の時
この章では、落城に至るまでの時代の動きと城内での様子を語った後、常高院(お初)の手で、江戸に居る「お江」の元へ
「制覇」
江の秀忠の妻としての暮らしぶりと春日局との有名な確執についての話が少しと織田と浅井の血持つ者に天下を取らせるという江の執念が描かれている
険悪な仲の春日局が手鏡を欲しがるそぶりを見せたので江から春日局へ渡される
おね、茶々のそうであったように江も手鏡に執着してる様子はない
「葛藤」
将軍家光を取り巻く者たちがその才能を警戒した忠長は、濡れ衣と思われる不祥事の責を負って切腹
江の危篤の知らせを京で受けた秀忠、家光、忠長のそれぞれの動き方と忠長の側近として仕える春日局の次男と忠長が数々の濡れ衣に対して申し開きの機会も与えられない無念さを語る場面で、この家族の置かれている状況が分かりやすく纏められている
鏡は、忠長夫人で落飾した後は光松院(織田信雄の孫)の元にある
この話では、織田浅井の血に固執した江は、自分の出来の良い息子と織田の孫との間に生まれる子が将軍職を継いで行けば実父を殺され、織田の実権を奪われた無念を晴らせるという思いが強かったのでより家光の廃嫡を望んでいたというように書かれている
「かりがね」前編
時代は少し進み、四代将軍家綱夫人の手元にある
この時代は、大火などがあったせいで、なにやらいわくのある手鏡は「御鏡供養」と称して長々と経をあげられ祀られていたり、また蔵の奥へ仕舞われたりしていた
その後、不吉の鏡とも呼ばれていた手鏡の話に興味を持った五代将軍綱吉が探しださせたが実物は興味を引くほどでもなかったのか、お気に入りの側用人備後守牧野成貞に下げ渡す
縁起が良いとは言えない手鏡を持て余した牧野から出入り商人の手を経て雁金屋宗謙の元へ
理由は家業に身が入らずに趣味と遊びに興じている次男の市之丞が見たいと言いだしたためであった
「かりがね」後編
父親が亡くなり、雁金屋の店を継いだのは勘当を解かれた長男で、次男三男は相変わらずの趣味三昧の暮らし
この次男が後の尾形光琳で三男は権平から深省と名をかえ乾山焼きで有名な尾形乾山
鏡は、乾山の勧めもあり(不吉な鏡)、光琳から元の持ち主「越後屋」へ戻され蔵に入れられる
鏡は、光琳と一緒に過ごした頃が一番楽しかったと語っている
「赤穂義士」
越後屋では蔵の隅で不用品の様な扱いを受けていたが、小僧が貰いうけ眺めたりしていたのを番頭にとがめられ「(そんな不吉な鏡)捨ててしまえ」とごみ溜に捨てられヒゲ面の男に拾われる
時代は、吉良邸討ち入りの頃
このヒゲ面の男は討ち入り直前になり義士から抜けた男であり、討ち入りが美談として語られる中で、名乗る事もできずひっそりと暮らしながら、討ち入りは私怨だったのではなかったのか?との疑問を持っていた
殿中で刃傷に及んだ本当の理由を聞いてもうやむやな返事しか返されず、聞きただしてはならないような雰囲気のまま討ち入りへとなだれ込んで行った
浅野内匠頭の短気が問題だったのではないか?本当の理由を聞けば、こんな事でお家は取り潰され家臣達やその家族たちはこのような目にあったのか・・
「あこがれ」
鏡は、木曾街道追分の地蔵堂の中にいた
どのような経緯でここに来たのかは分からない
そこを通りかかった、元松前藩藩士 湊源左衛門が鏡を懐に入れ平賀源内の元へ
エレキテルや石綿で作った燃えない布など発明していた源内だったが鏡を見ては「つまらん」とつぶやいていた
もう一人「つまらない」が口癖の意次の愛妾、由布
屋敷の天上にぎやまんを敷きその中に金魚を泳がせたり、と贅沢な暮らしをしているが、元は町人の娘だったのか、窮屈で退屈な生活らしい
源内の手で磨き上げられた鏡は、由布の元へ
「嵐の前」
松平定信の台頭で、外国との交易に興味があり蝦夷に興味を持ち巡検使を送っていた意次は難しい立場にたたされる
面白い物を追い求めていた源内は、人を殺めた罪で獄中で狂死する
意次も石高も減らされ生活もかわり、幕府内でも権限もほぼなくなってくる
鏡には疲れ果てた顔の意次が映し出される
「浮き沈み」前編
意次、失脚
上屋敷も召し上げとなり、2日うちに立ち退くよう幕府から言い渡される
屋敷の外からは町人たちの投石、値のはる家具などが家中の者たちから持ち去られる中、下屋敷への移動が始まる
慌ただしい中、由布が鏡を持って近くに住む小野忠友の元へ行き、忠友の家臣に鏡を半ば押し付けるようにして渡してくる
忠友は意次の息子を養子に向かえ縁籍となっているが、変わり身早く息子を廃嫡し意次とのつながりを断った
由布は、不吉な鏡を忠友に押し付けることで、仕返しをと思ったのだろうか
その後、鏡は水野忠友から松平伊豆守信明の元へ届け物の中の一品として渡るが信明は、古い鏡など興味が無い
捨てようと思っていたところへ意次が手をつけた蝦夷開拓の後始末で現れた久世広民にこれ幸いと渡す
田沼意次を失脚させた松平定信だったが、蝦夷で起きているらしい不穏な動きの詳細を探るために人を派遣することになり、広民が推薦したのが蝦夷に詳しい青島俊蔵(意次の元で蝦夷巡検使の竿取りとして同行)
鏡はお守りとして俊蔵に渡され蝦夷を目指す
「浮き沈み」後編
不遇が続いていた俊蔵だったが漸く妻をめとり(体の大きい働き者の女)、その妻お竹も同行して松前へ
懐にはお守りとして鏡を入れてある
国後で蝦夷人の叛乱が起き背後にロシア人がいるらしいとの噂の本意を探るため老中首座の松平定信の命で蝦夷へ向かった俊蔵だったが、江戸へ戻ると蝦夷での俊蔵の行動に不審のかどあり、と投獄され憤死する
「阿蘭陀宿長崎屋」
俊蔵が亡くなり、体が丈夫だったお竹は宿屋で住み込みで働きながら暮らしていた
鏡は俊蔵の形見としてお竹の元にあったが蝦夷へ一緒に行った最上徳内が長崎に向かう途中に訪ねてきた折に、いろんな土地へ行きたかった俊蔵の思いを託し鏡を渡す
この後、鏡はシーボルトの手に渡る
「黒船」
シーボルトの屋敷に飾られていた鏡は、オランダ通詞の森山栄之助の手に渡る
栄之助は、ペリーとの交渉役をすることになる
「落日」前編
鏡は森山からヒュースケンの手に渡っていたが、ヒュースケンは暗殺され現場から暗殺犯によって持ち去られ清川八郎の手に渡る
その後、攘夷派の集まりの中で意見が分かれその場をに逃げるように立ち去る八郎が落して行った鏡を拾ったのが芹沢鴨
壬生の浪士組の話が中心となる
「落日」後編
相撲興行の失敗や金策に走る浪士組達の話、鴨の不穏な動きに注意をはらう近藤勇たちの動きの中で近藤は、沖田らに鴨殺害を命ずる
鴨の殺害現場に落ちていた鏡は近藤の手に渡る
その後、14代将軍家茂の侍医として京に来ていた松本良順の手に渡る
家茂の死で江戸に戻る事になった良順とともに、鏡も江戸へ
江戸で医学所を開いていた良順の元へ、吉原通いの挙句に伝来の刀を売り父に斬り捨ててやると追い回されていた土肥庄次郎という男が逃げ込んで来る
良順の元で手伝いを始めた庄次郎、なかなか器用で患者の評判も良かった
幕末の争乱期、眠っていた武士の血が騒いだのか彰義隊に入隊する
古い鏡は弾よけになるかもしれないと良順が庄次郎に鏡を渡す
見事、庄次郎の懐で弾よけとなり粉々に砕け散る
庄次郎は後に松廼家露八と言う吉原の幇間となる
「あとがきに代えて」
ポルトガルを出る前、どのような目的で鏡が作られたのかなどについて少し物語が書かれている
この最後の文書は、作者が亡くなる1週間前に書かれたもの