 「武士たちの作法」 中村彰彦 光文社
「武士たちの作法」 中村彰彦 光文社
これを読むと、ちょっとした「武士の薀蓄ウンチク」が語れちゃうよ
「雑兵たちの知恵」では、その仕事内容(平時と合戦)が詳しく書かれていて、足軽との違いなど詳しくは分からなかった事など説明されていて「おー、そうだったのか~!」と今後本を読むときに参考になる知識が満載
時代劇によっては、ごっちゃにされていたりするからね
武士階級の(上士・中士・下士に分かれている)平時と合戦の時の身分について説明も、分かっていたつもりでいたけど、実は微妙な知識のままだった事がこれを読んでスッキリ
上士は平時には主君の政事(まつりごと)を補佐し、合戦となれば部将(司令官クラス)として出陣すべき身分の者たち
中士は、それらの部将たちの指揮下に入って戦う者たちだが、戦国から幕末までの合戦の戦闘単位は「○○組」と呼ばれる事が多かったので中士たちは「組付き」と表現されることもあった
下士とは足軽のことで、れっきとした士分だが、鉄砲足軽、弓足軽、槍足軽の三者に分かれていて、戦場の最前線で戦う事を義務付けられている点が特徴
雑兵は、平時では中間として武家に雇われているが合戦となると、馬の口取り、草履取り、槍持ち、馬印持ち、旗印持ちなどを務める士分以下の者たちも少なくなかった(足軽が同じ役目を任じられる場合もある)
「武士たちの作法」では、戦での体制のひとつ「折り敷き」についての話が興味深かったかな
折り敷くとは、全軍が一斉に右膝を地面につけ左膝を立てて腰を下ろし低い姿勢を取る事を言い、戦国時代から太平洋戦争まで一貫して軍事用語として用いられた。号令は「折り敷け!」
この「折り敷く」を時と所を得て効果的に用い劇的な結果を招き寄せた戦として、真田幸村の真田軍が紹介されている
大阪夏の陣最終日、幸村率いる1万3千あまりの兵は天王寺の茶臼山に折り敷いて南方からの徳川軍の接近を待ち構えていた。「真田の赤備え(旗印、具足、馬装、槍の柄の色を赤一色で統一)」が最期の突撃に移るべく折り敷きの構えを解いて、旗印や槍を押し立てて一斉に立ちあがった光景は、全山が一気に躑躅(つつじ)の花に染め上げられたような迫力ある美しさだった。
映像化して欲しいわ~
sexcellent!
後半は、会津の事(山本八重の事)、会津松平藩初代藩主保科正之について熱く語っている(作品にもあるしね)
その間で、ちょくちょく「民主党批判」特に「菅直人批判」が挟み込まれる←相当嫌いな模様
あと、NHK大河ドラマ「江」の事も時代考証がめちゃくちゃだと(保科正之の扱いに嘘があったと)思いっきり馬鹿にしてたね(あんな馬鹿ドラマ、言われて当然だ!)
「天下人になれなかった男たち」で面白い文章があった
後継者選びを間違えた武田信玄や息子の出来が悪かった例として上げられた大友宗麟と息子義統(父子で不出来)に並んで書かれていたのが「関東に目をむけると、もう一人かなりのオバカサンがいた。今川義元のせがれ氏真だ」 ( ´艸`)
小説を読んでいる様な面白さのある本でした(内容が盛りだくさん)
現在かかえている本



図書館に待機中の本
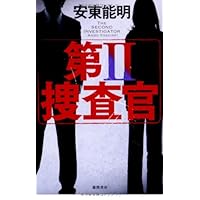
葉室麟の「月神」は、つまらないので途中まで読んで返却
この後も、まだまだ本が届く予定 (((゜д゜;)))