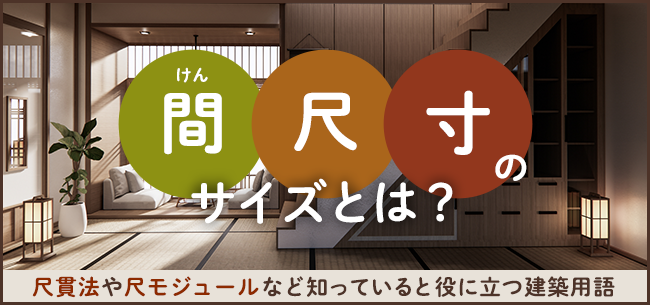- 白銀比(はくぎんひ)〜日本文化の真髄〜
みなさんは、黄金比(おうごんひ)と云う言葉を聞いたことありますでしょうか?
よく、美術の分野でとり入れられている、人が最も美しいと感じるバランスの比率のことです。(1対1.618)
有名なものですと、
ミロのヴィーナス、
モナリザ、
パリの凱旋門などに見られます。
身近なものですと、
名刺、クレジットカード、タバコの箱、台風の雲の渦、オウム貝の殻、アサガオの蔓など自然界にも多くみられます。
恥ずかしながら、今回お話する、
白銀比についてはつい最近になって知りましたので、これから共有したいと思います。
知ることになった1つのきっかけは、
畳の大きさ(3尺=910㍉×6尺=1820㍉)に対する漠然とした疑問でした。
言うまでもなく、畳2枚で正方形になり、
それを1坪と呼んでおります。
最近の間取りでは、和室は少なくなってきたようですが、茶室の四畳半などの正方形のイメージが多いと思います。
そういった、畳や和室に端的にいえば、
正方形と云う形にこそ、
日本文化の美の象徴とも云うべき、
白銀比が隠れているのである。
そもそもの発端は、日本建築の材料である木材の切り出しのところからはじまるのですが、
丸太から最大限の角材を取り出そうと考えた時、曲尺(さしがね、かねじゃく)を使って正円の直径と円に内接する正方形の1辺の長さを出します。
この時、正方形の1辺の長さを1とすると、
その正方形の対角線は、1.41421356……
(ひとよひとよにひとみごろ…無限に続く無理数)つまり√2(ルート2)です。
この1対 1.414 の比率のことを、
白銀比(別名大和比=日本人が美しいと感じる比率)と呼びます。
『雪月花の数学』著者、桜井進氏曰く
もちろん、最初は定規をあて測りながら作品を制作したわけではない。
アーティストは自らの腕と技、そして直感だけを頼りに作り上げた結果として、そこに黄金比や白銀比が現れたとみる。
もともと私達の心のなかに誤差ゼロの比率=『こころの定規』ともいうべきものがあり、感じるものすべてを判断しているのではないかという見解でした。


日本では、丸太の柱加工からはじまり、
法隆寺の金堂・五重塔、平安京の町づくり、
現代でも、武道館の屋根や東京スカイツリーまで、その比率を散見することができます。
また、建築だけではなく、
華道、
阿修羅像などの仏像、
葛飾北斎の浮世絵や
俳句(5:7調の調べ)にも使われています。
身近なものでは、ドラえもん、トトロ、キティちゃんなどのアニメキャラ、
A4用紙、B5用紙などのコピー用紙にも使われています。
A4でいえば、短い辺を1とすれば、
長い辺が、1.414になります。
長い方の辺を半分に折ると、
できた長方形が、また白銀比の長方形になります。
この比率が無限に続いていきますので、これを白銀長方形と呼んでいます。
また、折り紙も基本的には
正方形の紙から、鶴など、色々なものを
無限に折ることができます。
逆に風呂敷(正方形)は色々な形のもの(箱や一升瓶、丸い西瓜など)を包みこむことができます。
コレは、
正方形と云う四角形の中に円相をみている
有限のもののなかに、
無限を観ている。
(茶室の正方形は、方丈(ほうじょう)とも呼ばれ、狭い四畳半のその空間は、世界全体を表すものと捉えられています。)
太陽(天照大御神)の円相に
八百万の神をみる
型ともとれる。
肉体と云う制限の中に、
魂(たましい=みたま)と云う無限をみているのである。
生命を=みたま=円相と観る。
しかし、珠のように丸い形から、
みたまと云うのではない。
空のうちに円満具足して自由自在であるから仮に称して、円相と云うのである。
和室の中に、
日本文化の真髄が内包されているのであるというのが、
今回の新たな発見でありました。
余談ですが、
日本では明治以来、物を測る単位として尺貫法とメートル法が並存していましたが、戦後のGHQの占領政策の一環としてアメリカの圧力により、日本の計量法が改定され、
昭和34年からは尺貫法の使用が禁止され、メートル法の使用が義務付けられました。
GHQはなぜこのようなことを日本に押し付けたのでしょうか?
それは日本弱体化計画の一環で行われたのです。
一国を弱体化する為に有効なことの一つに「文化の破壊」があります。
文化を破壊する有効な手段は「言語破壊」と「計量法の破壊」があります。
〜尺貫法復権運動 永六輔〜
昭和51(1976)年、知り合いの指物師から曲尺で仕事をして警察に呼び出された、という話を聞いた永先生は、この計量法の在り方に疑問に感じ政治家に相談するが改正は不可能と告げられる。
義憤を発した先生は、自らのラジオ番組「誰かとどこかで」で尺貫法復権を提唱、全国の職人衆に決起を呼びかけたほか、自ら尺貫法を使用し警察に自首するデモンストレーションや、曲尺鯨尺の密造密売、プロパガンダ芝居「計量法伝々」の全国公演などの形で尺貫法復権運動を大々的に展開した。
その結果、法律自体の改定は行なわれなかったものの処罰は行なわれなくなってゆき、尺貫法の使用は黙認されるようになったという。
(大永帝国書陵部 「尺貫法復権運動」http://motoda.exblog.jp/1250295/)
今でも計量法自体は依然として尺貫法を認めず、取引などには使えないことになっています。
しかし永六輔さん(『上を向いて歩こう』の作詞でぼくは覚えてます)こうした運動が伝わって、やがて処罰されることはなくなっていきました。
普段、間(ケン)・尺(シャク)・寸(スン)・分(ブ)・坪(ツボ)といった単位を使っても捕まらないのは永六輔さんのお陰といってもいいでしょう
現在建築図面上はメートル法で表記されますが、それは尺貫法で出てきた数字を、メールル法に置き換えて表示しているだけです。
永六輔さんはじめ、尺貫法復権運動に協力してくださった方に感謝します。
(今回書いてる途中で、計らずも最終的にこうなりました)
ご静聴ありがとうございましたm(_ _)m
参考文献 雪月花の数学 桜井進著作
参考ユーチューブ
希望の日本再生チャンネル
黄金比と白銀比(はせくら みゆき)