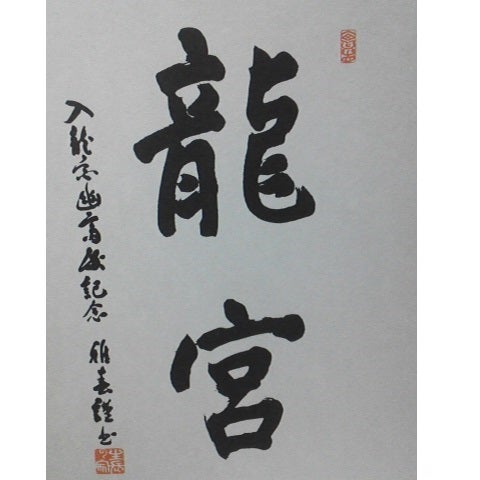浅草上野入門講座 受講修了す
本日令和6年(2024)3月22日(金)、カトリック浅草教会に参りました。
10時からのミサに出て、11時からの入門講座に参加。「一緒ごはん」の日でもありました。
恐らく此方を訪問するのは今日が最後でしょう。
晴佐久昌英神父さんが異動されるからです。
私が此方へ参るのは晴佐久神父さんのお話しを聴くためでした。
とてもよい話をされるのです。
新しい赴任地にも参るつもりですのでお別れではないのですが、浅草と兼任されていた上野教会(先週訪問)の行事に参加するのはこれで終わりですので、卒業シーズンでもあり、なんとなくしんみりとして、なんとも感慨深いものがありました。
少し来し方を振り返ってみます。
初めて神父さんのお名前を知ったのは平成25年(2013)9月頃でした。当時書いていたmixiの2013年09月10日の日記に「カトリック神父の晴佐久昌英さんという方のHPに行き当たりました。」と記しています。以下のHPだと思います。
神父さんのお話しを生で聴いてみたいと思いましたが、当時は多摩に居られたので遠方でもあり叶いませんでした。
その約3年後。チャンスが巡って来ました。神父さんが浅草と上野教会の主任司祭に就かれると知りました。近付いてきました。
そうして初めて浅草教会の門をくぐったのは、やはりmixiに書いていましたが平成28年(2016)7月5日のことでした。以下のように記しています。
浅草橋駅から歩いて少しの鳥越神社とカトリック浅草教会に参りました。
目当てが神社でなくて教会だったのが私のカワッタ?オモシロイ?ところです。
晴佐久昌英(はれさく まさひで)神父さんのお話を聴きたくて参りました。
信者以外でも誰でも参加無料という「入門講座」というのがありまして、そこに参加。
この神父さんについては2013年ごろに、そのご存在を聞き知り、ここの日記にも書いていました。いっぺん生でお聴きしたいと思っていたのです。念願かないました。
晴佐久神父さん…珍しい名前ですね…はその世界では有名なお方で、なんというか、救済力があるというんでしょうか、そんな感じです。信奉者も多い分、批判者もいるらしいですが。
さて私の参加は初顔でもあり、どこから来られたのですか?などいろいろ聞かれましたので、神主だとも伝えますと、やはり珍しがられました。ちなみに神父さんは浄土真宗のお寺さんに呼ばれたりして話をしにいかれたりもされています。あるいはプロテスタントから呼ばれたりも。
で、私が興味深く思いましたのは、晴佐久神父さんが「カトリックと神道は親和的なんですよね…」と仰ったことでした。
「親和的」というのはどういうことなのか、ここで説明する力がありません。
「カトリック」とはそもそも「普遍的」という意味だそうで、この辺りに関係がありそうです。難しいことはひとまずおいて、こんなお話も聞きました。
教会の近くに氏神の鳥越神社があり、私も参拝しましたが、その地域の祭りにも協力的なようで、お神輿の休憩場所を提供したりされたとか。それでお礼のお神酒をいただいたとか。またそうしたご縁でつい先日の水上祭(大祓の人形を流す神事)にも招かれたとか。へぇ~と思いお聞きしました。
カトリックがみんなそんな感じなのか分かりませんが。
でもプロテスタントと違ってカトリックにはそういう感じもあるようですね。
晴佐久神父さんは上野教会も兼任されてるとのことで、今度はそちらにも行ってみようかなと思っています。
地域の個別具体的な場で普遍に触れる、普遍を語る、みたいなことに興味があります。
参考:ぜひ読んでいただきたいもの=神父が新聞に寄稿されたもの(東京新聞)
宗教の普遍性(上)
http://www.fukuinnomura.com/wp-content/uploads/2014/03/04dddc25f3b69a177e7d3e0557b37b0e.pdf
宗教の普遍性(下)
http://www.fukuinnomura.com/wp-content/uploads/2014/03/135b4fe2d5f515627b6813175c572e66.pdf
以上。
また同年7月14日の日記にも書いていました。
前回の続き。
晴佐久神父からコピーをいただいた文章について紹介します。
「固有信仰と普遍宗教」
柄谷行人氏が岩波の雑誌『図書』に「思想の散策」と題して連載しているもの。その11回目(7月号)です。
「祖霊信仰は世界各地に普遍的に見られるものである」として縷々述べられています。
最後の方を引用します。長くなりますが要約力がないのでお許しを。
≪キリスト教は先祖崇拝を否定するという通念から見ると、ライプニッツが以上のような考えを支持するのは訝しく聞こえる。しかしカトリックには、マリア崇拝や多くの天使、聖人への信仰など多神教的な要素がふくまれている。たとえば、晴佐久昌英神父はつぎのように説教している。
カトリック教会は、伝統的に十一月を死者の月として、死者と深い交わりを持つ時として過ごします。言うなれば、カトリックの「お盆」です。日本では亡くなられた方々をお盆にお迎えしますけど、尊い習慣ですね。死者を大切にしないということは、生者も大切にしないということです。現代において、死者と交わりを持つことはすごく大切だと思いますよ。しかも、単にこちらからその方々のために何か祈るというよりは、その方々のほうが私たちのために祈り助けてくれていると信じて深い交わりを持つことが、豊かな生を生きるためにどうしても必要なことです。(中略)この、すでに天にある方が我々のために祈っているという信仰は、実にカトリック的な信仰です。その代表格は聖母マリアということになるんでしょうが、すべての天使と聖人、そして亡くなった家族、友人が、天にあって神のそばで我らのために神にとりなしてくれる。そのように永遠の天の世界と胎児の地の世界をしっかり結んで、天地の通路、天への産道となったのが「道」であるイエス・キリストという救い主なのです。(中略)こうして私たちはこの世にあって愛し合って生きていますけれども、考えるまでもなく、天の方々が私たちを愛してくれている愛のほうがずっと強い愛ですし、そういう天上の愛に支えられて、ようやく私たちもこの世界で愛し合うことができるのでしょう。たぶん、本当に愛するために私たちは死ぬのです。(『あなたと話したい』教友社、2005年)
このような考えがカトリック教会で公認されているのかどうか、私は知らない。しかし、私が驚いたのはここに先祖信仰が見出されることではない。それが柳田のいう固有信仰と類似していることだ。それは、子孫らがいかなる態度をとろうと、祖霊はひたすら子孫らを愛し見まもるという点においてである。
通常、先祖信仰では、死者と生者の関係は互酬的である。つまり、生者が死者を弔うから死者は「御霊」になるのであり、それゆえに、祖霊は生者にお返しをする。ところが、ここには、そのような互酬性がない。祖霊は一方的に、つまり、無条件で子孫を愛することになっている。それはまさに、柳田が日本の固有信仰と見なしたものと同じであるように私には思える。しかし、それは日本人というより人類の固有信仰である、と私は思う。では、どうしてそれが特に日本に見出されるのか。次回にそれを考える。≫
御覧の通り、晴佐久神父の著書より引用がなされています。そのこともあって神父さんが「入門講座」で取り上げられたようで、私が今回参加する以前のことのようでしたが、私が神主ということもあってコピーをくださったのでした。
それで、神父さんが、この文章について、ここで重要なのは、として指摘されたのは、神(祖先)と子孫の関係は「互酬的」でなく、「一方的で無条件」ということでした。
なるほど、おもしろい、と思いました。
ちなみに柄谷氏の連載は、先に出版されている、柳田国男先生についての評論『遊動論―柳田国男と山人』(文春新書、2014)と同じような内容かなと思います。
このようにして教会通いが始まりました。
一番初めは門をくぐるのにたいへん勇気がいりました。門の前で躊躇逡巡することしばし。やっぱり止めておこうか、帰ろうか…と。でもせっかく来たのにこれで帰ったら空しいだろうな…とか。そうして思い切って中に入っていったのでした。懐かしい。入門講座は信者でなくてもいいのです。
コロナ下の2年間は不参でしたので実質5年半ぐらいの間でした。初期の頃を除き毎回メモを取っていたのですが、その記録を調べると少なくとも浅草上野合わせ53回は通っていました。
何が私をそうさせたのか。
説明するのは難しい。
とにかく「聴きたい」と思ったのです。
「本当」のことが、「本物」が語られていると思ったのです。
これからもお話を聞きに足を運び続けることでしょう。
【追記】