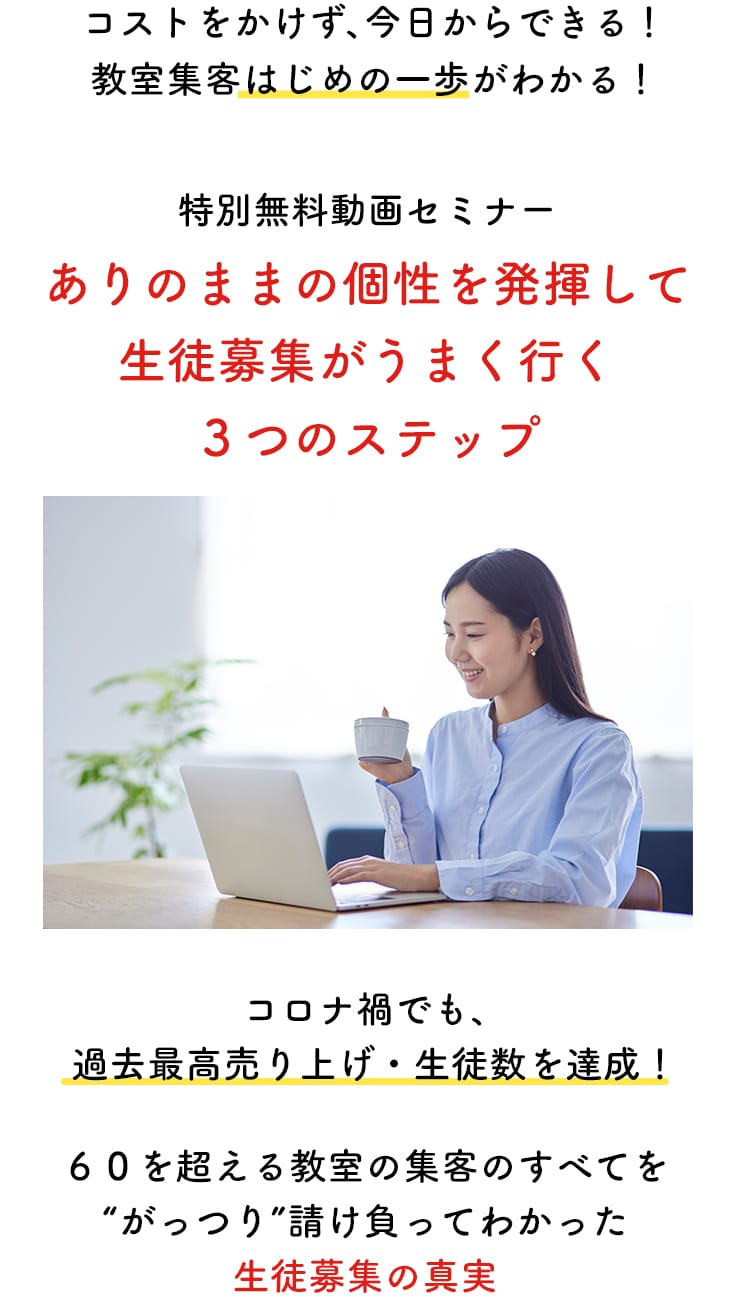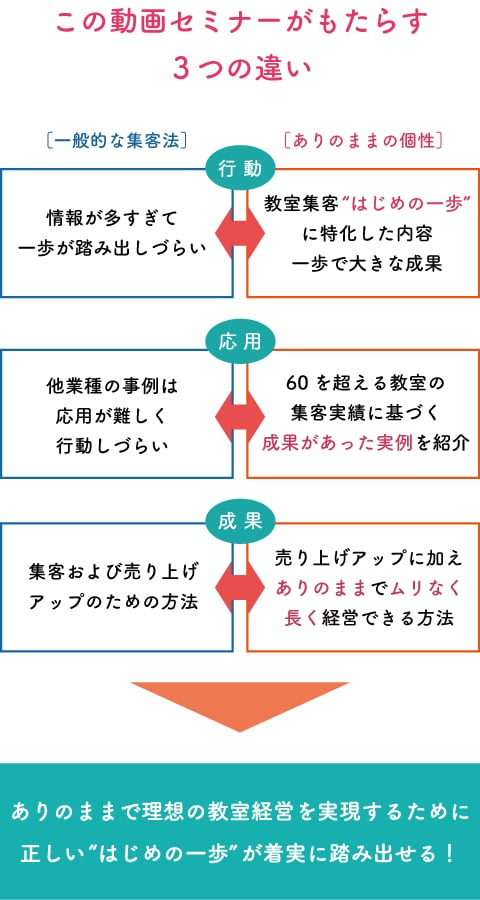【Googleマップで差をつける!自宅教室の集客を強化する秘訣】
教室の集客にお悩みですか?
この動画では、教室における
効果的なSNS集客法とノウハウを紹介しています。
教室の集客力を向上させるための
具体的なアイデアや戦略が学べます。
理想の教室を実現するためのヒント
教室の集客術を知りたい方はぜひご覧ください。
【制作者プロフィール】
■ 増地 崇(教室経営コーチ)
2004年にネットビジネスで起業する。
現在まで、30業種以上のwebサイト制作
およびマーケティング担当を歴任。
20代のときに、野球スクールのインストラクターとして
累計1,000名を超える選手をサポート。
退職後は、祖父が創業し母親が経営を引き継いだ
学習塾のネット集客にも携わる。
1日500件のポスティングを2日連続で
敢行したり、毎月、塾前のポスターを
デザインし掲示、既存生へのDM・ニュースレターの作成、
塾およびトイレ清掃などお金をかけずに集客するための
アナログ的な実践も数多くこなしてきた。
その経験をもとに、2011年から教室のネット集客を
サポートする事業を開始。
現在まで、30のジャンルを超える
教室ビジネスの経営支援を行ってきた。
サポートでは、集客アドバイスのみに留まらず、
コンセプトの立案〜セールスコピー(教室紹介文)執筆〜
WEBサイトデザイン〜WEBマーケティング〜
WEBサイトメンテナンスおよび
経営コーチングまでを一人ですべてこなしている。
その結果、生徒数5倍、ホームページ経由で
テレビにも出演したレザークラフト教室、
新規オープン1ヶ月で30名の生徒を集客した
フラダンス教室、1年で生徒数が52名から
90名にまで増えたピアノ教室、
6ヶ月で利益が2倍になったボイトレ教室、
遠方からも入会希望者が殺到する
ピラティススタジオなどのサポート実績がある。
また、その実績が書籍で紹介されたり、
専門誌にも執筆している。
【これまでサポートしてきた教室】
レザークラフト教室・オンライン占いスクール・
ピアノ教室・パン教室・野球スクール・某大手学習教室・
英語スクール・オンライン英会話スクール・学習塾・空手教室・
護身術教室・書道教室・オンライン学習塾・太極拳教室・
パソコン教室・プログラミング教室・某大手音楽教室・
ピラティススタジオ・レイキスクール・フラワーアレンジメント教室・
エステスクール・ボリウッドダンススクール・ボールダンス教室・
ボイストレーニング教室・バイオリン教室・音楽教室・
フラダンス教室・ヨガスタジオ・電子書籍出版スクール・
数学教室・アロマ、クレイテラピースクール・ウクレレ教室・
造形教室・絵画教室・テーブルコーディネートスクール etc
教室集客の“はじめの一歩”とは?
※提供を終了していたり、別の動画が配信されている場合がございます