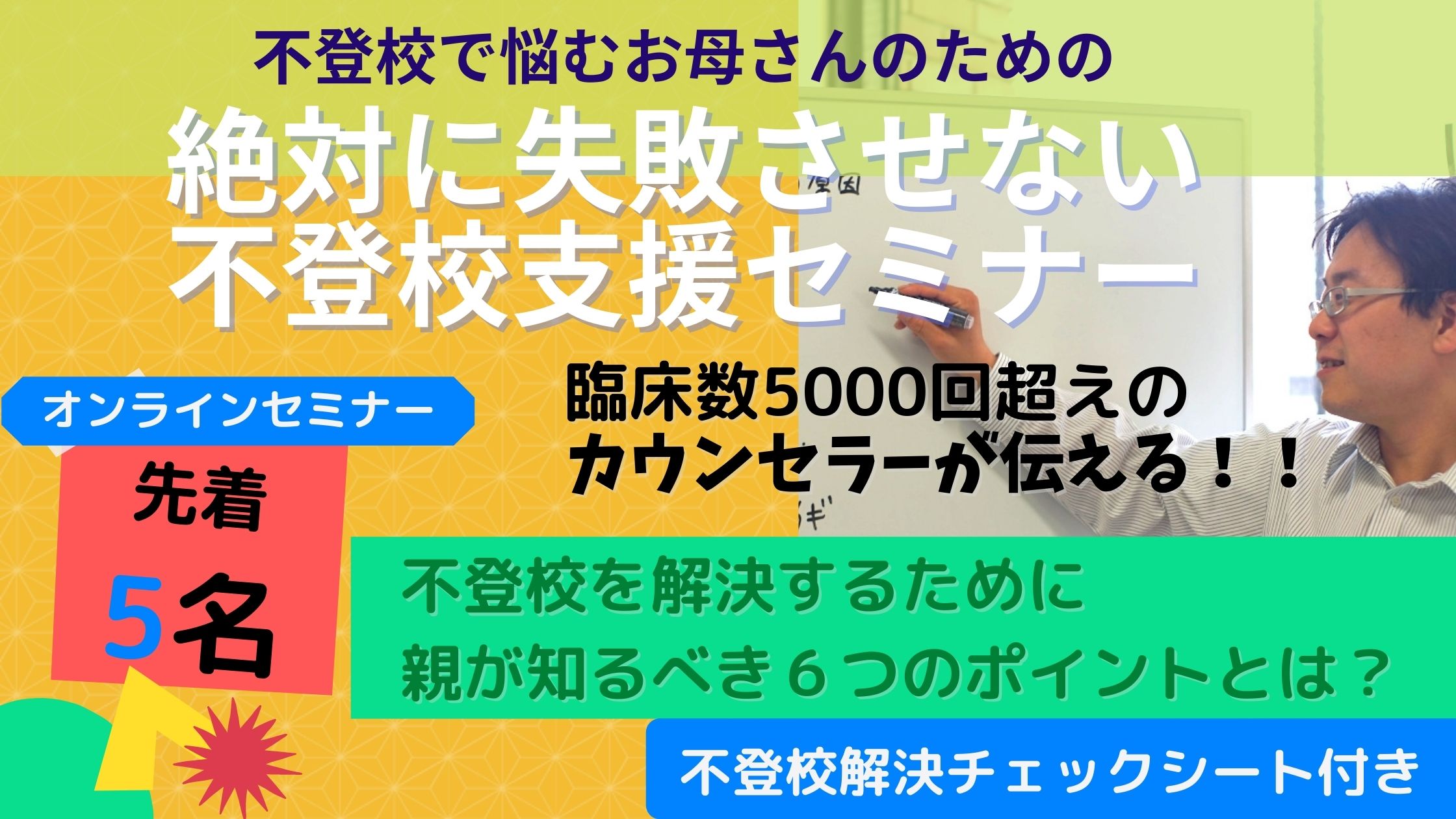いつも読んでいただいてありがとうございます。
不登校専門心理カウンセラーの田中です。
今回は今日のメルマガで発行した内容の転載です。
私の不登校カウンセリングの根幹の一つなので、
ブログにも掲載させていただきました。
私のカウンセリングのスタイルでもあるのですが、
不登校支援の基本は「後出しじゃんけん」です。
どういうことかというと、
親は「子どもが発言してから動く」ということです。
例えば、子どもが「これがしたい」という前に、
「これはどう?」と声をかけると、
多くの子どもは戸惑います。
不登校のお子さんの場合、
相手の気持ちを推し量ってしまって、
自分の気持ちを押し殺してしまう傾向が高い。
もちろん、
「お母さん、それは違うから嫌よ」
と言えればいいのですが、
そう言い切るエネルギーはないことが多いです。
そのため、
「お母さん、違うと言ったら悲しむかな」
と思ってしまって、
自分の心を押し殺して、「うん、わかった」と答えます。
もう少し具体的に言いましょう。
大人が「学校に行ったら」と言い続けて、
ある日子どもが無理やり学校に行こうとするのはよくあることです。
そうなると大人は「良かった」と一安心します。
でも子どもに中では、
「なんか違うんだけど・・・」という違和感をずっと抱えたままです。
でもそうした気持ちを周りはわかってくれません。
それが続くと、ある日再不登校となります。
要はエネルギー切れです。
ただ、再不登校は結構怖いです。
子どもの中では「また学校に行けない。自分はもう終わりだ」
と一層自信を失くし、回復にはさらに時間がかかります。
じゃあどうすればいいかというと、
次の順番を心掛けることです。
- 不登校の特性から子どもを理解する
- 理解する中で子どもが安心して発言できる環境を作る
- 子どもが「〇〇したい」と言ったことに沿う
- 一緒に取り組んで解決していく
この一連の流れを私は「後出しじゃんけん法」と呼んでいます。

要は「先にグーを出すのではなく、
相手がグーを出してから、どの手を出すかを考えましょう」
ということです。
そのためには、相手が「グーを先に出してもいい」と
思えるような状況を作り、手を出した後で、子どもが
「勝ちたいのか、アイコがいいのか、負けたいのか」を確認した後で、
そこに沿って対応していくということです。
先に手を出すのではなく、
相手が出してから一緒に考えていく。
これが大事です。
ちなみに、後出しじゃんけんが上手な人は、
子どもを理解するスキルが高いです。
「ああ、この子はこういう子だな」と思えると、
先回りを上手にすることができます。
子どもが「学校に行きたいかどうか」を確認する前に、
学校に行ける支援を進めても意味はありません。
まずは子どもとの関係を築いていき、
子どもの心が回復した後で、
「あ、学校に行きたいな」と言い出した時に、
学校に行くかどうかを考えていくことが正規のルートです。
もちろん、子どもによっては、
ある程度先に手を出したほうがいい場合もあります。
そのためにも子どもを理解するスキルが必要なのです。
ちなみに、このスキルは先天的なものではなく、
適切な知識を学ぶことと、カウンセリングによる気づきを
繰り返すことによって誰にでも獲得することができます。
不登校解決カウンセリングでは、
そうしたスキルの獲得を短期間で得ることができます。
もしよろしければ、
不登校解決カウンセリングの体験セミナーを無料でしています。
毎月2回開催しています。
よろしければどうぞご参加くださいね。
ではでは、また来週お会いしましょう♪