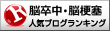
脳卒中・脳梗塞ランキング
⭕️CHAT GPT-(ゴルフ後の痛みについて−8−肩甲上腕リズム-1)
●肩甲上腕リズムでの 下部分の動き
(0度〜45度)の問題
●ハピクニの質問→
2025年10月末にゴルフで痛めた健側の左腕が挙がらない状態で困っています。 ハピクニの分析によると医師の画像診断では 腱板損傷はなく、おそらくハピクニが考えると筋肉自体の炎症と神経自体の炎症が原因であると思われます。神経の問題なら次第に時間の経過とともに回復すると思いますが、筋肉の炎症により筋力低下が一番の原因だと考えています。
具体的には、肩甲上腕リズムでの 下部分の動き(0度〜45度)の範囲で腕を挙げる動作が出来ないことが原因だと思います。
一方、 肩甲上腕リズムでの 上部分の動き(90度〜180度)の範囲は辛うじて出来ます。
これを回復させるリハビリやトレーニング
を教えてください。
●参考→肩甲上腕(けんこうじょうわん)リズムとは、腕を上げるときに肩甲骨と上腕骨(腕の骨)が連動して動く一定の法則のことです。
●参考図→人形町整形外科ペインリハビリクリニック
主な特徴とメカニズム
動く比率(2:1の法則)
腕を横から真上まで180度上げるとき、上腕骨が120度、肩甲骨が60度(上方回旋)動きます。
この「2:1」の割合で協力し合う仕組みを指します。
動き出しのタイミング
一般的に、腕を上げ始めて最初の30度(または45度付近まで)は主に腕の付け根の関節(肩甲上腕関節)が動き、それ以降に肩甲骨が大きく回り始めます。
メリット
この連動があるおかげで、広い可動域を確保できるだけでなく、肩の筋肉(インナーマッスル)が効率よく働き、関節の安定性が保たれます。
リズムが崩れるとどうなる?
猫背や肩甲骨周りの筋肉(前鋸筋や僧帽筋など)が硬くなると、このリズムが崩れます。
肩の痛み・インピンジメント: 肩甲骨がうまく動かないと、腕の骨が肩の屋根(肩峰)にぶつかり、痛みや炎症を引き起こす原因になります。
可動域の制限: 四十肩・五十肩のように腕が上がりにくくなるトラブルに直結します。
●参考文→グーグルAI
●ChatGPTの回答→
状況の整理と自己分析がとても的確です。
「0〜45°の立ち上がりができないが、90〜180°は何とかできる」という所見は、臨床的にも初動筋群+神経抑制の問題を強く示唆します。
以下は
腱板断裂なし/炎症後の筋力低下+神経性抑制
を前提にした、安全性重視・回復段階別リハビリです。
⑴ なぜ「0〜45°」だけ挙がらないのか(重要)
主に関与する構造
0〜45°の挙上は 「重力に逆らって立ち上げる」最も負荷の高い角度で、以下が鍵になります。
●棘上筋(最重要)
●三角筋前部
●肩甲骨の初動安定(前傾・上方回旋の準備)
神経の“出力許可”(炎症後はここがブレーキになる)
👉 90°以上ができるのは
反動・代償・肩甲骨の勢いで動かせている可能性が高いです。
⑵ 原則(これを守ってください)
❌ やってはいけないこと
痛みを我慢して挙げる
90°以上ばかり鍛える
ダンベルでいきなり前挙
⭕ 守るべきルール
痛みは「0〜2/10」まで
0〜45°だけを徹底的に再教育
反動・すくみを完全に排除
⑶ 回復の核:0〜45°専用リハビリ(超重要)
【STEP1】神経再教育(毎日・最優先)
目的:筋力ではなく“出力スイッチ”を戻す
① テーブルスライド(前方)
椅子に座る
テーブルに手を置き、体を前に倒して腕を前へ滑らせる
自力ではなく「滑らせる」
挙上角度:0〜45°
🕒 10回 × 2〜3セット
② 壁前挙(超軽負荷)
壁に向かって立つ
指先で「登るように」挙げる
肩がすくんだら中止
🕒 5〜10回 × 2セット
👉 これは神経と棘上筋の再接続が目的です
【STEP2】棘上筋・三角筋前部の“安全な筋トレ”
③ スキャプション(30°前方)
正面ではなくやや斜め前(30°)
肘は軽く曲げる
挙上は45°までで止める
💡負荷:
最初は 0.5kg以下 or チューブ
重さより「動きの質」
🕒 8回 × 2〜3セット
⑷ アイソメトリック(静止)
壁に拳を当てる
腕を前に挙げようと力だけ入れる(動かさない)
角度:20〜30°
🕒 5秒 × 5回 × 2セット
👉 炎症後の筋には非常に効果的
④ 肩甲骨の準備運動(超重要)
⑤ 肩甲骨セッティング
肩を「下げて・軽く寄せる」
その状態で深呼吸
🕒 5呼吸 × 3セット
⑥ 前鋸筋活性(壁プッシュ)
壁に手をつく
肘を伸ばしたまま肩甲骨だけ前に出す
🕒 10回 × 2セット
👉 初動が出ない人の必須種目
⑦ 進歩判定の目安(重要)
次に進んで良いサインは:
反動なしで 45°まで自力で挙がる
翌日に痛みが残らない
肩がすくまず動く
❌ これが出たら一段階戻す:
夜間痛
動作後にズーンとした重さ
首や僧帽筋の張り増加
⑧ 回復の見通し(現実的な目安)
神経性抑制優位 → 2〜6週間
筋炎症+萎縮 → 1〜3ヶ月
脳梗塞後の健側酷使が背景にある場合
👉 通常より回復は遅いが、回復余地は大きい
⑨ 重要な一言
「挙がらない筋を鍛える」のではなく
「挙げる許可を脳に出させる」
この視点で行ってください。
必要でしたら
1日の具体的メニュー表
ゴルフ復帰を見据えた段階的負荷
図解(A/Bスタイル)
も作成できます。
どこまでやりたいか教えてください。
●腕を挙げる メカニズム順番→
は以下の通りです。
①開始: 三角筋や棘上筋の活動により、まず肩甲上腕関節で腕が持ち上がり始めます。
②連動: 腕の角度が増すにつれて、僧帽筋や前鋸筋が働き、肩甲骨が同時に回旋(上方移動)します。
③完了: 最終的に肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節の両方の動きが組み合わさり、腕が頭上まで完全に上がります。
この複雑な連携により、人は広い可動域で腕を動かすことができるのです。このメカニズムのどこかに問題が生じると、肩の痛みや動かしにくさにつながることがあります。
⭕️腕が挙がらないという一連のハピクニの感想→私はゲームはしませんが、ゲームの終わりに出て来るラスボス(オペを進めた頚椎症の専門医師)と天使(整体接骨院治療)のような感じです。
つまり、
人生の分岐点 or 完全回復への分岐点で、天使と悪魔が現れ出てくる感じです。
⭕️おまけ
●腕の上げ下げから判断される原因
①0°~30°程度の範囲内で痛み動かしづらさがあれば、棘上筋
②30°~60°の範囲内で〃三角筋
③60°~120°の範囲内で〃棘上筋
④120°~180°の範囲内で〃棘下筋、小円筋
●参考図・文→らいおんハート整骨院 武蔵野



