“「いじめは正義だから 悪をこらしめているんだぞ」
そんな風に子供に教えたのは 僕らなんだよ”
―天使と悪魔 SEKAI NO OWARI
18日は セカオワアルバム発売日で。
初回盤は武道館DVDがついていますのよ、なんと豪華!
あのライブに行くことが出来てよかったなぁ。
時間は 早いなぁ。しみじみ。
19日は なんだか胸がざわざわすると思ったら
河合隼雄先生の命日で。
あぁ、もう 5年。
どれだけのものをいただいたか はかりしれない。
同じ様に今もどれだけのひとが 先生が生きていたことに、遺されたものに
救われていることだろう。
きっとあの笑顔で見てくださっている先生に、恥じぬ生き方をしたい。
20日 終業式、1学期終了。
怒涛の学期末…バタバタバタっと。
夏も子どもの心理検査やら何やら慌ただしいですが、
ひと安心。
いつも 学期が終わると 思うこと。
誰も命を落とさなくて、本当によかった。
そして いじめのニュースで 日本中も騒がしかった、この学期末。
今だから
書かなきゃいけないな、という想いに 駆られました。
“いじめは下火になるどころか、ますます深刻さを加えている。
これは、いじめ問題の根の深さを如実に示している。
それと共に、これまで「いじめの根絶」をかかげて、日本中で努力してきたやり方に、
どこか反省すべき点がなかったか、考えてみる必要があることを示唆している。
いじめによる自殺が生じてから、何としてもいじめを無くさなくては、という気持ちが国民の間に強くなったし、
文部省をはじめ教育機関もその線に沿って努力してきた。
しかし、その姿勢は結果的には子どもたちに対してますます監視の目を強くし、
彼らを圧迫することになっていなかっただろうか。
加えて、「原因」をさがして除去してしまおうとする性急な態度は、
「悪者」を見つけては罰することにつながっていなかっただろうか。
それで問題を解決したような気になっていたとすれば、それは大きな誤りである。
「いじめは絶対に許さない」という厳然とした筋を通す態度と、
悪者を見つけだして罰していこうとする態度は、似て非なるものである。
前者は子どもたちを守る強い壁として存在しているのに対し、
後者は子どもたちを圧迫するブルドーザーのように作用する。
いじめをなくす一番よい方法は、「いじめ」のことにせっかちに対処するのではなく、
子どもたちに伸び伸びとした楽しい生活を準備することである。
なんとかしていじめをなくそうとか、見つけだそうと頑張るのではなく、
子どもたちがリラックスできる状態をつくりだしていく、親や教育者の温かい姿勢が大切なのである。
このように考えると、今の子どもたちのおかれている状況は、
あまりにもかわいそうではなかろうか。
大人からの監視の目は強い。
「受験」の重圧を早くから背負わされ、しなくてはならぬことが多い。
家族の間にはほんとうに心の交流する時間が少なくなりすぎている。
子どもたちが「やり切れない」「むかつく」状況をつくっておき、
まるで、いじめをせざるを得ないような状態に追い込んでおきながら、
いくら「いじめの根絶」を叫んでも無理というものである。
(中略)
いじめは、大人がどんなに監視していても、やろうとすればできるし、
なかなか大人の目には見えないものである。
いじめを無くすことは大切なことである。
しかし、それを無くそうと肩に力を入れるのではなく、むしろ肩の力を抜いて、
「いったい自分は、子どもたちが自由に楽しく生きていくために、どれほどのことをしているだろう」とか、
「子どもたちと一緒に楽しい時間をどれほど過ごしているだろう」とかいうようなことを、それぞれの大人が考え直してみる必要があるのではなかろうか。
そのように楽しい時間を共有することもなく、
ただただ、いじめはダメ、と言うのは、問題を深刻にしているだけである。 ”
(『縦糸横糸』 河合隼雄 1996)
もちろん マスコミからだけでは伝わらないことも多いだろうけど。
最近のニュースを見ていると。
この学校や教育委員会は、
何を守っているんだろう?と 思わざるをえなくて。
何を守りたいんだろう、
何を大事にしたいんだろう、
自分の子が自殺してしまった立場だったら同じことを言えるのだろうか、
何でここまで想像力が足りないんだろう、
教育って何だろう。何を教え育てているの。
わたしは、子どもが育つのに
“こんな大人になりたい”と思えるひとが周りにいることって
ものすごく大事だと思っていて。
もちろん小さいうちは 誰かを恩師と崇めるまでは無くても
この大人は 自分たちを愛してくれているな、ちゃんと見てくれているな、とか
この大人は 自分の仕事が好きなんだな、きらきらしているな、 とか
この大人は 大事なことをごまかさないな、とか
ちゃんと感じるものだと思うのです。
悪者探し、くさいものには蓋をする、
そんな大人を見ていたら
安心して過ごせるだろうか。
未来に希望を持てるだろうか。
「いじめ」を「病気」に置き換えてみると
通じるところが多いなと ふと思って。
そりゃ無いほうがいい、
でも今も世の中にはたくさんあるのも事実で
見つけたら無視しないのも大事、
そして日々予防するのも とても大事。
目を背けるほど 命にかかわる。
自分が子どもの時も、そうだ。
色んなところで、いじめは起こっていた。
異質と感じる相手を排除しようとしたり、
自分がターゲットにならなければ安心だったり、
そういうのって 小さい子にも備わっている本能みたいなものなのかどうかは、
わからないけれど。
人は 心。
言葉は 心。
人は 否定され続けると、
心が壊れてしまうから。
大人になると(もちろんわたしも) あの頃の感覚を忘れてしまうけれど、
小学校中学校の頃って特に
家と学校で過ごす時間が ほとんどで。
その世界の中で生きていて。
ちっちゃい心でいっぱい、
今日は平和に過ごせますように、って 祈りながら通学路を歩いている子も
きっとたくさんいて。
もし その家と学校どちらかでも
居場所が無くなってしまったら。
否定され続ける 恐怖でしかない場所になってしまったら。
どちらでも それを話せることが出来なかったら。
ましてや、周りの子どもや大人が それをわかっていて無視していたら。
その子の日々は、どれだけ苦痛だろう。
地獄だろう。
わたしの勤務先の小学校でも中学校でも、
正直 いじめは日々 起こっていて。
先週も今週も 先生方と対応しながら、話を聞きながら。
学校が「狭い世界にならないこと」は
本当に大事だと思っています。
内田樹先生が過去におっしゃっていた
“将来、社会全体がこうなればいいな、という世界の縮図が
いま 自分が居る場所であると良い、
そうであるように努めるのが大事”
というお話、わたしはすごく大事にしていて。
完全に無くなることはないかもしれない、
けれどそうやって人の心を殺すのは絶対にいけないことだ、という姿勢を
教職員全員が持ち、予防につとめ、
何かあったら すぐに&全体で対応、子どもたちに隠したりごまかしたりしない。
そして何より日頃から 子どもたちが安心して過ごせる環境作りに努めること。
話しやすい大人、きらきらしている大人がたくさんいること、
授業が楽しくていろんなことを知りたいと思えること、
学校自体も 家庭に、地域に ひらかれていること。
いじめる側にも そこには心が在るはずで。
かつて自分がいじめられていたから 恐れていたり、
家庭に居場所が無かったり、
とにかく自信がなかったり。
自分はこれをやりたい、とか 認められている、って自信がある子は
周りのひとのことも 自然に受け入れられるんだよね。
人の心を殺してしまう前に
芽が小さいうちに
ひとりひとりの心を 多くの大人の目で見て 愛して 守ることが大事だと思う。
日々 事件だらけだけれど、そんな姿勢で
素晴らしい先生方とお仕事が出来ていること
わたしは自分の居る場所を、誇りに思います。
まさに 将来の日本が こうであればいいな、って場所だし、
今後もそうであるように努め、つなげて広げていかなければならないのだと思っている。
大人たちは、わたしたちは
何を守っているの。何を教えて育てているの。
死を選ぶことでしか 哀しみや正義や疑問を訴えかけられない命なんて
あるわけが無いんだ。
あってはいけないんだ。
自分を生み育ててくれた両親にも言えない苦しみは どれほどか。
自分より先に我が子が 失われた世界の苦しみは どれほどか。
起こってしまったことは 事実をきちんと明らかにして 隠されず
関係者に話してもらえますように。
周りの生徒のみなさん、保護者やご家族の方々の心のケアが 丁寧になされますように。
今も 友達、先生、親、家族、
誰にも言えず苦しんでいるひとも。
相談するのも恐怖、という気持ちも強いだろうけれど。
その心や命を守るため、早めに相談してほしいな、と思います。
24時間いじめ相談ダイヤル 0570-0-78310
※上記のダイヤルに電話すれば、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm
各都道府県の臨床心理士会も連携しています。
人としても SCとしても
色々考えてしまう夏だけれど。
どの子どもたちにとっても
夏休みは良いものでありますように。
縦糸横糸 (新潮文庫)/新潮社
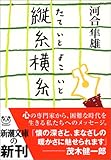
¥540
Amazon.co.jp