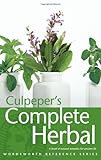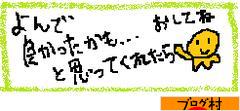一昨日は二十四節気のひとつ「白露」でした。
陽の極まりを過ぎ、
吹く風には秋の気配がしています。
今日はグレゴリオ暦の9月9日で、
Twitterなどを見ていると、
「重陽」という言葉が目につきます。
そういえば、朝5時になっても
窓の外はまだ暗いまま。
日の出がすっかり遅くなっていました。
実際の重陽節は、
今年は10月の9日ですが、
新暦9月9日と、旧暦8月9日が重なって、
999の3つ揃い。
新旧二度重陽節を楽しんでも
バチはあたりませんね。
しかも!
今朝はこんな素敵なプレゼントが届きました。
なんと横浜在住のJ先生が、
月餅と媽祖様のお守りを
贈ってくださいました。
台湾で、私が一番行くのが
媽祖廟なのですが、
先日都内に出た際、
帰りに横浜媽祖廟に行こうと思いつつ、
行けなかったので、
心残りだったんです。
もちろんJ先生にはそんなことは
お話していないので、
嬉しいやらビックリやら。![]()
先生ありがとうございました!
お昼ごはんの代わりに
月餅を頂いております![]()
ところで、話はぐるんと変わりまして。
この世界には、
「照応」という考え方があります。
一見無関係に見える物事が、
それぞれ関連しつながっているという考え方は
現代にも受け継がれています。
例えば占星術は、その根本は、
天の星の運行と大地で起こることには
関係性がある(照応している)
という考え方がベースになっています。
占星術に興味が有る方には
よく知られていることですが、
かつて占星術を使った医学というものが
非常に重視されている時代がありました。
その時代に活躍した在野の医学者
ニコラス・カルペパーが記した文献には、
天体と人体との関連や、
様々なハーブと天体との関連などが
様々に著されています。
17世紀に書かかれたにも関わらず、
今でも重版を重ねられているのですから
恐るべき大ベストセラーです。
※私が持っているのはコレです。
一方東洋に目を転じると。
西洋が四大エレメンツ、
東洋は五行の違いはあるものの、やはり、
世界と人体との照応が考えられてきました。
これは私の私物の「東醫寶鑑」という医書です。
著者のホ・ジュン(許浚/허준)は
1539年に生まれた李氏朝鮮時代の医者です。
私は1999年に放送された、
チョン・グァンリョル版の
ドラマ「ホ・ジュン宮廷医官への道」で、
この書物のことを知りました。
日本では「チャングムの誓い」というタイトルで
人気が出た「大長今」は中宗王の時代で、
ホ・ジュンはおよそ50年後、
その三代後の宣宗王から光海君の時代に
活躍した人でした。
日本では豊臣秀吉がいた頃になります。
 | ホジュン~伝説の心医~(ノーカット完全版) DVD-BOX 第一章 19,440円 Amazon |
※こちらは2013年のキム・ジュヒョク版のホジュン
「東醫寶鑑」は1613年、
光海君の時代に発行された書物で、
23編25巻で構成された
アジア圏では広く読まれた医書のひとつです。
日本では1724年に徳川吉宗が
江戸時代初の官版医書として
日本版を発行し、
更に75年後再版されました。
中国でもほぼ日本と同時期に発行され、
さらに日本の再版本を元にして
1809年に復刻本も作られています。
近年では、2009年に、
ユネスコの世界記録遺産に指定され
話題となりましたが、
残念なことに、日本では
現代語訳は既に絶版となり、
日本語でこの本を読む事は
とても難しい書物です。
私はドラマを初めて見て以来、
5,6回以上視聴したほどに、
このホ・ジュンと「東醫寶鑑」に
興味を惹かれました。
もちろん医学なんて、
私にはハードルがあまりに高いので、
単なるミーハー趣味ですが。
なんとか「東醫寶鑑」を読みたい・・と、
何年も探しているうちに、
ある時、台湾の友人から
昭和46年(民国暦61年)に出版された
「台湾発行東醫寶鑑」を
誕生日プレゼントにいただくという
幸運に恵まれました。
手擦れのしたその本の裏表紙には、
中国医薬学院というサインがあり、
15世紀の書物が
20世紀の台湾で学ばれ、
21世紀日本で私が手にしていると思うと、
なんだか感慨深い気持ちになります。
さて。その「東醫寶鑑」ですが、
内景篇巻一を開くと、
照応についての著述を
読むことができます。
※ページの写メです。ここには漢字だけですが
ハングルで表記されている部分ももちろんあります。
私の拙い翻訳が青字の部分です。
赤字で説明もつけてみました。
孫真人曰
(孫真人は言った)
天地之内 以人為貴
(天地の内で 人を貴いとなす)
頭圓象天 足方象地
(人の頭が丸いのは天をかたどり
足が四角いのは地をかたどる)
天有四時 人有四肢
(天に四季があるように
人には4本の四肢がある)
天有五行 人有五蔵
(天に五行があるように
人には五臓がある)
※五行:木・火・土・金・水
五臓:肝臓・腎臓・心臓・脾臓・肺
天有六極 人有六府
(天に6方角があるように
人には六腑がある)
※六極:東西南北+上下の6方向
六腑:内部が腔となっている六つの内臓。
大腸・小腸・胃・胆・膀胱・三焦
天有八風 人有八節
(天に八風があるように
人には大きな8関節がある)
※八風:北・北東・東・南東・南・南西・西・北西から吹き
季節を生じ人体に影響を与える風のこと。(注1)
八節:両肩、両肘、両膝、両足の付け根
天有九星 人有九竅
(天に九星があるように
人には9つの穴がある)
※九星:九星と呼ばれるものは幾つか存在する。(注2)
九竅:口・両目・両耳・両鼻孔・尿道口・肛門
天有十二時 人有十二經脉
(天に十二時辰があるように
人には12の経脈がある)
※十二時:時間を二時間づつで区切っていく時法。
「〜の刻」という言い方でお馴染み。
十二経脈:正経十二経脈のことで
五臓と六腑、心包のそれぞれに繋がる12種類の
気の流れる経路のこと。
天有二十四氣 人有二十四兪
(天に二十四節気があるように
人には24の経穴がある)
※二十四氣:1年の太陽の黄道上の動きを
視黄経の15度ごとに24 等分したもの。
現在の日本では二十四節気と呼び、春分秋分などは
祝日にもなっている。
二十四兪:陰部から顎への一直線上にある24の経穴.
天有三百六十五度 人有三百六十五骨節
(天が365度であるように
人には365の関節がある)
孫真人は本名を 孫思襞と言い、
現代では保生大帝として信仰されている方で
医学に長けた人であったと
言われています。
その医術は神に通じる程で、
龍の目や虎の喉の不調を治したという
そんな伝説があるほど。
私の高雄スピリチュアルツアーに
ご参加してくださった方なら、
これを読んで「あれ?」と
気づいた方もいらっしゃるかも。
そう。ツアーでご案内している、
蓮池潭の龍虎塔の真ん前にある、
あの大きな廟が保生大帝廟です。
(廟の中でこのお話をしましたね![]() )
)
ホ・ジュンは「東醫寶鑑」の中で、
まず最初に保生大帝がこう語ったのだと、
この世界と人間の体の照応関係について
記述しています。
ここの部分は、先ほどあげたドラマでも、
最終回間近の回で、
ホ・ジュンが師匠から教えられたこととして
記述していく様子が描かれています。
更に「東醫寶鑑」ではこう続いていきます。
天有日月 人有眼目
(天に日月があるように
人には目とまなこがあり)
天有晝夜 人有寤寐
(天に昼夜があるように、人は起きて寝る)
天有雷電 人有喜怒
(天にカミナリとイカヅチがあるように
人には喜びと怒りがある)
天有兩露 人有涕泣
(天に雨露があるように、
人には涙や鼻水がある)
天有陰陽 人有寒熱
(天に陰陽あるように人には寒熱がある)
地有泉水 人有血脉
(地に泉があるように人には血潮があり)
地有草木 人有毛髪
(地に草木があるように人には毛髪がある)
地有金石 人有牙齒
(地に金属や石があるように
人には牙や歯がある)
皆禀四大五常 假合成形
(みなこの四大五常の関わりの中で、
ひととき合し形を成すのである)
このように読んでいくと、
歴史の中で、西も東も人々は、
森羅万象の中に
様々な出来事の法則を見つけ出そうと
知恵を集積し続けてきたのだと
なんとも言えぬ感慨を覚えます。
そして、人間が築いてきた、
さまざまな「文化」というものが
なんと素晴らしく楽しいものであるかと
心から思うのです。
現代の日本に生きる私達は、
どんな物を過去から受け取り、
そして未来へと受け継ぐことができるのでしょうか。
そして、この照応について考えていると、
ふと、以前、FBで、
地球暦の杉山開知くんが
あることを疑問に思っていたことを
思い出しました。
それは、日本の天皇家の儀式に関することでした。
長くなったので続きます。
====================================
(注1)
黄帝内経霊枢の
九宮八風篇七十七によれば以下のとおり。
風従南方来、名曰大弱風。
其傷人也、内舍於心、外在於脈、気主熱。
風従西南方来、名曰謀風。
其傷人也、内舍於脾、外在於肌、其気主為弱。
風従西方来、名曰剛風。
其傷人也、内舍於肺、外在於皮膚、其気主為燥。
風従西北方来、名曰折風。
其傷人也、内舍於小腸、外在於手太陽脈、
脈絶則溢、脈閉則結不通、善暴死。
風従北方来、名曰大剛風。
其傷人也、内舍於腎、
外在於骨与肩背之膂筋、其気主為寒也。
風従東北方来、名曰凶風。
其傷人也、内舍於大腸、
外在於両脇腋骨下及肢節。
風従東方来、名曰嬰兒風。
其傷人也、内舍於肝、外在於筋紐、其気主為身湿。
風従東南方来、名曰弱風。其傷人
「春秋左氏伝」の昭公二十では
以下のように記述がある。
東北曰炎風,艮氣所生,一曰融風
東方曰滔風,震氣所生,一曰明庶風
東南曰熏風,巽氣所生,曰清明風
南方曰巨風,離氣所生,一曰凱風
西南曰淒風,坤氣所生,一曰涼風
西方曰飂風,兌氣所生,一曰閶闔風
西北曰厲風,乾氣所生,一曰不周風
北方曰寒風 坎氣所生,一曰廣莫風
この私の翻訳では「東醫寶鑑」内に、
歴代醫方として
当時の著名な医書名一覧があり、
その中に霊枢が含まれていたことから
そちらを採用して考えています。
(翻訳と言えるレベルではないですが)
「春秋左氏伝」昭公二十には、
八風:又名八法,
即利、衰、毀、譽、稱,譏、苦、樂,
因此八法常為世人所愛憎,
而且又能煽動人心,所以叫做八風。
ともあるので中韓文献を読まれる方は、
頭の片隅においておくと良いかもです。
(注2)九星は九天星や紫白九星などがある。
それぞれを以下に列挙する。
「九天星」
天蓬、天芮、天冲、天輔、天禽、
天心、天柱、天任、天英
「紫白九星」
一白、二黒、三碧、四緑、五黄、
六白、七赤、八白、九紫
ただし、ホ・ジュンの時代
天文観測が盛んに行われていた事から、
実際の天体である可能性は
・・ゼロではないでしょう。
この辺りはきちんと調べていないので、
いづれまた調べてみたいと思います。
あなたにもできる!
ハヌルの透視能力開発講座・初級編
【東京会場】
満席になりました!有難うございます!※キャンセル待ちのみ受付中
◯日時:10月23日(日)13:30-16:30 (満席)
◯会場:HUB cafe東京 2Fイベントルーム
東京都中央区八重洲1-5-9
☆東京駅八重洲中央口より徒歩5分

◯料金:13,000円
◎キャンセル待ち申し込み先
![]() FBページのメッセージよりお送りください。
FBページのメッセージよりお送りください。
件名「東京透視講座キャンセル待ち希望」
http://peatix.com/event/194129
【名古屋会場】
名古屋は全て満席になりました!有難うございます!
■新しい視点と気づきの為の霊視セッション























クリック応援お願いします

 にほんブログ村
にほんブログ村