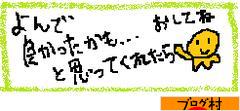最近、スピリチュアルとお金の関係について
いろいろ考えていました。
スピリチュアル・・というより、
心とお金の関係と言ったほうが
よりストレートかもしれません。
昔からいろんな雑誌では
「安い服をたくさん買う一過性の満足より
高い服を1つ買って長期間の満足を」
という記事が、年に1度は出てきます。
また、いろんなブログを読んでいると、
「人は安物を大切にしない」という意見も
本当によく目にします。
そして、一方、
自営をされている方の中からは、
「無料や低価格で集客したり仕事を行うことは、
自分自身の仕事の価値を低下させることだ」とか、
「無料は無価値と同義である」とか、
更には「そういう事をする人がいるから
迷惑をしているんだ」
というような
意見も聞こえてきたりします。
TwitterやFacebookを眺めていれば、
何かというと利権だのなんだという言葉が踊る話や、
現在の消費というもの自体を否定する話、
また、お金のシステム自体を
変えねばならないなどなど、
地球規模や国家規模の大きい話から、
もっと身近なセッションや鑑定や、
ライブの観覧、食事、売買etcetcは、
物々交換、低価格、無料が正しいんだ
という主張もかなり目にします。
こういった話のポイントを一旦まとめてみると
有料無料、金額の高低・・という辺りに
集約される気がします。
そして、これらのベースには、
まず第一に、
利益を得ることに対しての否定感があります。
その次に値段の高低が価値評価の現れとみる考えが
乗っかっているように思います。
例えば単純に安い物は質が悪く、
高い物は質が良いという考えは
値段=価値評価になります。
しかし、低価格のものでも
良いものはあるという意見もあります。
特にスピ系では
無料や低価格をバンザイとする意見が
根強い印象です。
なかには無料or低価格だという点で、
本物偽物を見分けるという考えもあります。
つまり、高いのは、
「利益を得ている」からで、
それは良くないことだという考えなのですね。
これはスピ系に限らない話です。
「原価厨」という言葉をご存知でしょうか?
原価厨とは
商材・サービスを
金銭と引き換えに取引する経済活動において、
「その商材・サービスの提示価格に対し
原価が幾らであるのか」という部分に強く拘り、
あまつさえ彼らの言う原価なるものが
提示価格とかけ離れたものであった場合は
事業者への非難すら行う者達を
揶揄した言葉である。
(出典元☆)
いわゆるネットスラングのひとつですが、
「損をしない為に徹底的に原価と比較」したり
「利益を得ることは良くない」ということを
全面に押し出してくる人々のことです。
(詳細はもう少し違いますが、
ここでは、そんな感じの人だと思ってください)
こう書くと特殊な人々のように見えますが、
案外そうではないのが今の世の中だと思うのです。
例えば、パワーストーンブレスでも、
ビーズの原価が幾らだから
もっと安くできるはず!とか。
パステル絵画だったら、
マーメイド紙とパステルだけが原価なのに、
こんなに高く売ってる!とか。
もちろん大切なお金を支払うんですから。
高い安いは気になって当然だと思いますが、
その根底にあるのは、
この人は「搾取して利益を得ている」のではないか
という感覚が見え隠れしているような
気がするのです。
そんなことを考えている時、たまたま、
「アートの価格」についての番組を見ました。
アート作品の値段はどうやって決められていくのか、を
一般向けに解説する内容でした。
そこで出てきた話は、
今の上に書いたような内容について考えるのに、
少しヒントになるような話でした。
まず、ある商品があって、
値札がつけられているとします。
それを見て、その値段ならOKと思える時、
価格と自分がその商品に思う価値は、
ほぼ一致しているという前提を立てます。
逆にそこに書いてある価格が、
思ったより安い、または高いと思う時は
自分がその商品に思う価値と一致していない時です。
この心が感じている商品価値というものは、
欲しいと思う人数が増えれば増えるほど
商品在庫数等に関わらず上がっていきます。
つまり、本来、価値とは
自分の心の中に存在しているということです。
そして、その価値あるものを、
自分が納得する価格で購入できたら、
とても嬉しいと感じるのです。
その逆だと損したと感じるのですね。
例えばカバンを買おうと
予算を30万で考えていた時に、
それを20万円で買えたら嬉しいですよね。
10万得した気持ちになるでしょう。
この得した10万の部分を
経済学では消費者余剰と呼びます。
一方、そのカバンを売る側は、
そのカバンを作るのに10万かかったとします。
それが20万で売れたわけですから、
10万得したことになりますね。
この10万の部分を
経済学では、生産者余剰と呼びます。
(消費者)納得する価格で買えたら嬉しい
(生産者)納得する価格で売れたら嬉しい
この嬉しいの部分が余剰です。
余剰が大きければ大きいほど、
人は得をしたと感じます。
これを先ほどの例で表すと、
(消費者)30万ー20万=10万
+ =20万の余剰の発生
(生産者)20万ー10万=10万
という図式になります。
この20万の部分が大きくなればなるほど、
得をしたという気持ちになっていくので、
喜びを感じる度合いが強くなっていきます。
余剰は両者の幸せにつながっているのですね。
(この余剰を生み出すために
お金が生まれたという流れも出ていましたが、
その辺りは私はまだ勉強中なので
ここでは差し控えます)
こう考える時、経済は、
取引を通じて喜びを増やす動きを
持っていると言えるでしょう。
つまり、本来は
提供者の余剰と購入者側の余剰があるのですが、
利益を得ることを良しとしないとする人々の意見には、
どうも提供者余剰の部分だけが
過剰にクローズアップされている
ーー利益を貪っているようにみえる
のではないか、という
可能性が見えてきた気がします。
おそらく、それは
「原価」の意味を
取り違えているからなのかもしれません。

(☆から引用)
この図を見てみれば分かる通り、
総原価(コスト)とは様々な部分を含んでいます。
しかし、原価厨のように
「材料費」などに単純に矮小化して比較をしてしまうと、
総原価の殆どが考慮されなくなってしまいます。
そして利益=余剰のしめる部分が肥大しているように
見えてくるのではないでしょうか。
サロン運営やヒーラーや占い師など、
さまざまな自営の方の
実際のこの総原価の部分は
そのサービスを受ける人には想像が難しい部分でしょう。
例えば目で見て触れるものであれば、
それは産地を確認したり、
縫製を確認したり、
味で判別したり等々できますが、
さまざまな講座、音楽、ヒーリング、霊視など、
体験や経験がその人によって
感想が変わるものなどの場合、
口コミ等が価値の判断の助けにはなります。
そして価格がその反映とみなすことも
ある程度はできるでしょう。
ただし、先ほども書いたように、
本来価値は私達一人ひとりの中にあるもの。
世間の意見は目安であって
「あなたにとっての価値」とは
一緒でなくとも良いのだと思います。
先日の開運商法詐欺のように、
中には大変困ったことをする業者も
もちろん存在すると思います。
それは悲しいことです。
けれど、私たちは、
誰しも「喜び」を生み出すために
コミュニケーションを取っていて、
その現れのひとつが、経済であり、
ビジネスなのだと、
この記事を書きながら、
改めて私は、そう思うのです。
私達ひとりひとりが、
真摯なきもちで仕事をし、
お客様がこちらへ向き合ってくださる時、
そこには「余剰」
ーー「幸せ」が生まれるでしょう。
【追加】
※次回と次々回の3回にわけて、
お金の話をしていこうと思います。















クリック応援お願いします


 にほんブログ村
にほんブログ村