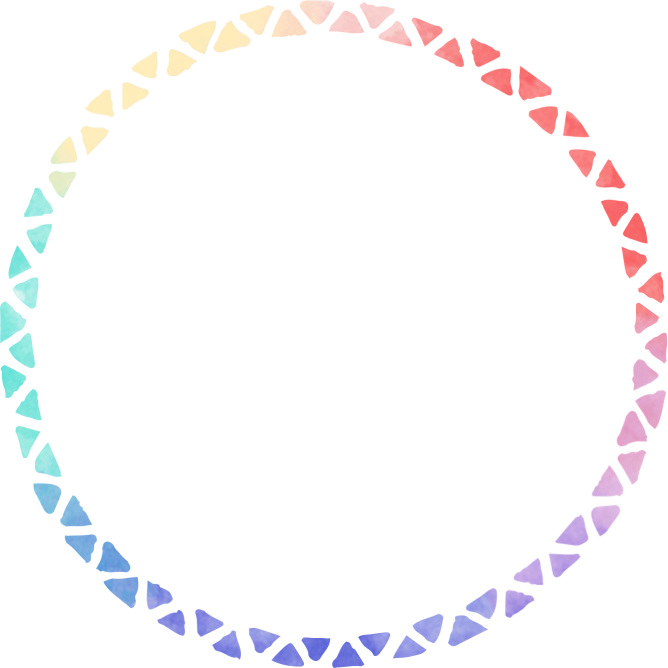エッセイ書こうとして、またしてもゾンビ小説書いてしもうたのです
さらに、流行病で療養してる最中にハロウィン終わってしまって……今更感が満載ですけど……USJは5日までハロウィンしてるらしいのでご容赦ください
今回は、ほっこりぞっくりの人形ゾンビ達のお話です。ホラーじゃないので、ご安心ください
ゾンビさん達の名前・性格・生前の死亡経緯等は全てワタシの妄想の産物です
(ミザリー、テオドールなど、前作の『美しき世界』の設定のままのゾンビさんもいます )
)
8000字程度で、読了目安時間は15分ほどです。
……この二ヶ月間、毎日ときめきとワクワクを与えてくださったUSJの全てのゾンビさん達に心からの愛と感謝を捧げます。
これからも、益々のご活躍でありますように

本当に、ありがとうございました!

今でも、ちくりと胸をさす。
幼子らの甘えた声が耳を掠めるたびに、遠い過去がまざまざと呼び起こされる。
――にいちゃん、あそぼ
"あの日"、何も知らない妹弟達を山遊びに誘って、そのまま皆を置き去りにした。
そうしなければ、自分が父親に叱られたから。
飢えていく家族を守るために、自分は妹弟を見殺しにしたのだ。
際限なく襲い来る過去の後悔や自責の念を振り払うように、ミカエルは大きく頭(かぶり)を振った。
そうして、静かに両手指を組んで神に祈る。
飢えに苦しんだ両親や妹弟達が、天国で幸せに暮らしていることを。
深い後悔と自責の念に囚われたまま命を落とした自分は、家族の元には行けなかった。
それでも――
魔界のものと成り果てて、ようやく自分も出逢えたのだ。
今度こそ、何に変えても守り抜くと決めた、大切な存在たちに。
一 、
「あでゅゅやっ!」
「みしぇる、じゃまっ!」
「んんんっ、まっ!」
賑やかに言い争っている2人の幼児に、周囲から苦笑いの視線が向けられていた。
対して、1つ結びのアニーは最近、口にする言葉数が増えてきて一気にやかましくなった。――が、いかんせん乱暴な口調が多く、周囲から窘められることも多い。
ミシェルもアニーも、口減らしのために生まれてまもなく実親の手で葬られているので、家族の温もりなど知る由もない。
互いに、姉妹のように仲良く遊ぶことが常だが、ときにはこうして諍うこともある。
「じゃま、どいてっ!」
「んやわぁぁ!」
今も、遊んで欲しいミシェルと、1人で遊びたいアニーの仁義なき舌戦が盛大におこなわれているのだ。
「アニー、乱暴はいけませんわ」
「そうよ、2人とも仲良く遊びなさい」
見かねたウェディングドレス姿のリリアスと、メイド服のミザリーが声をかけるが、どうやらアニーはお冠らしい。
口で言っても退(ど)かないミシェルに立腹して、両手でミシェルの身体をドンと強く押した。
「じゃまっ!」
「んきゃっ」
不意をつかれたミシェルが、そのまま大きな音を立てて地面に尻もちをつく。
その弾みで、地表で腐りかけていた花から、細長い焔のような緋色が伸びて、空中へとゆらりと立ち上っていく。
"不死蝶"と呼ばれる虫で、その身に緋色の炎を纏わせているので、彼ら――アヤカシの存在達がランプ代わりに使うこともある。
転んだミシェルは、しばらく呆然としていたが、やがて、「ふぇぇ」とか細い声を上げた。
「アニー、ミシェルに謝りなさい!」
「べーっ!」
諌めるミザリーに、真っ赤な舌を出して反抗すると、アニーはあろうことか、手にしていた哺乳瓶の"中身"を、半べそをかいて座り込んでいるミシェルに向かって発射した。
「きゃははっ」
「んやっ!」
哺乳瓶の中身――苺ミルクを顔面に浴びたミシェルは、短な悲鳴を上げた。
さらには、近くにいたミザリーやリリアスにも苺ミルクを引っかけると、アニーはパタパタと足音を立てて皆から離れた場所に移動し、そこで再び、「あっかんべー」と舌を出す。
「ちょっとアニー! こっちにいらっしゃい、お説教よ」
「まぁ、アニーったら。お転婆もほどほどになさらないと素敵なレディになれませんわよ――ねぇ、ミシェル……」
ミシェルの様子を伺おうとしたリリアスが、はたと動きを止める。
「あら……ミシェル?」
きょろきょろと辺りを見回すリリアスの顔から――すでに、生気なく青ざめているが――一気に血の気が引いていく。
「ミザリー! 大変ですわ、ミシェルの姿が……」
「え?」
リリアスの大声に驚いて振り返ったミザリーが目にしたのは、地面に残ったミシェルの小さな足跡だけだった。
*
「それで、足跡もすぐに分からなくなって。ミシェルの足じゃ、まだそう遠くまで行けないはずなんだけれど」
焦った口調のミザリーの報告を聞きながら、ミカエルは「うーん」と小さな唸り声を上げつつ腕を組んだ。
自分達が棲むポゼッスド・プレイシングスから、仲間のミシェルが姿を消してしまったのだ。
アニーと軽く喧嘩になり、ミザリー達が目を離した一瞬の隙に、ミシェルはどこかに行ってしまったという。
まだ幼いゆえに、彼女がどんな行動を取るか誰も把握が出来なかった。
「万が一、他のエリアに迷い込んでいたりすれば……」
自分の口から出た言葉に背を震わせると、ミカエルは大きく頭を振った。
「とにかく、オイラ、探してくる! 一刻も早く見つけてやらなきゃ」
「だけど、ミカエル1人で行くのは危険ですわ」
「そうよ、せめて誰か2,3人は一緒に行かなきゃ」
「ううん。外の世界は危険がいっぱいだから、みんなはここに居て。もしも、ミシェルが見つかったら保護を頼んだよ。それから、アニーのことも見ていてあげて」
トタトタ、と靴を鳴らしながら駆け出すと、ミカエルは皆に指示を出しつつ、辺りに視線を走らせる。
ミシェルは丸いベビーボンネット(帽子)を身に付けているので、比較的目に留まりやすいはずなのだが――。
「いないなぁ」
そんなに広くもないポゼッスド・プレイシングスの隅から隅まで、重箱をつつくように皆で一斉に探したが、それでもミシェルの姿はどこにもない。
こんな事態は初めてだった。
*
「おーい、ミシェルー!」
「ミカ、だめだ。こっちにもいない。足跡も匂いも辿れない」
魔術師のリックが、手にした袋をファサファサと靡かせながら走り寄ってくる。
その額には大粒の汗が浮き、隈取りした面差しはいつにも増して陰気さを漂わせていた。
リックは生前に魔物召喚の術中に失敗して、体表がどろっとした怪物を呼び出して喰われた経緯があり、命を落としたあともその怪物と半統合した姿で過ごしている。
「ここまでしても見つからないなら、他のエリアに出たと考えた方が良いかもね」
カツン、と小気味良くヒールを鳴らして颯爽と登場したマリアも、端正な面立ちを険しくしかめて言う。
マリアは、有名なモデルだったが、同業者達から妬まれて建物の屋上から突き落とされて命を落とした過去がある。
そのため、アヤカシとなってからも他者と関わることは少ない孤高の美女だ。
脳天がパックリ割れているのも、彼女のチャームポイントだとミカエルは思っている。
「ウァーッ」
続いて、わずか10歳で40人もの町民を殺めた連続殺人鬼・ジャッキーが血濡れのナイフを振り回して、ミカエルの元に走り寄ってきた。
彼女は恥ずかしがり屋だが、血を見ると大興奮してはしゃぎだす癖がある。
そのジャッキーも、今は真剣にミシェルの捜索に尽力してくれていた。
「ジャッキー、ミシェルはいたか?」
「ウァァン」
リックの問いに、ふるふると首を横に振ると、ジャッキーはおもむろに懐から小さく割った人骨をいくつか取り出して、ミカエルに手渡した。
「オイラにおやつくれるの? ジャッキー、ありがとう」
「ウァー」
人骨の一欠片をキャンディー代わりに舐めながら、ミカエルは皆をぐるりと一瞥する。
「オイラ、外に行ってくるよ」
皆が一斉に、ごくりと喉を鳴らす。
このポゼッスド・プレイシングスから一歩出れば、そこは種族の違う異形の者らが跋扈する弱肉強食の世界だ。
弱き者は容赦なく淘汰される、そんな阿鼻叫喚とした場に、ミカエルは1人きりで赴こうとしている。
「ウァ……」
不安げな眼差しのジャッキーの背中を優しく撫でると、ミカエルは顔を上げて「ミシェルを見つけたら、保護を頼んだよ!」と努めて朗らかに告げて、さっと踵を返して走り出した。
二、
――にいちゃん、あそぼ
忘れられぬ幼子らの声を耳の奥に響かせながら、ミカエルはひたすら駆けた。
見慣れた景色はとうに消え、一層濃い闇が辺りを包み込んでいる。
――にいちゃん
甘えて寄り添う妹の温もりが、傀儡の肌から伝わってくる心地がした。
死ぬ寸前まで激しい自責の念に襲われて、魂となったあとに現世を彷徨い歩いていた自分は、愛着の深い玩具の傀儡人形に、その魂を乗り移らせた。
まだ家族みんなが生きていた頃、母が買ってくれた唯一の玩具で、妹弟達ともたくさん遊んだものだ。
姉達が身売りされ、両親やミカエル自身も身を粉にして日がな働き通したが、それでも飢えは深刻になるばかり。
ついには妹弟達を口減らしで間引いたが、それでも生活状況が改善することもなく結局は家族みんな死んでしまった。
次々に死んでいく家族の姿を目の当たりにして、ミカエルの胸の内には後悔と自責ばかりが膨らみ積もった。
皆で生きるための方策を、どうしてもっと考えてやれなかったのか。
守るべき大切な家族に何もしてやれない己の無力さにも、深く打ちのめされた。
生前にその苦衷を味わったからこそ、ミカエルは今周りにいるみんなを大切に守っていくと決めたのだ。
今度こそ、後悔しないために。
そして、誰にも悲しい思いをさせないように。
過ぎた時間は取り戻せない。
だからこそ、これからの未来を大切にする。
そうして、それは見殺しにした妹弟達への償いでもあるのだ。
ミシェルもアニーも、どこか幼い妹達に姿が重なって見えて、ミカエルには愛おしい存在だ。
(早く、見つけないと)
焦燥が胸をつついた刹那、前方から異様な空気が流れてきた。
*
迷い込んだ"隣の世界"の住人らが、一堂に会してこちらを睨みつけていた。
獲物を見つけた彼らは一斉に殺気を放ち、ミカエルめがけて全力で駆けてくる。
怒号とけたたましい足音が乱雑に絡み合い、ミカエルの肝をぞくりと冷やす。
「ひっ……ひやぁぁっ!」
喉から腸(はらわた)が飛び出たような叫び声を上げると、ミカエルは来た道を全速力で駆け戻る。
思考の糸がぷつりと切れたように、無心のままでひたすら駆け抜けて、息も絶え絶えに大きな木の影に逃げ込んだ。
幹にもたれかかるようにして座り込むと、胸元に手を当てて乱れた呼吸を必死に整える。
「ミ……ミシェル、いなかった、よね」
誰にともなく口にして、ミカエルは大きく息を吸った。
死んだはずの身体なのに、胸がドキドキと激しく脈打つ心地がする。
――と、ガサリと背後の草むらから音がした。
「ひっ」と短な悲鳴を上げて、ミカエルが両手で頭を抱えて震え出すと、小さな足音がトットッと近付いてくる。
そうして、痙攣するミカエルの右肩がポンと叩かれた。
「きゃぁっ!」
甲高い悲鳴を上げたミカエルが弾かれたように顔を上げると、そこには見覚えのあるアヤカシの姿があった。
「ア……アシュリー!? な、なんでこんなところに……っ」
「んんー!」
顔が3面あるアシュリーは、元はどこかの国の皇族の姫君だったらしい。
国同士の争いで一族もろともに滅ぼされた際に、恨みを飲んで死んだ家臣や皇族らの怨念に引っ張られて天国に上ることが出来ず、"狭間の世界"をさまよっている。
「んんぁーっ!」
そのアシュリーが、じっとミカエルを見つめながら必死に何事かを訴えてくる。
さらには――
「カモメのおうちはどこでしょう」
歌うような口調で問うたのは、水兵人形に魂を乗り移らせたテオドールという少年だ。
人であった頃から知能に遅れがあり、彼はこの台詞以外を口にすることはあまりない。
「テオ……! ど、どうして君まで!?」
視線が合わぬままで、テオドールが淡々と告げる。
「ミシェル、いない。さがす」
「んんっ!」
テオドールに賛同するように、両手を腰に当てたアシュリーも、力強く頷いた。
*
どうやら自分の後を追ってきたらしい2人を前に、ミカエルは複雑な心境だった。
ただでさえ勝手の分からない"よその世界"なのに、果たして自分一人でこの2人を守りながらミシェルを探し出すことが出来るのか。
胸底から滔々と湧き出す不安を必死に押し殺すように、ミカエルは大きく頭を振った。
「2人とも、来てくれてありがとう。だけど、ここはポゼッスド・プレイシングスじゃないから、怖いことも多いよ。危険がいっぱいなんだ。オイラが2人を守るから、ちゃんとそばにいてね」
ありったけの気丈さを出して告げた言葉に、しかし、アシュリーが首を大きく横に振った。
「え、アシュリー?」
「んん、んーっ!」
「アシュリーが守るって。みんなを」
虚空を見つめながら、テオドールが通訳する。
知能に遅れがあるものの、ときおり、彼は賢さを露わにすることもある。
生前からテオドールに仕えていたミザリーが、いつか「テオ坊ちゃんはとても賢い」のだと口にしていたことをミカエルは思い出した。
「あ……アシュリー、ありがと……っ」
緊張が解けた途端、目からぼろぼろと涙が溢れた。手の甲でぐしぐしと涙を拭いながら、アシュリーとテオドールに向けて精一杯微笑んでみせると、アシュリーが片手で拳を作って勇壮に振り上げてみせる。
そのまま、アシュリーの細い指先がミカエルの片手をそっと掴んだ。
そうして、繋いだ手に力をこめながらアシュリーが前方を指さす。
「うん、ミシェルを探しに行こう」
アシュリーの隣に立つテオドールとともに、3人は肩を並べて歩き出した。
三、
「こ、これをあげるからオイラ達のこと食べないでっ」
「んんんっ!」
青ざめた顔のミカエルが差し出したのは、先ほどジャッキーからもらった人骨の欠片だ。
骨を差し出された異民族のマントの男は、にたりと口元を引き上げて鷹揚に頷いた。
「骨をくれるなら、お前達を取って食うことはしねぇぜ。ただ、何で"こっちの世界"に入ってきた?」
「じ……実は、オイラ達の仲間が行方知れずになっちゃって。こっちに迷い込んで来てないかなと思って探しに来たんだ」
「んんっ!」
仁王立ちになったアシュリーが、剛毅な眼差しを男に向けると、彼は「ケケっ」と愉快そうな笑い声を上げた。
「なるほどなぁ。それで、居なくなったのはどんな奴だ?」
「まだ赤ちゃんなんだよ。言葉は喋れないけど、意思疎通は出来る。白いベビードレスを来ていて、金髪の伸びかけの毛がふわふわ~って風に靡くと可愛くて……」
「んっ」
こくりと首肯するアシュリーと、虚空を見ながら指先をヒラヒラ動かしているテオドールにも視線を向けると、眼前の男は「ふーむ」と唸り、しばしの逡巡のあとで近くの草むらを丹念に調べだした。
ミカエルとアシュリーも丁寧に調べて行くが、結局、ミシェルの痕跡は見当たらなかった。
すっかり肩を落とすミカエルを気の毒そうに見つめると、男は一旦、その場を離れた。
やがて足早に戻ってきた男の手には、猫の頭蓋骨ほどの大きさの赤い実がたくさん盛られた籐籠がある。
「あの……それは?」
「トマトって、野菜だ」
「トマト……」
「おう。隣の吸血鬼どものとこにも行ってみな。本来なら吸血鬼は人間の生き血のが喜ぶだろうが、生憎と今この世界に迷い込んだ人間はいねぇから。トマトでも、手土産ぐらいにゃなる。アイツらにこれを渡しゃあ、お前らの身の安全は守られるだろ。吸血鬼のばぁさんの機嫌が良けりゃ、その赤ん坊の情報も何か聞けるかもしれねぇ」
ずいっと押し渡されるようにトマトを受け取ると、ミカエルは男に向かって深々とお辞儀をした。
「お兄さん、ご親切にどうもありがとう」
「ふん。まぁ、困ってるんだったら助けてやらねぇわけにもいかねぇしな」
そっぽを向きながら、ぶっきらぼうな口調で言う男の頬がどこかほんのり赤らんでいるように見えて、ミカエルはきょとんと小首を傾げた。
*
「それで?」
眼前の老女の鋭い目付きに半べそをかきながら、ミカエルは手にしていた山盛りのトマトの籠を老女へと差し出した。
「こんなもので、我らの機嫌が取れると思うたか」
「ひぇ……っ、あの」
老女にぎろりと睨まれた刹那、ミカエルの股の間がちょろりと湿った――ような気がした。
(あ、チビった……)
こっそりとアシュリーとテオドールを見遣れば、彼らは平然とした面持ちで老女と向き合っている。
(チ……チビってる場合じゃないぞ。オイラが、みんなを守ってやらなきゃ)
その姿を目にして、ぐっと唇を噛み締めると、ミカエルも老女を真っ直ぐに見つめ返す。
「と……トマトがお好きだと伺ったのでお持ちしました! そ、それで……あのミシェルを」
「ミシェルだと?」
峻厳な口調で問われ、ミカエルは身を縮めて口を噤んだ。
「んんっ!」
「ミシェル、どこ」
怯んだミカエルの代わりに問うた2人へと冷酷な眼差しを向けると、老女――タルマが大仰に溜息を吐く。
タルマは吸血鬼の親玉で、年齢の割に所作もキビキビとして口調も視線も随分と威圧的だ。
「左様な者は、こちらの世に迷い込んでおらぬわ。分かったなら、即刻お戻り。さもなくば、お主らの腐った血をわしが1滴残らず啜ってやるぞ」
「血はあげられませんので、トマトをどうぞ!」
「ふん」
藤籠を押し出すようにして捧げると、ミカエルは小さく深呼吸して再びタルマに向き合った。
「突然押し掛けて、本当にごめんなさい。だけど、どうかミシェルをこちらで見かけたら、ポゼッスド・プレイシングスに連れて来てほしいのです。ミシェルに酷いことをしないでください」
深々と頭を下げるミカエルを一瞥すると、タルマは鼻を鳴らした。
「しようがないね。ああ、分かった。約束しよう」
「ありがとうございます……! 良かった、話せば分かってくれる人で」
「魔の者と成り果てても、我らにも威厳と誠実さは残っておる。我が同胞らを危険に晒さぬのであれば、誰彼構わず襲うこともせぬわ」
「タルマさんも、みんなが大事なんですか?」
「答えるまでもない」
素っ気なく言うと、タルマはマントを翻して部屋の扉を指さした。
その指示に従ってミカエル達が部屋を出ようとした刹那、外からドタドタと大きな足音がする。
「うぅやぁあぁ!」
続いて聞こえた叫び声に、ミカエルとアシュリーが弾かれたように顔を見合わせる。
テオドールは1人、ぼんやりと虚空を見つめたままだ。
「え……今の声って」
「んん」
戸惑い半分、期待半分でミカエルが扉を開けるより早く、大声で喚きながら外から入ってくる者があった。
「タルマ様っ、不審者ですわ!」
「何事だい、騒々しい」
「気味の悪い白い人形が――」
血相を変えて部屋に飛び込んできた、背まで伸びた白髪の妙齢の女性の背後から、再び「うやぁぁぁ」と元気な声がする。
そうして、ミカエル達にとって想い焦がれた白い顔が、続けて現れた。
「この不気味な人形が、わたくしのゴキブリを奪おうとするのですっ!」
「うやぁぁん!」
「ミシェル……っ!」
「んんっ!」
皆の声が一度に重なると同時、それよりさらに迫力のあるがなり声でタルマが「おだまりっ」と場を一喝した。
四、
「ミシェル、そのゴキブリどうするの?」
「んややぁ」
「んんっ」
両側からミカエルとアシュリーに手を繋がれたミシェルが、得意げな顔で「やにゃああ」と告げる。
一行は、タルマの所から退散して今は"故郷"に向かって歩を進めている最中だ。
「リトとアニーにゴキブリ見せてあげる、って。ミシェル、言ってる」
皆の少し前を歩いていたテオドールが通訳した。
リトも、ポゼッスド・プレイシングスにいる仲間で、虫が大好きな少年だ。
「リト、喜ぶだろうね。ゴキブリなんて、ポゼッスド・プレイシングスではあまり見かけないから」
その声に満足げに頷くと、ミシェルは繋がれていた両手をパッと離して、洋服のポケットをガサゴソ漁り出した。
ポケットからは、吸血鬼の姫君から分けてもらったゴキブリ2匹と、鎌持ち虫、ドクロトンボ、ネバネバ芋虫などたくさんの虫が出てきて――最後に、赤い炎を身に纏わせた"不死蝶"まで出てきた。
「どこで、そんなに捕まえたの?」
「んやぁ」
結局、ミシェルは喧嘩のショックで飛び出したわけではなかったらしい。彼女の頭の中は、常に"楽しいこと"を求めているのだ。
「あちこち歩きながら捕まえた、って。ミシェル楽しそう」
満悦で笑うミシェルに脱力しながらも、ミカエルは「とにかく、本当に無事で良かった」と安堵の息を吐いた。
そうして、ミシェルの片手を大事そうにぎゅっと握りしめる。
――にいちゃん
耳を掠めた幼子らの幻聴に、ミカエルは目元を和らげた。
(今度はちゃんと、守れた……かな)
握るミシェルの手に、在りし日の妹弟達の面影や体温が重なった。
過去にはもう戻れないけれど、今この瞬間にも、自分のそばには守りたい存在がいる。
それがどんなに幸福なことなのか、ミカエルは改めてしみじみと身に染みて感じていた。
果てのない時間を彷徨うなかで、いつか、自分の無力さや後悔を乗り越えていけるように。
そして、守るために強くなる。
「テオドール、アシュリー。たくさん助けてくれて、本当にありがとう。2人がいてくれて、オイラとっても心強かったよ」
テオドールはこちらを見向きもしなかったが、アシュリーが嬉しそうに微笑んで胸を張った。
何も知らないミシェルも、つられて胸を張る。
穏やかな笑い声が響くなか、4人は弾むような足取りでポゼッスド・プレイシングスへとようやく戻ってきた。
*
「ミカエル! 無事だったのね!」
「ああ、ミシェルもいるわ!」
「テオ坊ちゃん、アシュリー! あなた達まで居なくなって、皆がどれだけ心配したか!」
4人の姿が見えた途端、一斉にあちらこちらから皆が走り寄ってきて、あっと言う間に全員に囲まれた。
ウェディングドレス姿のリリアスの背に隠れるようにして佇んでいたアニーが、こっそり顔を覗かせてミシェルの方を見ていた。
その視線にすぐに気がついたミシェルが、アニーにじゃれつき、2人はその場で楽しく遊び始める。
いつもの見慣れた光景に、皆が安堵の息を漏らす。
「ミシェルも、テオも、アシュリーもみんな無事だよ――」
ミカエルが皆を安心させるように努めて穏やかに告げていると、突然、ミザリーが言葉を遮るようにしてミカエルの身体を両腕でぎゅっと抱きしめた。
「ミカエル! 無事に戻ってきてくれて本当に……良かった」
涙声でそう伝えるミザリーの背をとんとん、と優しく叩くと、ミカエルもミザリーをぎゅっと抱きしめ返す。
互いに、今は自分の肉体ではないけれど、伝わる温もりが、"心のあった場所"をほんのりと温(ぬく)めていく。
自分が感じるのと同じように、ミザリーや皆の心もこうして温かくなればいいのにと、ミカエルは強く願った。
死してなお、自分には大切な存在がたくさん与えられた。
それは、生前に出来なかったことを今しっかりとやり遂げなさいという"大いなる存在"からの指示なのかもしれない。
「ミカエルは、凄腕のベビーシッターだね。君がいれば、ここの子ども達は皆安心してすくすく育っていけるよ」
頭が前後ろ逆についた青年・ジョルノが大袈裟な手振りで言えば、皆から陽気な笑い声が溢れだす。
「任せてよ。オイラが、みんなを守るからね」
そうして答えたミカエルの芯のある返事に、皆の笑み声が一層朗らかになって、辺りを柔らかく包み込んだ。
(了)