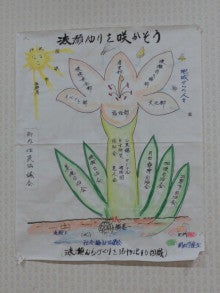10月28日(月)
早朝、宿舎を出発し、高速を乗り継いで白川町に向かった。国道41号線はバイパスが延長されていて当初の予定より2時間ほど早く現地に到着することができた。日本最古の石を展示している「石の博物館」が建つ道の駅で少し休憩をした。飛騨川沿いに作られた小さな公園を少し歩いてみる。
飛騨川の水量は多めだった。
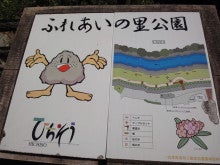

道の駅になっているこのスペースには、「石の博物館」がある。随分前になるが、入場してじっくり見学したことがある。飛騨川流域には飛水渓と命名された一帯があり、巨岩が多くあり、独特の淵が多く存在する。その岩群から実に古い時代の岩石が見つかっているのだという。たいして石に興味のない筆者でも案外退屈することなく見学できた記憶がある。今も健在。


紀北町の宿舎を出発してから走り通しだったので、気分転換。再度目的地向かって車に乗った。
「七宗橋」にやってきた。その昔、まだスノータイヤなど履いたことのなかった頃、開発したソフトのメンテでやってきて、この近くで待機したことを思い出した。雪が多くなって、不慣れな道で事故にでもなるとそのソフトを使ってくれている業者さんが作業に来なくてはならなくなる。そこで、迎えに行くから、自力で来ないようにとのことだった。渋滞の中、そんなことがあったのを思い出した。2001年に導入してもらってから10年以上、長い付き合いになる。
大病した後、自活するためソフト開発を手掛け、生計を立てることができるようになったのは、この国道41号沿いでの受注が続いたからだった。そういう意味では、現在の平穏な暮らしを作りあげてくれた地帯だとも言える。あんなこと、こんなことと次々と思い出していた。

国道41号沿いにある「天心白菊の塔」。何度も何度もこの塔の横を通過していながら、何故か立ち寄ることがなかった。天心とあるから岡倉天心に関連したオブジェかな、と思っていた。
今回、初めて立ち寄り、案内板を呼んだ。そこには、この近辺で起こった悲しい事故のことが書かれていた。昭和48年8月18日午前2時過ぎ、この地方を襲った集中豪雨のため国道沿いの山が崩れ通りかかったバスを直撃。104名が亡くなったという。その事故以外でも14名の方々が亡くなっており、それらの方々の中空に漂う御霊を供養するために建てた塔だった。
先日も筆者の仮住まっている紀北町の国道42号線で崩落があったばかり。どちらの国道も河と山の間を走っており、切り立った山際が崩れる危険性は常にある。冥福を祈った。


4時間ほどで目的地に到着。この前にお邪魔してから10年くらい経つのではないか。それでもそんな時間の経過を忘れてしまう対応ぶり。業務用ソフトだけで繋がっていたのではないという感覚があった。互いの近況も話し、久々にソフトのリニューアルも検討したりして、仕事というより、一種の交流の時間という気がした。
この道路の先々にも同じような付き合いが続いている方々が活動されている。久々にひとつひとつ訪問しないといけない。何社かは、福井にいるとき、九頭竜峠越えで訪問したこともある。
今度は、当初のように三重からということになる。当時は、まったく目に入らなかった、田畑の状態や道沿いの草の管理状態など、それぞれの土地で暮らす人々がどんな風にその土地を大切に扱っているのかが見えてくるようになった自分に気づく。
早朝、宿舎を出発し、高速を乗り継いで白川町に向かった。国道41号線はバイパスが延長されていて当初の予定より2時間ほど早く現地に到着することができた。日本最古の石を展示している「石の博物館」が建つ道の駅で少し休憩をした。飛騨川沿いに作られた小さな公園を少し歩いてみる。
飛騨川の水量は多めだった。
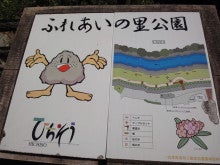

道の駅になっているこのスペースには、「石の博物館」がある。随分前になるが、入場してじっくり見学したことがある。飛騨川流域には飛水渓と命名された一帯があり、巨岩が多くあり、独特の淵が多く存在する。その岩群から実に古い時代の岩石が見つかっているのだという。たいして石に興味のない筆者でも案外退屈することなく見学できた記憶がある。今も健在。


紀北町の宿舎を出発してから走り通しだったので、気分転換。再度目的地向かって車に乗った。
「七宗橋」にやってきた。その昔、まだスノータイヤなど履いたことのなかった頃、開発したソフトのメンテでやってきて、この近くで待機したことを思い出した。雪が多くなって、不慣れな道で事故にでもなるとそのソフトを使ってくれている業者さんが作業に来なくてはならなくなる。そこで、迎えに行くから、自力で来ないようにとのことだった。渋滞の中、そんなことがあったのを思い出した。2001年に導入してもらってから10年以上、長い付き合いになる。
大病した後、自活するためソフト開発を手掛け、生計を立てることができるようになったのは、この国道41号沿いでの受注が続いたからだった。そういう意味では、現在の平穏な暮らしを作りあげてくれた地帯だとも言える。あんなこと、こんなことと次々と思い出していた。

国道41号沿いにある「天心白菊の塔」。何度も何度もこの塔の横を通過していながら、何故か立ち寄ることがなかった。天心とあるから岡倉天心に関連したオブジェかな、と思っていた。
今回、初めて立ち寄り、案内板を呼んだ。そこには、この近辺で起こった悲しい事故のことが書かれていた。昭和48年8月18日午前2時過ぎ、この地方を襲った集中豪雨のため国道沿いの山が崩れ通りかかったバスを直撃。104名が亡くなったという。その事故以外でも14名の方々が亡くなっており、それらの方々の中空に漂う御霊を供養するために建てた塔だった。
先日も筆者の仮住まっている紀北町の国道42号線で崩落があったばかり。どちらの国道も河と山の間を走っており、切り立った山際が崩れる危険性は常にある。冥福を祈った。


4時間ほどで目的地に到着。この前にお邪魔してから10年くらい経つのではないか。それでもそんな時間の経過を忘れてしまう対応ぶり。業務用ソフトだけで繋がっていたのではないという感覚があった。互いの近況も話し、久々にソフトのリニューアルも検討したりして、仕事というより、一種の交流の時間という気がした。
この道路の先々にも同じような付き合いが続いている方々が活動されている。久々にひとつひとつ訪問しないといけない。何社かは、福井にいるとき、九頭竜峠越えで訪問したこともある。
今度は、当初のように三重からということになる。当時は、まったく目に入らなかった、田畑の状態や道沿いの草の管理状態など、それぞれの土地で暮らす人々がどんな風にその土地を大切に扱っているのかが見えてくるようになった自分に気づく。