ふ「時代の変化に柔軟に対応してきた」日本最古の理容室「麻布 I.B.KAN」が明かす長く美容室を続ける秘訣

ヘアサロンを開業してから30年間、経営が続いているのは全体の0.01%しかないと言われています。長くお店を続けるのは本当に大変なことです。そんななか日本には約200年もの間、営業を続けている理容室があります。それが1818年に開業した麻布 I.B.KAN。
なぜこんなにも長くお店を維持できているのでしょうか? その理由を聞きに七代目蔦屋吉五郎を継承したオーナーの西原道雄(にしはら みちお)さんに会いに行ってきました。
文明開化も戦争も乗り越えてきた。でも潰れなかった
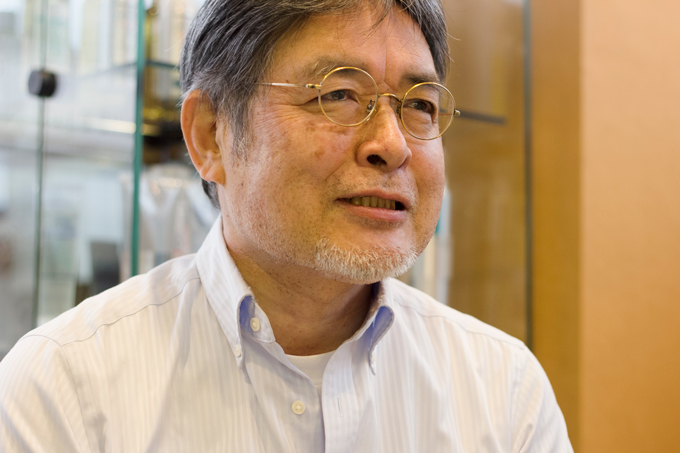
-麻布 I.B.KANの創業から現在までの歴史を教えてください。
初代が『蔦屋吉五郎(つたやきちごろう)』と名乗り、麻布の地に開業したのが始まり。理容師ではなく、まだ“髪結い”と言っていた時代です。四代目の頃に断髪令(散髪脱刀令)が発令されて、多くの髪結いが廃業に追い込まれたなかで、四代目は、当時すでに西洋理髪を学んでいたため、廃業しないですみました。文明開化の時代の波にうまく乗れたんですね。五代目はかなりの道楽者で(笑)。この辺(麻布十番)に持っていた土地をほとんど売り渡しちゃった。まぁ、店は守ってくれたからよかったですけど。そして私の父親である六代目が継いだのですが、六代目がすごかった。才能もあったし、理容界の発展にも貢献したので、僕らの世代の理容師で知らない人はいないってくらい有名。いわゆる”理容界のレジェンド”ですね。その父が病気で倒れたのをきっかけに、私が七代目を襲名して、今に至ります。
-長い歴史の中で、経営危機はありましたか?
太平洋戦争のころ、ハサミが金属回収されてしまったり、麻布十番一帯が焼け野原になって店がなくなったときは大変だったと聞きました。あとは、私が学生の頃。フォークブームが起こって、男性がみんなロングヘアにした時期があったんです。髪の毛を切ってくれないから、理容界全体が10年くらい落ち込んで。そのときは「もう、バリカンは博物館行きかな」なんて思いましたね。
-そんな中で七代目を継がれたのは、なぜでしょうか?
継ぐのが当たり前だと思っていましたから。もうそのときには理容師として20年くらいハサミを持っていたし。あんまり深く考えていませんでした。
『革新の連続』『小さなおもてなし』『スタッフを思いやる』が大切

-客観的にみて、なぜ麻布 I.B.KANが長く経営維持ができているのだと思いますか?
経営は『革新の連続』なんです。ずっと同じことをやっていてはダメ。パーマが流行ったらパーマを勉強して、カリアゲが流行ったらカリアゲを勉強する。そういう努力を続けないと生き残れない。それまでのスタイルに固執しすぎないで、時代に柔軟にやってきたのがよかったのかもしれません。
-例えば、七代目はどんな革新をされたのでしょうか?
今でも新しい技術を貪欲に学んでいます。一番は、店の名前を変えたことかな。以前の店名が『ヘアサロン西原』だったんですが、言いづらかったというのもあって、よりグローバルに見えるように、ローマ字にしたんです。麻布I.B.KANのI.B.は英語のIVY(蔓)とInternational Beautyの意味があります。ほかにも、まだテレビが高価な時代にテレビを導入してお客さまたちが店で楽しめるようにしたり、インターネットが普及する前にパソコンを買って画像を見せながら髪型を選んでもらうシステムを作ったり。時代に合わせてやってきました。
-お店を長く続けるためには、お客さまの存在が欠かせません。お客さまをリピーターにするためにどんな努力をしていますか?
たとえば、髪を切っている途中で急に雨が降ってきたら、お客さまに傘をあげるんです。貸すんじゃなくて、あげちゃう。ちょっとしたことですけど、そういう小さいおもてなしを大切にしています。
-外国の方も多くいらっしゃるそうですね。
5台の椅子が全部外国人で埋まることもあります。土地柄、大使館や、外資系企業に勤めている人が多くきてくださいます。大使館では、大使が変わるとき申し送りの一つに入っているみたいですね。『髪を切るときは麻布I.B.KANで』って(笑)
-外国の方は文化も違いますし、おもてなしも難しくないですか?
外国人だからって意識はあまりしてないですけどね。おもしろい話があってね。外国ではシャンプーのときに『かゆいところありませんか?』って聞かないんですって。かゆいところと聞かれても、背中や足がかゆいと答えてもいいのか分からないので困るそうなんです。おもてなしだと思っていたことが逆に困らせることもあるんだなぁと思いましたね。
-現在勤務されているスタッフの4人のなかで、13年目在籍と11年目在籍の方がいらっしゃるそうですが、スタッフを辞めさせない秘訣は何でしょうか?
なんだろうなあ。うちは紹介で入ってくる子が多いという理由もありますが、使い捨てや即戦力という考え方ではなく、温かく見守りながらゆっくり育てることをモットーにしているのがいいのかなと。たとえば、美容室では、お店が終わってから毎日技術トレーニングをさせるところも多いですよね。早く鍛えて早く仕事させようという経営者の思いがあるんでしょう。でも、うちは毎週水曜と金曜の2回って決めているんです。業界で主催している英語教室に行かせたり、休みの日に講習会に参加するときは受講料の半額補助をしたりもしています。
-スタッフを大切にされているんですね。
結局、どんな仕事も“人”が全てですから。どこもそうだと思うんですけど、人材確保が経営の要であり、一番の課題ですよね。いかに優秀な人を集めるか。これは僕も、今でも悩んでいることです。
親の背中を見て息子が家業を継ぐことを決意

-息子さんが八代目蔦屋吉五郎を継ぐ予定だそうですが。
はい。2018年と決めています。ちょうど創業200年になるのでキリがいいかなと。
-継ぐための条件はありますか?
ないですね。伝えたいことも特にないし(笑)
-今、なかなか家業を継ぎたいと言う若者が少なくなってきているなか、継ぐと言ってくれているのはありがたいことだと思います。
そうですね。私は継がせたいと思ったことはないんですよ。『継げ』といったこともないし。でも継ぐって言ってくれたのは、背中を見てくれていたんだと思います。働いている私の背中を見て『あぁ、この仕事も悪くないな、継いでもいいな』って思ってくれたんじゃないかな。
そこで八代目蔦屋吉五郎を継承する西原地昭さんに、“お店を継ぐこと”について伺いました。
-2018年に八代目を継承されるそうですが、継ぐことに躊躇はありませんでしたか?
西原地昭:大学生の頃、そろそろ就職を考えようというときに、僕のテーブルの席に理容専門学校のパンフレットがそっと置いてあったんです。それで「やっぱり継がせたいんだな」と思って。私自身も、中途半端な会社に就職するくらいなら継ごうと思っていたので、すんなりと受け入れられました。
私が一番大切にしているのは、“究極のいつも通り”。理容室のお客さまの多くは、髪型も劇的な変化ではなく、安定を求めていらっしゃる方が多いので、椅子に座って目を閉じて、目を開けたら、いつも通りに仕上がっているということを目指しています。それってすごく難しいことなんですけどね。2年後に名前を継がせたいというのは、周りからなんとなく伝え聞いています。気負いはあまりありませんね。
名前をついだからといって父がすぐに引退するわけでもないし。僕にも息子がいるのですが、継ぎたければ応援するという感じです。息子の人生ですから。でも、七代目のように、この場所で輝く親父の背中はちゃんと見せておこうと思います
-最後に七代目。美容界・理容界の経営者さんたちに、店が長く愛されるためのアドバイスをお願いします。
まずは時代の波に合わせる柔軟性を持つことと、店のファンを作ること。見落とされがちだけど、地域に根付く経営をすることも重要だと思います。うちも地元の組合に入ったり、中学生の職業訓練などにも参加しています。その地域の人々と情報交換をしたり協力し合っていったら、店も街も活気づくんじゃないかな

- プロフィール
- 麻布I.B.KAN
オーナー/西原道雄(にしはら みちお)
1818年から続く理容店の長男として昭和24年に生まれる。高校卒業後、理容学校に進学。他店で5年間修行したのち、ヘアサロン西原(麻布I.B.KANの前身)へ。20年ほど前、七代目蔦屋吉五郎を襲名。麻布十番生まれ、麻布十番育ち。
(取材・文/酒井美絵子 撮影/QJナビ編集部)

