西多昌規(精神科医)
一流のビジネスマンは、テンパらない!
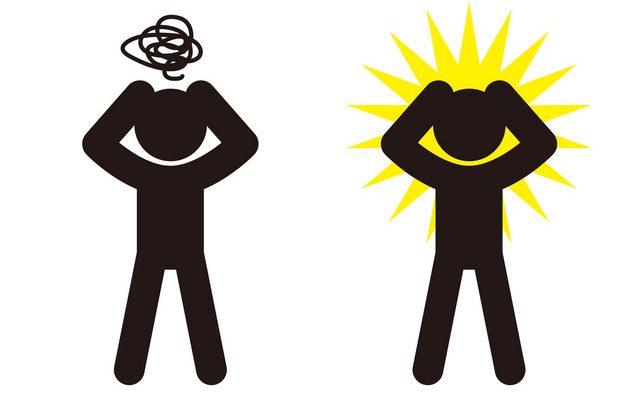
忙しすぎてアタフタ、会議やプレゼンで緊張──いわゆる「テンパった」状態になると、実力が発揮できず失敗に泣く羽目に!? しかし、正しい対処法を知っていれば心配ナシ。平常心を保つワザを、精神科医・西多昌規先生にうかがった。
テンパった状態=「キレる寸前」
仕事が次々振りかかり、頭の中がいっぱい。慌ててしまって言葉もうまくまとまらない……。そんな人を見て、周囲は「テンパってるなあ」とささやき合います。
いわゆる「余裕ゼロ」の状態を表わすこの言葉、語源は麻雀の「聴牌(テンパイ)」。聴牌とは、役ができて「上がり」になる寸前であると同時に、他のメンバーの上がりを誘う危険な状態でもあります。ここから、抜き差しならない一触即発の精神状態になることを「テンパる」と言い表わすようになったのです。
この状態に陥ったことのないビジネスマンはおそらくいないでしょう。とりわけ、多忙な中間管理職にとってはお馴染みの感覚ではないでしょうか。
しかしこの状態、すべてが悪いわけではありません。テンパっているということは脳が緊張状態にあるということであり、緊張は集中力を高める上で欠かせないものでもあるからです。
適度な緊張感を活かして仕事を進められるなら、それは「良いテンパり」。このとき人は、自分の精神状態をコントロールできています。反対に、緊張が過度になってコントロール不能になった状態が「悪いテンパり」。こうなったときの心は吹きこぼれる寸前の鍋、決壊寸前のダム、噴火寸前の火山──つまり、あと少しで暴発する状態です。
暴発とは、「キレる」ことを意味します。「もう駄目だ!」と叫んでその場から走り去ったり、「いちいち俺に聞くな!」と同僚を怒鳴りつけたり。そんな姿を一度でも周囲に見せてしまうと、評価は大きく下がります。これまでコツコツまじめに働いてきた人も、「あの人、キレると危ないよ」という噂が立つことで、重要な仕事が回ってこなくなる恐れもあります。脳内物質が思考フリーズを引き起こす
このように、テンパることはビジネスマンにとっての「脅威」。これに対処するために、まずはテンパっているときに脳で何が起こっているのかを知っておきましょう。
テンパったときはたいてい、頭が真っ白になって思考がフリーズしてしまいます。これは緊張時に分泌される「ノルアドレナリン」などの神経伝達物質が、脳に刺激を与えすぎて起こる現象です。ノルアドレナリンは脳内の短期記憶機能、つまりワーキングメモリの働きを鈍らせる傾向があります。すると情報処理がうまくいかず、「言われたことが頭に入らない」といった状態を引き起こすのです。
加えて、前頭葉の疲労もテンパりを招きます。前頭葉は感情コントロールや論理的思考、高度な判断などを司る部位なので、ここの機能が低下すると必然的に余裕が失われるのです。
前頭葉の疲労を招く要因は、睡眠不足やストレス、運動不足など。皮肉なことに、いずれも多忙なビジネスマンの生活につきものの要素です。
ちなみに、テンパりは「伝染する」傾向も持っています。テンパった人が一人現われると周囲はその人物に気を使い、神経をすり減らします。そのせいで、周囲までテンパりやすくなるのです。また、人間の脳内にあるミラーニューロンと呼ばれる細胞は「モノマネ機能」を持っています。目の前の人の言動に刺激を受けると、この細胞が脳の中で同じ言動を再生するのです。これも伝染の原因になると考えられます。
テンパったときの応急処置とは?
このように、自分にも周囲にもダメージを与えてしまうテンパりは、どうすれば抑制できるのでしょうか。
最も簡単なのが「ひと休み」。仮眠を取れば睡眠不足が軽減できますし、殺気立った部屋を出てトイレで頭を冷やせば、気持ちが落ち着きます。
「タイムリミットを設ける」という方法も有効です。もうこれ以上耐えられない、というときに「あと十五分だけ頑張ろう」というふうに、終わりを意識すると乗り切れることが多いのです。
ちなみに、十五分は人間の集中力の波の最小単位と言われています。この区切りで一息入れると落ち着きを取り戻しやすく、再び仕事に戻ったときリズムに乗りやすくなります。
「呼吸」を活用するのもお勧めです。深呼吸をすると副交感神経が活性化し、リラックスできます。息を吸ったまま止めて腹部にぐっと力を入れ、内臓全体に圧力をかける「バルサルバ法」も試してみましょう。何度か繰り返すと、効果的に副交感神経を高めることができます。副交感神経がリラックス時に働くのなら、テンパりの真っ最中にいるときは当然、交感神経が活発になっています。
ここで即効性を発揮するのは、歩き方やしぐさ、話すスピードなどを全体的にスローにしてみること。落ち着きを取り戻せるだけでなく、周囲に「テンパってるなあ」と思われずにすむ効果もあります。
どんなときでも「テンパらない人」に
このように、とっさにテンパりを抑える方法は多々ありますが、究極の理想は「どんな状況でもテンパらない人」になることです。
まず、過去の経験に照らし合わせて「自分がテンパりやすい状況」をリストアップしてみましょう。「部下が一斉に確認を求めてきたとき」「反対意見を言われたとき」などを列挙して、次にそうなったらどうするか、と考えておくとよいでしょう。
そして、同僚とは日頃から笑顔で気持ちよく接すること。日々のコミュニケーションが円滑なら、いざというとき周囲のサポートも得やすく、一人で抱え込まずにすみます。もし抱え込んだとしても、「周囲は味方だ」と思えれば、大変な中でも安心感があるはずです。
「完璧を期しすぎない」ことも重要です。自分への要求水準が高すぎると少しのミスで動揺してしまうからです。「大事なところさえ押さえておけば、少しぐらい間違ってもいい」というふうに、鷹揚に構えましょう。
このように、「テンパり防止術」はセルフコントロール術でもあります。これはビジネスマンとしても、一人の「大人」としても欠かせないスキル。いかなるときも動じないメンタルの持ち主は、「デキる人」という評価だけでなく、周囲からの確かな「信頼」も得ることができるでしょう。