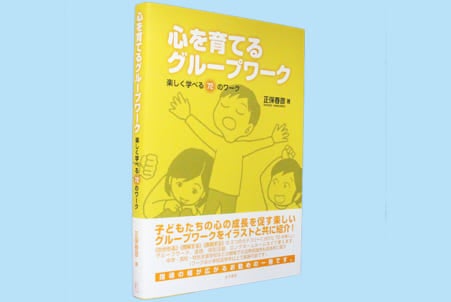【新しいグループワークの枠組み】
心を育てるグループワークとは、従来の構成的グループ・エンカウンター(SGE)やグループワーク・トレーニング(GWT)、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)そしてインプロ(インプロヴィゼーション、即興)などの活動を、かかわる活動、理解する活動、表現する活動の3つの活動に集約・再編した新しいグループワークの枠組みです。
〈かかわる〉
これらの活動はすべて他者とかかわることによって成り立っており、その意味ですべて「かかわる」働きという側面を持っています。
〈理解する〉
その中で特に構成的グループ・エンカウンターは、他者とのかかわりを通じて自他についての理解を深めるという活動であり、この構成的グループ・エンカウンターに代表される「理解する」という働きがあります。
〈表現する〉
他方、インプロの本質は「表現する」ことです。他者とかかわり、他者のアイディアを受け入れ、発展させることで新しい表現を生み出していきます。
これらの関係を図示すると以下のようになります。
かかわる心、理解する心、表現する心の3つの働きです。
これらの3つの心を観点から子どもたちの心を育てていくのが心を育てるグループワークです。
《本書の特徴》
【イラスト】
本書では、厳選した72のワークを3つのカテゴリーに分けてイラスト入りで紹介しています。
《かかわる》
《理解する》
《表現する》
【3つのマインド】
すべてのワークは「楽しく」実践できることを基本としています。
それは子どもたちの心の中にある「成長への力」を前提としています。
そして、実践の場で起こることを「開かれた心(オープンマインド)」ですべて受け入れていくことが基本です。これらは心を育てるグループワークを支える3つのマインドです。
【多くの実績】
これらの活動には多くの現場での実践実績があります。
それらは一般の学校から不登校児が多く通うフレックススクール、知的障害特別支援学校、非行少年親子の合宿など多岐にわたります(M中学校、K高校(フレックススクール)、K特別支援学校、A家庭裁判所)。
それらの多様な現場での実績については第7章「さまざまな実践」で詳しく述べられています。
これらの活動はほとんどの学校、その他の現場で実施が可能です
およそできないところはないと言えます。
【難易度の表示】
また、各ワークは難易度の違いはありますが、一部を除いて特に対象年齢を定めてありません。
各ワークには難易度を★で示してあります。
難易度とはグループワークへの取り組みの準備状態の程度ということもできます。
★はだいたいどんな集団でもできる活動です。
★★は一定程度の準備状態が必要なワークです。
★★★はグループワークに対してかなりの経験・慣れが必要なワークです。そうでない場合は、ワークに対して積極的に取り組むことができなかったり、心的外傷を負ったり、時には身体に危険が生じることもあるワークです。
(かかわるワーク例)
上記のように難易度は3段階に分けてありますが、それはワークについての分類であり、子どもたちに合わせた分類ではありません。
意外に思われるかもしれませんが、どんなワークも子どもたちはその発達段階に応じた反応を示してくれるので、子どもに合わせてワークのレベルを細分化する必要がないのです。
(スゴロク・トーキングと究極の選択!にはキッズバージョンが用意してあります。申し訳ありませんが小学校低学年では実施できるワークに一定の制約があります。)
【順序】
また、各種のワークは実施にゆるい「順序」があります。
それらの「順序」は「準備」「類似」「発展」で示してあります。
「準備」はそのワークを実施する前に済ませておくと円滑な実施が期待できるワークです。
「類似」は時間に余裕がある場合に併せて実施するとよいワークです。
「発展」は次に進むとよいワークです。
これらを参考にワークの順序を意識して「流れ」を構成することにより、年間計画を立てることができます。
また前述の第7章「さまざまな実践」には各種の学校での実践例が具体的に記述されています。
【1/100の実践】
1/100の実践とは年間10回(10時間)の実践のことです。
中学校・高校では10時間は年間総授業時間(約1000時間)の1/100に当たります。
毎月1回、年間で計10回の実践を行うと、子どもたちの心の発達や集団形成に大きな効果をもたらします。
全学校生活時間の1/100でグループワークを行うことによって、学校生活全体に好影響を及ぼすことができるのです。
是非、みなさんも心を育てるグループワークを実践していただいて、子どもたちの心を育ててください。
【目次】
はじめに
第1章 現代の子どもたちを取り巻く状況
現場でのさまざまな体験から
新しいタイプの学校
社会の変化
第2章 学校で活用されるグループワーク
人間関係の力
構成について
学校現場で活用されているさまざまなグループワーク
構成的グループ・エンカウンター(SGE)
構成的グループ・エンカウンターと時代背景
グループワーク・トレーニング(GWT)
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)
インプロ
各種グループワークの比較
グループワークを用いることの意義と注意点
第3章 グループワークにおける学び
学びの躓きと心の傷つき
学校教育機能の心理臨床化
楽しむことと学び
楽しむことと学びの関係=たの▷まな
グループ・ワークにおける学び
第4章 心を育てるグループワークとは
現代社会とグループワーク
効果的な実践に向けて
構成的グループ・エンカウンターにおけるかかわりと出会い
構成的グループ・エンカウンターのエクササイズの再検討
グループワーク・トレーニングとインプロ
3つの基本コンセプト
かかわる
いう,きく,する,よむ(iksy)
理解する
表現する
心を育てるグループワーク
第5章 グループワークの進め方
グループワークの流れ
アセスメント
オリエンテーション
スタートライン
インストラクション
ウォーミングアップ
ワークとのりしろ
抵抗とその対処
グループワークの矛盾とオープン・マインド
シェアリング
シェアリングの落とし穴
グループワークを支えるマインド
グループワークの進め方・まとめ
第6章 心を育てるグループワーク i-Work
本章の内容について
かかわるワーク
理解するワーク
表現するワーク
第7章 さまざまな実践
M中学校
K高校
K特別支援学校
A家庭裁判所における活動
第8章 計画的な実践
1/100 で効果を上げる
学校での組織的・計画的導入のポイント
担任の関与
リニアモデルとスパイラルモデル
授業以外での実践
資料 附表・索引
基本的コミュニケーション能力測定尺度iksy
索引
若い女性と老婆
引用文献
おわりに