人気ブログランキングに参加しております
わが国の近代化を再検証すべき
今から八十三年前の昭和八年四月、大亜細亜建設協会(後に大亜細亜建設社)の機関誌として『大亜細亜』が発刊された。それを主導したのが、満州に王道楽土の理想を掲げた笠木良明である。
笠木の理想が、欧米列強の帝国主義に象徴される西洋覇道に対する東洋王道の理想の堅持であったことが最も重要である。私たちはいま、アジアと向き合うに当たり、西郷南州の精神敗北後の近代化路線、その路線によって推進された日清戦争にまで遡って、わが国の近代史を再検証する必要があるのではなかろうか。
笠木は、明治二十五(一八九二)年七月二十二日、栃木県足尾町松原で生まれた。栃木県立宇都宮中学校、仙台第二高等学校を経て東京帝国大学法学部に入学、大正八年七月に卒業すると、満鉄に入社、在東京東亜経済調査局に配属された。当時調査局にいた大川周明らとの出会いによって興亜思想に目覚めた笠木は、猶存社に参加する。ここで笠木は、大川のみならず、北一輝、満川亀太郎らから強い影響を受けたと考えられる。
笠木の普遍的思想の萌芽を確認する上で、大正十四年八月『日本』に発表された「愛国の唯一路」は格好の材料である。ここで笠木は頑迷な愛国者を批判し、「我等の愛国心は厳正雄渾なると共に聡明なるを要す。我等の愛国心は栄螺固陋ではなく、祖国より始めて全世界を真正調和裡に導く所の一切を包括し解決する魂」だと書いている。満川と同様に、彼は興亜の前提としての日本改造を重く見て、日本は「まづ第一に道義的に資格ある自国自身の正義化を大眼目として活動すべき」と説いていた。
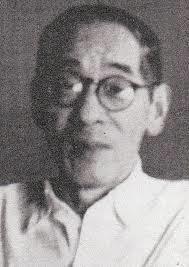
さて、笠木は昭和四年四月に東亜経済調査局から大連の満鉄本社に転勤することになった。笠木は満州情勢が動き出す中で、大連を中心とする同志を集めて議論を開始した。
一方、笠木と盟友関係を築くことになる中野琥逸は、京大時代に猶存社に参加し、行地社時代には関西行地社を結成、さらに猶興学会を結成して同志の輪を広げていた。昭和二年に奉天で弁護士を開業、やがてここは満州を志す青年たちの拠点となった。中野は、同志の庭川辰雄、江藤夏雄らとともに、満蒙に道義国家を建設する構想を抱き、奉天特務機関や関東軍と連絡をとるようになっていた。
もともと中野と面識のあった笠木は両グループの交流を進め、昭和五年秋一大結集へと向かう。十一月のある日、大連の笠木仮寓の床の間に飾ってあった書幅「独座大雄峯」に注目が集まった。「独座大雄峯」は、唐代の禅師百丈壊海が、「有り難いこととはどういうことですか」と問われた際に発した言葉で、「自分が一人、この山に座っている事ほどありがたい事はない」ほどの意味である。この書に因んで、笠木・中野連合は「大雄峯会」と名付けられた。
昭和六年九月十八日に満州事変が勃発すると、大雄峯会周辺は緊迫度を増していく。事変からちょうど一カ月後の十月十八日、大雄峯会は奉天の妙心寺で総会を開き、板垣征四郎、石原莞爾ら関東軍幕僚らと対面する。石原は「満蒙問題の解決はもはや言論や外交では不可能であるから、満鉄沿線を対象として理想境域を建設することによって実績で証明するよりほかにとるべき方法はない」と語り、大雄峯会に協力を求めてきた。笠木らは石原の提案に賛同し、自治指導部設置に向けた方針策定を急いだ。そして、大雄峯会と満州青年連盟の案を統合した「地方自治指導部設置要項」が決定され、十一月一日自治指導部が発足した。大雄峯会、満州青年連盟からそれぞれ七名ずつが参加し、笠木は連絡課長に、中野は顧問に就任した。
稀有の大文章「自治指導部布告第一号」
いよいよ、笠木がその理想を体現するときが来たかに見えた。まず彼は、全身全霊で「自治指導部布告第一号」を起草した。「自治指導部の真精神は天日の下に過去一 切の苛政、誤解、迷想、紛糾等を掃蕩し竭して極楽土の建立を志すに在り、茲に盗吏あるべからず、民心の離叛又は反感不信等固より在らしむべからず。住民の何国人たるを問はず胸奥の大慈悲心を喚発せしめて信義を重んじ、共敬相愛以て此の画時代的天業を完成すべく至誠事に当るの襟懐と覚悟あるべし。謂ふ所の亜細亜不安は軈て東亜の光となり、全世界を光被し全人類間に真誠の大調和を齎すべき瑞兆なり。此処大乗相応の地に史上未だ見ざる理想境を創建すべく全努力を傾くるは、即ち興亜の大濤となりて人種的偏見を是正し、中外に悖らざる世界正義の確立を目指す」
「世界史の実践課題に向って巨歩を印した 稀有の大文章」(井上実)と評された通り、笠木の崇高な理想が余すところなく示されている。
十一月半ば過ぎから、自治指導員たちは二名一組となり、奉天省内の二十一県に入っていった。どの県でも張学良に任命された地方官吏が逃亡してしまい、無政府状態に陥っていた。指導員たちは、匪賊討伐、窮民の救済、借金の世話、学校開設、不良日本人の摘発など、あらゆる問題に対処しなければならなかった。
しかも、任地に赴く際、軍隊や警察の保護などなかった。彼らは、一切武器も持たず、果敢に住民の中に入っていったのである。指導員のほとんどが、笠木の説く理念に殉ずる覚悟を持った者たちだったのだろう。
昭和七年三月一日の満州国建国に伴い、自治指導員は県参事官に再編された。このとき、笠木は独自の構想を描いていた。新たに資政院を設け、県参事官の人事を司掌するとともに、建国理想の原理的究明のため研究部を設置するというものだ。笠木が研究部に渡辺海旭、田崎仁義らとともに招こうとしたのが、宮島大八であった。
勝海舟─西郷南州─宮島大八の文明観
笠木は、「覇道あることを許さぬ真人」としての宮島大八の生き様に強く惹かれていたのである。大八の魂は、勝海舟の魂であり、あるいは西郷南州の魂でもあったかもしれない。
大八の父宮島誠一郎は、南州、海舟と極めて緊密な関係にあり、西洋近代の覇道主義とは異なるアジアの道義を追い求めた人物である。明治十一年九月二十四日、南洲の「逆賊」の汚名が未だ晴れぬ中、誠一郎は副島種臣らと密かに西郷一周忌を開いている。翌明治十二年に東亜振興を目的に設立された「振亜会」(翌年「興亜会」と改称)の中心人物笠木良明として運営に当たった。
慶應三(一八六七)年十月二十日に生まれた大八は、興亜会の「興亜学校」で中国語を学び清国に留学、日清戦争勃発に直面し、明治二十七年悲嘆のうちに帰国した。彼が真っ先に訪ねたのが海舟だった。そして大八は、日清和親の重要性を説く海舟の考え方に傾倒していったのである。
松浦玲氏が『明治の海舟とアジア』で指摘しているように、海舟は、南州が江華島事件を批判した篠原国幹宛書簡(明治八年十月)に基づいて、南州は征韓論者ではなかったと主張するようになる。海舟は、南州に独自の文明観を仮託し、伊藤博文らが進める欧米型近代化路線に抵抗し、同時に日清戦争にも反対の姿勢を鮮明にしたのだった。それにぴたりと歩調を合わせていたのが誠一郎であった。
海舟は、日清戦争の講和においては、領土割譲に反対し、独自の中国論を展開している。「支那人は治者が誰であろうと頓着しない」「支那は国家ではない。ただ人民の社会だ」と述べる一方、次のように中国との連携を説いている。
「支那の実力が分かつたら最後、欧米から ドシドシ押し掛けて来る。ツマリ欧米人が分からないうちに、日本は支那と組んで商業なり工業なりやるに限るよ。一体支那五億の民衆は日本にとつて最大の顧客サ。また支那は昔時から日本の師ではないか。それで東洋の事は東洋だけでやるに限るよ」
注目すべきは、笠木が明治政府の政策に抵抗する海舟の主張に思いを寄せていたことである。『大亜細亜』には、海舟のアジア外交論が掲載されていたのである。昭和十一年七月には、宇佐彦麿が「海舟先生の対支意見」を寄せ、「今や我国は国際政局上危機に際会し、殊に対支問題が最重大化してゐる時、先生の対支意見を紹介して先人の見識を回顧玩味するのも意味多いことゝ思はれる」と述べて、日清韓三国の連合策、日清戦争後の講和における領土割譲に対する反対論、対支優越感への批判等、海舟の主張を整理した。さらに、昭和十二年二月には角田貫次が「海舟先生東方意見抄」と題して、再び海舟のアジア外交論を紹介している。
支那事変の拡大に直面し、海舟の議論を見直そうという機運があったとも推測されるが、笠木は二人の人物から直接海舟の思想を継承していたと考えられる。一人が、海舟の直弟子であった、笠木の友人松崎鶴雄であり、もう一人がほかならぬ師大八であった。
(続く)
↓クリックをお願いします↓