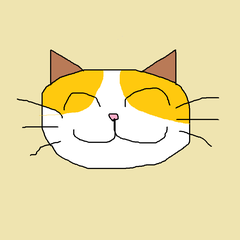能登半島地震及び豪雨、各地の豪雪、火災、原発、地震などの
数多の災害被害者の皆様に心からお見舞い申し上げます。
雷の人身被害がありましたが、地球温暖化のせいか、災害の
激甚な被害が増えているようです。
復旧復興に向けて、また、生活困窮する多くの国民のために
政府が血の通った施策を実行してくれるよう、願います。
また、農業漁業に従事する方々のご苦労も増し、食糧の確保が
困難になってきている上に、世界各地では戦争紛争で生命を
脅かされ多くの人々が苦しみ…地球はこれからどうなって
しまうのか、恐ろしくなります。
一人一人の力は小さくても、世界中の人々が互いを尊重して
知恵を出し合い、地球規模の危機を乗り越えていくような
潮流が起きますようにと祈るばかりです。
音楽之友社こどものバイエル上巻
イ短調の残り2曲、履修順は43番、41番です。
今回は、43番
曲の形はおなじみの A-A-B-A です。
まず、生徒演奏楽譜のAAの部分ですが、
生徒さんには二人の会話の形とお伝えします。
さて、生徒担当の主役のメロディーですが、
短いスラーのAAと長いスラーのBで出来ています。
短いスラーのAですが、
1・2・4段の2小節目は、ミの音が2回ではなく、
ラシドラ|ミ~ミ~|シレドシ|ド~~~|
ラシドラ|ミ~?と問われ
ミ~|シレドシ|ド~~~|
と答えます。
スラーの終わり「ミ」と次のスラーの始まりの「ミ」、
当然、弾き方も変わります。
連弾のパートもそれに呼応していて、いわゆる「伴奏」
の形ではありません。
生徒と一緒に同じメロディーを歌い始め、その後、
もう一人がそのメロディーを追いかけて繰り返します。
輪唱のようなカノンの形です。
生徒:ラシドラ|ミ~ミ~|シレドシ|ド~~~|
先生:ラシドラ|ミ~ミ~|
|ラシドラ|ミ~~~
生徒と先生の二人で会話をしている会話のアンサンブル
になっています。
そして、Bの部分です。
長いスラーのBですが、2小節ずつの部品で出来ており、
前半後半とも、上がって下がる音型ですが、
1回目は単純な上行下行
シドレミ|レドシラ|に合わせて、自然に
クレッシェンド~デクレッシェンド となります。
2回目ですが、
シドレミ|レドシラ|シドレミ|
と勢いをつけて盛り上がった後に レドドシ|
と下りてくる時にためらい?足元を確かめる?
という感じで“足踏み”をします。
ドとド、続けて同じ音を弾くので、レガートで繋げる
という手指の使い方も練習します。
※生徒さんには、なぜ2回シドレミ|レドシラ|と
繰り返さないかしらね?と質問したりします。
次のメロディーが「ラ」から始まるので3段目は
「ラ」で終わると“座り”が悪くなります。
ここで、次に戻ってくるAへの繋がりに大きなテンポの
揺らぎが生じます。
かなり大人っぽい表情表現が求められていると思います。
そして、ここでもハ長調に少しだけ変身します。
42番は3段目の冒頭でハ長調の明るい和音が出てきますが、
43番では、後半がハ長調に変身します。
それも、主役のメロディーとハモる形です。
シドレミ|レドシラ|シドレミ|レドドシ|
E |Am |G |C E |
1回目のシドレミはイ短調で、悩み?悲しさ?のように
感じられます。
それが、2回目のシドレミはハ長調のGの明るい響きで
パッと光が差してくるような展開です。
EとAmはイ短調の、GとCはハ長調の和音です。
この響きの変化も、連弾でなければわかりません。
こんな単純な曲でも、音楽的に様々な表情表現を
習い始めの初心者にも体験させてあげようという試み、
やっぱり、バイエルさんて凄いなあ、と感心します。
では、また。