ご訪問ありがとうございます。
アメブロはサブブログで、FC2がメインブログです(ブログ名は同じ)。インド・チェンナイ関連記事は80%ほどはアメブロにもコピペ投稿していますが(FC2の方がカテゴリ分類が細かく検索しやすい)、乳がん&乳房再建関連の過去記事は主な投稿しかこちらにコピペ投稿していません。(詳しくはこちら目次を)。コメントはFC2からお願いします。宜しくお願いします。
----------------------------------
今日は肩についてちょっこらと。
肩の手術が必要となる怪我には大きく分けて下記の2つがある。あくまでも私の理解なので、それ前提に参考にして下さいね。
①反復性/習慣性脱臼
「あ、肩が外れた、肩関節が外れた」が肩の脱臼だ。一度脱臼して適切な処置を行えば、それ以降、肩の脱臼とは無縁の人もいれば、何度も肩の脱臼を繰り返す人もいる。後者が反復性/習慣性脱臼だ。反復性/習慣性脱臼の主な原因は2つ。1つは、もともと関節が緩く外れやすい体質。もう1つは、ラグビー・相撲などのコンタクトスポーツによる怪我、交通事故などの外傷だ。肩関節が外れると聞くと、ネジが外れたようなイメージだが、外傷/怪我で脱臼になった場合は肩関節の骨の欠損が伴う。骨が欠けたことにより、関節が外れやすくなり、頻繁に外れる反復性/習慣性脱臼になる。骨の欠損・損傷度合いは、怪我の度合いにより異なる。手術では骨の対するアプローチとなる。繰り返しになるが、あくまでも素人の私の理解だ。
②腱板断裂
肩の腱板、つまりインナーマッスル・スジの断裂だ。加齢(老化)や使いすぎが原因になると聞く。なので高齢者に多い。手術では筋肉・スジに対いするアプローチになる。詳細はここ。
①と②の説明文の長さから分かるように、私が昨年秋に受けた手術は①だ。30代前半にスキーで左肩を初めて脱臼、温存治療後20年ほどは問題なく各種スポーツを楽しんだ。が、4年ほど前にジムでトレーニング中に再脱臼し、その10ヶ月後にまた脱臼。反復性/習慣性脱臼となり標準的な肩脱臼に対する手術を受けた。10ヶ月ほどのリハビリを経てインド・チェンナイへ。手術から1年ちょっとあたりから、チェンナイでヨガを始めた。この左肩手術及びシリコン・パイのことがあったので、パーソナルレッスンから初め、私なりに慎重にヨガの強度を高め、ヨガにのめりこんでいった。
ヨガを初めて半年ほどからヘッドスタンディングも始めた。時々、左肩に不安を感じることがあったので、かなり慎重にしていた。なぜなら、肩で上手くバランスがとれないと、首に負担がかかってしまい首を痛めてしまう可能性があるからだ。首の怪我は頸椎の怪我に繋がり後遺症が残る可能性もある。因みに、肩の手術の執刀主治医からは「ブリッジはやめておいた方がいい」と助言を受けたので、ブリッジは挑戦しなかった。
手術から3年目。肩に不安・嫌な感じを覚えて近所の整形外科専門病院へ。詳細は省略するが、大学病院で2度目の手術を受けた(1度目は福岡、2度目は東京)。先に触れたように、肩を脱臼をした場合、肩関節の骨が欠け、それにより肩関節が外れやすくなる。なので、外れないように欠けている肩関節部分にアンカー(紐)をつけるが(こんな単純ではない。かなり荒っぽい素人の説明)、私の場合は、1度目に取り付けたアンカーが殆ど機能しておらず再発していたことが2度目の手術で判明した。肩の骨の損傷(欠け度合い)も進んでいた。その原因は、肩専門の整形外科医の研究対象になっているらしく原因は推測の域を出ない。アンカーは肩の骨に固定するが、固定した個所の骨が溶けてくるなどの見解が出てるらしい(私の理解レベル)。
それで、昨年秋の2度目の手術では、私は損傷が進んだ肩関節の骨に人工骨2つを装着し、多くのアンカー(紐)でしっかり目に固定した。「右側は乳がんの患側。殆どないとは思うが、右腕に負荷をかけすぎるとリンパ浮腫になる可能性もゼロではない。日常生活で左腕を通常に使いたい。なので、リハビリは頑張るので、左肩をしっかり目に固定して欲しい」と術前に主治医に伝えた。
主治医曰く、結構大変で時間がかかる手術で、病名では「難治性、反復性・習慣性脱臼」となっている。正式名はコレなのかは分からないが、「難治性」がついているのは確かだ。
手術から8か月(術後3ヶ月は装具による固定)。現在は、毎日自宅でリハビリ(サボり気味だが)、2週間に1度、病院でリハビリ、毎週整骨院で治療(シリコンパイにより背中が凝るのでその治療がメイン)を行っている。想定通りの回復で順調らしい。50代半ばのおばちゃんにしては上出来ぽい。既に日常生活ではほぼ問題はないが、私はもともと肩周りが柔らかく、可動域が広かったので100%は戻っていない。それでも、同年代の平均よりもは可動域が広いかもしれない。そこまで戻っている。
じゃー、今、何を一番気を付けているのか。それは、肩を動かすときに、肩甲骨から動かすことを習慣づけることだ。加齢や運動不足、姿勢の悪さで、肩甲骨が十分に動かない人がとても多い。それでも腕は問題なく上がるが、肩関節には負担がかかる。それを続けてしまうと、肩のインナーマッスル・腱板の断絶に繋がるなど肩を痛めていまう。「50肩とか、腕が上がりづらいとかで、その改善運動のためにラジオ体操をする人がいるが、肩を動かす時にちゃんと肩甲骨を意識して肩甲骨を使わないと肩を悪化させてしまう。が、それを知らない人が殆どで....」と主治医が言っていた。
肩に問題がない人でも、大きな肩甲骨の動きをよくして可動域を広げておくと、肩の怪我・痛みを防ぐことができる。多分、肘への負荷も減る。
私のスポーツへの復帰?だが、ゴルフ・ジョギングは問題なし。ヨガについては主治医は難色を示している。全てのヨガのポーズが駄目なわけではないので、しっかり学んでヨガを!となると思う。ストレッチも同様だ。少し負荷をかけながら、肩関節の可動域を広げるポーズが注意だ。例えば、肩甲骨の動きを抑えながら腕を上げるや、体重をのせて肩をストレッチするなどだ。これらは私はNGだ。
今はまだ肩の関節周り筋肉の「ほぼ」全てがががスムーズに動くようになって、肩関節の動きが「ほぼ」正常になった段階。やっと本格的な低負荷な腱板・インナーマッスル強化トレーニングが始まったばかりだ。アウターマッスルは日常生活でも鍛えられるが、インナーは意識しないと強化できない。が、地味過ぎる!
ヨガは誰にでも出来そうなイメージがあるが、頑張り過ぎて負荷をかけすぎたり、無理をしたりすると怪我に繋がる。自分の出来る範囲で、特に精神的な部分に注目すれば年齢問わず誰にでもできるのだが、日本人はポーズの美しさを追求して頑張り過ぎる人が結構いるので、注意が必要にも思う。
最後にシリコンパイ。左肩のトレーニング時は左右どもに行っているが、右側のトレーニングのためか、シリコンパイの違和感が増し気味だ。もう難儀!シリコンパイは今年の秋で7歳。被膜拘縮は多少は進んでいると思うので、もうちょっとケアしないと違和感が増すように思う。左肩に気を取られていると、シリコンパイのケアを忘れてしまう。
今日のオマケは今年はじめに新しくなった東京メトロ銀座線渋谷駅。リハビリ通院で最近、よく使う。
「読んでよかった」と思われたら
↓応援クリックをお願いします。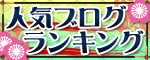
人気ブログランキングへ
クリックすると「乳がん」カテゴリーのブログ一覧に飛んだり
「インド」カテゴリーに飛んだりします。ご了承を。コントロール不可みたいで.....