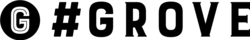皆様、あけましておめでとうございます。
元旦はニューイヤー駅伝、今日は箱根駅伝(往路)を見て、お雑煮を食べてダラダラしておりました。
時を戻すと(ぺこぱ風に)大晦日はNHK紅白歌合戦ですよ!
Vaundyさん、藤井風さん、Ado(ウタ)さん、Official髭男dism、King Gnu、星野源さん、あいみょんさん、milet(ミレイ)さん、Aimer(エメ)さん、MISIAさん、Superflyさん、ユーミン、back number、安全地帯、時代遅れのRock’n’Roll Band…などなど、ワクワクしながら見ていました。
そんな紅白歌合戦、出場歌手によって尺はまちまちで、曲の長さもありますが、パフォーマンス(演出)によって持ち時間は人それぞれ。
それにはどんな基準があるのか?
2022年に関しては、NHK推しの10組という記事が面白く、今の紅白に至るまでを自分なりにまとめてみました。(新年一発目も長文!![]() )
)
紅白歌合戦 誰がパフォーマンス時間を長く与えられたのか
記事によると4分以上番組に出ていたのは以下の10組。
1;10分00秒 桑田佳祐 feat. 佐野元春,世良公則,Char,野口五郎★
2;6分54秒 VAUNDY(バウンディ)
3;6分50秒 ディズニースペシャルメドレー ★
4;5分56秒 安全地帯★
5:5分32秒 松任谷由実 with 荒井由実★
6;5分31秒 MISIA※トリ
7;4分43秒 福山雅治※大トリ
8;4分17秒 あいみょん
9;4分09秒 藤井風
10;4分00秒 星野源
(★印は「企画」もの)
企画もの、トリ以外で長尺なのはVAUNDYさん、あいみょんさん、藤井風さん、星野源さん。
記事では、以上の4人をNHKが重要視した「世代的に広く聞かれる歌手」として位置付けたとしています。
ただ、よく言われる紅白歌合戦とNHK音楽番組の密接な関係から言うと、星野源さんは冠番組が2つあるし、あいみょんさん、藤井風さんは二回目の出場歌手、初出場のVAUNDYさんはいつからNHKの推しに⁉︎と思ったら、2022年は3回ほどNHKに出ていました。
今更ながら、着々と布石が打たれていたのを知った次第です![]()
では、実際の視聴者推しはどうだったのか?
NHKの音楽Youtubeチャンネルから推察してみます。
NHKさん、番組終了直後から1分弱のショートバージョンではあるものの、紅白のハイライト動画を歌手ごとにアップしていました。
![]() はその再生回数です。
はその再生回数です。
アップしたタイミングにもよる誤差はあるかもしれませんが、SEKAI NO OWARI、TWICEなどネットでの好みどおりのランキングになっている気がします。
SEKAI NO OWARIは一日足らずで121万回再生ですよ。(30日にはレコ大も取ってるし注目度大。)
最低でも5.1万回再生なので、前述の幅広い世代に聞かれている歌手という選抜基準で言えば、NHKの読みはあながち間違っていないんじゃないかなと。
そして、ハイライト動画の再生回数から見るに、毎年よく言われる「馴染みのある歌手がいない」問題と通じるような気がしてきました。
視聴者と出演者のギャップが生まれたワケ
”出演回数の推移を見れば、2010年代中期から生じた新陳代謝が、順調に進みつつある。ベテラン勢が退場し、5回以下の新人・若手が増える傾向が見られる。1990年代中期から2010年代中期まではベテラン勢が多く、そこからは意図的に世代交代をしようとする意図が感じられる”
要するに、以前は音楽を聞くのがレコードやカセットテープ、CDといった記録メディアだったのに対し、今はネットでストリーミング配信がメインとなり、紅白もCD売上等のオリコンチャートではなく、配信中心のビルボードチャートを重視したことにより新陳代謝が進んだとのこと。
![]() によると、2022年9月時点でYoutubeの全世代の利用率は87.9%。
によると、2022年9月時点でYoutubeの全世代の利用率は87.9%。
年代別に見ると、20代が最も多く97.7%、2番目に多いのが10代で97.2%、次いで30代の96.8%と続きます。最も利用率が低いのは60代の67.0%。
なお、音楽がストリーミング配信やDL販売へと急送に進んでいったきっかけ。
![]() 2001年10月24日、初代iPodを発表。
2001年10月24日、初代iPodを発表。
この発表の後、すぐにヨドバシカメラへを予約しにいきましたよ!
思えば音楽プレイヤー発売の頃から、視聴者層が徐々に分断されていったのかもしれません![]()
それでも、2001年当時に比べればスマホの普及効果もあり、2022年Youtubeを利用する60代の67.0%は充分浸透していると言ってもいいのかなとも思いますけどね。
ただし、視聴頻度で言えば、60代以上は他の世代に比べかなり少なそうです。
ちなみに、ストリーミング配信で自分が使っているのはAmazon Musicで、自分は以前プレイリストを作成する際、かつてCDで聞いた曲を沢山セットしていました。
ただ最近は仕事中などにAmazon Music umlimitedで「注目のソング」をひたすら聞いていることが多くなり、そこから気に入った曲を見つけ、プレイリストに追加するようになりました。
そのおかげで、あまり最近の紅白との剥離を感じていないのかもしれません![]()
データから見る紅白歌合戦70年の歴史
”70~80年代にかけて、歌謡曲と差異化したニューミュージックやロックバンドのアーティストは、主体的に『紅白』に出演しない傾向があった。「J-POP」という言葉が人口に膾炙する前の70~80年代、『紅白』の音楽ジャンルは歌謡曲・演歌・アイドルの3本柱だった”
となると、今の紅白の主流はむしろJ-POPだと言えそうですね。
それでは、正直主流とは言えなくなった「演歌」は、ネットではどういう立ち位置なのか。
Youtubeで「演歌」を検索し、再生回数を調べると、坂本冬美さんの「また君に恋してる」2526万回が最高でした。
でも、この曲は違う違うそうじゃ、そうじゃなーい♪![]()
他にも石川さゆりさん、三山ひろしさん、中条きよしさん、山内惠介さん、島津亜矢さん、水森かおりさん、天童よしみさんなどは普通に100万回再生超えの動画もありました(太字は2022紅白出場歌手)。
ただし、自分のチャンネルはあっても登録者数では苦戦してることから、ネットでの注目度はイマイチのよう![]()
だから、今年流行ったキツネダンスとコラボした山内惠介さんや、なかやまきんにくんが登場した天童よしみさんのように、ただ歌うだけではないタイプの動画再生数が伸びていることから、演歌+αの演出スタイルは今後も続くでしょうね。(個人的には水森かおりさんの謎解きコラボが楽しめましたが、再生数は伸びていないですね![]() )
)
話を元に戻すと、前述のYoutubeの支持層から見るに、10代、20代などはそもそもテレビをリアルタイムで見る機会が減り、今やテレビを圧倒的に指示するのは60代以降なのかなと。
そう考えたら、テレビ支持層にとっていくらネットで流行ってますからって言われても、すぐには理解できないですよね![]()
ただゲームですら目まぐるしく変化しているのに、テレビも番組自体が時を重ねれば重ねるほど、どこかで新陳代謝をせずに紅白が昔のままでいたら、テレ東の「年忘れにっぽんの歌」とどう違うんだよ!と逆にツッコミが来ませんかね⁉(そもそも全国とキー局では注目度が違う?![]() )
)
なお、自分が学生だった頃は演歌が正直うざい存在でした![]()
でも、今となっては、色んなジャンルの歌をたくさん聞けるのが紅白のいいところ。
普段ほとんどテレビを見なくなった自分ですら、紅白を流してるだけで大晦日気分が味わえるし、それに興味のない歌は休憩タイムなんです![]()
NHKはCMがないのでちょうどいいんです![]()
結論としては、主なテレビ視聴者の年代層には合わなくなりつつある紅白歌合戦だが、世界や日本で活躍している代表的なアーティストを、幅広い年代の人たちにも楽しんでもらいたい。そして、テレビもネットのように盛り上げてもらいたい思惑がある。
と、そんなところでしょうか。
さっそくまとまりのない長文で始まりましたが![]() 、皆様、今年もよろしくお願いします
、皆様、今年もよろしくお願いします![]()
おまけ
毎回エンディングでは曲と映像が変わる、アニメ『チェンソーマン』オープニング エンディングスペシャルムービー。
各回のEDとOPがまとまっているありがたい動画で(それまでは各回EDが独立してアップされていた)、年末は仕事中のBGMでした![]()