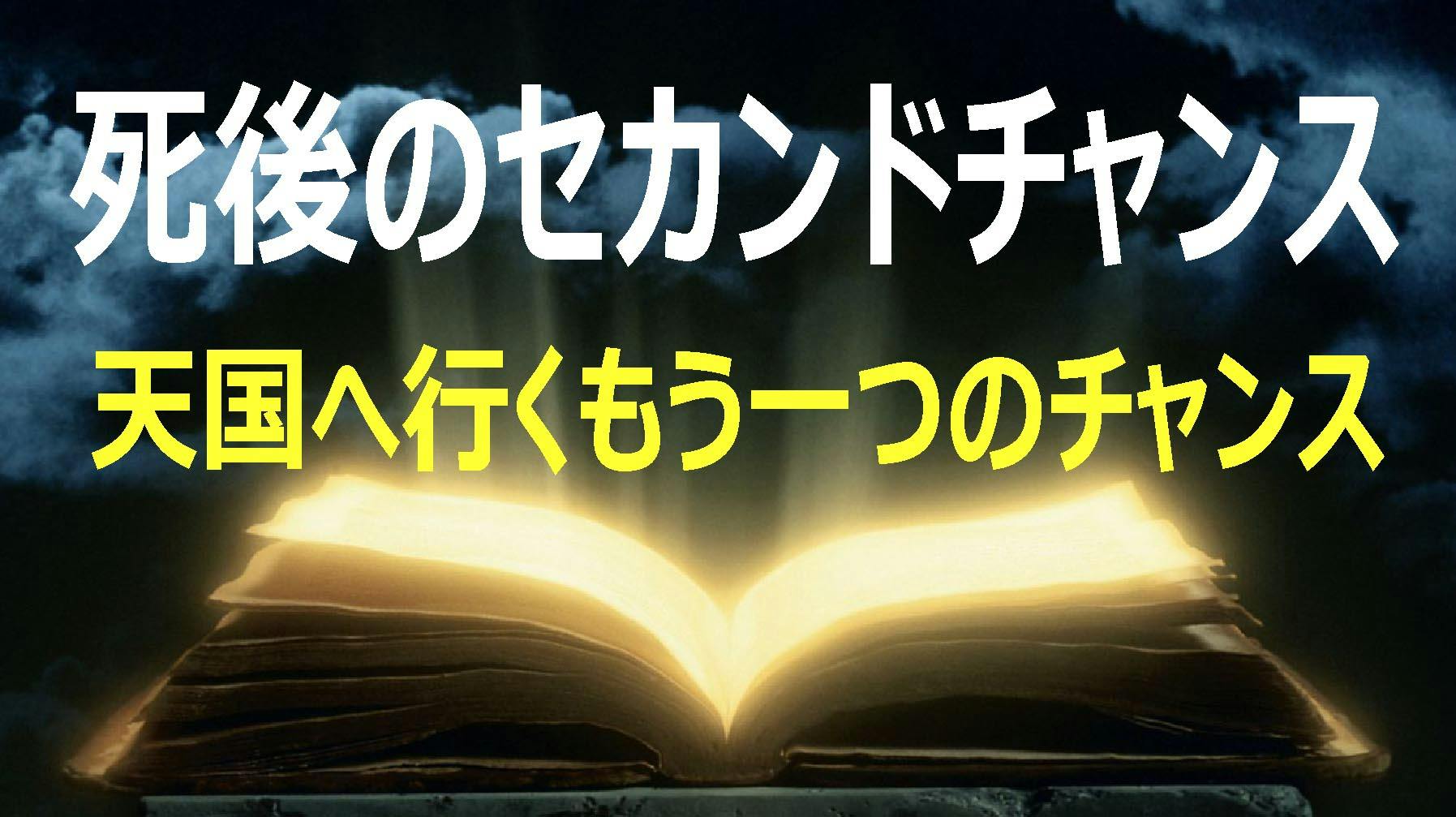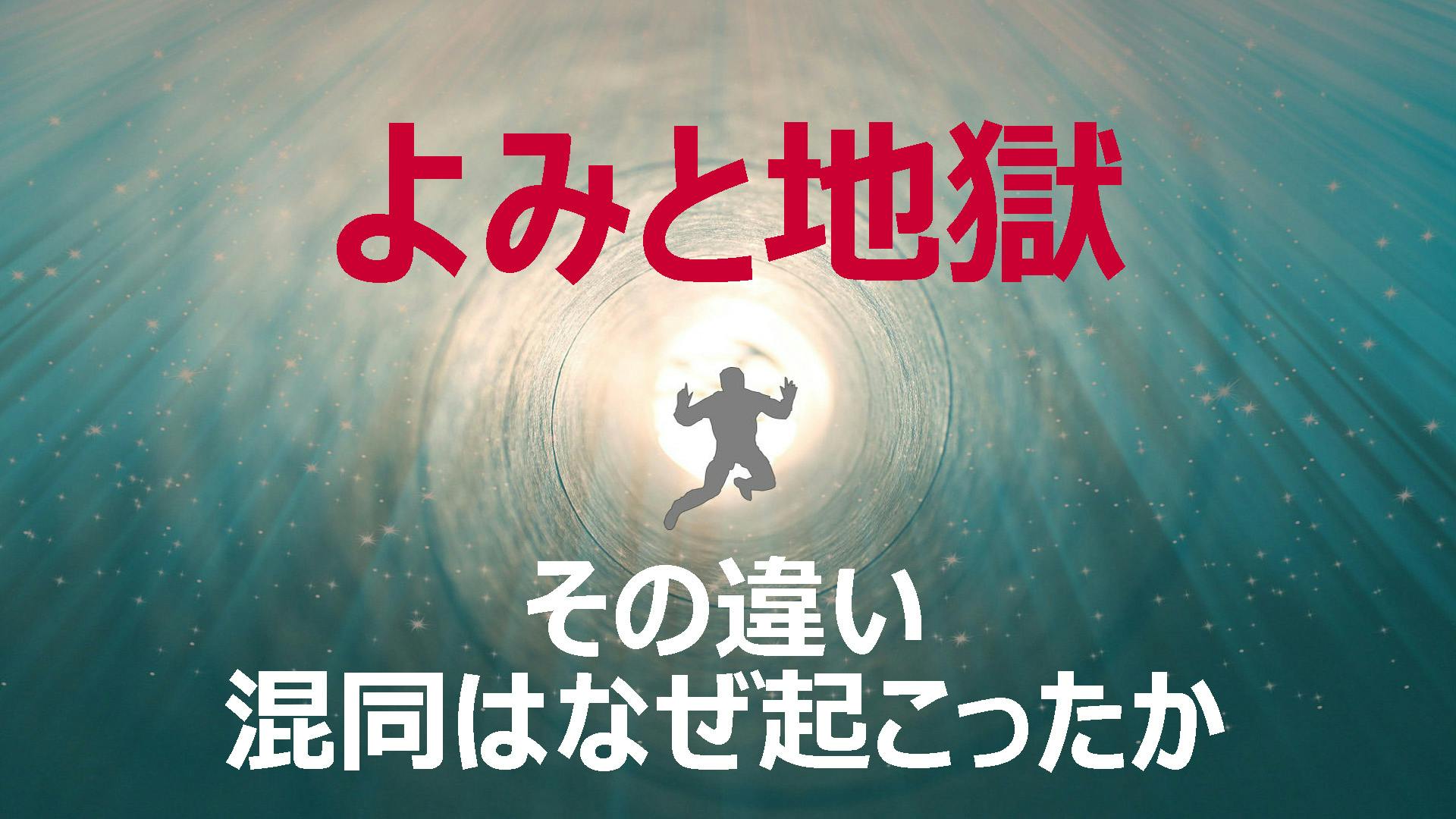まだまだ暑い日が続いておりますが、皆さまもお変わりなくお過ごしでしょうか

もしもよろしければ、早朝に語られたメッセージの方をぜひシェアさせて頂ければ幸いです
かつて、イエスの弟子達はキリストの真実を知り黙ってはいませんでした。
たとえ迫害され、少数派の意見であっても宣べ伝え続けました

大多数の意見に合わせ、世の流れに沿って黙ってしまう事により、大切な真実は封印されたままとなってしまうのです。
近年でも未だに日本人のクリスチャンは少数派であると言われ続けています、、、 それは遠回しに、ほとんどの者達が天国へ行けないのだと言われているようで、全く理解に苦しみました
それは遠回しに、ほとんどの者達が天国へ行けないのだと言われているようで、全く理解に苦しみました
(※しかしながら実際には、欧米やキリスト教諸国と言われている国においても、真のクリスチャンはごく僅かだと言われているので、結局はあまり変わらないのでは?と思われます
 )
)
ところが昨今 「天国」か「地獄」の2択説は、完全に誤った解釈であると知りました
「天国」か「地獄」の2択説は、完全に誤った解釈であると知りました

以前にも一度シェアさせて頂いた内容ではありますが、とても大切なトピックとなりますので、今一度別のビデオを抜粋させて頂くと共にシェアさせて頂きたいと思います (*´▽`*)❀

死後どうなるのか
私たちは死後、どこへ行くのでしょうか。
死後どうなるのでしょうか。
ここで聖書の死後観を見てみましょう。
聖書が語る死後界としては、「天国」、「よみ」、「地獄」の三つがあります。
「えっ、天国と地獄の二つではないの?」と言われる方もいるかも知れません。
しかし二つではなく、三つです。
~このうち「天国」は、永遠の至福の場所です。
そこには神とキリストがおり、愛と幸福と永遠の命が支配しています。
そこは「神の王国」なので、神とキリストを人生の「主/王」として信じる者が入るとされます。
一方「よみ」は、一般的な死者の世界です。
世の終りの「最後の審判」(神の裁きの法廷)の時までの、一時的な場所として存在しています。
「地獄」は、最終的な刑罰の場所です。
~旧約聖書には、この「よみ」という言葉が何度も出てきます。
「よみ」は、実は日本の神道でいう「黄泉」に、そっくりです。
日本神道でも旧約聖書でも、「よみ」は暗い、死者の「けがれ」に満ちた所とされています。
よみという死者の世界
「よみ」は、しばしば「地獄」と混同されてきましたが、別の場所です。
旧約聖書によると、かつて(イエスキリスト以前の世界)人は死後、どんな人でも---良い人でも悪い人でも、神の信者でも不信者でも---皆「よみ」に行きました。
~人の死後の世界としての「天国」という観念が始まるのは実はイエスキリスト以降、つまり新約聖書の時代になってからなのです。
~「よみ」は又、世の終りになると、最後の審判と呼ばれる神の法廷に、その中の全ての死人を出します。
そしてその死人の最終的行き先(天国か地獄か)が決定された後、空になった「よみ」は、地獄(火の池)に捨てられるのです。
ヨハネの黙示録20:14
つまり、「よみ」と「地獄」は全く別のものです。
よみの中
よみは、「暗く」「広く」「深い」場所で、幾つかの場所に分かれていると書かれています。
死んだ人は、生きていた時の行いに応じて、「よみ」のそれぞれの場所に行って、ある人は慰めを受け、ある人は懲らしめを受けるとされました。
~十七世紀に「欽定訳聖書」という権威ある英語訳聖書が出版されたのですが、これがひどい誤訳をしてしまったのです。
その訳は、「(ハデス)よみで苦しみながら目を上げると・・・」の箇所を、「(ヘル)地獄で苦しみながら目を上げると・・・」と訳してしまいました。
これは中世のヨーロッパでは、「よみ」という一般的な死者の世界と、「地獄」という究極的刑罰の世界の混同が起きていたからです。
~しかしこの言葉の言語(ギリシャ語)はハデスで、「よみ」という言葉です。
天国
~その後イエスキリストの降誕があり、初めて人の死後の行き先としての「天国」が語られるようになりました。
イエスキリストは、十字架の死の前夜に、弟子達にこう語りました。
「わたしの父(神)の家には、住まいがたくさんあります。・・・あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです」ヨハネの福音書14:2
キリストは十字架の死と復活、昇天を経て、人々が死後に行けるための場所を「天国」に備えに行くと述べたわけです。
~主イエスキリストを信じる者は、肉体を離れると、主と共になるために天国へ行く、ということです。
使徒パウロはまた、自分がまだ生きている時に「第三の天」=「パラダイス」にまで引き上げられ、その至福の光景を見、神の民が行く場所としての「天国」の啓示を受けています(ヨハネの福音書12:2~4)
~旧約時代の神を信じる聖徒達(アブラハム、ダビデ、他)の人々も、イエスキリストの昇天の際に、「よみ」から引き上げられて天国に入りました。(エペソ人への手紙4:8)
死後観の混乱
~かつて初代教会では、以上述べた理解がありました。
ところが中世になると、ヨーロッパで教会の堕落が起きました。
そして死後観も、聖書から外れたものになっていったのです。
ヨーロッパ土着の「地獄観」がキリスト教会に入り込み、「よみ」と「地獄」は混同されました。
とくに、「人間は死ぬと天国か地獄へ直行する」という誤った理解が広まりました。
しかし正しい聖書の教えは、「人間は死ぬと、天国かよみへ行く。神の御子イエスを”救い主”と信じる者は罪赦され、死後、至福の天国へ直に上げられる。」
一方、そうでない人は、「よみ」という一般的死者の世界へ行き、よみのそれぞれの場所で、自分の地上での人生を振り返る時を与えられる。
やがて世の終りに「最後の審判」と呼ばれる、最終的な行き先を決める神の裁判の法廷が開かれる。
よみの人々はその法廷において、過去と心の奥底を見られ、そのあと最終的に「天国」に入れられるか、「地獄」に収容されるかが決められる。
しかし欧米のキリスト教徒などには、いまだに違う理解をしている人がいます。
これは実は今日も、キリスト教世界において大きな問題です。
たとえば、「人間は死ぬと天国か地獄へ直行する」という誤解をしてしまった人は、「死んだ未信者は皆すでに地獄へ行った」と考えてしまいました。
「非キリスト教徒はみな地獄だ」、というわけです。
また、「福音(キリストの教え)を一度も聞く事なく世を去った人々も、みな地獄に行っていて、もはや救われるチャンスはない」と教えました。
しかし、もしそうなら昔の日本人の多くは福音を聞くチャンスも無く世を去ったわけですから、日本人の多くは地獄に行ってしまっていて、もはや救いの機会は無い事になってしまいます。
けれども、これは聖書からいえば、とんでもない曲解です。
実際は、彼ら日本人の多くや、また他の国で福音を聞くこと無く世を去った人などは皆、今は地獄では無く、「よみ」にいるのです。
死後のセカンドチャンス
聖書によればまた、「福音」を一度も聞いたことの無い人々」にも、「よみ」において福音を聞き、回心するためのチャンスが与えられます。
~これは聖書の次の言葉に基づいています。
「それはイエスの御名によって、天上(天国)のもの、地上(地球)のもの、地下(よみ)のものなど、あらゆるものがひざをかがめ、また、あらゆる舌が「イエスキリストは主である」と告白して、栄光を父なる神に帰するためである」(ピリピ人への手紙第二章10:11)
つまりイエスの福音は、「地下の者」=「よみの人々」のためにも存在している、と語られています。
また、「生きている者にも、死んだ者にも、御恵みを惜しまれない主」(ルツ記2:20)と書かれている。
神は、死者にも御恵みを惜しまない方であると述べられています。
~新約聖書にはまた、イエスが十字架死の後、復活するまでの三日間、「よみ」に降ってそこで福音宣教をしたと書かれています。
「キリストは、肉では死に渡されましたが、霊では生きる者とされたのです。そして霊においてキリストは捕らわれていた霊達のところへ行って宣教されました。」(ペテロの第一の手紙3:18~)
もちろん、よみにおいて福音を聞いたからといって、地上と同様、すべての人が信じるとは限りません。
信じるとは、単に神やキリストの存在を信じるということではなく、神とキリストを愛し、その教えてに従うことを意味しているからです。
セカンドチャンスへの賛否
実はこの論に対しては、プロテスタントの人々の間にも賛否があります。
~イエスの福音は、単に死後天国に行くためだけのものではありません。
この地上の人生を、物心共に豊かに生きるためのものです。
~イエスキリストが来たのは、私達がイエスの教えを通して、この地上で困難を乗り越え、力強く人生を切り開き、祝福を受けて幸福に歩むためです。
そうであれば、人がイエスを信じるのは、早ければ早いほど良いのです。
ですから、もし人生におけるイエスの祝福と導きをしっかりと伝道するなら、未信者は決して「回心を死後に延ばせば良い」などと考えたりはしません。
~大切なのは、「福音を一度も聞くこと無く世を去った人はもはや救われないのですか?」という問いに明確な答えを与えることです。
例え、イエスの福音を聞くこと無く世を去った人がいても、或いは福音を聞いたが信じないで世を去った人がいたとしても、「よみ」で再度福音を聞いて回心し、救われるための機会が与えられます。
~ただし、よみにおいて人の魂は裸であり、神に隠し事や嘘はできません。本当に回心しているか否かは厳しく問われます。
ですから、もし福音を地上で聞いたなら、信じてイエスの指導を受けて生きて行くのが最も良いということになります。
そうすれば人生を祝福に変えることが出来、また死後も至福の天国に直行出来ます。
これが聖書の教えです。
一方ある人は「セカンドチャンスの教えは聖書の信仰義認の教えに反する」と主張して反対しているようです。
しかしセカンドチャンス論は、まったくのところ信仰義認の教えそのものなのです。
死後の3つの場所
人は誰でも、「自分は死んだらどうなるのか」「どこへ行くのか?」という思いを持って生きているものです。
~本当はどうなのでしょうか。
宇宙万物を造られた「神」からの啓示の書「聖書」は、人間の死後の行き先を、明確に示しています。
~その神の法廷で、神に認められた人々は、その後天国に入れられます。
一方、神から退けられた人は、「地獄(火の池ゲヘナ)に入れられるのです。
地獄とは、つまり死の直後の場所ではありません。
地獄が使われるのは、世の終りの「最後の審判」の後です。
なぜ最後の審判があるか
~最後の審判の法廷には、救われた人々の名前のリストを記した「いのちの書」と呼ばれる書が提出されると、聖書に書いてあります。
その「いのちの書」に従って、「よみ」の人々の最終的行き先が言い渡されるのです。(黙示録20:12)
「いのちの書に名の記されていない者はみな・・・火の池(地獄)に投げ込まれ」(黙示録20:15)と書かれています。
このように「いのちの書」は、神の国に入る人々のリストです。
救われた人々の名簿です。
これは大切な点です。
つまり、「よみ」の人々が最後の審判を経て、もし全員「地獄」に入れられると決まっているのだとすれば、その法廷に「いのちの書」を提出する必要は全くありません。
さらに、もし「よみ」の魂が全員地獄行きなら、最後の審判という法廷すら必要ないのです。
なぜならそんな法廷を開かず、自動的に「よみ」の人々を地獄へ移せば良いからです。
~この「イエスキリストは主である」という告白は、救われる信仰告白です。
「もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる」(ローマ人への手紙10:9)と明言されています。
よみにあっても、そう信じるなら、救われて神の国に入るのです。
~キリスト再臨が間近になった患難時代において、「よみ」の人々の口からも、神とキリストに対する礼拝と賛美の声があがるのです。
事実、イエスキリストは、「死人が神の子(キリスト)の声を聞くときが来ます。・・・そして聞く者は生きるのです。(ヨハネの福音書5:25~28)と言われました。
イエスが「生きる」という時、それは救われる、永遠の命に生きるという意味です。
~ただし、これは必ずしも「よみ」に行ったすべての人が救われるという意味ではありません。
残念ながら、最終的には滅びる人々も少なくないのです。
キリストは、「滅びに至る門は大きく・・・そこから入って行く者が多い」(マタイの福音書7:13)と言われました。
キリストの「よみ」降り
かつてイエスキリストは天におられた神の御子でありながら、地上に人となって降誕し、約33年半の生涯をおくられたのち、十字架にかかって死なれ、死後は「よみ」に降り、三日目に「よみ」の中から復活し、40日間地上におられ、その後昇天して天に帰られたとされています。
イエスキリストは、十字架の死によって人々の罪の贖い(代価を払って救う)を全うし、復活によって死を破られた勝利者です。
~「よみ」はいわば留置場のようなものであり、裁判前の場所です。
一方、「地獄」は刑務所のようなものであり、裁判後、刑の確定後に収容される場所です。
「刑務所」では、もはや弁護人(イエスキリスト)も来る事はありません。
しかし「留置場」など裁判前の所では、弁護士も来てくれることがあります。裁判の時に、無罪となることもあります。
~今まで聖書の大切な真理は失われてきました。
けれども、「よみ」と「地獄」の区別をはっきり理解するなら、私たちは今や死後の世界の真実を知ることが出来ます。
~地上での回心が「よみ」での回心にはるかに優っていることは、火を見るより明らかなことです。
もしこのことをしっかり説くなら、「死んでから回心すれば良いじゃないか」という思いには決してなりません。
~「よみ」は、暗い、生気のない場所に過ぎません。
「よみ」に行ってからでは、私たちが人間として生を受けた使命を全う出来ません。
聖書を通し、この地上で生きている間に、人生の早い時期から神と共に生きることが、最も確かな祝福の道です。
大洪水以前の死者への宣教
さて、ノアの大洪水は、紀元前2,400年頃に起こりました。
一方キリストの「よみ」降りは、紀元後30年頃です。
すなわち、大洪水前に死んで「よみ」にいた死者は、少なくとも約2,400年間留め置かれた後、ようやく福音を聞く機会を得たわけです。
~生きている間に回心して、神と共に生きれば、死後は「よみ」を
経ずに、直接、天国に上げられ、至福の中に迎え入れられます。※また、幼児期に亡くなられた際にも同様だと信じられています(ルカによる福音書18:16~17)。
しかし、生きている時に神に背く生き方をし、死後「よみ」に下った人は、そこで数千年間、自分の蒔いたものを刈り取る期間を経験しなければなりません。
それは辛いものになるでしょう。
ですから回心は、福音を聞いたなら、生きている内にすべきなのです。
大洪水後の死者への福音
~大洪水後の「よみ」の死者に福音が語られるのは、とくに世の終末が間近になった時です。
聖書の「ヨハネの黙示録」に、いわゆる「患難時代」のことが記されています。
聖書によれば、世界はやがて「産みの苦しみの時代」と呼ばれる苦悩の時代を迎えます。
~その時、この世の矛盾や悪が一斉に吹き出し、末期症状が最高潮に達して、世界は出口を失うようになります。
しかし最終的に神が介入して、キリストが再臨し、すべての悪に終止符を打ち、神の国を地上にもたらしてくださると、聖書はいいます。
よみと地獄
日本人は昔から「よみ」(黄泉/陰府)という世界を知っていました。
神道では、人の死後の世界として「よみ(黄泉)」が信じられてきたのです。
~日本の教会でよく使われている「新改訳聖書」の訳者も、「あとがき」にこう記しました。
「新約聖書で、ハデス(よみ)、ゲヘナ(地獄)と訳出されているのは、それぞれ、
ハデス(よみ)「死者が終末のさばきを待つ間の、中間状態で置かれる所」
ゲヘナ(地獄)「神の究極の裁きにより、罪人が入れられる苦しみの場所」を指す。
米国等の使徒信条
日本にはまた伝統的に「よみ/黄泉」の観念があったことも、幸いしました。
しかし西洋では、中世の教会堕落時代以来、ヨーロッパの地獄観念が入り込み、「よみ」の観念は消え失せてしまったのです。
~日本人はよく、「キリストの福音を知らずに死んだ私の先祖や親族、家族などは今どこにいるのですか?彼らが救われる道はあるのですか?」という問いを発します。
「よみ」と「地獄」の混同は、そうした問いに対して、適切な答えが出来ない人を多く生んできたのです。
日本でも
~このように最近、よみと地獄の混同から抜け出し、死んだ未信者は地獄では無く「よみ」へ行っているという理解が広がり始めています。
~もちろん、まだまだ反対は強いです。
しかし反対論は、私の見る限り、どれも的外れなものばかりです。
死者のために
このように、よみに行った人々の最終的行き先は、まだ確定していません。
それが決まるのは、世の終りの「最後の審判」と呼ばれる神の裁判の法廷においてです。
それが「死後の裁き」と呼ばれるものです。
キリストの救いを知らずに死んだ私達の先祖などは、今その「よみ」にいて、自分の地上での人生を振り返りながら、その時を待っています。
私達は、神がその人々に恵みと憐れみをお与え下さり、「よみ」でキリストの救いを知ることができるよう祈ることが出来ます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() それは遠回しに、ほとんどの者達が天国へ行けないのだと言われているようで、全く理解に苦しみました
それは遠回しに、ほとんどの者達が天国へ行けないのだと言われているようで、全く理解に苦しみました![]()
![]()
![]() )
)![]() 「天国」か「地獄」の2択説は、完全に誤った解釈であると知りました
「天国」か「地獄」の2択説は、完全に誤った解釈であると知りました![]()
![]()