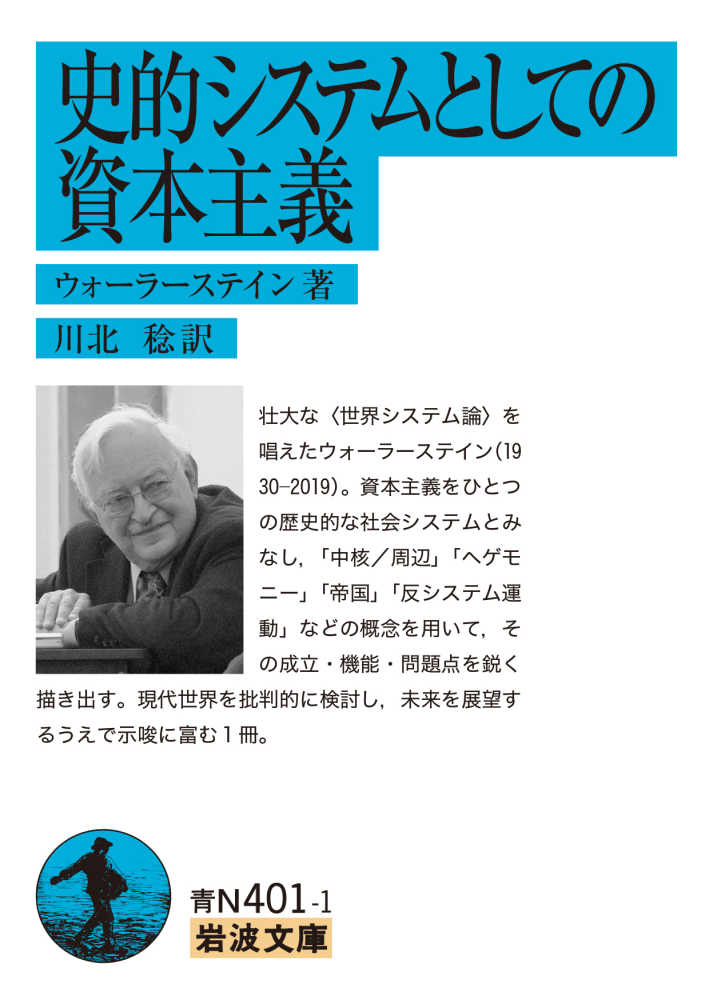シチリア島、アグリジェント付近の荒野。©マリンブルーの風。
樹木も育たない不毛の荒野が、ディ=ランペドゥーザの小説『山猫』の舞台。
【7】 『史的資本主義』「結論」――
「進歩」の逆説:《山猫》たちの生存戦略
前節までに、ウォーラーステインは9つの理由を挙げて、「進歩の観念」はイデオロギーであって現実ではない、ということを明らかにしてきました。しかし、その一方で「[進歩の観念]を生みだした歴史的現実」というものは、たしかに存在しました。「進歩の観念」は、近代の「資本主義的世界システム」が、その存続に必須のイデオロギーとして生み出したものだからです。そしてこのことは、「ひとつの史的システムから別のシステムへの移行」にかかわっています。
「進化論的な進歩の理論は、あとに来るシステムのほうが、まえのシステムよりすぐれている〔α〕、という仮説を含んでいるばかりか、かつて支配的であった集団に代わって、別の新たな集団が支配的になるという仮定〔β〕をも含んでいた。」つまり、「進歩の観念」には、システムの交替にあたって、古い支配的集団は姿を消し、代わって、より優れたシステムとともに新しい支配的集団が登場する、というストーリーが含意されているのです。
封建制から資本主義への「移行」について言えば、〔α〕資本主義は封建制よりも進歩したものであり、〔β〕その進歩は、「[地主貴族]〔…〕に対する[ブルジョワジー]の勝利、それも革命的勝利によって達成されたことになるのであった。」
「史的資本主義が、進歩的なブルジョワジーが反動的な貴族を打倒した結果として勃興してきた」というイメージは、ウォーラーステインによれば誤りです。そうではない現実の歴史過程を、私たちは「世界システム分析」の枠組みに沿って見てきました。
それでは、「打倒」でないとすると、そのへんの階層関係の動態は、どう推移してきたのでしょうか? それを象徴するイメージが、ウォーラーステインの言う「ディ・ランペドゥーザの戦略」です。(pp.169-170.)
『史的資本主義は、古いシステムが崩壊したために自らブルジョワジーに変身していった地主貴族によって生み出された、というのが基本的に正しいイメージなのである。彼らは、古いシステムを崩れるにまかせて・どこに行き着くかわからないままにしておくよりも、思い切った構造上の大手術を試みて、直接生産者を搾取する能力を維持する〔…〕というより〔…〕ますます強化する方法をとったのである。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,p.170. .
【8】 『史的資本主義』「結論」――
現代ブルジョワジーの「岐路」
封建制から資本主義への「移行」が、そういうことだとすると、同じことは、資本主義から次の「システム」への「移行」についても言えるはずです。「ブルジョワ革命などというものが存在しなかったのだとすれば、プロレタリア革命もまた」勃発したことなどないし、今後も永久に「ありえない」。私たちは「移行の問題について発想を変えなければならない」。
シチリア島、ボッジョレアーレの廃墟。1960年代に地震が続いたため廃村となった。
©BRUNO ZANZOTTERA, PARALLELOZERO / National Geographic.
「まず第1に、既存のシステムの崩壊に伴う変化と、十分に管理された変革とを区別しなければならない。」第2に、「管理された変革」――いわゆる「革命」――は、ひととおりではない。「進歩」と称して進歩ではない支配層の「居座り」戦略もあれば、そうではないものもある。「労働の搾取という実態」を保存または強化すべく、そのやり方にドラスチックな改変を加えるものがある。他方で、その種の「搾取を〔…〕激減させる〔…〕構造の変化」「比較的階級性の薄い社会への移行」もまたありうる。
つまり、「史的資本主義から別の何かへの移行が生じるか〔…〕が、現代政治の」争点ではない。「そうした移行は〔…〕いずれは起こる」。争点は、この「移行」の結果が、「現下のシステムと比べて倫理的にまったく違ったものになりうるか」、まやかしでなく「進歩と言えるものになりうるか否か〔…〕なのである。」(pp.171-172.)
『世界のブルジョワジーが迫られているのは、』ディ・ランペドゥーザ『山猫』の「サリーナ公爵」のように『保守的な態度をとって、現在のシステムが崩壊してゆくのを傍観し、結局、〔…〕より平等な世界秩序に変容していくのを許すか。それとも、勇気をもって移行過程を自ら管理し――〔…〕彼らは自ら「社会主義者」の衣装をまとう〔…〕――少数派〔支配層――ギトン註〕の利益のために、世界の労働者の搾取過程が〔…〕温存されるような別のシステムを創り出そうとするか〔…〕なのである。〔…〕
まさしく世界のブルジョワジーには、こうした政治的選択の可能性がひらかれている』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,p.172. .
【9】 『史的資本主義』「結論」――
反システム運動の「岐路」
『世界の社会主義運動は――すべての革命的』運動と『社会主義国家も〔…〕――ほかならぬ史的資本主義が生み出したものだ〔…〕。それらは、現在の史的システム〔…〕の内部の過程から生み出された排泄物だったのである。したがってそこには、この〔現在の――ギトン註〕システムの持つ矛盾や束縛がそのまま反映されてもいる。〔…〕そこから逃れることは〔…〕、今後もできないのである。〔…〕
社会主義的な国家において、労働の搾取が強化されていること、政治的自由が否定されていること、性差別や人種差別が根強く残っていることなどは、』それらの『国々が「資本主義的世界=経済」の周辺ないし半周辺地域に位置し続けているという事実との関係で捉えなければならない』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,pp.173-174. .
王冠付き「山猫 il gattopardo」:トマージ・ディ・
ラペンドゥーザ家の紋章。©Wikimedia.
じつは、ウォーラーステインは↑この引用から省略した部分で、社会主義の「運動や国家が持っている欠陥や限界」は、地球上まだ存在しない将来の「史的システム、つまり社会主義的世界秩序の属性ではない。」資本主義的システムの影響を受けた現在の社会主義運動や共産党国家の欠陥が、未来の「社会主義」に引き継がれることは無い、と言っています。
ウォーラーステインがこれを書いたのは 1982-83年で、当時はまだ「社会主義国家群」崩壊前であり、「社会主義」の実態も、未だ十分には知られていませんでした。ウォーラーステインが、(理念上の)社会主義を擁護する幻想から抜け出ていなかったのも、やむをえないことだったと言わなければなりません。
しかし、たんに論理的に考えてみても、「運動」が抱える矛盾や欠陥は、すべて、それが実現する政府や社会に引き継がれ、(多くの場合)拡大されて現れる――これは、必然的なことです。……いやいや、将来においては、現在とはまったく違う「社会主義運動」が展開されて、欠陥のない「社会主義」が築かれるだろう、‥‥などと考えるのも、現実的な見通しではないでしょう。
1982-83年に書かれた・この部分では、ウォーラーステインは、「資本主義的世界システム」に替わる将来のシステムを「社会主義的世界秩序」と呼んでいますが、未来の社会を「社会主義」と決めつける理由は、どこにも無いはずです。その後ウォーラーステインは、『入門・世界システム分析』執筆時には、このような「社会主義」幻想から完全に脱却しています。それは、すでにレヴューしたとおりです。
『したがって、反システム運動やそれが関係して作り上げた体制は、資本主義をして、確実に平等主義的な社会主義の世界秩序の方向へ向かって移行させようとする世界的な闘争に〔…〕どれだけの貢献をしたかという観点からでなければ、〔…〕評価されえないのである。〔…〕肯定的な力はいつでも肯定的な結果を生むとは限らず、時として否定的な結果をもたらす〔…〕。システムを弱めるものは、別の観点からすると、それを強化することになる。
従来の反システム諸運動の最大の貢献は、〔…〕叛乱を組織し、意識を変えさせ、〔訳者註――民衆の〕力を解放した』ことである。その『貢献度は、歴史的教訓』が、のちの運動に生かされることで、『時間の経過とともに〔…〕大きくなってきている。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,pp.174-175. .
『史的資本主義がまさにその発展の極に近づいている今こそ、本当の危険が生じているのだ。万物の商品化がいっそう進み、世界中の反システム運動の力が強まり、合理主義的なものの考え方が広がりつづけている今こそ、〔ギトン註――資本主義の存続にとって〕危機なのである。
現在の史的システムは、〔…〕その論理が部分的にしか貫徹していないがゆえに繫栄してきたのであり、それが〔…〕開花しきることは、システムの崩壊を早める〔加速させる――ギトン註〕結果になる。』しかも、『システムがまさに崩壊しつつあるあいだは、〔…〕その結果がどうなるかもかつてないほど不透明になる〔つまり、「カオス」的移行過程に入る――ギトン註〕〔…〕
共産主義はユートピアであり、〔…〕あらゆる宗教の終末論の化身である。それは歴史的な予測などではなく、現代の神話なのである〔そのようなものには、著者は興味を持たない――ギトン註〕。これに対して、〔…〕いつの日かこの世界に実現するかもしれない史的システム〔…〕は、歴史具体的なシステム〔…〕である。』それは、『少なくとも〔…〕平等や公正の度合いを最大限に高め、また人間自身による人間生活の管理能力を高め(すなわち民主主義を進め)、創造力を解放するような史的システムでなければならないであろう。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,pp.176-177. .
南イタリアの中世都市クラーユの廃墟。20世紀後半まで人が住んでいた。
©BRUNO ZANZOTTERA, PARALLELOZERO / National Geographic.
【10】 『資本主義の文明』「将来の見通し」
――政治制度:20世紀半ばまで
前節で、『史的システムとしての資本主義』第❹章「結論」の最後まで行きましたが、なお、改訂版(1995年)の増補部分「資本主義の文明」第❷章「将来の見通し」から、すこし拾っておきたいと思います。
本書の初版が出た 1983年といえば、まだ社会主義圏の崩壊よりも前で、社会主義諸国の実相も、いまだ十分には暴露されていませんでした。そのため、「移行」とそれ以後の将来にかんする展望が甘いのはやむを得ないことでした。前節で指摘したとおりです。
そこで、「崩壊」以後に増補された部分から、少し補っておきたいのです。
『あらゆる史的システムは、システムの幹部となる階層に報酬を与えることで生き延びた。〔…〕
史的システムは、〔…〕ろくな報酬を得ていない大衆をも、おとなしくさせておかなければならなかった。』そ『のためにふつう採用されてきたのは、力と信条の組合せであった。〔…〕信条とは、支配者は神聖だという信念と、階層秩序は絶対に必要なのだという信念とを結びつけたものである。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,p.236. .
ここでウォーラーステインは、「資本主義の文明」を4つの時期に区切って、そこにおける支配・統合の動態を概観しています。① システムの開始からフランス革命〔1789年〕まで。② フランス革命から第1次世界大戦〔1914年〕まで。③ 第1次世界大戦から「1968年世界革命」まで。④「1968年世界革命」から 20世紀の終りまで。
①「近代世界システム」が始まった 15世紀末から、18世紀末(フランス革命)までの時代には、「資本主義の文明は、古代以来の・正統性を主張する方式〔支配者は神聖で・階層秩序は必須との信念↑〕が」なお通用していると思っていた。だから、大衆に対する支配には問題がないとみなされていた。
そこで問題はもっぱら、いかにして「幹部層」に報酬を得させるかにあった。この時代には、「絶対君主を通じて中央集権国家」が建設され、それと並行して諸国家間には、「インター・ステイト・システム」とその内部のヒエラルキーが形成されていった。勝者と敗者が分かれた。そこで、「システムの幹部は、勝者となる国家機構と密接につながる」ことによって「しかるべき報酬を与えられた。」強力な国家とのつながりは、とくに企業家には重要だった。逆に、システムの幹部たちに支持された国家〔まずオランダ、つぎに英国〕が、他の国家〔スペイン,フランス,のちにはオランダ〕を抑えて強力になった。
② ところが、フランス革命を境にして状況が変わった。「資本主義の文明」は、大衆の黙従を保証していた古い信念体系〔↑〕を掘り崩してしまった。資本主義は、「〔産業革命・技術革新と結びついた〕科学主義、〔資本蓄積の効率化に必要な〕国家構造の官僚化、および〔労働力となる〕大きな人口の組織的動員」を必要とした。この3つを実現するには「政治文化〔ジオカルチュア:進歩と主権在民の思想〕の大規模な再活性化が必要になる。この再活性化の触媒となったのがフランス革命である。」フランス革命は、「人民(peuple)主権」〔主権在民〕の思想を広めることによって、合理主義の浸透と官僚制による法治を促し、教育訓練された労働者群を創り出して、資本主義の要求に応えたのです。
シチリア島、アグリジェント、「神殿の谷」。©Wikimedia.
マグナ・グラエキア(ギリシャ人植民地)時代・紀元前5世紀建造の
神殿群の遺跡。中央は「コンコルディア神殿」
今や、資本主義の広めた「科学主義」によって利巧になった大衆の忠誠を確保するために、支配の新たな「正統化」根拠として「人民主権 la souveraineté populaire, la souveraineté du people」が登場しました。しかし、この新たな「正統化」根拠は、古代以来の黙従的 “信念” とは異なって、「資本主義文明」の支配者に負担を強いたのです。たとえタテマエとしてであれ、「人民主権」を保障していると見せかけるためには、「幹部層」に「報酬」つまり《特権》を大っぴらに与えることはやめなければならない。資本主義は、「人民主権」を建前上維持しながら「いかにして幹部に報酬を与え続けるかというディレンマ」に直面することとなりました。
そればかりではない。いつまでも看板だけの「人民主権」では、当の「人民 people」が納得しなくなります。19世紀を通じて、労働者の参政権獲得要求は、しだいに大きくなっていきました。労働者が参政権を獲得するということは、賃金をはじめとする労働条件の改善に、国家が助力せざるをえなくなるということです。こうして、「労働者階級への報酬が」高くなると、「幹部への報酬は」それだけ減ることになります。
それでも、労働者の要求に譲って「ほんの小さなパイの切れ端」を与えることにすれば、それによって「世界の有効需要」が拡大し「資本蓄積を促進する」ことになるので、たとえ短期的には労賃コストがかさんでも、中期的には「幹部への報酬」は増加するだろう。――支配層の中の “賢明” な人たちは、そう考えました。
そこで、19世紀を通じて、1914年(第1次世界大戦)までは、「この調整メカニズムはみごとに機能した。」「中核諸国の労働者階級は」、㋐参政権獲得〔選挙権の拡大〕と、㋑国家介入による再分配〔社会保障・社会保険〕という「報酬引き上げの2つの筋道を与えられ」て、国家機構に「すっかり統合され、愛国主義〔…〕に染まっ」た。第1次大戦が勃発すると、各国の社会主義政党は、自国の政府を支持して戦争協力したのです。
しかも、この「調整」によって、「幹部」層は、「報酬」が減るどころか、むしろ増えていくように思われた。それというのも、中核諸国は、植民地獲得によって「世界の総資本蓄積」を「急速に拡大し、」周辺地域からの「搾取を著しく強化する枠組みのなかで、」この「調整」を実施したからである。
③ 第1次大戦の総力戦は、ヨーロッパの中核諸国を疲弊させ、周辺地域「に対する中核諸国の政治的支配を弱めた。」そこで、「[南]の民衆」つまり植民地と周辺地域の人びとが、弛緩した世界システムの支配から離れていかないようにすること、かれらを世界体制に「政治的に統合」することが、中核諸国の課題となりました。こうして、「中核諸国の内部ではすでに 19世紀に解決された政治的正統性〔…〕にまつわるディレンマが、20世紀」になると、周辺をもふくむ世界的規模でぶりかえすこととなったのです。そして、それに対する解決策も、19世紀のヨーロッパ内での方式を拡張したものとなりました。それが、「ウィルソン主義」です。
アメリカ連邦議会で対独宣戦を提議するウッドロー・ウィルソン大統領。
1917年4月2日。©The Library of Congress. 開戦に際してウィルソンは
国内統制を強化し、愛国団体を通じてナショナリズムを煽って労働運動・反戦
運動などを弾圧し、南北戦争以来となる徴兵を実施した。(Wikipedia)
「ウィルソン主義」は、㋐民族自決、㋑開発主義 の2箇条からなっています。㋐は、19世紀にヨーロッパの労働者階級が与えられたのと同じ政治的恩恵を、植民地と周辺地域諸国に与えようとするもので、その線に沿って多くの地域が植民地から独立しました。日本など、植民地化を免れていた国々は、国際機関で(形式的に)西欧列強並みの待遇を受けました。日本などは、それではなお満足せず、実質的にも対等のヘゲモニーを主張して離脱してしまうのですが。
㋑は、第2次大戦後にかけて、低開発国に対する経済援助として行なわれました。これは、ヨーロッパ諸国内では 19世紀から行われている「社会保障」の対国家・国際版です。日本も敗戦後は、その恩恵を大いに受けたわけです。(pp.236-240.)
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!