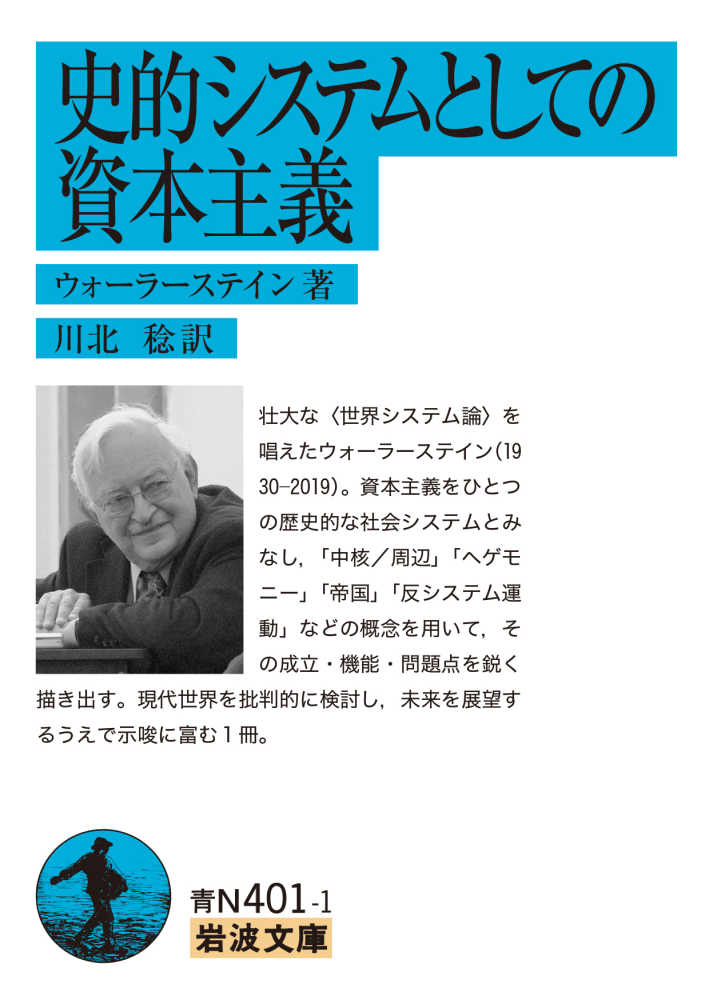アグリビジネスが描く未来の「農業工場」。©noukiya.co.jp.
【5】 『史的資本主義』「結論」――
「絶対的窮乏化」と「プランテーション」
かつてマルクスは『資本論』において、「絶対的窮乏化」法則を主張しました。資本主義的生産の発展とともに、労働生産性は上昇し、資本家は人件費を節約できるが、労働者は逆に、人手が要らなくなって解雇され、失業者増加の圧力で賃金水準は下がり、(資本家に比べて相対的にではなく)絶対的に貧困化する、というのです。しかし、マルクス自身『資本論』の他の箇所では、これと矛盾することも言っています。すなわち、生産力の増大は、人びとの欲望をレベルアップするというのです。だとすると、労働者の要求する「最低限度」の生活水準も上がっていくはずで、「絶対的最低賃金」――その水準を保証しなければ誰も雇われようとはしない金額:マルクスの云う「労働力の価値」――は上がってゆくはずです。
ウォーラーステインは、この後のほうの論理に沿って、「中核」生産過程の企業経営者は、人件費コスト上昇の圧力を受けて、利潤率低下に悩むことになる、と述べていました。「世界システム」全体で言えば、「周辺」地域から不等価交換によって吸い上げられた剰余価値は、「中核」地域の上層部に独占される状態から、同地域の労働者大衆にも、しだいに多く分配される状態に移行する、ということです。
マルクス主義の理論的問題としては、難しい論争〔「絶対的窮乏化」説 vs 「相対的窮乏化」説〕があるようですが、実際の歴史過程を支配してきた論理は、ウォーラーステインの述べるとおりだったと言えるでしょう。
ところで、ここでウォーラーステインは、それにもかかわらずマルクスの「絶対的窮乏化法則」は貫徹している、と言うのです。賢明な読者はお察しのことと思いますが、ウォーラーステインが言うのは、「周辺」地域,「周辺」的生産過程の人びとのことです。
たしかに、『いまの工業労働者は 1800年〔…〕に比べると、目を瞠 みは るくらい良い暮らしをしている〔…〕。しかし、工業に従事する労働者などというものは、〔…〕世界の人口のなかで〔…〕少数派でしかない。
⑦ 世界の労働人口の大多数は、農村地区に住んでいるか、農村と都市のスラムのあいだを往ったり来たりしている人びとで、彼らの生活は、500年前の祖先たち〔…〕と比べて悪化している〔…〕。食料は不足し〔…〕、栄養のバランスも悪くなっている。〔…〕生まれた子供が満1歳まで生き延びる確率は高まったけれども、〔…〕1歳以後の生存期待年数〔ゼロ歳児を除外した平均余命――ギトン註〕が上がっているかどうかは疑問で』ある。『彼らに課される労働は〔…〕厳しくなっているし、1日当りでも、〔…〕生涯全体でも、労働時間が長くなっている。しかも彼らは〔…〕以前より少ない報酬しか得ていないのだから、搾取率は急カーヴで上昇してきたことになる。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,2022,岩波文庫,pp.162-163. .
この「絶対的窮乏化」の原因が、「政治的・社会的にいっそう抑圧されるようになった」ためなのか、それとも「経済的に搾取を強化されたの」か、「この点の分析は難しい。」
オランダの植民地支配下・ジャワ島の強制栽培制度(Sistem Tanam Paksa)。
コーヒーの実を採取するジャワの女性たち。©Collectie Stichting Nationaal
Museum van Wereldculturen.「農民は土地の20%以上を政府指定の換金作物
(コーヒー、砂糖、藍など)の栽培にあてることを強制され、オランダには
莫大な利益をもたらした」。写真を見ると、農民は作業そのものを指揮
強制されている様子で、オランダ人らしい監督が監視している。事実上
農民所有地を占拠しての強制労働農場だったのかもしれない。
そこで、史的システムの歴史にさかのぼって考えてみることにします。
『資本主義以前の社会システムのもとでは、ほとんどの人びとは小さな共同体の中で生活していたわけだが、こうした共同体では一種の社会的規制が効いていて、個々人にはその行動について選択の余地』が『あまりなかったし、そもそも社会的多様性』が『なかったと思われる。これを〔…〕抑圧と感じた人が多かったことは疑いえないし、〔…〕満足した人びとの場合も、人間の可能性をごく狭く考えざるをえな』いという制約を受けなければならなかった。『史的資本主義を打ち建てるためには、こうした小共同体機構の〔…〕役割をどんどん小さくし、最終的にはまったくなくしてしま』う必要が『あったこと、周知のとおりである。
しかし、』それ『にとって代わったものは何だったのか。⑧ 多くの地域では、かつて小共同体機構が果たしていた役割は、長期にわたって「プランテーション」によって代行された。つまり、「企業家」によって運営される大規模な政治・経済機構による抑圧的管理(oppressive controle)が一般化したのである。「資本主義的世界=経済」における「プランテーション」は――奴隷制〔…〕であれ、囚人労働によるものであれ、分益小作制度であれ、賃金労働によるものであれ――「個人」にとっての活動の余地(leeway 行動の自由,余裕,ゆとり)を広げたとは言いにくい。
「資本主義的世界=経済」のもとにおける「プランテーション」は、非常に効率のよい剰余価値収奪の形式だと言うことができる。〔…〕従来は、鉱業や土木事業』の一部で行なわれたにすぎず、『農業生産には広範に採用されることのなかった生産様式である。〔…〕
〔ギトン註――資本主義的世界=経済のもとでの〕農業生産の管理は、〔ギトン註――資本主義〕以前の共同体機構による比較的緩やかな』規制・管理に代わって、『直接的で権威主義的なもの――ここでいう「プランテーション」――に置き換えられることが多かった。
しかし、』プランテーションに『ならなかったところでも、農村部における共同体機構の崩壊は、「解放」とは受け取られなかった。というのは、それ〔農村共同体機構の崩壊――ギトン註〕に続いてかならず〔…〕国家機構による管理の強化が見られたからである。というより共同体の崩壊は、しばしば国家による管理の強化に直結したのである。〔…〕国家機構は、直接生産者が地域内で自立的に諸決定〔生産に限らない――ギトン註〕を行なうことを、しだいに拒否するようになっていった〔…〕。こうして万事が労働の投入量を増やし、労働の専門化――このこと自体、労働者〔…〕の交渉能力を弱め、倦怠感を増すものである――を押し進める方向に作用した。』
ウォーラーステイン,川北稔・訳『史的システムとしての資本主義』,pp.163-165. .
「東洋拓殖株式会社」本社,ソウル。時期不明(1910-45)。 国書刊行会『目でみる
昔日の朝鮮』。「東洋拓殖」は、1908年、国策会社として設立され、日本人
移民の誘致を目的として、朝鮮人農民から 8万ha近い農地を奪取した(17世紀
の地籍簿を根拠に農地を没収し農民を追い出した)。しかし、日本人の入植は
進まなかったので、朝鮮人小作人を搾取する地主兼高利貸し経営に転じた。
つまり、「プランテーション」は、その内部のミクロな生産関係から言えば、さまざまなタイプがあります。賃労働なのか、奴隷制なのか、地主小作制度なのか、はっきりしない混合的なものもあります。
たとえば、オランダ領のジャワ島で行なわれた「強制栽培制度」は、教科書的な説明では、自営農民に対して商品作物の栽培を割り当てただけのように見えますが、実際には、小作制にも、賃労働にも似ており、奴隷制のようにも見えます。作付け強制される作物がみな外来のもので、作付け区画から栽培方法,収穫まで、オランダ人の商社員が半強制的に教え込んで監督することで、はじめて実現した。そういう事情が、複雑な制度実態を形成したのかもしれません。植民地政府の原住民統制政策の一環として公的に行なわれ、経営企業は、植民地政府機構と強く結びついていました。これも、「プランテーション」の一つのタイプと言えるでしょう。
日本も植民地支配国として、朝鮮や台湾で似た政策を行なっていました。
ウォーラーステインによれば、「プランテーション」は、「世界システム」の歴史の上では、「資本主義的世界=経済」によって地域の小共同体機構が解体されたあと、これを代行するものとして長期にわたって機能しました。その重要な役割は、小共同体のきづなから離れた人びとを「抑圧的に管理」し、「直接生産者の自立的決定」が行なわれないようにすることにあります。それによって、小共同体の時代よりも労働を加重しつつ、その成果を剰余価値として吸い上げることが可能になります。
「プランテーション」の・こうした「世界システム」における役割に注目すれば、歴史的概念としての「プランテーション」は、さらに広く考えてもよさそうです。
そこで私は、戦後の「農地解放」後の日本農業も、「プランテーション」の1タイプと考えることができるのではないかと思います。プランテーション企業の役割をしているのは、「農業協同組合」です。たしかに、「農協」の管理統制はゆるく、植民地の「プランテーション」ほど権威主義的ではないけれども、そのぶんは経済的拘束――機械化の奨励と、機械化ローンの金融,収穫の〔かつては強制〕買上げ・加工,等々――で補っています。
「農協」は、戦前の「産業組合」が母体であり、その当時は中堅的自作農民の自主的共同組織の色彩を持っていました。しかし、戦後は性格が反転します。小作農が解放され、直接生産者である農民による自立的決定が可能になったにもかかわらず、‥‥いや、なったからこそ、直接生産者の自立的決定を抑圧する国家政策として「農協」が組織された、という関係を見ることができます。
そして現在では、「農協」から、「アグリビジネス」を標榜する私企業へと、「プランテーション」管理の担い手は交替しつつあります。その現れが、「種子法」「種苗法」改正だと見ます。
以上は極論かもしれません。皆さんが首をかしげる姿が想像されます。しかし、「種子法」「種苗法」改正は、食糧自給率だけの問題ではない。――これは、言ってよいのではないでしょうか。
アグリビジネスが掲げる農村の未来図。©noukiya.co.jp.
【6】 『史的資本主義』「結論」――
精神的「絶対的窮乏化」:差別のイデオロギー装置
⑨「史的資本主義は、以前にはまったく存在しなかった差別(oppressive humiliation)のためのイデオロギー装置を発展させた。すなわち、〔…〕性差別と人種差別にかんするイデオロギーの枠組みが成立したのである。」
「性差別とは、たんなる男の女に対する優位を指すのではないし、人種差別もまた」たんなる「一般化した外国人嫌い〔…〕ではない。」そういうものは、「資本主義以前の史的システムにおいても〔…〕どこにでも存在した。」
資本主義社会システムのもとでの「差別」は、これらとは異なる独特のイデオロギーである。したがってそれは、資本主義システムが続く限り、なくならない。というのも、システムが、それら「差別」を必要としているからだ。
資本主義システムのもとで、「性差別は、女性を非生産的労働の領域に追いやった。」「非生産的」という言い方は、ほんとうは正しくない。家事、育児など、それらはウォーラーステインの分類では、5種の「家計所得」の一つ:「自給的活動」であり、労働力の再生産を担当する。資本主義にとって、これほど「生産的」な労働も他にない。が、資本主義システムの差別イデオロギーにおいては、資本を増殖しない活動は「非生産的」とされるのだ。
自給的労働への専門化と、それが役割義務として要求されることによって、「女たちに要求される労働は、」以前に比べて「はるかに厳しいものとなった。」ところが、「[資本主義的世界=経済]においては人類史上はじめて、生産的労働こそが権利の正当性を保証する基礎〔…〕とされたために、女性は二重に貶められたのである。」
「人種差別というのも、たんなるよそ者〔…〕に対する嫌悪感や抑圧のことではな」い。資本主義システムのもとでの「人種差別」は、異人種をシステムから放逐しようとするのではなく、逆に「史的システムの内部」に囲い込んで、「不当に安い報酬」で「生産的労働」に従事させることが、「人種差別の目標なのである。」ここに言う「史的システムの内部」とは、「世界=経済」が及ぶ限りの世界全体のことです。つまり、「人種差別」とは、アメリカの黒人差別や移民排斥〔排斥は、追い出すことが目標なのではない。「排斥」は、米国内で低賃金・貧困生活に留めるための抑圧手段。それが「移民排斥」の本質です。〕だけを指すのではない。多くの「周辺」地域の住民が、現地で低賃金労働に甘んじさせられているのも、不等価交換と並んで「人種差別」イデオロギーの結果なのです。
「性差別にしろ人種差別にしろ、いずれもいわば社会的過程であったが、そこでは[生物学]が決め手になっていた。」性差別も人種差別も、社会過程によって生み出されたものである……にもかかわらず、それらは「自然の資質の相違」だと見なされる。そこに、「差別」が「差別」であるイデオロギー性が存在します。まるで、差別は自然の相違に基く以上「社会的に解消することはできない」かのように。しかしそれは錯覚です。むしろ、こう言わなければならない:「差別を、[こころ]の持ちようや、あるコトバを禁句にすることによって解消することはできない。差別は、社会的にしか解消されない。」
「レイシズムは心身の健康を蝕む」。©blacknews.uk.
以上述べてきた「性差別と人種差別」は、前節で述べた物質的な「絶対的窮乏化」と対比して言えば、精神的「絶対的窮乏化」とも言えるでしょう。ただ、「差別」の効果は「こころ」を傷つけるだけではない。むしろ、労働を加重し報酬を切り下げる(あるいはゼロにする)という物質的な効果のほうが絶大であり、システムが「差別」イデオロギーによって追求する目標も、それら物質面にあるのです。
さて、物質的/精神的「絶対的窮乏化」の結果として、「資本主義的世界=経済」の・上から 10~15% の人びとと、残りの人びととのあいだの格差は、大きく広がってきました。ところが、「一見したところ、そのようには見えない」。格差は、「3つの事実」によって隠されています。
第1に、この社会は「実力主義社会」だ、というイデオロギーが「うまく機能して」いるからです。じっさいに、労働者とその上の階層のあいだでも、種々の民族・職業階層のあいだでも、ある程度の流動性は見られた。だから、格差は、もしあるとしても能力と努力の結果だ、と思ってしまうのです。もちろん、それは幻覚です。
「格差」が見えにくい第2の理由は、「従来の歴史学や社会科学が、[中産的諸階級]の内部で生じた現象〔…〕にばかり目を奪われてきた」からである。しかし、それは「資本主義的世界=経済」の総人口のうち、上から 10~15% の部分にすぎない。この部分は、「自ら生産するよりも多くのものを消費してきた階層」であり、世界システムの「幹部層」〔「中核国」の国民,「中核」生産過程の労働者等〕である。「近代世界システム」の歴史を通じて、この「幹部層」と、トップ 1%以下の「最上層部」とのあいだには、「かなり劇的な平準化の傾向が見られた。」「史的資本主義の内部で過去数百年に採用された〔…〕[進歩的]な政策の大部分は、世界の剰余価値の分け前」にかんして、この2集団のあいだの「分配の不平等を着実に緩和する効果をもってきた。〔…〕格差の縮小に成功した[中産層]〔「幹部層」〕の勝利の歓声があまりに大きいので、〔…〕残りの 85%〔…〕との格差がどんどん開いているという現実が見えにくくなっているのである。」
第3の理由としてウォーラーステインが挙げるのは、「ここ 10年ないし 20年のあいだ〔本書出版年を基準にすると、1964/74-83〕〔…〕絶対的両極化の速度はいくらか鈍っている」ということです。ただ、この第3点は、現在では妥当しなくなっています。現在は、北米・西ヨーロッパ諸国でも、著しい「格差の拡大」が認められています。(pp.165-169.)
【付記】 なお、誤解の無いように書いておきますが、いま日本のテレビ界で問題になっている「女性の上納システム」のようなものは、ここでウォーラーステインが論じている「性差別イデオロギー」とは別の問題です。「上納システム」にしろ「MeToo」にしろ、近代世界の「性差別イデオロギー」によって強められることはあるとしても、それらじたいは近代以前からあるものです。
資本主義だろうと封建主義だろうとゴキブリは出る。駆除すればいなくなる。それだけのことです。
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!