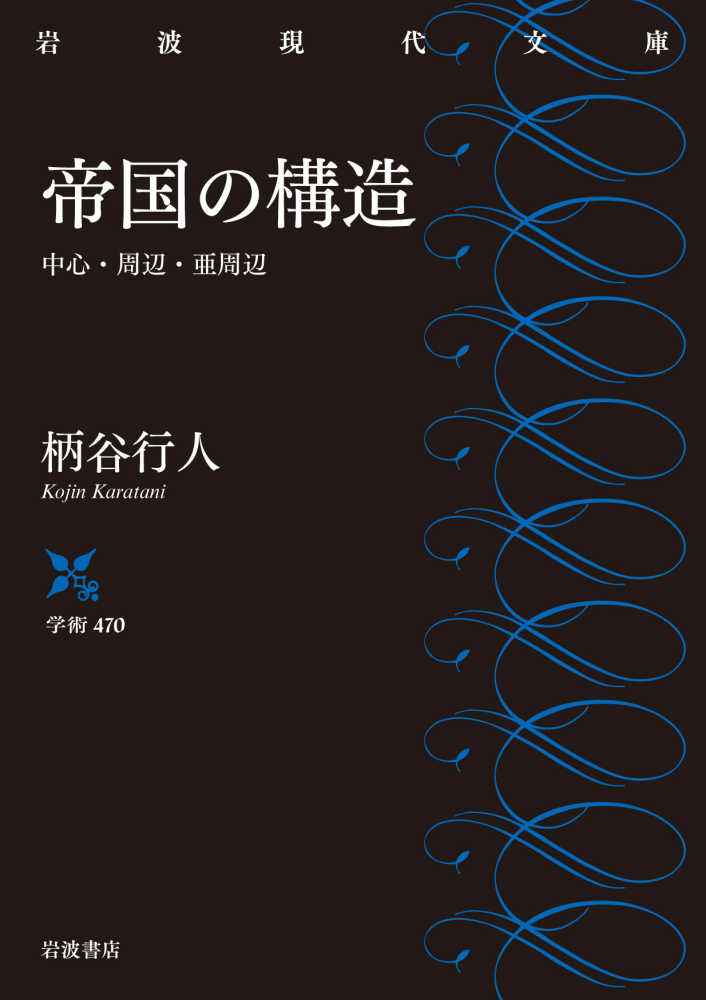ジョージア(グルジア),ムツヘタは 4世紀にキリスト教を受入れた「イベリア
王国」の首都。中央:スヴェティツホヴェリ大聖堂(11世紀再建)©shutterstock
【30】 《帝国》と「民族自決」――
ロシア帝国とレーニン,スターリン
『レーニンは初期から民族自決を肯定していました。もちろんそれを、「階級闘争の利害に従属させること」、また「民族自決」より、「民族のプロレタリアートの自治」を優位におくことを強調しましたが、それは、諸民族の抑圧-被抑圧の関係の根底に帝国主義がある、ゆえにそれと闘うことなしに民族自決はない、と考えたからです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.192.
つまり、レーニンの考えは、「近代世界システム」における帝国主義的支配・抑圧への対抗として「民族自決」を評価し、「民族自決」を、全世界的規模の “社会主義革命” の一補助手段ないし一局面として位置づけたと言えるでしょう。したがって、ソ連「一国社会主義」に転換した後のレーニンの民族自決政策は、基本的に、「社会主義」ソビエト国家(“プロレタリア独裁“ を名目とする官僚国家の支配)の下での「自治」という限度に制限されます。
その方向が、ロシア帝国の遺した複雑な民族問題を解決するものでなかったことは明らかです。なぜなら、1980年代にソ連邦が崩壊するとともに、抑えられていた各地の民族問題は、一斉に火を吹くことになるからです。ソ連はいわば、民族問題を “なだめて眠らせていた” にすぎません。
しかし、少なくとも表面的には、ソビエト体制が続いているあいだ、民族問題が大きく噴出することはなかった。ソ連邦の体制は、少数民族の文化を半ば育成しつつ、半ば抑制し、とくに政治的主張となる場合には抑圧し、ときには武力弾圧もまじえつつ、諸民族の自己主張を和らげて、ロシア「国民国家」と「大ロシア」ネーションへの統合をはかった。そう言うことができるでしょう。
ソ連が半世紀にわたって諸民族を安定させ、一定の自治と民族文化の発展にも取り組んできたことを、私はいまも、高く評価したいと考えています。もちろん問題が無いと言っているのではありません。そのことは、↓このあと詳しく述べるでしょう。それでも、現在の中国がしている少数民族に対する抑圧・同化政策と比べると、ソ連の政策の寛容性と保護の厚さが際立つのです。
とはいえ、たとえば 1923年に起きたグルジア人の独立運動に対して、グルジア出身のスターリンは「[大ロシア民族主義]の立場から残酷に弾圧した」。これは、域内諸民族に対するソビエト官僚国家の抑圧面が強化される・ひとつのきっかけとなりました。
じつは、ロシア革命1年後の 1918年にレーニンは、それまで否定していた連邦制を受け入れ、少数民族の連邦からの「離脱権」を認めていました。そしてソビエト憲法には、①民族が分離独立する権利、②分離しない民族には、大幅な自治が保障されること、③さらに、自治共和国を構成していない少数民族派の権利が保障されること、が明記されていました。
ですから、グルジアにも、分離独立権が保障されていたはずでした。しかも分離独立派は、共産党に反対する勢力などではなく、マルクス主義者だったのです。にもかかわらず、スターリンはこれを圧刹しました。
病床で事態を知ったレーニンは、党大会に覚書を送って批判しましたが、「時すでに遅し〔…〕まもなくレーニンが死去し、スターリン体制が確立〔…〕[分離独立する権利]も[連邦]も有名無実になってしまった。」(pp.192-193.)
ジョージア(グルジア)国。ゲルゲティの三位一体教会(14世紀建造)。
ジョージアのシンボルともいえる歴史的建造物。ソ連時代にはすべての
礼拝が禁止されていたが、多くの人が観光の名目で訪れた。©Veltra.com
レーニンが党大会に送った覚書には、次のように書かれています:
『私は例の自治化問題に十分精力的に取り組まなかったために、ロシアの労働者諸君に対して重罪を犯した。〔…〕
民族問題は、ひとまず解決されたとされているが、その解決なるものは、実は、われわれの正当性の根拠である・連邦からの離脱権・を反故 ほご にし、少数民族を、100パーセント・ロシア製の〔…〕ロシア官僚主義・の特徴たるロシア排外主義に、引き渡すのである。』
レーニン「大会への手紙」, zitiert in:柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.193.
レーニンのこの残念そうな告白から推測すれば、憲法に高々と謳 うた われた「分離独立権」はもちろん、「自治権」さえも、実際には、最初から有名無実なものだったと考えられます。レーニンの作った良い体制を、スターリンが悪く変えたのではない。レーニンの作った体制自体が最初から、名目と実体の異なるイカサマだったのです。
レーニンのソビエト体制の下で、ロシア人以外の諸民族は、「ロシア官僚主義」と「ロシア排外主義」の下に従属させられたのです。柄谷氏は、↓下のように説明していますが、文中の「スターリン」は、すべて「レーニンとスターリン」と読み替えなければ公平ではありません。
「レーニンは正しい。スターリンが悪い」と言いたいなら、スターリンがどんな制度変更をしたのか、事実をもって実証すべきですが、自称レーニン主義者たちが実証しているのを見たことがありません。スターリンだけを悪者にして、レーニンや・ボルシェヴィキのほかの悪者ども(粛清の犠牲者をふくむ)を免罪する・悪質な試みは、レーニンもろともに唾棄されるべきです。
『スターリンが抱いていたのは、近代国家に固有のナショナリズムです。ゆえに、同胞のグルジア人をためらうことなく弾圧したのは、彼らがスターリンの想定する「ネーション」を脅かしたからです。しかし、このようなナショナリズムは、必然的に、少数民族の分離独立運動をもたらさずにいない。それを暴力的に弾圧した〔…〕
ソ連邦は第2次大戦後、ナチスの支配下にあった周辺諸国を軍事的に「解放」し、ワルシャワ条約機構の〔ギトン註――くびきの〕中に入れました。そこでソ連圏が形成された。これは「帝国」ではなく、「帝国主義」的なものです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.194.
ここで柄谷氏が注目しているのは、第2次大戦後ティトーらパルチザン勢力によって解放されたが「ソ連圏」には入らなかったユーゴスラヴィアの場合です。ユーゴは、旧オスマン帝国、そしてハプスブルク帝国の領域であり、「民族自決」とは異なる原理が残っていたとも言えます。ユーゴは連邦制を採用し、国際政治的には「自由主義圏」「ソ連圏」どちらにも属さない「第三世界」を志向しました。
『重要なのは、ユーゴスラヴィアでは旧オーストリア=ハンガリー帝国の経験が受け継がれたこと、具体的に言えば、オーストリア・マルクス主義の伝統〔⇒:前回【28】〕があったことです。
チトーは多数の民族の連邦を維持するために腐心しました。もちろん、そこ〔ギトン註――連邦〕から「分離独立する権利」を認めたうえでです。また、大幅に言論の自由を許し、〔…〕野党を許容した。〔…〕経済的・文化的に西側と自由に交流しました。
しかしこのことは、チトー個人のカリスマに負う面が少なくなかった。彼の死後、ユーゴでは諸民族を統合する力が弱まり、また、資本主義経済の浸透によって生じた階級分解が、民族主義的な対立に転化するようになりました。1990年ソ連圏が崩壊する時点で、ユーゴスラヴィア連邦から〔…〕次々と民族国家が分離しました。
しかし、ユーゴスラヴィア連邦の経験は〔…〕人類にとって非常に貴重なものです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.194-195.
旧ユーゴスラヴィア国防省。ベオグラード,セルビア。1990年「コソボ紛争」時の
NATO による爆撃の爪痕を今も伝えている。©Veltra.com
【31】 現代中国と《帝国》――
毛沢東の「農民革命」
『私は先に、旧帝国が民族主義によって分解せず広域国家として存続したのは、民族よりも階級を重視したマルクス主義者が革命を起こしたところだけだ、と述べました。皮肉なことに、帝国はマルクス主義によって存続したのです。
しかし 1990年代にいたってソ連は崩壊し、ユーゴスラヴィア連邦さえ崩壊しました。それなのに、中国の体制は崩壊しなかった。なぜでしょうか。
孫文は最初、西洋の近代国家の観念に基いて中国の革命を考えていました。1911年清朝は辛亥革命で倒れたのですが、その結果生まれた共和制はまったく機能しなかった。軍閥が乱立し、その一人袁世凱が 1915年には帝政を復活〔…〕した。〔…〕
それに対して孫文は、中国革命のヴィジョンを修正しました。それには 1917年に起こったロシア革命の影響があります。孫文はレーニンと交流し、また、「連邦」による国家を構想しました。
孫文のタヒ後、彼の思想にあった2つの要素、西洋的近代国家建設と社会主義革命をそれぞれ受け継いだのが、蒋介石と陳独秀〔中国共産党の初期の指導者――柄谷註〕です。〔…〕
しかし、中国に社会主義革命を実現したのは、そのどちらでもなく毛沢東でした。〔…〕陳』独秀『は、中国革命の主役を産業プロレタリアートに見ていました。〔…〕ところが毛は、農民=農村革命を主張した。そのため、彼は一貫して共産党指導部から排除されました。
毛が農民による革命を考えたことは、それまでのマルクス主義の理論に反しています。彼がそれを考えたのは、〔…〕中国の社会的政治的構造と歴史に通じていたからです。王朝の交替期には、必ず農民・流民の反乱があった。それらに支持され、また、土地改革(均分化)を掲げることによって、新たな皇帝が出てきたのです。毛の政権も同様です。〔…〕毛は、帝国の経験に立脚したと言えます。
中国では、王朝の交替は「易姓革命」であり、新王朝には正統性が要求されます。その正統性は、①天命=民意にもとづくこと、また、②版図を維持ないし拡大することにあります。毛による革命は、マルクス主義から見ると異例のものですが、中国の「革命」観念には合致しています。〔…〕
毛の政策として際立つのは、第1に土地政策です。それは人民公社に象徴されます。これはソ連の模倣ではなく、これまでの王朝が何度も試みた土地公有化の伝統を継承するものです。
第2に多民族に関しても、清朝がとった政策を受け継ぎました。清朝は』王朝の出身民族である女真族(満州族)に特権をみとめるだけでなく、『チベットやウイグルを』それぞれ『「藩部」』として『優遇する政策をとっていた。共産党政権は、「藩部」をそのまま自治区とし、それらを優遇し援助した。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.195-197.
人民公社の食堂。1958-59年頃。©新唐人電視台
食事の配給を受けるため列を作る公社員の子供たち。時期不明。© 嵊州新闻网
1958-59年、農村の人民公社組織率は9割を超え、中国政府は「大躍進」を
自称したが、公社内では土地家屋のみならず、家畜犬鶏から食糧,一部の公社
では衣服・一切の私物にまで私有禁止が及んだ。食事の配給がとだえると、
自分の子供を食う事件が各地で続発、3600万人が餓タヒ・病タヒしたと言われる
「第1」の人民公社について、柄谷氏の説明には重大な疑問があります。たしかに、中国共産党政権の土地改革では、まず「合作社」として地主の粛清・農民間の協助促進から始めて、その基礎の上に国営企業的な「人民公社」を組織するという方式が取られました。これはおそらく、ソ連圏には無かったことです。しかし、中国における・その過程は、さまざまな問題を孕んでいます。ここでそれを論ずる余裕はありませんが、共産党の公式資料よりも、岩波新書『私は中国の地主だった』,石堂清倫『わが異端の昭和史 上』第5章. などの体験記から実態を学ぶことをお薦めします。成立の過程で噴出した問題は、完成後の組織を根底から規定します。
また、前近代の中国で「均分」土地改革が実際に行なわれたのは、唐王朝までです。唐の後期に「両税法」が施行されて〔780年〕以後、儒教官僚の間からはしばしば土地改革(土地所有の上限を定める「限田法」など)が提議されたものの、実施されたことはありません。
毛沢東革命は中国の伝統的な「革命」観念に合致している、という柄谷氏の主張には根本的な疑義があります。すくなくとも、柄谷氏は何ら説得的な根拠を示していない。
「第2」の少数民族政策に関しても、柄谷氏のような大雑把すぎる制度的把握で、どれだけのことが言えるのか、たいへんに疑問です。
中国では『どの王朝もそうでしたが、共産党による統治を正当化するのは、2つの条件です。経済的発展と社会主義。しかし、これらは根本的に背反するものです。経済的に発展しないならば他国に従属することになり、王朝としての正統性を失う。一方、経済的に発展すれば、階級的・地域的不平等が生じ〔…〕多民族の不平等に帰結し、〔…〕帝国の解体をもたらす。』
中華人民共和国『最初の 10年間に著しい経済成長があったのですが、それはまた階級の格差、都市と農村の格差、諸民族の格差をもたらしたわけです。それに対して、毛沢東は「継続革命」を唱え、急進的な平等化をはかった。それが「文化大革命」です。この継続革命は〔…〕中国における「易姓革命」の伝統に根ざしています。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.198.
↑上の写真からもわかるように、中国政府が「大躍進」として宣伝した時期は、1千万人単位の途方もない数の餓タヒ者を出した地獄のような時期でした。相対的に農民の生活が安定したのは、毛沢東以下「革命派」の力が後退し、劉少奇ら・いわゆる「実権派」が資本主義政策を進めた時期でした。それに対する毛沢東派の巻き返しが、「文化大革命」にほかなりません。「文化大革命」によって「平等化」が進んだなどという理解は、「タヒなばもろとも平等に」ということでないかぎり全くの大ウソと言わなければならない。
それでは、“社会主義” の名のもとに「平等化」は進展しなかったのか? 分野ごとに見れば、たとえば女性の社会的地位は、「文革」時期に限らず、飛躍的に向上してきました。共産党の中堅幹部にも人民解放軍にも、多数の女性が進出しています。女性の地位は、日本,韓国,台湾よりはるかに改善されています。教育の機会均等についても、1945年以前と比べれば大きく進んだと言えるでしょう。それでは、最も重要な「経済的平等」はどうか? すくなくとも、人口の大多数が飢餓線上をさまよった時代の状態を、私は「平等」だとは考えません。「平等化」の目的は “貧しい人を減らす/救う” ことにあるとすれば、ある社会の「平等」度は、“最も貧しい人の生活程度と数” をもって指標とすべきだからです。この点で、私は柄谷氏とは根本的に見解を異にします。
少数民族との関係を言えば、「文化大革命」で噴出した若者のエネルギーの向け先に困った毛一派は、「紅衛兵」たちに辺境地域への「下放」を命じました。これによって、少数民族地区にも多くの学生や都会の青年が移住し、進んだ技術や医療を普及させる功績があったことは事実です。しかし、共産党政府として、辺境地区の開発や生活向上のヴィジョンをもって「下放」を行なったとは思われない。「下放」した青年で、生きて帰って来た者は少ないと言われています。
食卓を囲むフルシチョフ,毛沢東,ホー・チミン,宋慶齢〔孫文の妻,中共副主席〕
1959年。©Wikimedia. ↑上の人民公社の食卓と比べよ。
【32】 現代中国と《帝国》――
鄧小平,天安門弾圧と “帝国” の行くえ
『鄧小平の政権は、資本主義的な経済発展を急激に進め、〔…〕成功しました。が、それとともに階級の格差、都市と地方の格差、諸民族の格差が生じた。そこから多くの問題、特に、少数民族の独立の要求が生じるのは当然のことです。〔…〕「帝国」を維持するためには、経済発展と同時に社会主義的平等性が不可欠なのです。
中国に必要なのは、近代資本主義国家に固有の自由民主主義を実現することでなく、むしろ「帝国」を再構築することです。もし中国に自由民主主義的な体制ができるなら、少数民族が独立するだけでなく、漢族も地域的な諸勢力に分解してしまうでしょう。〔…〕そのような〔…〕政権は民意に支持されない。つまり天命=民意にもとづく正統性を持ちえない。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.199.
「少数民族が独立」し「漢族も地域的な諸」国家に分かれる状態が、なぜいけないでしょうか? 柄谷氏は、それは「《帝国》の原理」に反する,「民意に支持されない」と言うのですが、はたしてそうでしょうか? ‥なるほど、世界史の教科書に出ている地図を見ると、過去の中国は、ほとんど常に統一された広域国家であったかのように見えます。しかしそれは、近現代の西洋的な「ネーション国家」「主権国家」の観念を過去に投映したイメージにすぎません。過去の「帝国」は、近代国家のような緊密に統合された組織体ではありません。近代国家と比べれば、さまざまな地域や集団が、ゆるく鷹揚につながっただけのバラバラな存在だと言ってよいのです。ひとつの近代国家よりは国家連合のほうが、過去の「帝国」に近く、「《帝国》の原理」を体現しやすいと言えます。また、そのような連合的ないし「連邦制」的な体制でなければ、「同化」圧力のない「諸民族間の寛容」を実現することはできないと思います。
『現在はどこでも、もはや小規模の国民国家ではやっていけない状態になっています。世界各地で、かつて世界帝国であったところに広域共同体ができつつあります。それはまずヨーロッパ共同体から始まった。〔…〕ヨーロッパ共同体は、』「帝国主義」の力を発揮するよりも『意識的に「帝国」の原理を回復しようとしています。
ヨーロッパ共同体に対応して、他の地域でもブロックが形成されるようになりました。たとえば、イスラム圏の諸国家が、イスラム主義というかたちをとってですが、一つのブロックをつくっている。このようなブロックは、過去の世界帝国の下で形成された文化的同一性にもとづいています。だから各地で、過去の世界帝国が復活しているように見えるのです。〔…〕そのなかで、中国だけは特に何もする必要がない。清朝という帝国が分節されずに残ってきたからです。〔…〕中国に必要なのは、そのことを自覚することです。つまり、国民国家の観念を超えて、積極的な意味で「帝国」を創出する方向をめざすことです。
〔…〕帝国の原理をもたないような広域国家は、必ず「帝国主義」となります。いまや各地の広域国家は、世界資本主義の下で帝国主義的な抗争に入っています。そして、世界資本主義の危機・没落が進行するとき、それは世界戦争に発展する可能性がある。では、それを阻止するのは、いかなる原理なのか。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.200-201.
天安門前広場で手に手に毛沢東語録をかざす紅衛兵たち。
1966年頃。©香港01/hk01.com.
柄谷氏は、「ブロック化」は悪いことではないと言っているのです。「地域ブロック」の形成は、それが「帝国主義」諸国によるヘゲモニー争奪を目標としたときには、20世紀の 2度の世界大戦の原因となりました。だから、アメリカをはじめとする「新自由主義」のイデオローグたちは、「ブロック化」を悪の代名詞と見なして警戒します。しかし、「ブロック化」は、アメリカをヘゲモニー国家とする「自由主義段階」〔1930-1990〕から、多極化した「帝国主義段階」〔1990-2050〕への流れのなかでは避けられないことです。のみならず、「ブロック化」が「帝国主義」ではなく他の理念を目標としてなされる場合には、「近代世界システム」と「帝国主義」を乗り超える可能性すらあると言えます。
もちろん、現状では、中国を含めて、世界のどの国家も国家連合も、「資本=ネーション=国家」の枠の中で動いており、したがって、その拡張は「帝国主義」に帰結します。それでも、柄谷氏の視点は注目に値します。「近代世界システム」を超えようとする動きは、各処ではじまっており、過去の「《帝国》の原理」に学ぶことも、そのひとつとなりうるからです。たとえば、EU(ヨーロッパ共同体)諸国が、一方ではアジア途上国への帝国主義的経済支配や兵器輸出を続けながら、他方で、移民受け入れなどによって意識的に矛盾の緩和をはかっていることは、肯定的に評価できるでしょう。
「世界戦争を阻止する原理」とは、カントの「永遠平和」――「世界共和国」の原理であり、それは「《帝国》の原理」に淵源している、と柄谷氏は言うのです。たしかに、中国でも過去に康有為らが唱えた「大同世界」の理念などは、「《帝国》の原理」の一面を発展させたものであり、カントの「永遠平和」とともに人類の未来を指し示すものと言えるでしょう。
しかし、現実の中国の国家体制が、それらを添加しただけで理想的なものになるとは思えません。理想と・「3回目の帝国主義」の現実との間には、何重もの断層があります。
「経済発展と社会主義の矛盾」という・柄谷氏の中国を見る視角は、ありふれた皮相的な見方ではないかと思います。仮にそれを認めたとしても、それをそのまま民族問題に延長するのは間違えです。
むしろ、民族問題は、「経済発展+社会主義」つまり中国共産党国家の「資本=国家=ネーション」が、他民族(チベット、ウイグル、モンゴル)の伝統的な宗教・社会と矛盾するところから起きているように私には思われます。それというのも、中共国家は、「社会主義」イデオロギーで固めながらも、やはり国家的資本主義だと考えるからです。国家的資本主義が拡大すれば「帝国主義」となるのであって、それを《帝国》と見間違えてはならないと思います。
中華人民「ネーション」の拡大は、それに対する抵抗として、諸民族の民族自決・小国民国家の分離独立を呼び起こす、と柄谷氏は言います。それは、そのとおりです。
しかし、この「近代世界システム」固有の矛盾・アポリアを解決する《帝国》を、現在の中国の集団主義的・集権的な社会主義に見出そうとするのは無理だと思います。《帝国》が帝国の原理の「高次の再現」となるためには、集団主義(ないし、個人主義と集団主義の矛盾)は乗り超えなければならない。
では、そのために、今後どんな階梯が予測されるのか? ‥「第2の天安門事件」も、私はありうると思っています。
天安門事件後、戦車に占領された天安門前広場。1989年6月。©JBpress.
上で述べたように、「一つの国家」が中国の伝統だという思い込みは間違えです。 また、中国のような「広域国家」がそのまま、カントの理想的「世界共和国」につながるわけでもありません。この点は、カントのほうをもっと掘り下げてみる必要があるでしょう。
あるいは、より検討に値するのは、カントよりもライプニッツかもしれない。柄谷氏やカントのように、究極の「世界共和国」を実体視してしまうと、「国家の揚棄を唱えて国家の強大化に帰結する」という「近代」のアポリアから脱出できません。しかし、いわば「近代以前」のライプニッツには、「国家」ではない “普遍 etate uniwersala” のヒントが隠されているかもしれない。最近、自分の書いた (10) を読み直してみて、そう思いました。
ともあれ、「柄谷世界史構想」のうち・《帝国》の部分を取りあげたこのレヴューは、このへんで締めくくりたいと思います。
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!