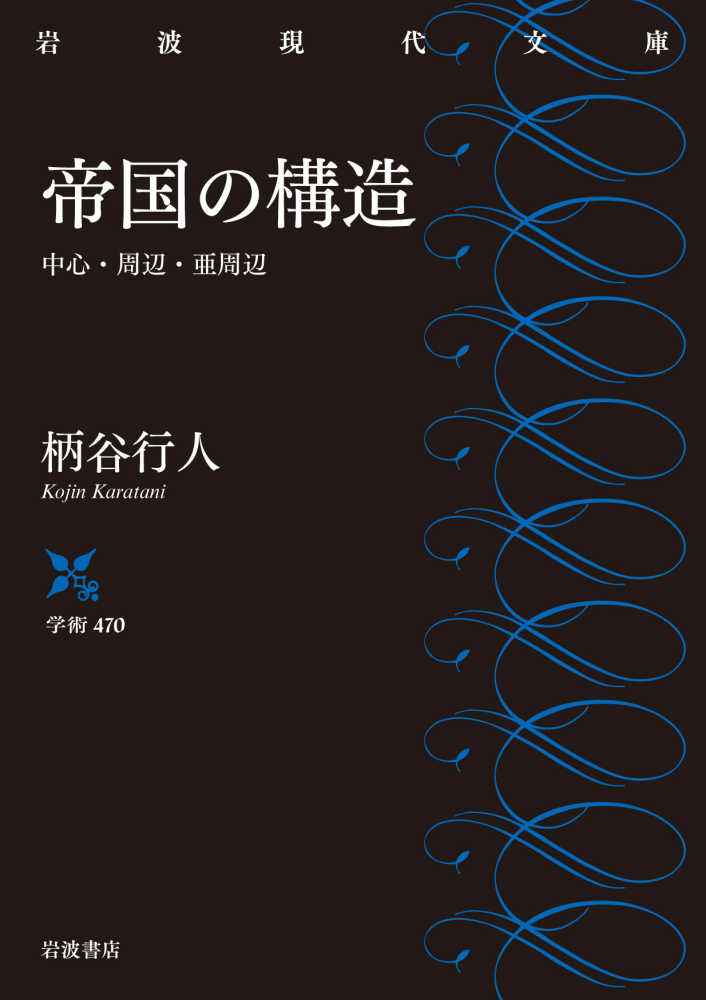テオドール・デ・ブライ「インディアンを拷問するスペイン人」
バルトロメ・デ・ラスカサス(1484-1566)『インディアスの破壊について
の簡潔な報告』に掲載された凹版画。©MeisterDrucke-912186.
【22】 「地理上の発見」の実像――
「西洋」は、いつ「東洋」を追い越したか?
『19世紀以後、このような世界帝国は西洋列強の隆盛のもとで没落しました。西洋中心主義的な史観が支配的となったのは、その結果です。
たとえばマルクス〔…〕《商品流通が資本の出発点である。〔…〕世界商業と世界市場が、16世紀に資本の近代的生活史をひらく。》〔『資本論』第1巻4章1節〕このような見方は〔…〕あまりにも西ヨーロッパを中心にした見方です。「世界商業と世界市場」は、それ以前からありました。ただ、ヨーロッパはその外にいたのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.163.
アンリ・ピレンヌによると、西ローマ帝国滅亡後のヨーロッパ経済は、「イスラム国家の出現によって、交易の場であった地中海から」閉め出され、「内陸部に、そして自給自足的経済に向かった。」11世紀末からの「十字軍」遠征は、ヨーロッパが旧来の交易世界を取り戻すきっかけになったと言える。近世以後「西ヨーロッパが経済的に興隆したのは、たんにその内部での生産力の発展によってではなく、その外の世界商業と世界市場に参入」していくことによって、であった。
イタリア諸都市のルネサンスは、「アジアの帝国との交易によって」はじめて可能になった。ところが、オスマン帝国ができて 1453年に「ビザンツ帝国を滅ぼしたため」ヨーロッパ諸国は「陸路ではアジアの通商圏に向かうことができなくなったのです。」そこで、喜望峰回りでインドに達する航路を開拓した。
「なぜそうしたのか。どうしてもアジアとの交易に参入したかったからです。」思い出してほしいのですが、コロンブスはジェノヴァ出身のイタリア人で、スペイン王家の金力を借りて、地球を半周してインドへ行く航路を見つけるために西へ向かったのです。結果的に、アメリカ大陸へ達したのですが、それは思わぬ僥倖だったといえます。というのは、彼につづいてスペイン人は南アメリカで銀山を獲得したからです。
『インディアスの破壊についての簡潔な報告』挿絵 凹版画。
もともとヨーロッパは、イタリアのルネサンス都市にしても、アジアの豊富な物産と交換できるような産物を持ってはいませんでした。オスマン帝国があいだに立ちふさがったくらいで交易に支障が出たのは、アジアにとって当時のヨーロッパは、たいして魅力ある貿易相手ではなかったからです。しかし、アメリカで銀山を手に入れてからは事情が変わります。アンチル諸島や南アメリカの「先住民を征服して過酷な労働を強制して」タダ同然で手に入れた銀を、アジアに持ちこんで交易を行なうようになったからです。これによって、ヨーロッパは初めて、「アジアとの交易に」直接参入できるようになったのです。(『帝国の構造』,pp.163-164.)
南米チリ大学の教授であったアンドレ・グンダー・フランクは言う:《ヨーロッパ人はアジア域内交易に参入することで、ヨーロッパよりもはるかに生産的で豊かなアジア経済から利益を得ることができた〔…〕、それは究極的にただアメリカの銀のおかげによってのみ可能であった。》〔『リオリエント――アジア時代のグローバル・エコノミー』〕
『したがって、「大航海時代」によって世界市場が開始したかのように言うのは、〔…〕正確ではありません。「大航海時代」は本来、ヨーロッパ人がモンゴル帝国のつくった世界通商圏に参入しようとする動機から始まったのですから。実際、西ヨーロッパに経済発展が生じたのは、そこに参入するようになってからです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.164-165.
アダム・スミスが『諸国民の富』を書いた 1776年の時点、つまりイギリス産業革命の真っただ中でも、「中国はヨーロッパのどこと比べてもずっと富裕な国である」。また、「中国の東部諸省および東インドのベンガル諸州で、農業および製造業の改良が昔からなされている」とスミスは述べています。ルネサンス以来のヨーロッパには科学技術の発展があり、アジアにはそれが無い、というような見方は、19世紀以後になって言われるようになった偏見にすぎないことが判ります。
東洋に対するヨーロッパ人の見方が一変したのは、「19世紀になって〔…〕西洋諸国が東洋の帝国を圧倒するようになっ」てからです。(『帝国の構造』,p.165.)
『インディアスの破壊についての簡潔な報告』挿絵 凹版画。
フランクは次のように指摘します:
《1800年以降のヨーロッパの「テイク・オフ」は、ヨーロッパに例外的に存したいかなる科学的,技術的,制度的「準備」に基礎をおくものでもなかった、〔…〕ヨーロッパにおける発展が、ルネサンスにおいて得られたと称されている「有利な滑り出し ヘッド・スタート」に基礎をおいていたなどというのはさらにまちがえであるし、ギリシャやユダヤ主義からすぐれた「合理性」や「科学」を継承していたという思い込みのまやかしに至っては、言うまでもない。これらの〔…〕「知見」はすべて、神話にもとづいたヨーロッパ中心主義的イデオロギーにすぎず、実際の歴史にも社会科学にも基礎をおいていないのである。》〔『リオリエント』,p.383〕
【23】 1800年頃〈東/西〉逆転…の意味――
「世界システム」が「世界帝国」を凌駕した
アンドレ・グンダー・フランクの上記の本は、ウォーラーステインの「近代世界システム」論に対する批判として著名になりました。2人の理論的なカナメの争点はどこにあるのかというと、‥柄谷氏によれば、それは、1800年頃の「西洋」⇔「東洋」の優位逆転を、必然的なものと考える(ウォーラーステイン)か、それとも、可逆的・一時的な順位の交代と考える(フランク)か、にあります。柄谷氏自身は、この争点についてはウォーラーステインのほうを支持しています。
ここで柄谷氏は、ウォーラーステインを補強する根拠として、ブローデルを援用します。ウォーラーステインの「近代世界システム」は、あくまでも近世・近代を射程とした議論なので、それ以前――15世紀以前――については、ブローデルの言う「世界=経済」に接続させて理解するわけです。
ブローデルをモディファイした柄谷説によれば、「西ヨーロッパでは[世界=帝国]〔柄谷氏の言う世界《帝国》に同じ〕が成立しなかった。」《帝国》という上からの統制原理・が無い処で「王,領主,教会が競合し、その間隙をぬって自立的な都市が栄えた。そのことが、ヨーロッパの社会構成体における交換様式Cの優位、すなわち世界=帝国とは異なる世界=経済をもたらした。」
つまり、「世界=経済」とは、世界《帝国》には包摂されない「亜周辺」であった中世ヨーロッパにおいて胚胎したシステムであり、それが 1500年以後に「世界システム」として成長し、1800年頃には、ついにアジアの諸・世界《帝国》を凌駕するに至った。それが、「近代世界システム」にほかならないわけです。
プラハの旧市街(旧市庁舎からの眺め)。2世紀のプトレマイオス世界地図には
ゲルマン人の街として描かれている。その後、スラヴ系チェコ人,ユダヤ人が
来住し、中世西欧とアジアを結ぶ陸上交易路の要衝として栄えた。©Wikimedia.
「世界=経済」すなわち「近代世界システム」が「世界=帝国を凌駕したことには根拠があります。」それは、「世界=経済」特有の交換様式C優位の論理(→自由貿易の強要,ヘゲモニー支配,‥)であって、《帝国》の原理とは相容れないものです。そして、「18世紀にいたるまで局所的なものでしかなかった」それが、1800年頃までには全世界を覆うようになり、世界《帝国》を凌駕するに至った。
ですから、現在のように、ヨーロッパ中心の「世界=経済」が凋落し、ふたたび「東洋」の優位が戻ってくるように見えても、それは「世界=経済」(近代世界システム)の中でのヘゲモニー国家の移動にすぎない。「東洋」の優位回復によって、当然に「世界=経済」そのものが消滅し、「世界=帝国」に戻る、ということにはならないのです。「東洋が再び優位に立つとしても、それは世界=帝国の回帰ではない。」「世界=経済」の中で、こんどは「東洋」が中心になるということだ。したがって、その “中心移動” はむしろ「世界=経済(近代世界システム)の圧倒的優位を意味する」(pp.167-168.)。しかしながら、‥‥
『フランクの主張のなかで正しい点は、世界=帝国と世界=経済が、「単一の世界」に属していることです。それらは』古代の「世界=経済」であったギリシャ・ポリスの当時からずっと、『同時的かつ相関的に存在してきた。つまり〔…〕世界=経済は、世界=帝国という「中心」に対して「亜周辺」にあったのです。』「世界=経済」を『ウォーラーステインのように、歴史的発展段階として見てはならない』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.168-169.
ここで、「世界=帝国」システムと、「近代世界システム」につながる「世界=経済」システムとの性格の違いを、かんたんにまとめておきましょう。
「[世界=帝国]システムは、交換様式Bに基く世界システムです。服従=保護という交換によって、諸部族,諸国家を統合する」。そして帝国は、「交易の安全を保証し、交易に課税」したり、みずからの官僚的特権商人に交易を行なわせたりして、大きな利益を得ました。「つまり、帝国は交換様式Cを拡大する」。帝国が版図を広げる動機は、領土欲よりも遠隔地交易による莫大な利益にあるのです。
「したがって、東洋の帝国は貢納制〔…〕だけでは理解できません。そこには〔…〕交換様式Cを発展させる契機があった。」
「しかし、帝国には限界があります。それは、帝国では交易が国家によって管理されるということ、いいかえれば交換様式CがBの管理下にあるということです。」
それが、「帝国の亜周辺で発展した世界=経済との違いです。」この違いは、「なによりも都市に現れます。帝国においては、〔…〕都市は政治的な中心」であり、政治の中心であることによって「経済的な中心になるわけです。」バグダードは、カリフの居城があるアッバース朝帝国の首都であり、当時の世界でもっとも繁栄した経済都市でもありました。しかし、モンゴルの来襲によってアッバース朝が滅びると、経済都市バグダードも亡びたのです。帝国の都市は、政治の中心でなくなると、経済の中心でもなくなるのです。(pp.169-170.)

リューベックの市庁舎。リューベックは、中世の海港都市として繁栄し、
1226年には神聖ローマ皇帝の特許状を得て帝国自由都市となり、
北海・バルト海の交易を独占した。©Wikimedia.
これに対して、「世界=経済」においては、国家による交易統制が行なわれません。そもそも、〔近世に絶対王政国家が誕生するまでは、〕広域の商業を統制できるような集権的な国家が存在しなかったからです。
『西ヨーロッパでは集権的な国家が成立せず、王や封建諸侯が乱立抗争する状態が続いたわけですが、その間に成立した都市では、国家の統制なしに交易がなされた。
つまり、ここでは』帝国とは『逆に、交易の中心である都市こそが政治的にも中心となります。しかも世界=経済では、中心はたえず移動します。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.171.
ブローデルによると、「世界=経済」には必ず、交易の「極」となる都市、すなわち「商業活動の兵站中心地に位置する都市」が存在します。「情報・商品・資本・信用・人間・注文・商業通信文がそこに流入してはまた」出てゆく〔ブローデル『物質文明・経済・資本主義――15-18世紀』〕。そうした「極」を、「多数の中継都市が遠巻きに」取り囲んでいます。それらの都市の間には競争があり、たえず自分が「極」になろうと競い合うので、中心は「たえず移動します。」こうして、「世界=都市は、アントワープ→アムステルダム→ロンドン→ニューヨーク」と移動してきました。
『どの都市が繫栄するかは政治的な力とは関係ありません。逆に、それが政治的次元を左右するようになります。帝国ないし東洋的専制国家とは異な』国家が都市および交易を管理するのではなく、むしろ「世界=経済」の国家は『逆に、都市の自立を進めます。』ヨーロッパの絶対王権は『自由な交易を妨害する封建領主を制圧し、さまざまな封建的特権を廃止する〔…〕。
ゆえに、絶対王権は、王と都市(ブルジョワジー)の結託の産物です。それは交換様式CがBを凌駕するということです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.171-172.
したがって、「世界=経済」において「都市の自立を進め」「交換様式CがBを凌駕する」のを助ける国家は、必ずしも絶対王権である必要はない。絶対王権は、中世末という時代において、この役割を担ったにすぎません。より後代においては、共和政国家や、現代の「開発独裁」ないし「発展途上型独裁」国家が、そうした役割を果たすこともあります。これらいずれの場合にも言えることは、「国民国家が中央集権的な体制を通して生まれるということ、そして、その根底に世界=経済の優位があるということです。」(p.172.)
15世紀末のジェノヴァ。『ニュルンベルク年代記』1493年 から。©Wikimedia.
「世界=経済」が「世界=帝国」とは異なる・もう一つの重要点は、「世界=経済」には「圏外」というものが無い、ということです。「世界=帝国」には、「中心,周辺,亜周辺」という同心円状の構造がありました。「亜周辺」は、「帝国」の中心部から一方的な統制を受けることはなく、相対的に独立した地位で、選択的に影響を受け入れることができるのでした。そして、その外側には、ほとんど交渉のない「圏外」の世界が広がっています。
ところが、「世界=経済」では「圏外は成立しない。世界の全地域が交換様式Cの浸透を免れないのです。世界=帝国の周辺も同様です。」世界=経済が浸透してゆくと、まず、「世界=帝国」の「周辺」部が「世界=経済の周辺に組み込まれます。」やがて、「世界=帝国」の中心部までもが組み込まれてしまうことになります。(『資本論』の言う「本源的蓄積」とは、この「組み込み」が、“正常な” 近代化過程として行なわれた場合にほかなりません。↓下で述べるインドの場合は、むしろ「組み込み」が近代化を困難にしてしまう “異常な” ケースです。)
また、「世界=経済」では、「亜周辺」も成立しえません。どんな地域も例外なく、交換様式Cの圧倒的な浸透の波に呑みこまれていきます。
そして、「世界=経済」では「中心」のたえまない移動によって、ヘゲモニー国家が交替します。「ヨーロッパの中でも、ジェノヴァからスペイン、オランダ、さらにイギリスへ」。ルネサンス・イタリア,ジェノヴァのコロンブスが、スペインに移って、カスティリア女王の協賛と財政援助を受けてインド航路開拓の航海に出たのは、最初のヘゲモニー国家交替を象徴するできごとでした。
しかし、18世紀までのこの交替劇は、ヨーロッパ内部でのローカルな中心移動だったと言えます。1800年前後から事情が変わります。「産業革命」が、ヘゲモニー国家イギリスの行動に変化をもたらしたからです。その結果、〈東西の逆転〉、「世界=帝国」と「世界=経済」の地位の逆転が起こりました。これを端的に示すのは、「イギリスがインドを圧倒」したことです。(pp.172-173.)
『イギリスはそれまでインドから綿製品を輸入していましたが、産業革命のあと、インドから原料を輸入しそれを加工してインドに輸出するようになった。これによって、インドはその伝統的な産業と社会構造が根本的に解体されるようになったのです。他方、このことがイギリスを世界=経済におけるヘゲモニー国家にしたのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.173.
機械生産による安価な綿織物がイギリスから入って来ると、インドの綿織物工業は壊滅的打撃を受けました。かつて「世界に冠たる織物の町」と言われアダム・スミスも称賛したベンガル都市ダッカの人口は、15万人から 3万人に急減。インド総督ベンティングは 1834年にイギリス本国に送った年次報告書に、「世界経済史上、この惨状に比すべきものは見いだせない。職工たちの骨がインドの平原を白色と化した。」と書いています。
イギリスにおけるキャラコの機械生産:プリンティング。1835年頃の版画。
©Wikimedia. キャラコはインドの伝統的綿織物で、積出港カリカットの名から
キャラコ(Calico)と呼ばれたが、英産業革命後インドは逆に輸入国となった。
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!