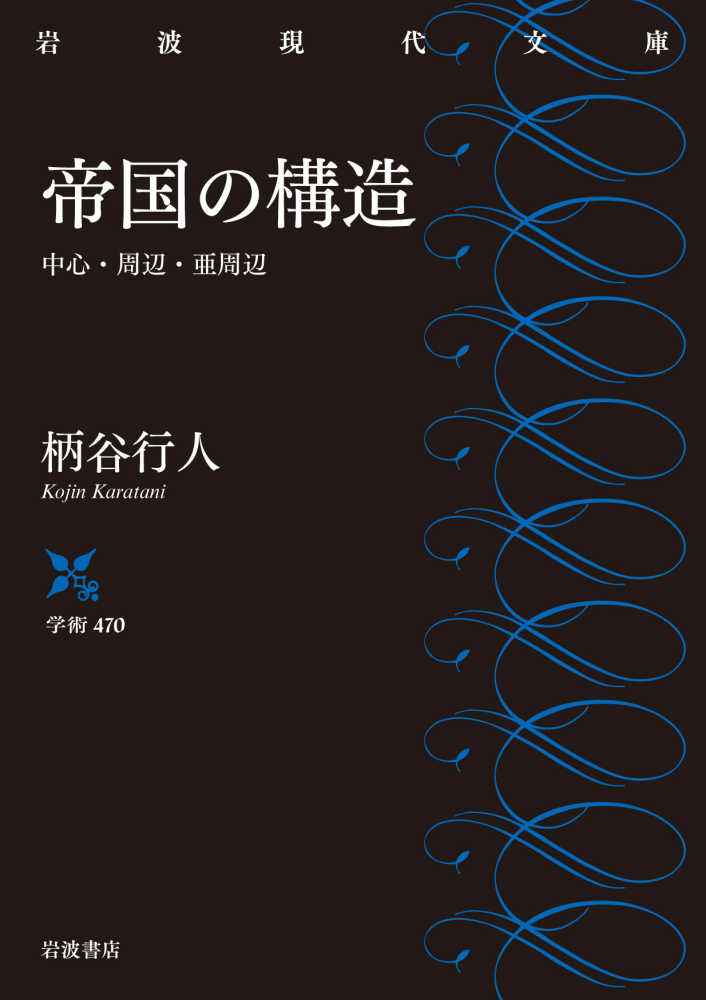モンゴル軍のバグダード攻囲戦。1258年、モンゴル帝国第4代ハーン・
モンケの命を受けた弟フレグのモンゴル軍は、バグダードを包囲して
降伏させ、アッバース朝カリフを捕えて処刑。アッバース朝イスラム帝国
は滅亡した。『集史』パリ本の挿絵。©Wikimedia.
【16】 モンゴル帝国と「唐」
『チンギスは、世界征服によって平和を実現することを、天から与えられた使命だと言ったそうです。もちろん、これは伝承ですが、人びとがそれを信じた、そしてそれが人びとを動かした〔…〕ことは事実です。このような考えは、それまで遊牧民から出て来なかったものです。では、どこから来たか。チンギスが言う使命は、中国にあった・君主を超える「天命」の観念から来たといえます。それは、たんなる征服や支配ではなく、広範な通商を可能にするシステムを創り出す使命です。この考えは草原から来たのではなく、いわば唐帝国から来たのです。〔…〕
しばしば言われるのは、チンギス・ハーンが極めて残虐だったということです。しかし実際は、彼は残虐さを誇張して宣伝したようです。その風評を聞いて怖れた人々は無駄な抵抗をしなかった。だから、ほとんど戦闘もしていない。さらに、彼の征服は掠奪ではなく、平和と通商の確立に帰結することが歓迎されました。〔…〕
元の皇帝フビライは、世界帝国全体のハーンとなった。モンゴル世界帝国の一員でありながら、同時に中国の皇帝として「天命」に従う義務をもっていました。このような例が中国の歴史になかったわけではありません。〔…〕一時期の唐王朝がそのようなものであった〔唐の太宗は,遊牧民諸部族から「天可汗」の称号を受けた――ギトン註〕』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.144-146.
柄谷氏によれば、モンゴルはチンギス・ハーンの時代からすでに、中国王朝国家から――キタイ帝国を通じて――「天命」の理念のみならずさまざまな技術的成果を受け継ぎ、それらが、モンゴルの広大な征服と世界帝国の建設に大きく寄与した、というのです。
『誰もが注目するのは軍事力、とくに騎馬による機動力です。それは駅馬による通信網を含みます。
しかし、それなら他の遊牧民国家にもあったはずです。』モンゴルがそれらを圧倒して征服を成し遂げた『力はどこにあったか。それは、唐から得た数々の武器です。その一つは、高性能の攻城用兵器です。もともと中国の国家は、騎馬の遊牧民に〔…〕歩兵』で『対抗したのですが、その武器』が『弩 ど〔いしゆみ〕』でした。『弩は、ふつうの弓より長射程・高威力です。モンゴルは、それを用いて騎射する戦術をとった。さらに、西方では攻城包囲戦専門の漢人部隊が編成された。
その意味で、モンゴルは、遊牧民国家の軍事力と〔ギトン註――中国〕専制国家の軍事力を綜合したわけです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.145-146.
中国王朝は「弩」を、とくに遊牧民との戦闘で多用しましたが、利点は射力が強いこと、欠点は連射ができないことでした。そこで、連射ができるように機械装置を装備した各種の「連弩」が発明されています。下図↓は、三国時代から使われたもので、諸葛孔明が発明したとされ、「諸葛弩」と呼ばれました。ほかに、足踏みペダルで操作する大がかりな「連弩」も使われました。
壬辰倭乱(秀吉の朝鮮出兵)での明軍。連弩を使用している。
©Wikimedia.
つぎに、モンゴル帝国が成立した効果・影響に関しても、唐はじめ中国王朝とのかかわりを抜きにしては語れません。
『古代中国の4大発明〔…〕羅針盤・火薬・紙・印刷〔…〕が発展したのは唐の時代およびその後です。これらがヨーロッパに伝わったことが、さまざまな変化をもたらしたのです。〔…〕モンゴルは、中国の帝国にあったものをその外に持ち出すことによって、近世の世界にいたる大変化をもたらしたのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.146.
「紙」は、唐とアッバース朝イスラム帝国が接触した「タラス河畔の戦い」〔751年〕で、唐の製紙職人がイスラム側の捕虜となったことから西方に伝えられました。これは偶然の機会で伝わったわけですが、モンゴル帝国では、「羅針盤」と「火薬」が、意図的に西方に伝えられています。また、そのころアラビアでは、印刷された紙幣が使われるようになっていますから、「印刷術」の伝播と製紙法の本格的導入もモンゴル帝国時代だったことになります。
「羅針盤」の使用と西方伝播が起きたのは、モンゴルが陸上のみならず海上帝国でもあったためです。「中国の海上交易は唐代にありました。しかしそれはアラビア人によって開かれたものです。」宋代には、中国人や高麗人の民間業者も海上交易に参入するようになりました。そして、元代になると、国家が積極的に海上交易を推進したのです。元の商人は、羅針盤を使用して「海上に進出し、東南アジアからインド洋に至る海上通商圏を形成しました。」(pp.146-147.)
『中国の王朝で陸と海のパワーを統合したのは、元が初めてかつ最後であったと言えます。こうしてモンゴル世界帝国〔…〕の下で東南アジアからインド,アラビア,ヨーロッパに至る交易と生産の発展が可能となった。ヨーロッパでも、ヴェネツィアなどのイタリアの都市国家が隆盛し「ルネサンス」を享受できたのは、それらの都市がモンゴル帝国が作った「世界通商圏」の周辺にあったからこそです。西ヨーロッパで「近代世界システム」が生まれてくるのは、それ以後の話です。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.147.
モンゴル軍に攻囲されたアラムート城砦の開城。1256年、モンケハーンの命を
受けたモンゴル軍は、暗殺教団として著名なイスマイル派の支配するイラン
高原を攻略、漢人攻城部隊の弩(いしゆみ)の威力で多数の山城を陥落
させ、イラン高原を平定した。『集史』パリ本の挿絵。©Wikimedia.
【17】 モンゴル《世界帝国》とイスラム
チンギス・ハーンとその息子たちによってつくられたモンゴル帝国は、「大元国」「チャガタイ・ハーン国」「キプチャク・ハーン国※」「イル・ハーン国」の4ウルス(国家)からなっています。各ウルスを、チンギスの息子たちを始祖とする4つの分家:フビライ家,チャガタイ家,ジョチ家,フレグ家が統治しています。
註※「キプチャク」: 日本の世界史教科書が使用している「キプチャク汗国」なる名称は誤りで、正しくは「ジョチ・ウルス」。柄谷氏は「キプチャク・ハーン」などと称しているが、もちろん、こんな称号のハーンは存在しない。wiki「ジョチ・ウルス」参照。
チンギスの血統によって4ウルス(汗国)が統合されていることは、「一見すると家父長制的」で、遊牧民の原始的性格を残しているかのようです。しかし、別の見方をすればこれは、「チンギスの血統カリスマがもたらした統合性」であり、チンギスの《世界帝国》の「使命」を受け継ぐ血統と考えられたがゆえに、彼らは多くの部族・地域集団の臣従を得ることができたのです。
4ウルスの上に立つモンゴル帝国全体の「ハーン」は、会議(クリルタイ)での相互承認によって選ばれました。その限りで、旧来の部族連合体の原理が生きています。しかし、チンギスの血統に伝わるとされる《世界帝国》の「使命」理念が、広大な地域の人々を統合する原理は、部族社会にも遊牧民国家にも無かったものです。(pp.148-149.)
『モンゴルはもともと小さな部族でしたが、征服された遊牧民部族が “チンギス”〔ギトン註――というカリスマと帝国理念〕に従うことで、モンゴル人となったのです。こうして各地で “モンゴル人” が続々と生まれた。〔…〕
4大ウルスは、のちにそれぞれ、清,ムガール,イラン,ロシアの帝国になっていきました。〔…〕トルコ系が作ったオスマン帝国も、広い意味でモンゴル帝国のなかに入れることができます。それらに共通するのは帝国の原理を持っていたことです。たとえば、宗教的・民族的寛容があった。〔…〕
元の宮廷には、商業に従事するイスラム系のイラン人、〔…〕マルコ・ポーロのような外国人がおおぜいいました。ハーンであるフビライにとっては、中国だけでなく、西アジア・中央アジアのことが同様に大切だった。そして元だけでなく、モンゴル帝国ではどこでも、民族的・宗教的な差別が無かった』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.148-150.
法恩寺・五百羅漢、マルコ・ポーロ(左)とフビライ。盛岡市,北山「法恩寺」。
明治時代以来の中国史研究では、元王朝では漢人が差別されていたかのように説明しますが、これは多分に偏見に基いています。たとえば、「モンゴル人,色目人,漢人,南人」という身分差別があったと書いている世界史の教科書がありますが、これは身分ではありません。この種別は、元代末期に「科挙」が復活した時に設けられた受験枠なのです(pp.149-150)。平等に受験させると、漢人が有利になるのは明らかですから、種族ごとに枠を設けたのです。こういうことは、現代のアメリカの大学でもやっています。「差別」とは言えないでしょう。
さて、西アジアでも中国と同様に、モンゴルに征服される以前から帝国がありました。アッバース朝イスラム帝国です。イスラムはアラビア地方から出てきた宗教ですが、そのままで帝国の原理となりえたわけではありません。広大な帝国を形成しえたのは、「イスラム教を民族的なものと切り離すことによって」でした。
弱小部族であった『アッバース家は、非アラブのムスリムであったペルシャ人の支持を取り付ける必要があった。そこでアラブ人の特権を否定し、すべてのムスリムに平等な権利を認めた。それによって、初期のアラブ的国家から、信仰を中核とするイスラム帝国に転換したのです。
また、中央集権化をめざしたアッバース朝は、自主性の強いムスリム軍を抑えるために、マムルークと呼ばれる奴隷軍人〔主にトルコ系遊牧民出身。奴隷として購入されてイスラム世界に帰化――ギトン註〕による常備軍を作った。
この結果、アッバース朝は、東西交易,農業灌漑の発展によって繁栄し、首都バグダードは巨大な都市になりました。またここで、アラビア,ペルシャ,ギリシャ,インド,中国などの諸文明の融合がなされ、学問が著しい発展を遂げ、近代科学に多大な影響を与えた〔…〕
しかし、この帝国はその後、〔…〕1258年に侵入したモンゴルに一撃でやられてしまったのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,p.151.
イスラム帝国は、10世紀以後には各地でスルタンが自立し、アッバース朝カリフの宗教的・政治的権威のもとで、ゆるい結合を維持していました。北アフリカのファーティマ朝と、イベリア半島の後ウマイヤ朝は、それぞれカリフを自称しており、イスラム世界には3人のカリフ(教主)が並び立っていたことになります。
バグダードのアッバース朝カリフがモンゴルに屈服して事実上消滅〔1258年〕した後は、エジプトのマムルーク朝、イラン・アナトリアのモンゴルイル・ハーン国,北アフリカの諸スルタン朝が分立した。
イル・ハーン国は、第7代ガザン・ハーンが仏教からイスラム教に改宗し〔1295年〕、イスラム法(ハラージュ[地租],イクター[軍人に俸給として与える徴税権]等)に則った税制改革を行なって、それまでモンゴル式に恣意的に行なわれていた臨時課税・徴発を一掃した。(⇒:wiki「イルハン朝」)
このように、モンゴル帝国は西方では、イスラムと接触してその要素(イスラム法,すなわち「万民法」!)を取り入れることで、《帝国》の原理を強化した面があると思われます。が、柄谷氏はこの点に言及していません。もう少しイスラムを評価してよいのではないかと思います。
「モンゴル」。セルゲイ・ボドロフ監督。2007年,STV。
しかし、柄谷氏は逆に、イスラム教が、モンゴルに征服されることで世界宗教として成長したことを強調するのです:――「モンゴル以後のイスラム帝国は、アラブの部族連合体の拡張であった時期のイスラム教国家とはレベルが違います。モンゴル帝国はイスラム教に乗っ取られ」たが、そのイスラム教は、実はモンゴルの支配によってもたらされた」、つまり、その時はじめて世界宗教に変容したものなのだ。従って「イスラム教を受け入れたことは、モンゴル帝国の[原理]を変えることにはならなかった」(p.153.)
柄谷氏の言う「イスラム教の変容」とは、①神義論(サラフィー主義)の発生、②神秘主義(スーフィズム)の抬頭、です。
『イスラム教はムハンマド以来、布教=征服戦争によって全戦全勝〔…〕で広がった。だからそこには、ユダヤ教にあったような「神義論」が無かったのです。たとえば戦争で負けると、なぜ神は神を信じる者に敗北を与えるのかという問題が生じます。それに答えるのが神義論です。』
モンゴルに征服されることで、『なぜムハンマドの教えに従っているのに敗北するのか。〔…〕この問いのなかで、イスラム教そのものが変わったのです。そこから生まれたのがサラフィー主義です。この敗北は、ムハンマドの教えを完璧に実現した原初のムスリム共同体が堕落したからだ、というものです。今日の “原理主義” は、このような考え方に根ざしています。〔…〕
より重要なのは、神秘主義スーフィズムが一般に抬頭したことです。これは、神との合一を説くものです。個々人は神と合一するのだから、法学者や神学者は不要です。これが教団国家を否定する考えであることは言うまでもありません。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.152-153.
‥‥しかし、「神義論」にしろ「神秘主義」にしろ、《帝国》の原理にとって必要なものでしょうか? 《帝国》にふさわしい「世界宗教」〔交換様式B〕ということで言うと、神義論や原理主義、「教団国家を否定する考え方」などは、それとは逆に、国家を否定する方向(交換様式D)に向かうのではないか。それらは、「世界宗教」よりも「普遍宗教」の要素なのではないか、という気がします。ここは、柄谷氏の指摘に賛成できません。
【18】 モンゴルの残照――ロシア帝国
「フビライの時期に成立したモンゴル帝国は、多元的複合的な世界帝国です。」フビライの死後に分裂し、1305年に再統合。しかし、中国の元は 1368年に滅ぼされ、「他の地域でも帝国は崩壊」していきます。が、モンゴル帝国は「ある意味ではその後も続きます。〔…〕近世の各地の帝国はすべて、モンゴル帝国に由来すると言っても過言ではないからです。」
ロシア帝国も、「モンゴル帝国の影響を受け」て成立した帝国の一つです。ロシア帝国は、「ギリシャ正教の国家として、あたかもビザンツを受け継いだかのように見えますが、そうではありません。」
キエフ,「聖ソフィア大聖堂」。キエフ公国の主教座大聖堂として 1037年に
建立された。当時ウクライナ語はまだ存在しなかった。「キーウ」は誤り。
「最初、ロシアはキエフにありました。」キエフ公国は、「バルト海と黒海を繋ぐ交易の中心として栄えた都市国家です。ビザンツとのつながりが生じたのは、そのころです。しかし、キエフ公国も、その後に発展したモスクワ公国も、とうていロシア帝国を作るようなものではなかった。」
ロシア帝国を生みだすことになる「大きな変化は、1238年、チンギス・ハーンの孫バトゥー・ハーン」の征服によってもたらされた。キプチャク・ハーン国が建てられ、「モンゴルによる統治が 250年続きました。この間に中央集権的な体制が確立され、その版図も巨大化しました。その下でハーンの支持によって強くなったモスクワ公国が、キプチャク・ハーン国をしだいに弱体化させ、1502年に滅ぼした〔※〕。ロシア帝国は、ここに始まります。」(pp.156-157.)
註※「モスクワ公国が滅ぼした」: この記述は不正確。モスクワ公国は 1380年クリコヴォの戦いでジョチ・ウルスの当時の事実上の支配者(クリミアの部族長。ハーンではない)を破ってから貢納を怠るようになり、ジョチ・ウルスから自立した。そのころから、ジョチ・ウルスは弱体化し、カスピ海北岸域に縮小。1480年、アフマド・ハーンはイヴァンⅢ世のモスクワ公国軍とウグラ河畔で対峙したものの戦闘に至らず。1502年にはクリミア・ハーン国に攻略されて首都サライが陥落、ジョチ・ウルスは多くの汗国に分裂した。そのなかで、モスクワ公国がとりわけ多くモンゴルの国家体制を継承したということはない。
柄谷氏は、モンゴル帝国「の骨格が[ロシア帝国]として残った」「モンゴルの支配がもたらした中央集権的国家体制と広大な版図、そして多民族を包摂する帝国の原理が」ロシア帝国として残った、と言うのですが、史実とは思えない。史観としても可能かどうか。
ロシア帝国の中央集権原理は、《帝国》とは異なるものだと言わざるをえません。そこには、民族的寛容が乏しいからです。近代のロシア帝国体制から見る限り、その異民族支配の原理は、寛容とは逆の「分割統治 Divide et impera」:支配下の異民族を互いに争わせて統治を容易にするやり方です。このようなことは、モンゴルも中国王朝も行なっていません。
また、ロシア帝国の版図が拡大したのは、たくさんの地域政権や小汗国に分裂したジョチ・ウルスの旧領域を改めて征服していったのであって、ジョチ・ウルスないしモンゴル帝国から領土を継承したのではありません。
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!