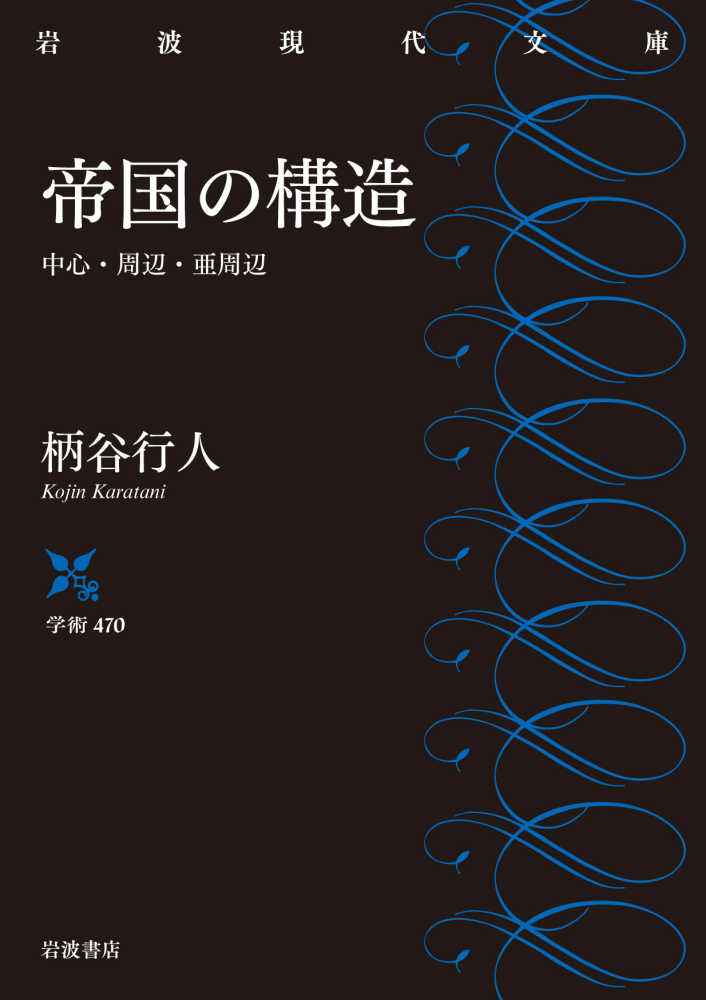均田制の実施状況を記録する北朝西魏の文書。スタイン将来敦煌文書。
『詳説世界史研究』山川出版社。
【13】 “変革の500年” ――漢《帝国》下の民衆運動
『漢王朝崩壊後に息を吹き返したのは〔…〕老荘思想である〔…〕。老荘のいう「無為自然」は、根本的に国家の否定でした。そして、この考えが漢の末期に表面化してきます。〔…〕それは〔…〕民衆のあいだに広がった宗教だった〔…〕。それがのちに道教』となった。
これに対して、初期の『漢王朝が採用した老荘思想は、むしろ統治者のための思想であって、本来のものとは異なります。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.135.
老子・荘子の思想は、漢代に民間でも広まり、しだいに神秘的・宗教的性格を帯びるようになりました。「後漢の末期には、疫病が蔓延し大量の流民が生まれた」が、そのなかで、民間老荘思想の系譜を引く張角の「太平道」・張陵の「五斗米道」が広がり、張角の結成した「太平道」教団は、数十万人の農民を集めて軍隊組織のようになり、「黄巾の乱」を起こして後漢王朝倒壊の原因となります。
つづく三国時代には、「五斗米道」が魏の曹操に保護されて渭水~黄河流域に広がっています。
柄谷氏によると、これらの民衆宗教は、「千年王国」的な反乱運動を引き起こしただけでなく、氏族共同体崩壊後の・農民たちによる集落形成の動因としても作用したのです。
『秦・漢王朝では郡県制の下で、旧来の氏族共同体は解体され、たんなる行政単位としての「村 そん」になってしまった。そこで、被支配者は自発的に集落を形成しました。それが「塢 う」と呼ばれる共同体です。〔…〕
中国の〔ギトン註――村落〕共同体は、農民が、国家が押し付けた機構に対抗して作ったものである。〔…〕
農民のこのような活動は、〔…〕何らかの「思想」なしにはありえません。〔…〕それが統治者の思想である儒家でなく、道家〔老子・荘子――ギトン註〕に近いものとなるのは当然です。〔…〕民衆が国家的枠組みから自立しようとすれば、「無為自然」を説く老荘に依拠することになります。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.136,311(2).
儒教には、孟子が考えた「井田法」という・土地共有による農民共同体のプログラムがありました。「井」という字の形に耕地を区画し、周囲の8個の区画は8戸の農家に平等に与え、中央の区画は共同で耕作させて、その収穫は国家に納める。というものです。
孟子は、これが、周王朝で行なわれていた理想的な土地制度だとしました。が、これは、農民のためというより、統治者が、労働力と兵力を確実に確保するための手段という性格が強いものです。後漢末のような疫病や飢饉に見舞われたとき、農民はむしろ、逃亡によって、このような統制に抵抗するか、あるいは自ら、より任意な共同体を形成しようとします。その際、農民たちを結びつける結合原理は、周王朝の権威でも合理的理想主義でもなく、宗教的なものでなければなりません。
『交換様式の観点から見ると、〔ギトン註――漢の初め、農民が自ら組織した〕「塢」のような共同体は、行政によって解体された氏族共同体にあった互酬性を自主的に回復する意味があります。〔…〕いいかえれば、交換様式Aを高次元で回復すること、つまり交換様式Dをめざすものです。ゆえに、それは宗教的な形態をとるのです。
漢王朝の崩壊以後〔ギトン註――中国歴代王朝〕に起こった反乱』も、何らかの宗教結社と結びついたものが少なくない。これらは、キリスト教などさまざまな宗教に基いて『世界各地に起こった千年王国運動の一種』だと見てよい。『それは、〔…〕交換様式Aを高次元で回復する社会運動だということ』ができます。
中国では漢以後も、『国家機構とは別に、人々が民間で自治的な共同体、幇 パン、あるいは「郷里空間」を作るようになった。そして、〔…〕民衆運動として国家機構に刃向かうことになります。そして、〔…〕新たな王朝をもたらす。〔…〕自治的な民衆組織や流民の反乱から新王朝へ、という過程がくりかえされた。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.136-137.
たとえば、14世紀・元末の「紅巾の乱」は、仏教・浄土宗系の白蓮教徒によるもの。ただし、「紅巾軍は白蓮教団を母体としたが、実態は盗賊や流民の寄せ集めだった」(wiki「紅巾の乱」)。仏教僧で紅巾軍の一派の指導者だった朱元璋は、江南の覇権を得ると、一転して白蓮教団の弾圧を開始し、全土を統一して明王朝を建てています。
また、隋・唐の建国は宗教反乱とは関係ありませんが、創設者はいずれも、遊牧民の征服王朝・北魏の武将出身です。これらのことが意味するのは、《帝国》というものが、千年王国的宗教結社、反乱農民や、周辺異民族など、異質な集団から様々な原理を吸収して成立するものだということです。交換様式で言えば、Bを主としながら、それに「A,C,Dの要素を組み込むことによって成り立つ」のが《帝国》である。
西域,亀茲(クチャ) ,キジル千仏洞の前にある鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)像。
亀茲国の王族だった鳩摩羅什は、カシミールに留学して仏教を学んだが、帰国後
来攻した「五胡十六国」前秦の捕虜となり、後涼→後秦と移された。後秦王の
依頼で仏典約300巻を漢訳し、仏教中国伝来の基礎を築いた。©Wikimedia.
【14】 “変革の500年” ――征服王朝の土地改革
「たとえば、漢王朝は、」北方の塞外にいた「遊牧民の匈奴に悩まされた。それは武力が不足していたからだけでなく、遊牧民を包摂する原理をもたなかったからです。」その点で、漢はまだ完全に《帝国》になったとは言えない。
「中国に真に帝国と言える王朝が成立したのは唐においてです。」漢が倒れた後、周辺の遊牧民が「中華」の領域に入って来て「五胡十六国」を建国しますが、最後に華北を統一したのは、鮮卑族の北魏王朝です。遊牧民の征服王朝である北魏が中国にもたらしたものは2つ:「均田制」と「仏教」です。
「均田制」は、農民に一定の広さの土地(一代限りの口分田+世襲の永業田)を与えて、「租・調」の税貢と力役をとる制度です。「五胡十六国」時代に、遊牧民の諸王朝は、漢族農民を強制移住させて田地を割当て、税役を収取する政策(計口受田)をしばしば行なっていました。これを、一般的な土地制度に拡大したのが北魏の「均田制」で、以後、北朝の歴代王朝から隋・唐まで継受されました。つまり、遊牧民族による征服王朝で発達し、隋・唐による統一で中国全土に及んだことになります。
中国の「均田制」が、日本でそれを継受した「班田収授」と違うのは、支給面積がたいへん広いことです〔隋唐の場合、規定上は、永業田20畝[約1.2ha]+口分田80畝[約4.8ha]〕。←これは、男子一人の受給面積ですから、戸内に 15歳以上の男が2人いれば2倍になります。
このことは、当時の農業技術と関係があります。当時、華北の畑作では連作は稀れで、隔年耕作・輪作が行なわれ、休耕地も多かったことが、北魏の農書『斉民要術』から判ります。したがって、広い支給面積は、休耕地や未墾地を含む土地の割り当てだったと考えられます。そのなかで、どれだけを開墾して耕作するかは農民に任されていたのでしょう。要は、定められた税役さえ出せば、それでよかったのです。
もっとも、首都近郊のように人工調密で可耕地の少ない地方では、規定どおりの面積を支給することはできません。「口分田80畝」は、実際には支給の上限値だったと考えられます。
後世、中国の官僚や歴史家は、「均田制」を、「井田法」という孟子の農民ユートピアを実現したものだとして称賛し、日本の学者も、20世紀までは、そう考える人が多かったのです(それゆえに、現実に実施されたのかどうか、疑問に思う人も多かった)。しかし、↑トップ画のような実施記録文書が発見されて、規定通りの支給と返還が行なわれていたことが明らかになると、その制度的意味と由来についても見方が変わってきました。現在では、「国家」の強い土地所有規制と徴税政策に基く・征服王朝由来の制度と考える傾向が主流になっているようです。(⇒:wiki「均田制」)
「均田制」は、「農民から租税と兵役を安定的に確保する、王権強化の政策なのです。」(p.138.)
五台山(山西省忻州市)。最高峰が3000m を越える高地に 47所の寺院(最盛期には
300所以上)が営まれる中国仏教の聖地。最初の寺院創建は北魏代。©Wikimedia.
他方、「仏教」は、北魏で「国教として導入され、僧侶が国家官僚となった」。「隋・唐王朝でも仏教が隆盛しました。とくに唐では、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教」、ゾロアスター教、マニ教が西から入ってきました。唐王朝が、これらを受け入れて保護したのは、世界帝国として、「部族や民族を越える普遍的な原理を必要とした」からです。中国プロパーの儒教や道教では、世界帝国の統治には不十分だったのです。「唐代には儒教の発展は見られません。」
もっとも、仏教は、老荘思想のもとに解釈され、また、中国特有の論理的体系化が施されて、中国的な仏教として発展しました。「天台宗,華厳宗,浄土宗,そしてとりわけ禅宗です。」(p.139.)
『唐にかんして重要なのは、何よりも、それが遊牧民国家であることを維持した点です。唐の太宗(李世民)は、遊牧諸部族たちから天可汗の称号を得ました。つまり、彼は中華の皇帝であるだけでなく、遊牧民世界のハーンとなった。このことは、〔…〕世界帝国という観点から見ると画期的なできごとです。〔…〕唐は、遊牧民国家の原理と農耕民国家の原理を統合しようとした。それは、内部的な矛盾を抱えることになります。〔…〕が、唐王朝が滅んだあとも、農民国家と遊牧民国家を統合するという課題が追求されました。〔…〕
漢は大帝国でしたが、その周辺部、とりわけ匈奴を抑えることはできなかった。唐も同様で、ソグド人安禄山の反乱によって衰退するにいたった。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.139-140,149.
唐王朝が、遊牧民/農耕民の両国家原理を統合しようとして抱えこむことになった「内部的な矛盾」とは何なのか、柄谷氏は具体的には述べていません。が、それを考えてみますと、まず「均田制」は、唐代における土地売買の盛行によって、大土地所有と「佃戸」(小作人)が増えたために、逃亡農民が増えて支給ができなくなり、租・調・力役の収取もできなくなって崩壊します。その結果、「安禄山の乱」後に「両税法」(資産課税)が施行されます。
もともと漢代には大土地所有が増え、それが諸侯の反乱を惹き起こす一因になったと思われます。柄谷氏が「無為」=自由放任政策の効果として触れていたことがらです。
その後、「五胡十六国」の動乱を経て、強力な遊牧民的国家原理をもった北魏・北朝諸国が、国家の農民支配を建て直したのが「均田制」だったと言えます。それは隋・唐でさらに強化されたのですが、けっきょくは、富商・豪農による大土地所有の盛行という農耕社会の特性現象を抑えきれなかったことになります。
他方、「仏教」については、その伝来と隆盛、およびそれと同時に、仏教教義の体系性・神秘性に刺激されて宗教形式を整えた「道教」の隆盛は、唐代の儒教を影の薄いものにしてしまいました。儒教を国家統治の教学とする中華王朝にとって、これはゆゆしいことです。たとえば、則天武后の統治による混乱の背景には、武后と側近貴族たちの仏教への傾倒がありました。
儒教をどうするか。官僚統治のイデオロギーを、どう確保するのか。この課題は結局、唐王朝では解決されず、つぎの宋王朝に引き継がれることになります。宋代における「科挙」の整備確立と、仏教(禅宗)の影響を吸収した新興儒教「朱子学」の成立がそれです。が、それらは同時に、「佃戸」小作制を拡大させて抬頭してきた新興地主層・に対する官僚制国家の対応でもあったのです。
1111年の東アジア。©Wikimedia.
【15】 遊牧民《帝国》の系譜
さて、唐滅亡以後の歴史については、史観によって、描く筋書きが大きく異なってきます。
伝統的な中国史研究では、唐→宋→明→ と続く王朝系譜が主流とされてきました。宋と明に挟まった元の時代は、征服王朝のいわば暗黒時代で、進歩が止まった時代だとされたわけです。つまり、漢民族の王朝だけが正統だと‥。しかし、それなら隋・唐はどうなるのでしょう。これら2王朝の創始者は、遊牧民王朝北魏の武将で鮮卑族(拓跋氏)です。
柄谷氏の描く筋書きは、東アジア世界を《帝国》として見ているので、漢民族かどうかは関係ありません。遊牧民族でも、「中心」を征服してしまえば、それ自身が「中心」です。そうすると、唐のあとは:
唐→遼→金→モンゴル(元)→明→清→
となるでしょう。宋が抜けていますが、世界史地図↑を見ればわかるように、宋という王朝は中国全土を支配していません。北のほうに、最初から「遼(キタイ)」があります。そのあと北西に「西夏」ができて、やがて北半分が「金」になります。
『唐にあった課題を真に受け継いだのは、宋よりも、キタイ(契丹)帝国だというべきでしょう。〔…〕耶律阿保機〔…〕は、916年唐滅亡後の混乱に乗じて契丹国〔遼――ギトン註〕を建て〔…〕遊牧民であったキタイの世界に農耕民国家の原理を持ちこみ、複合的な国家を作ろうとしたのです。』
北魏,隋,唐,『いずれも拓跋氏による王朝です。彼らは遊牧民国家と農民国家を統合する複合国家を形成しようとした。しかし、それが伴う内的な矛盾・葛藤をもち続けたわけです。
唐の時代にもすでにその葛藤が顕著になっていましたが、唐以後にはそれが両極に分解しました。南宋が、唐にあった遊牧民国家の要素を払拭する方向に進んだのに対し、キタイ帝国は、〔…〕統合を維持しようとしました。そのために内部抗争が絶えず、宋を攻略する余裕がなかった。キタイ帝国は滅亡しましたが、その企図の核心は〔…〕草原世界に伝えられたということができます。』その結果は、『モンゴル帝国が築いた元王朝として』中国に回帰してきた。
『つぎの明朝では、元の時代を斥ける漢族主義が生じましたが、事実上、モンゴルの制度を受け継いでいます。たとえば、全人口を軍戸と民戸に分けるやり方は、遊牧民と定住民を分けるキタイ帝国以来の二元組織を受け継ぐものです。
中華史観では、元は侵入者が築いた王朝であり、一時的なアクシデントにすぎないかのように見なされます。が、モンゴルは単なる侵入者ではありません。それ〔元を含むモンゴル帝国――ギトン註〕は、鮮卑,唐,キタイによって受け継がれた「帝国」を受け継ぐものでした。モンゴル帝国、〔…〕チンギス・ハーンは、明らかにキタイから学んだのです。』
柄谷行人『帝国の構造』,2023,岩波現代文庫,pp.141-143.
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!